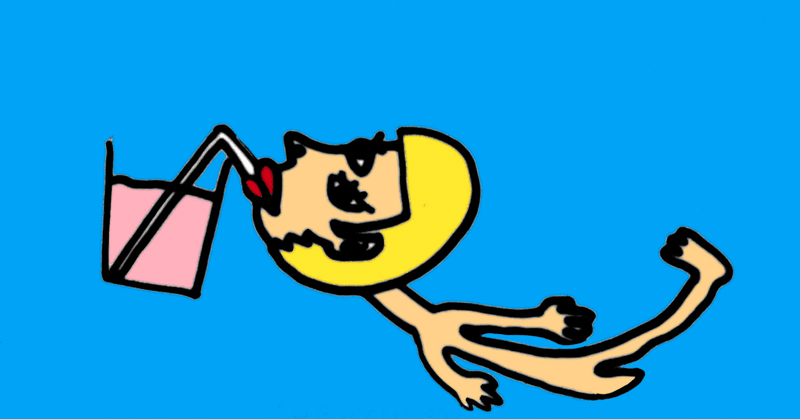
知的障害って?〜「発達障害」と診断された人のための「発達障害」の説明書13〜
一緒につくるマガジン
【「発達障害」と診断された人のための「発達障害」の説明書】と題して、マガジンの連載をしている。
このマガジンは、『一緒に作るマガジン』という設定。
「受け身ではない、主体的な学びの機会を作りたい」
という思いからの『一緒に作るマガジン』。
マガジンの作成に読者が参加してもらうことで、きっと、受け身ではない、主体的な学びの機会が作れる。
もし何か質問が出たら、次回はその質問について取りあげた記事を書きたいし、もし自分の記事を取り上げても良いという方がいれば、次回はそれについて一緒に考えたい。
そんな風に、発達障害のことについて読者と一緒に考え、理解を深めていきたい。
ここでの皆さんとのやりとりこそ、リアルな「発達障害」の説明書になり得ると考えている。
「発達障害」の説明書、よかったら、一緒に作りましょう。
知的障害って?
アメリカ精神医学会が出している診断マニュアルDSM-5における知的障害の診断基準は、以下のようになっている。
DSM-5では、知的能力障害(知的発達症)という診断名で記載されている。
知的能力障害(知的発達症)は,発達期に発症し,概念的, 社会的,および実用的な領域における知的機能と適応機能両面の欠陥を含む障害である。以下の 3つの基準を満たさなければならない。
A 臨床的評価および個別化,標準化された知能検査によって確かめられる,論理的思考,問題解決,計画,抽象的思考, 判断,学校での学習,および経験からの学習など,知的機能の欠陥。
B 個人の自立や社会的責任において発達的および社会文化的な水準を満たすことができなくなるという適応機能の欠陥。継続的な支援がなければ,適応上の欠陥は,家庭,学校,職場,および地域社会といった多岐にわたる環境において,コミュニケーション,社会参加,および自立した生活といった複数の日常生活活動における機能を限定する。
C 知的および適応の欠陥は,発達期の間に発症する。
つまり、『知的機能の欠陥』と、『適応機能の欠陥』の2つが存在しており、またそれが発達期に発症しているときに、知的発達症いわゆる知的障害の診断が検討されるということである。
『知的機能の欠陥』とは、知能検査で測られるIQなどが、標準よりも低いということ。
『適応機能の欠陥』とは、社会的に求められる、自立した生活が困難であるということ。
最近はIQが低いというだけで「知的障害」とすべきでないという世の中の流れが強くなってきている。
IQだけでなく、社会に適応できているかどうかをしっかり見ましょうという風潮のようである。
たしかに、それぞれの人に対してどれだけのサポートが必要かを見るという意味では、IQよりも社会への適応能力を見る方が理にかなっているという気はする。
知的障害者というレールの上で生きるということ
ここでは、特別支援教育と、その先の就労という側面から、知的障害を考えたい。
知的障害を持つ子どもは、特別支援学級や特別支援学校に在籍することが多い。
特別支援学級について、文部科学省は以下のように定めている。
小学校、中学校等において以下に示す障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために設置される学級。
【対象障害種】
知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症・情緒障害者
特別支援学級(以前は特殊学級という名称であった)は、昔は各学校に1クラスしか開設されておらず、上に挙げた障害のある子どもたちが、みんな同じ学級で授業を受けるということも少なくなかった。
しかし、現在では多くの学校で、「知的障害児クラス」「自閉症・情緒障害児クラス」「病弱児及び身体虚弱者クラス」「肢体不自由児クラス」など、複数の障害種別のクラスが開設されており、それぞれの子に合わせたカリキュラムや支援というものが用意されている。
特別支援学級には、上に挙げたような障害を持つ子どもが在籍できるということになっているが、特別支援学級に在籍するために、医師の診断書や知的障害者手帳などが必須というわけではない。
特別支援学級への在籍の可否は、市町村の教育委員会が、子どもや保護者のニーズ、学校や専門家の意見等を総合して決定するということになっている。
知的障害者手帳
知的障害者手帳の話にも触れたい。
知的障害と行政が認めた人に対しては、知的障害者のための障害手帳が発行される。
知的障害者のための手帳は、自治体によって、療育手帳と呼ばれたり、愛の手帳と呼ばれたりとまちまちである。
また、知的障害の基準も各自治体によって少しずつ違っていたりする。
だから、ある自治体で知的障害と認められていた人が、別の自治体に引っ越して知的障害と認められなくなった、といったことも起こり得る。
なんでそんなことが起きているのかというと、
知的障害者のための手帳については法律で定められていないからである。
国が全国一律の基準を定めていないため、各自治体がそれぞれの基準で判定している。
したがって、自治体によって少しずつ基準が異なるということが起こっているのである。
それではダメだろうということで、法律化の話はよく話題になっているけれど、具体的な動きはまだ見られていない。
少し話が横道に逸れたが、そもそも知的障害手帳を持っていると、どんな恩恵を受けることができるのだろう。
それについては次回、書きたいと思う。
次回は、知的障害者手帳を所持していることによって受けられるサービス、そこからはじめて、就労の話と特別支援教育の話を結びつけてまとめられればと思う。
知的障害を持つ人が、自分の能力を最大限に活かしながら、生き生きと生活できるために、私が必要と思っていることについて書きたいと思う。
お時間のある方は是非、よろしくお願いします。
▼【「発達障害」と診断された人のための発達障害の説明書】
▼その他のマガジンは以下よりご覧いただけます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
