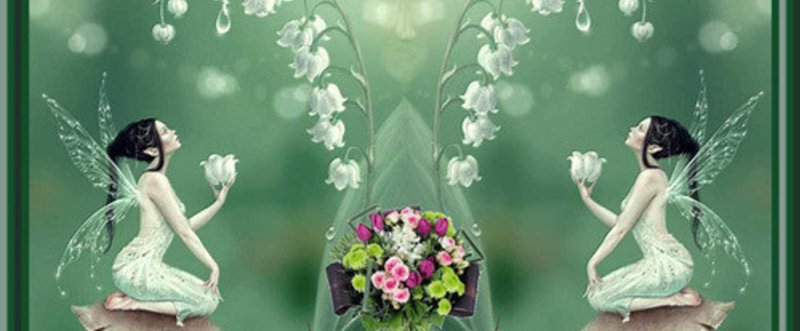
喜捨
皆様、初詣へ行かれて賽銭箱にお賽銭を入れて来られたと思いますが、お賽銭につきまして、今回は祖母からの受け売りをお話させていただきますね。
お寺で賽銭箱にお金を入れる事を、仏教では「喜捨」というそうです。
「喜んで捨てる」と書きますが、これは、「どうかお守りください」「願いが叶いますように」「日々の暮らしに感謝します」「願いが叶いました、ありがとうございました」など、様々な思いを込めお賽銭を入れるものと思いますけれども、喜捨の本当の意味は、自分自身が持っている執着心を捨てる、ということなのだそうです。
例えばお金に対する執着心や、もっと沢山の物が欲しいという、物欲、欲望を振り払う為に、お賽銭箱に入れるのです。お金と一緒に邪心や執着心を捨て去ることで、心が洗われ、清らかな心となり、ここに喜捨の意味があるそうです。
この、喜捨の心はお賽銭の時ばかりではなく、どのような時にも応用できます。例えば「認められたい」「周囲から評価されたい」「理解されたい」と、思ってしまうということ、人間ならばこのような承認欲求を持つことって、私をはじめ当然のことですが、その思いが過ぎると自己中心的な思いも時には生まれてしまうこともあります。そうすると「自分だけが評価されればいい」「自分だけがうまくいけばいい」「自分にメリットのあることだけやればいい」という、損得勘定が生まれてしまいます。特に現代は競争社会ですから、自分さえ良ければ、という誘惑に負けてしまうことがあるかと思います。
ですが、そのような気持ちばかりではなく、喜捨の心を持つことが大切ですよ、ということなのですよね。
誰も見ていないところで善いことをする、何の利益、得にもならないような事を引き受ける、誰からも評価されなくても、誰からも褒められなくても、認められなくても、喜捨の心をもってを引き受けてみると、結果、心を豊かにし、邪心を振り払い、陰徳を積む事となるのですよね。そして、不要な執着心から解き離れ、心が楽になる、と、いわれます。(例えば、寺社に願掛けをしてお賽銭を入れますが、このお賽銭はその寺社の維持運営修繕等に役立ちますので、その善行に対して徳を積むこととなり、御利益が生まれるといいます。)
子供の頃はあまりよくわかりませんでしたが、この年になると、成る程、と、思えるようになりました。
周りの評価を気にし過ぎると、全てを損得で考えるようになってしまい、自分本来の生き方ができ難くなってしまい、自分の人生ではなく周りに如何思われるかということばかり考えるような、落ち着かない息苦しい人生となってしまいますが、評価、損得抜きの人生を歩んでみると、それまでの息苦しい執着心から解き放たれ、最終的に得をするのではなく、徳を積む事に繋がり穏やかな人生になるのだなあなんて。(^^)
・・・と、初詣の際、お賽銭箱にお賽銭を入れる際に、祖母のお話を思い出したのでした☆
有難く頂戴致しましたサポートは、動物保護施設への募金及び易経研究の為に使わせて頂きます💓
