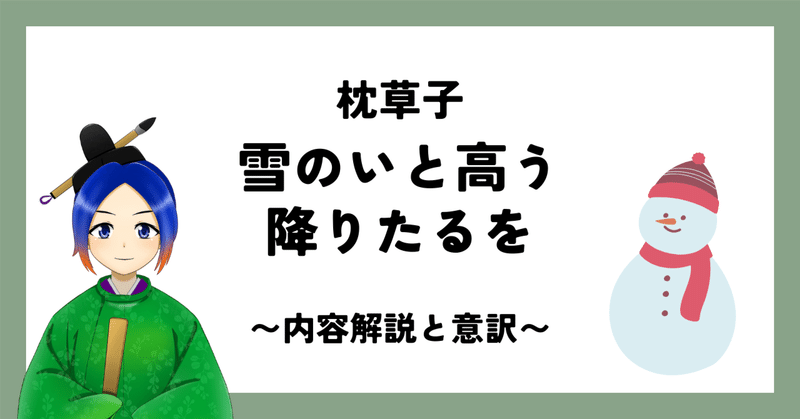
【古文解説】雪のいと高う降りたるを〈枕草子〉内容解説|万葉授業
こんにちは、よろづ萩葉です。
YouTubeにて古典の解説をする万葉ちゃんねるを運営している、古典オタクVTuberです。
ここでは、枕草子の一節『雪のいと高う降りたるを』の内容解説を記していきます。
原文
雪のいと高う降りたるを、例ならず御格子参りて、炭櫃に火おこして、物語などして集まり候ふに、「小納言よ。香炉峰の雪いかならむ」と仰せらるれば、御格子上げさせて、御簾を高く上げたれば、笑はせ給ふ。
人々も「さることは知り、歌などにさへ歌へど、思ひこそよらざりつれ。なほ、この宮の人にはさべきなめり」と言ふ。
現代語訳
雪がずいぶん高く降り積もっているのに、いつもと違って御格子を下ろし申しあげて、角火鉢に火をおこして、話などして(女房たちが)集まり(中宮定子様のおそばに)お控え申し上げているときに、
「少納言、香炉峰の雪はどうかしら」と(定子様が)おっしゃるので、(私は女官に)御格子を上げさせて、御簾を高く上げたところ、お笑いになった。
仲間の女房たちも「その詩は知っているし、歌を詠むときに引用したりするけど、それは思いつかなかったわ。やはり、この中宮にお仕えする人としては、それがふさわしいわね」と言う。
「白氏文集(白居易)」
こちらは清少納言お得意の「有名な漢詩をもとにした会話」のお話。
この時代、有名な漢詩といえど知識を必要とする会話ができる女性というだけでも頭が良いとされていた。
もとの漢詩をどのように取り入れるか?というのが、清少納言の得意とするところである。
この話では、『白氏文集(はくしもんじゅう)』のこちらの詩句が引用されている。
遺愛寺鐘欹枕聽 香爐峰雪撥簾看 (白居易)
遺愛寺の鐘は枕を欹(そばだ)てて聴き、
香爐峰の雪は簾を撥(かか)げて看る
この詩を用いて、中宮定子は清少納言に問いかけをしたのである。
意訳
雪がずいぶん高く降り積もっているのに、いつもと違って御格子を下ろして、角火鉢に火をおこして、
おしゃべりをしながら女房たちが中宮定子様のおそばに集まっているときに、
「少納言、香炉峰の雪はどうかしら」
と定子様がおっしゃるので、
私は女官に格子を上げさせて、御簾を高く挙げ、外の雪が見えるようにすると、定子様は笑った。
仲間の女房たちも、
「その詩は知っているし、歌に引用したりもするけれど、そうするのは思いつかなかったわ。
この中宮にお仕えする人としては、それがふさわしいわね」
と言う。
解説
中宮定子は、清少納言のことを心から認めています。
この問いかけは、清少納言がどんな面白いことを言うか、試したかったのでしょう。
清少納言はその場の皆の予想に反して、気の利いたことを言うのでも、歌を詠むのでもなく、ただ御簾を上げて雪を見せました。
このとき、おそらく定子も外の景色が見たかったのでしょう。
定子が清少納言に対して笑ったとき、とても満足そうな顔をしていたのだろうと想像できます。
定子のサロンとは
「この中宮にお仕えする人としては、それがふさわしい」と女房たちが言っていますね。
頭の良い中宮定子を面白がらせてこそ、ここに仕えるのにふさわしいのです。
定子は、清少納言など教養豊かな女房たちを集めて文学や芸術などの会話を楽しんでいました。
これを、定子のサロンと呼びます。
サロンというのは貴族階級の社交場という意味です。
定子のサロンの一員たるもの、
頭の良い返しができてこそだということです。
どれだけレベルの高い集まりだったのだろうかと思わされますね。
枕草子からの一幕でした。
千年も昔の作品なのに、現代にも通じる話が多く、
古典文学を楽しむ入り口としてはとっつきやすいのではないかと思います。
動画
ご覧いただきありがとうございました🖌️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
