
今月読んだ本 (12)
2024年3月
今月もkindleで読んだ英語の本の話から。今月はJeremy Rifkin "THE AGE OF RESILIENCE"を読みました。不明を恥じますが、リフキンという名前は昨年初めて知りました。もう80歳に近い国際的にも著名な社会思想家で、西欧各国の政策にも影響力を持つ人物のようです。地球温暖化などの環境問題に対処するためには、現代の資本主義社会の根本からの変革が必要だという事は今では半ば常識になっていますが、その大元は、たぶん、この人あたりにあるのでしょう。よく知りませんが、「グリーン・ニューディール」政策なども、この人やナオミ・クライン等が主導したのかもしれない。同じような問題意識から出発して「人新世の資本論」を書いた斉藤幸平さんは、「グリーン・ニューディール」政策などは一種のごまかしで効果が無い。資本主義からコモン(共同体)主義としてのコミュニズムへの変換がいまこそ必要なのだと訴えているわけですが、確かに、この本を読んだ限り、リフキンの主張は数字やエビデンスによって読者を知的に説得するというより、やや文学的、情緒的でもあり、社会的なアジテーションとしては温和に過ぎるかなと思えるものでした。
"THE AGE OF RESILIENCE"は"THE AGE OF PROGRESS"に対応する言葉で、resilienceとは辞書的には回復力とか反発力という意味があり、この本では「再野生化」する地球環境への回復力という意味で使われているようです。しかし私は、成長主義の社会からの転換という趣旨で、この本のタイトルを「持続可能な社会」という意味に受け取りました。リフキンさんはこの本で様々な提案をしていますが、最も力を入れて書いているのは、将来を担う子供達をできるだけ自然に触れさせて育てようという、まるで養老孟司先生のような主張でした。古今東西、賢者の考えることは似ているものですね。この本を読んでいて、私は若い頃に愛読した、ケネス・E・ボールディングの「二十世紀の意味」という本のことを思い出しました。この人は「宇宙船地球号」という言葉を発案した人で、やはり人類の将来を案じる賢者の一人でした。ボールディングが心配した最大のものは人口爆発による地球の環境破壊や食糧危機でしたが、実は私は現在の環境問題やエネルギー問題の基底にあるのは人口問題だと今も考えています。人口減少が始まった日本をはじめとする東アジアの未来はその意味で明るいとさえ考えています。それはともかく、リフキンのような賢人が各国の政治や政策決定の現場にもっと増えればいいなと思った読書でした。
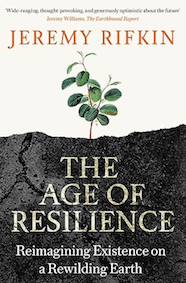
次に読んだのは、平野啓一郎「本心」。今回の芥川賞受賞作である九段理江さんの「東京都同情塔」を選者の一人として平野さんは絶賛していましたが、本作を読んでなるほどと思いました。全く違う話ではあるが、小説のテーマや世界観がなんとなく似ているんですね。最近はすっかりベストセラー作家になった平野さんですが、この小説ではかなり重いテーマを扱っています。大江健三郎にとっても重要だったテーマ。「信仰を持たない人間がいかにして救われるのか。」という問題。要するに「死」への向かい方の問題ですね。無限の宇宙空間の中での死すべき人間としての存在の闇に立ち向かったパスカルは、結局、キリスト教の信仰に救いを見つけたが、信仰のない自分はどう生きればいいのか。大江さんが選んだのは、祖先たちと同じように、死ねば四国の森に戻るのだという古代からのアニミズム的な考えだったようです。さて、平野さんはどう考えたか。
この小説の主なテーマは、安楽死を望んだ母親の「本心」はいったい何だったのかということの追求ですが、SF的なギミックも使いながら、実に面白く巧みに物語として描かれています。その追求の過程で、とても重い問題である「死」に関する平野さんの哲学や思想がさまざまな形で展開されている。平野さんが尊敬する三島由紀夫が「美しい星」でSFの形を借りてその死生観や哲学を語ったように。その意味で、この小説はまさに平野さんの思弁小説としてのSF(スペキュラティブ・フィクション)でした。実に面白かった。さて、この小説で披露された平野さんの死生観はというと、簡単に言えば(本当はもっと複雑ですが)、宇宙と一体化して死の恐怖を克服するというものでした。まあ、それはこの小説だからなので、他の小説ではまた違った死生観を描かれるかもしれません。人間なんてそんなものです。それはともかく、最近は、平野さんの小説は映画化されることが多く、映画としても賞をとるなど、とても素晴らしいもので嬉しい限りですが、この小説も映画化されるようです。小説と映画は別物ではありますが、どんな映画になるのか楽しみです。
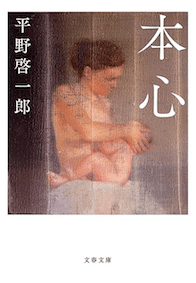
最近、SNSと朝日新聞で間隔をおいて連載されている柄谷さんの回想を面白く読んでいます。特に、抽選で当たって、アメリカで在外研究をすることになり、アメリカでの在外研究の経験がある江藤淳にどこに行ったらいいかを相談した。江藤淳はちょうど日本に来ていたイエール大学の人を紹介してくれた。その人は柄谷さんを気に入って、なんと、研究員ではなく客員教授として迎えてくれることになった。その報告を聞いて、江藤さんは羨ましそうにしていたという話が面白かったですね。ポール・ド・マンとの出会いなど、このイエール大学での様々な経験が、その後の柄谷さんの仕事や運命を大きく変えた事を考えると、まったく人生というのは偶然によって成り立っていることがよくわかります。というのは余談。
さて、今月読んだ柄谷行人さんの「帝国の構造」ですが、アメリカでの研究生活によって発想が芽生えた、生産様式ではなく交換様式からマルクスを根本的に読み直すという柄谷さんの後期の一連の仕事のひとつです。つまり、「世界史の構造」と、未読ですが、「力と交換様式」の間をつなぐ仕事が「哲学の起源」やこの本などだということになります。「哲学の起源」は既に読んで感銘を受けました。今回は「帝国の構造」。普通、難解な哲学の本を読んでいると、途中で、何が何やら解らなくなって自分の頭の悪さを嘆くことが多いんですが、柄谷さんの本は、平易ではないにしても、いつも論旨が明快で創見に充ちていて、読むと自分までも頭脳明晰になった気分になってしまいます。だから、私も長年にわたって柄谷さんの本を読み続けているわけですね。どこまで理解できているのかは疑問ではありますが。この本も実に楽しく読めて賢くなった気分です。この文庫本の帯には「柄谷国家論の集大成!」とありますが、どういうことでしょうか。
下部構造が上部構造を決定するとしてマルクスが考えた下部構造は生産様式のことだった。しかし、それでは世界史はうまく説明できない。生産様式ではなく、交換様式として考え直すべきだというのが柄谷さんの交換様式論ですが、それは、A:互酬、つまり贈与と返礼(共同体)、B:略取と再分配(国家)、C:商品交換(資本主義経済)、D:いったん解体されたAが高次元で回復したものとすると、これまでの世界史はAからB、BからCへと発展してきた。Dはまだ実現していないというものです。簡単にいうと、この交換様式論を世界システムの諸段階にあてはめてみたのが、この本だということになります。A:ミニ世界システム、B:世界=帝国、C:世界=経済(近代世界システム)、D:世界共和国(カント)というわけですね。これ以上の紹介は煩雑になるのでやめておきますが、柄谷さんは帝国というものに、かなり好意を持っているようです。なぜなら、帝国というものは内部に多様な民族や宗教を包摂するシステムなので、基本的には自由で寛容な政体だったからです。現代のEUを新時代の帝国だと考えればよくわかります。柄谷さんによれば、現代はCの段階であって、ヘーゲルが「歴史の終わり」として構想した、資本=ネーション(国民)=ステート(国家)の三位一体のシステムで成り立っている。しかし、周知のように、そのシステムは今やさまざまな点で限界を迎えている。私たちにはDの世界システムが必要だ、そのためにはBも参考になるよ、というのがこの本での柄谷さんの主張だと私は理解しました。でも、どうすればDの世界がやってくるのかはわからない。柄谷さんにもわからない。でも、日本を帝国の亜周辺国家だと規定した部分の記述などは実に冴えていて、これぞ柄谷行人と声をかけたくなりました。

次に読んだのは小熊英二「日本社会のしくみ」。もう5年前の新書ですが、ようやく読めました。小熊さんの本はみんな分厚いことで有名ですが、この新書本も分厚い。なにしろ小熊さんは完璧主義なので、対談をするにも、前もってその人の著書を全て読破するという人ですから、論文や本を書くにもとにかく資料を博捜する。分厚くなるのも仕方がありません。この新書も、そんな風に手に入る限りの資料を調べた上に、一般向けにわかりやすく図解やグラフで説明してくれていますから、実に説得力がある。結論としては、もう知っているよという事でも、これだけの根拠とともに示されれば、より知識に確信が持てる。私は、この新書を高校や大学の必読参考書にしたらどうかと思ったくらいでした。問題の所在に気がつけば、もうその問題は半分解けたも同じだというのが、「見える化」理論の考え方ですが、この本は、戦後日本社会を「見える化」したものだからです。
戦後の日本社会を分析しようとした小熊さんがこの本で特に取り上げたのは雇用関係でした。さきほどの下部構造の話とも通じますが、日本社会の政治や文化を分析する際に、その下部構造として雇用システムが重要であることに気づいたからだそうです。学者として、世界各国に滞在した経験を持つ小熊さんは、日本の雇用習慣の特異さに興味を抱いた。そして研究を始めた結果がこの新書です。この本の最後に、著者の小熊さん自身が、この本の骨子をこのように記しています。「日本では企業と地域を横断した労働運動や専門職運動が弱く、横断的な労働市場や階級意識が形成されなかった。『カイシャ』と『ムラ』を社会の基礎とみなす意識と、現存する不平等を階級間ではなく企業間の格差とみなす意識が生じたのはそのためである。」また、それに続く文章で、各国とも単色ではないが、日本は「企業のメンバーシップ」が支配的な社会、ドイツは「職種のメンバーシップ」が支配的な社会、アメリカは「制度化された自由労働市場」が支配的な社会と分類されているのが、なるほどと思わせました。
小熊さんも言うように、終身雇用、年功序列、一括定期採用といった、日本の特異な雇用習慣は「国民性」で説明できるものではなく、あくまでも近代に形成された歴史的なものです。グローバル時代に入って、これらの雇用習慣も変化せざるを得ませんが、その際にいきなりグローバル・スタンダードにあわせば混乱が生じます。政財界、労働界が一緒に知恵をしぼらないといけない。雇用習慣が変われば、日本社会は根本的に変わるでしょう。なお、私自身のことを言えば、私は大卒新人として定期採用されてそのまま停年まで勤めました。中小企業だったので、私のような者は少数派でした。たぶん、仕事が性に合っていたんでしょう。幸運でした。作家の橘玲さんによると、日本人は世界一仕事が嫌いなのだそうです。その原因はたぶん、性に合った仕事ではなく会社を選ぶという、日本のメンバーシップ型雇用習慣にあるのではないでしょうか。この本を読んで、そんな感想を持ちました。

40年ぶりに文庫化されたと少し前に話題になっていた浅田彰さんの「構造と力」を買って、ざっと再読しました。40年前、発刊後すぐ読んだので、今でも書棚のどこかにあると思って探したんですが見当たらない。仕方なく買いました。千葉雅也さんの解説に興味もあったし。というのも、SNSで東浩紀さんが文庫の解説を断ったとデマを流されたことを嘆いていたからです。浅田さんと東さんの関係を考えれば誰もが解説は東さんだと考えると思うんですが、出版社は大学生らに人気のある千葉さんを選んだようです。それはともかく、40年前と言えば私は既にサラリーマンになって10年以上過ぎていましたが、時々、三浦雅士さんが編集長の雑誌「現代思想」を読んだりしていました。ですから、当時の論壇のスターの一人だった栗本慎一郎さんが「天才浅田少年」の凄さをさかんに宣伝していたので、浅田さんは登場前から一種の有名人でした。ですから、「構造と力」が出版された時もすぐに買って読んだわけです。読んで、実に頭のいい人だなと思いました。ほぼ同時期に思想界のスターになった中沢新一さんはほぼ私と同年代ですが、浅田さんはかなり年下でした。当時わずか26歳。もう天才と呼ぶしかないですよね。
先ほど触れた柄谷行人さんの回想で柄谷さんはこんな事を書いています。文芸評論家として出発した柄谷さんは徐々に対象を哲学や思想に移していったんですが、西洋の思想の最前線の知識はほとんどなかった。友人だった三浦雅士さんに教えてもらったそうです。後に、雑誌「批評空間」を浅田彰さんと共同で編集することになってからは、三浦さんの役割は浅田さんがすることになった。東浩紀さんは、この雑誌「批評空間」で、まだ学生時代にデビューしました。東さんもまた天才少年だったわけですね。東さんが浅田さんと違ったのは、その後も旺盛に執筆活動をつづけ、ついにはアカデミアの世界を離れて自らの言論メディアを造り出したことです。などと、ここまで本の内容とは無関係なことを書いてきましたが、この年齢になっても、私には浅田さんの著書を批評する能力も知識もありません。まことに困ったことです。でも、あれから40年経って、かつては輝ける存在だったポストモダン思想は今では色あせているように見えます。結局は、高度に知的ではあるけれども脳内の言葉遊びに過ぎなかった。ほとんどの社会人の現実の生活にとっては関係のないことだったとなっている。とうことで、思潮の主流は哲学から社会学に変わったわけです。さて、明らかに当時の大学生を想定読者にしていたこの本が40年後に初め文庫になった。さて、今の大学生の諸君はどんな感想を持つのか興味があります。
余談ですが、同時期にスタートした中沢新一さんが書きすぎだと思うくらい多くの本を出版しているのに対して、浅田さんはほとんど本を出さないことで知られています。だからこの処女作「構造と力」がいまだに代表作のように思われている。なぜ本を書かないんでしょうね。たぶん、頭がよすぎるのだと思います。それと体力。私は一度だけ生の浅田さんの講演を聴いたことがありますが、浅田さんは中年になっても少年のような体型で、小柄で華奢な人でした。本を書くにも体力は必要です。

今月最後に読んだのは、松岡正剛「源氏と漱石」。千夜千冊エディションの一冊です。今年は個人的に「源氏物語イヤー」にしようと思っているので、この読書はその一環です。最近、松岡さんの回想も朝日新聞に連載されていて、長年の読者である私は、毎回興味深く読みました。松岡さんは京都出身で御父君は呉服屋さんでしたから、源氏物語的なものとは子供の頃から親しんでおられたようですが、初めて源氏物語について書いたのは9年前、71歳になってからでした。その、松岡さんのネットページ「千夜千冊」に3夜連続で掲載された文章がこの文庫に収録されています。松岡さんのことですから、単なる源氏論ではない。膨大な専門書などの情報を「編集」したうえの万華鏡のような源氏語りになっていました。松岡さんは源氏物語は、「うた」と「もの」の語りだという。特に「もの」。「ひと」でも「こと」でもなく「もの」。「もの」には「もののけ」も含まれる。たしかにそうですね。生き霊にも死霊にもなった六条御息所が典型ですが、「源氏物語」は物の怪に充ちている。なるほどと思いました。また、「もの」は「もののあわれ」につながる。というわけで最後は、本居宣長と折口信夫の源氏物語をめぐる「もののあわれ」論になって、この千夜千冊、「源氏物語」の三夜は終了しました。この中で、松岡さんが、与謝野晶子訳の源氏を評価し、私の敬愛する丸谷才一さんと大野晋さんの対談「光る源氏の物語」を、「源氏物語」を読む際の最良の伴侶だと書いてくれていたのも、個人的には嬉しいことでした。題名でもわかるように、この本は日本文学史全般を取り上げたもので、他にも松岡さんならではの興味深い文章が満載(松岡さんの用語を使えば連打)なんですが、今回はあえて源氏物語の部分だけを取り上げました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
