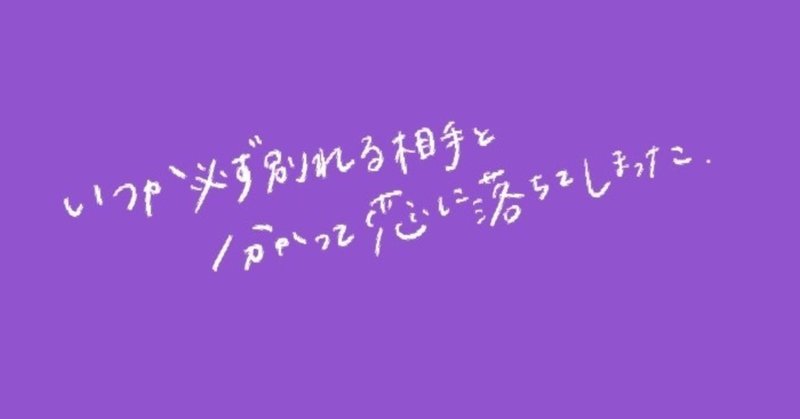
いつか必ず別れる相手とわかって恋に落ちてしまった
例外はあるだろう。
でも、大抵の場合はいつか別れがくる。
何年かの幸福な時間の後、唐突に、あるいはじわじわと。
しばらくは心の整理ができず、泣いたり、幸せだった過去をぼうっと眺めたり、ひたすら誰かと話して消化しようと試みたりする。それでだんだん実感が湧いてくる。
それでもいつも、好きになったことを、出会えたことを後悔はしない。
いつかわたしの前からいなくなったとしても、あなたの人生は続いていく。
強がりなんかじゃなく心から、向かう先が幸せであれと心の底から願う。
「卒業」という別れの痛みを何度も、何度も繰り返して、それでもアイドルを追いかけてしまうのはなぜだろう。
※この記事は映画『Documentary of 乃木坂46 いつのまにか、ここにいる』のネタバレを含みます。
メンバーが卒業するということ
今回のドキュメンタリー映画では、西野七瀬の卒業発表からラストライブまでを主軸に構成しつつ、多くのメンバーがグループを去る様子が描かれた。
映画の中で、何度か繰り返し出てきた問いがひとつある。「アイドルって卒業しなきゃいけないものなんですか?」……問いかけるカメラマンに対して、一期生の1人である秋元真夏が口にした言葉が印象に残った。
「何度も、ここに残ればいい、乃木坂46は実家みたいなものだから、残って他の活動も続けていけばいいってここ(のど元)まで出かかった」
細部は異なるが、こんな言葉だったと思う。
自身も卒業を決めたキャプテン・桜井玲香も、舞台などグループを離れた活動を積極的に行う生田絵梨花や白石麻衣も、グループに居続けてきたからこそ味わう「見送る側の寂しさ」を語っていた。
グループを卒業しても芸能活動を続けるアイドルは多いし、そうでなくとも仲が良いメンバー同士なら友達として会ったり連絡を取ったりすることはできるはずだ。
それでもやはり、卒業は重い。
卒業発表をした西野七瀬と、仲の良かった高山一実が撮影現場ではしゃぐシーンでのナレーションがそのことを的確に物語っていた。
「喜びや幸せを、それまでと同じように共感することはできなくなるかもしれない」「それはまるで失恋のようだ」
嘘みたいに仲が良いと語られるグループ。不器用に少しずつ紡いできた先輩、後輩、同期生との人間関係。多くの時間を共有し、体を寄せ合い、涙をぬぐい、ティッシュを配り、円陣を組み、シンクロしてきたからこそ、その時間が失われることはまるで「失恋」のように、とても怖くて痛いことなんだと思う。
推しが卒業するということ
メンバーの卒業は、私たちファンにとっても最も痛みを感じる瞬間の一つだ。
「名前の由来?飛ぶ鳥のように…ですかね」いつもちょっと照れ隠しのように苦笑しながら質問に答える、齋藤飛鳥が私の推しだ。いまカメラの前でいたずらな表情を見せている彼女も、鳥のようにいつかどこかへ飛んでいってしまうときが来る。
同窓会に参加したことで、昔の自分と向き合う姿。後輩たちと過ごす何気ない姿。「期待しない」が口ぐせだった彼女が、今は人に期待するようになったかもしれない、と打ち明ける様子で映画は幕を閉じる。
変わらない魅力を持ちながらも、見えないところで少しずつ変わっていく姿に、あっという間に羽が生えて飛び立ってしまうんじゃないかと怖さを覚えてしまう自分がいる。
痛みを恐れながら、それでも
大好きな人と離れるのはつらいけど、別れを乗り越えたら成長できる…そんなのは綺麗事だ。「大好きな人に会えなくなることに、強くなる必要ありますか?」大園桃子の言葉は私の気持ちそのものだった。
映画を通して別れの時を追体験するたび、胸がギュッとなり息が詰まった。涙を流しながら、この時に戻れたら、と真剣に願ってしまったりもした。
ここから先のグループの旅路には、また様々な別れの痛みが待っているだろう。私の推しもいつしかその時を迎えるのかもしれない。それがすぐ先の話なのか、数年後なのかは今はまだわからない。それでも、私は乃木坂46を見続けていたいと思っている。
「いまのこのメンバーじゃなくてもお仕事はできていたかもしれないけど、また違ったカラーのグループになっていたと思う」生田絵梨花が語るように、アイドルグループは個の集合体で群像劇だ。いまのこのメンバーでのパフォーマンス、空気感はまさにこの瞬間にしかないもので、卒業していくメンバーがいればグループは確実に姿を変え、違う表情を作り出していく。
三期生、そして四期生が織りなすハーモニーはすでに新しいものを乃木坂の中に吹かせている。与田祐希のひとしずくの涙も、早川聖来のぐちゃぐちゃの涙も。
私がステージに立つ彼女たちにできることは「いつの間にか、ここにいた」あの子たちに、「ここに来てくれてありがとう」と伝えること。
いつか別れる時が来るとしても、彼女たちの一生のなかの「いちばんキラキラした場所」をしっかりと見届けたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
