
心理学をビジネスに生かす
心理学は様々な場面で使われている。
人間関係の形成のため、ストレス軽減のため、ビジネスのためなど幅広いところで注目されている。
知っておくと、ビジネスの場面で役立つ心理学を見ていく。
第1話 目次
1.ぶつかり合い
2.専門用語は使わない
3.ナンバーワン
4.ピーク・エンド
1.ぶつかり合い
会議などでみんなが賛成している意見に対して、自分も賛成しておけば間違いないという経験をしたことは誰もがあるだろう。
「同調行動」と呼ばれる心理が働くためで、集団の中で仲間はずれにされないように同じ行動をとっておこうとするのだ。
しかし、我慢を重ねて精神状態にもよくない時には、自分の意見を主張することも時には必要となる。
仲間はずれにされることは気分はよくないが、ぶつかり合うことで、もっとわかり合える関係になることもあるのだ。
2.専門用語は使わない
仕事ではあえて専門用語を使わない方が良い場面もある。
わかりやすい言葉に置き換えた方が、相手に伝わり信頼を得られることもある。
その業界しか使わない用語は、取引先にはわかりづらいこともある。
知らない用語を使われることで、アウェイ感を感じさせてしまうこともあるのだ。
ホームで試合をするような雰囲気を、出来るだけ作っていこう。
専門用語を使わざるを得ない時は、手短にわかりやすく説明しよう。
3.ナンバーワン
どうにかしてこの商品を売りたいと思った時に、「ナンバーワン」という威力を発揮する言葉がある。
人は1位という言葉に弱いのだ。
1位というからには、多くの人に支持されていて、すごいに違いないと無条件に認めてしまうのだ。
どうしても売り込みたい時は、どんなこじつけでも良いから「ナンバーワン」を見つけてみよう。
それが難しければ、トップクラス、最大級など言葉を濁して売り込むことを考えると良い。
4.ピーク・エンド
交渉が決裂すると、その場の空気はなんとなく重たいものになってしまう。
こういう時は次に期待が持てる明るい終わり方にしてみよう。
そのためには最後に「ありがとうございました」の一言を必ずつけ加わえよう。
「ピーク・エンドの法則」によると、楽しかった経験や辛かった記憶は、ピーク時と終了時の快・不快の度合いで決まると言われている。
最後に与える印象が、のちの印象に大きく影響を与えるのだ。
ビジネスで交渉が決裂したとしても、最後に良い印象を与えておけば、次へのチャンスにつながるのである。
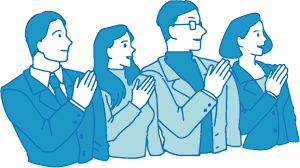
ビジネスでは人間関係の形成、交渉、販売などの場面で心理学がよく使われる。
コツやポイントを掴むだけでも、自分の動き方、仕事への向き合い方が変わってくる。
コツやポイントをしっかりと押さえていこう。
第2話 目次
1.感謝→謝罪
2.ハッタリの効用
3.時計を見る
4.聞く耳を持たない人へ
1.感謝→謝罪
取引先や上司から飲みに誘われたが、行く気にはなれない。
そんな時に気分を害さずに断るには、感謝を必ず伝えよう。
誘ってもらい嬉しいが…という気持ちを真っ先にアピールすることが大事である。
感謝→謝罪と続けることで、有無を言わせず断られたという印象を与えないのだ。
感謝されたというインパクトが強いため、相手の気分を害さないことになる。
2.ハッタリの効用
ビジネスでは自分を強く見せなければならない。
そんな時は身振り手振りをいつも以上にオーバーにすると良い。
人間はそそのかせばその気になりやすい生き物である。
わざと書類をバシッと叩いてみたり、おまかせくださいと胸を叩いてみよう。
強い自分を演じるように行動することで、自分でも強くなったかのように錯覚し、ハッタリも効いてくるのである。
3.時計を見る
腕時計をディスクに置いたり、携帯をテーブルに置いて時間を気にする人と仕事をする場合は気をつけた方が良い。
時計を見るのは野心家で、上昇思考が強い人に多いと言われている。
常に時間に追われているという切迫感をもっているので、ストレスが溜まりやすく、ちょっとしたことで怒りだす傾向がある。
八つ当たりしてくることもあるので、大切な話しは短時間で済ませるようにしよう。
4.聞く耳を持たない人へ
言動に配慮が欠けていて、注意しても直らない部下がいたら「役割演技」を仕掛けてみよう。
役割演技とはいわゆるロールプレイングのことで、仕事で起こりうる場面を想定して適切に対応出来るように学習するもの。
この場面で演じる人ではなく、審査する方の役割を与えてみよう。
自分以外の人がその場にふさわしくない対応を目の当たりにしながら、自分の対応のまずさに気づいていく。
演じている人に対して注意することで、自分が自分の言葉に説得されるという効果がある。
自分の身に置き換えて、物事を考えられるようにしていこう。

無意識のうちにビジネスの中で心理学が使われていることもある。
意識して使うことでさらに生産性は上がっていく。
細かくポイントを見ていくことにしよう。
第3話 目次
1.仕事が出来ることを印象づける
2.ハネムーン効果
3.人脈の使い方
4.時間の使い方
1.仕事が出来ることを印象づける
ビジネスにおいて、この人は仕事が出来るということを印象づけておくことは肝心である。
一度、この人は仕事が出来ると認識されると、大失敗しない限りイメージは覆されることはない。
最初に下した評価を変えることは、自分は人を見る目がないと認めることになる。
能力に関する評価はそう簡単には変わらない。
出来ると認めた人が失敗しても、今回はたまたまと良心的に解釈するのだ。
自分の評価が誤っていたことを認めたくないのが、人間の本能なのである。
2.ハネムーン効果
行き詰まったら、思いきって環境を変えれば新境地が開けて、現状を打破出来る気がする。
人間は新しい環境に置かれた時に自然とやる気や満足度が上がる。
これを「ハネムーン効果」という。
しかし、環境を変えて一時的に上がった満足度は、時間の経過とともに低下してしまう。
「ハングオーバー効果」と呼ばれ、新天地に慣れてしまうことで、逆に不満が増大していくのだ。
環境を変えるだけでは、根本的な解決にはならないことを自覚しなければ、腰を落ち着けることはないだろう。
3.人脈の使い方
自分は自信があるのになかなか認めてもらえない場合、自分とウマの合う人にアピールすると良い。
人は同じ価値観をもつ人がいいと言っているものに対して、信頼を寄せるという傾向がある。
例えば有名人が身につけている物が、爆発的に売れたりする。
人気のあるコメンテーターの発言に多くの人が賛同して、世論にまかり通ったりもする。
「準拠集団」という心理で、自らが評価を下すよりも、信頼している他人の評価の方が信頼出来ると感じるのだ。
上司の心を動かしたければ、上司が信頼している相手から「彼はこの分野に向いている」と進言してもらうようにしよう。
遠回りにはなるが、直談判よりもきっと効果があるだろう。
4.時間の使い方
努力だけではどうにもならないことは多々あるが、時間だけは誰にでも平等に与えられている。
時間の使い方については努力をして、勝ち組になれるようにしたい。
同じ仕事でも半日で終わらせるのと、丸1日かかるのでは、残った時間に歴然と差が出るのだ。
段取りや集中力など、取り組み次第で誰でも半日で終わらせることは可能だ。
時間の勝ち組になるには、仕事の進め方に対するアイディアをたくさんもつこと。
そのための準備や段取りをすることが重要となるのだ。

上司との付き合い、部下の育成、取引先との交渉、集客などビジネスの場面では様々な心理学のポイントがある。
心理学を学んでいる人といない人では、圧倒的に差が出ることがわかっている。
第4話 目次
1.共感してから判断
2.返事がない時
3.要点メモの効果
4.内観法
1.共感してから判断
上司に仕事を押しつけられそうになった時に、他の仕事もあるので無理ですと断った経験があるだろう。
こうなると上司もカチンとくるし、査定にも関わってくる。
断る場面では、否定的なフレーズを前面に出さない方が良い。
まずはわかりましたと素直に受け入れた上で、抱えている仕事とどちらを優先させれば良いか聞いてみよう。
大事なのはわかりましたと受容(共感)すること。
共感した上で、でも…と判断を委ねることで、面目を潰されたとも思わずにスムーズに事が進んでいくだろう。
2.返事がない時
やっとの思いで作成した企画であるが、相手から連絡がないということもある。
直接電話やメールで聞くのも野暮な話。
忙しくて連絡をしそびれている場合もあるが、はっきりとNOを突きつけるのに躊躇している場合もある。
どうしても返事がほしい時は、わざと空メールを誤送信するというウラ手を使ってみよう。
すぐにメールを入れて詫びるのがコツ。
その時にそういえばあの件ですが…と探りを入れて、相手の反応を確かめてみよう。
3.要点メモの効果
忙しい相手には話を切り出しても、最後まで聞いてもらえないことが多い。
そんな時は伝えたい内容を記したメモを渡すのが効果的。
メモならちょっと手の空いた時に目を通してくれる確率が高い。
伝えたい要点をまとめて、あとで目を通してくださいと渡すようにしよう。
そもそも人は耳で聞くより目で読んだ方が理解しやすい。
とりあえずメモで要点を伝え、あとでじっくり時間を作ってもらうという方向にもっていこう。
4.内観法
ビジネスパーソンとの関わりの中では、緊張する場面が多い。
緊張する場面ではあえて弱音を吐いてみると良い。
はじめてお会いするので緊張してますと、内に秘めたものを吐き出してみよう。
「内観法」というもので、自分の心の中を冷静に観察し、ありのままの気持ちを言葉にするという方法である。
心の動きを口にすることで、胸につかえていたわだかまりがなくなり、悩みが生じる余地もなくなるのだ。
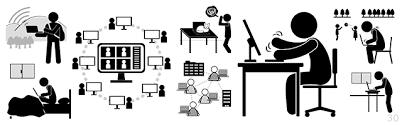
心理学の深さを知ることで、人との向き合い方が変わったという報告をもらうことが増えてきた。
知識を学び実践に生かすことが大切である。
即実践出来る心理学を紹介していく。
第5話 目次
1.目立つ長所をはずす
2.おごるより割り勘
3.朝型
4.文章は紋切り型
1.目立つ長所をはずす
人をほめる時には自分への信頼感を得られるようなほめ方をしたいものだ。
そのためには他人の長所を見つけよう。
例えば営業成績が抜群の部下がいたら、報告書がいつも丁寧で素晴らしいなど、最も目立つ長所をあえてはずしてほめると良い。
本人がそれほど意識していないところをほめることで、自分のことをちゃんと見てくれているという印象を植えつけることが出来る。
その結果、信頼感はグッと高まっていくのだ。
2.おごるより割り勘
部下と飲みに行く時に、飲み代は上司が払うという風潮があるが、割り勘にした方が良い。
部下にもきっちりお金を出させる公平さが強調され、上司の人格を決定づける。
支払い額と人望は比例しない。
あの上司は払いたがるとか、見栄っ張りだというマイナスイメージを生んでしまうのだ。
フェアに割り勘にした方が好感を持たれることが多いのだ。
3.朝型
早起きは三文の徳というが、対人関係においても早起きはいいことづくしだ。
時間ギリギリに出社してきて冴えない顔をしていると、良いイメージはもたれない。
朝からスッキリした顔をしている人の方が好感を持たれるのだ。
朝からスッキリしている人は、元気、健康、自己管理が出来るというイメージがつく。
これを機に朝から活動出来る人を目指してみよう。
4.文章は紋切り型
ビジネスで断りの文章を書く時は、丁寧で紋切り型がオススメ。
感情の入り込む余地があると、気持ちを逆なでしたり未練が残ってしまうのだ。
取引先に対しても気持ちが入った文章だと、それに答えようと感情移入してしまう。
親近感のある文章で期待させといて断るなんてと、逆に感情的になることがあるのだ。
相手に逆なでされないためにも、ビジネス文書はあえて紋切り型を使うようにしよう。

ビジネスにおいて、深い人間関係はつきものだ。
心理学のテクニックを使いながら関係性を築いていくことが成功への道のりとも言える。
心理学の深さを学び、ビジネスに生かせるようにしていこう。
第6話 目次
1.プライドの高い人
2.出来の悪い部下
3.ポジティブな言葉
4.急な敬語
1.プライドの高い人
プライドの高い人がいると、周囲もどう扱って良いか悩む。
仕事の内容に優劣をつけたいのか、雑務を頼めば嫌な顔をする。
こういう人に対して、簡単に落とせるフレーズが実はある。
それは「助けてください」である。
プライドの高い人には、他人を下に見て優越感に浸りたいという願望がある。
この仕事は◯◯さんにしか出来ないので助けてくださいと頼めば、上機嫌で協力してくれるだろう。
こちらがへりくだらないといけないのかと思うより、口では下手に出ておいて、心の中では優位に立っていれば良いのだ。
2.出来の悪い部下
上司が出来の悪い部下をかわいがっていたら、親心とはちょっと意味合いが違うと考えて良い。
出来の悪い部下をかわいがっているのは、自分にとって都合が良いのだ。
自分には対した能力がないと思っている上司ほど、優劣な部下にその地位を脅かされることを恐れているのだ。
頼りないけど自分を慕ってくれる部下をそばに置いて置くと、自分の不安を忘れることが出来る。
出来の悪い部下は自らの不安への防衛壁としてそばに置かれているのだ。
部下ががんばり出した時に応援するより、横やりを入れるようなら要注意人物なので気をつけよう。
3.ポジティブな言葉
会議中に自分の意見に反対意見をぶつけられるといい気はしないが、そんな時は「ご意見ありがとうございます。それについては~と考えます。」と切り返してみよう。
大切なのは相手の意見を受け入れたということ。
ポジティブな言葉で返すことで、懐の深さや視野の広さをアピールすることが出来る。
もしもひるんでしまい、そうですね…と相手に合わせた受け答えをしたら、説得力がなくなってしまうので気をつけよう。
反対意見を受け止めた上で、それでも自分はこう思うとなれば、主張にさらなる説得力が生まれるのである。
4.急な敬語
やっとのことで親しく話せるようになった人が、急に丁寧な敬語で話し始めたら距離をおこうとしていると思って間違いない。
人は気のおけない相手とは砕けた話し方をするが、それほど親しい間柄でなければ敬語を使う。
今まで親しく話していた人が急に敬語を使うようになったら、なにか異変があることで間違いない。
長年付き合っている得意先が、急によそよそしい態度をとったら要注意。
こんな時は相手の気持ちに気づかずにあの手この手で売り込むと、今までの信頼関係すら失うので注意しよう。
相手がしゃべり尽くして言うことがなくなった時に、意を汲んだ提案をすると飲んでくれる場合がある。
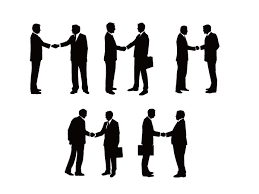
時と場合によって心理学の生かし方は変わってくる。
だからこそ心理学を学んでバリエーションを増やすことで、人付き合いが変わってくるのだ。
さあ、今日も心理学を学び実践に生かしていこう。
第7話 目次
1.あえて不快な物言いをする
2.魔法の決めゼリフ
3.一目置かれるために
4.わざと焚きつける
1.あえて不快な物言いをする
交渉が難航しそうな時は、あえて相手を不快にさせるような物言いをすると良い。
反発を招くことで、相手の本音を引き出すのだ。
相手を怒らせるのではなく、反論したくなるギリギリの線で挑発するのである。
本音を言うとこちらは引かせてもらっても良いんですとカマをかけてみよう。
すると、この際だからはっきり言わせてもらうけど…と露呈してくる。
こうなるとしめたもので、あとは自分のシュミレーション通りに話を進めていけば良いのだ。
2.魔法の決めゼリフ
こんな話を聞いたんですがと、業界の最新事情を訪ねられることがある。
全く知りませんと答えるなら、ライバル会社の方が情報通だと思われてしまう。
かといって話を合わせたとしても、後でそれがバレたら信頼を失なう。
どうにかこの場を取り繕い、悪い印象を与えることなく逃げ切りたい場合には「すみません。宿題にさせてください。」という魔法の言葉がある。
宿題というワードを出すことで、自分を低く見せ、相手を立てることが出来るのだ。
あいまいなビジネス表現ではあるが、相手の気分を害することはほぼないのである。
3.一目置かれるために
部下や後輩が出来ると人を動かす難しさに気づく。
言葉の使い方一つで、思わずついていきたくなるリーダー像を演出出来る。
それは否定語を使わないこと。
人は誰かに肯定されたい、認められたいという「承認欲求」をもっている。
そんな時にでも…のような否定語を使われると、頭から拒絶されたように受けとれかねない。
でもがんばれではなく、確かに厳しいな、だからこそがんばってくれと励ますだけで、部下のもつ印象は変わってくるのである。
4.わざと焚きつける
決して能力がないわけではないのに怠けているのか、闘争心がないのかやる気の見えない人がいる。
そんな時はわざと焚きつけて発奮させてみよう。
例えば、あえて難しいプロジェクトに起用し、意欲が感じられなければ、やっぱり君には無理だったかとわざと言ってみる。
こんな言い方をされて、自分が情けないと感じない人間はまずいない。
はずかしさとともに、反発心が芽生え、やる気スイッチが入っていくのだ。

上司として、部下としてどうやったらうまく関係性が築けるのかを悩む人は多いだろう。
心理学のポイントをうまく押さえながら、良好な関係を築くことが働きやすさにつながっていく。
味方につける方法を見ていこう。
第8話 目次
1.逆手をとって味方につける
2.リスペクトのコツ
3.上手に持ち上げる
4.好奇心をかきたてる
1.逆手にとって味方につける
何をするにも批判的なことを口にする人はいるが、反発するわけにはいかない。
こんな時は発想の転換をして、意見を利用させてもらおう。
物事を悲観的に考え、他人の意見を批判しなくては気が済まない人は、ネガティブな見方をするとはいえ常に思考を働かせている。
批判は常に最悪の事態を想定していると考えれば良いのだ。
批判された時には、なぜそう思うのかを逆に聞いてみよう。
その意見を拾い上げ、起こりうる最悪のシュミレーションを活用させてもらうと良いのだ。
2.リスペクトのコツ
社会に出ると自分より年上の部下をもつことがある。
心境は複雑だが、相手へのリスペクトを忘れてはならない。
実力主義とはいえ、年下の部下に注意するかのような口調では角が立つ。
年上の部下は人間として先輩だし、社会人としてのキャリアもそれなりにあるという自負がある。
最初に敬意の念を示した上で、本題を切り出すのがポイントだ。
年上の部下の自尊心も保たれ、やる気を出してくれるだろ。
3.上手に持ち上げる
飲みに行くと必ずカラオケに行きたがる人がいる。
しかし、カラオケ好きの人に限って歌が下手だったりする。
こんな時はどのように立ちふるまうのが良いか。
いや~癒されます、元気になりましたなど、当たり障りのない抽象的なほめ方をしよう。
歌とは関係ない前向きな感想を言えば、本人はご満喫なのである。
4.好奇心をかきたてる
職場でスピーチする場面がある時に、これから3分12秒のスピーチをしますと、中途半端な数字を切り出してみよう。
確実にみんなの注目を集めることが出来る。
これは「ピーク・テクニック」と呼ばれている。
普通はキリのいい数字をもち出すが、あえて崩す。
そうすることでいとも簡単に、好奇心をかきたてることが出来るのだ。

人と人との関係から成り立つビジネス。
心理学のポイントを押さえるだけで成功に近づいていく。
第9話 目次
1.即断即決
2.3つの原則
3.予告話法
4.あえてつまらない話題を
1.即断即決
確実に相手を落としたい場合には、与える選択肢を絞ろう。
よかれと思って多くの選択肢を提示すると、かえって迷う条件が多くなる。
AとB二択にすると品質だけ選べば良いことになる。
そこに別の機能を備えたCが登場すると、単純に同じ要素を比べれば良いという話ではなくなるのだ。
最終的な決断が遠ざかる恐れがあるので、AかBどちらかで決断を迫るようにしよう。
すると、即断即決を促しやすくなるのだ。
2.3つの原則
会議の流れを思い通りにしたい場合には、「スティンザーの3原則」というものがある。
①以前に自分と議論を交わした相手が会議に参加する場合、その人は自分の正面に座る傾向がある。
②ひとつの発言が出ると、その後に出る発言は反対意見が多い。
③議長のファシリテートが弱いと参加者は正面に座った人と話したがり、逆に議長の発言力があると参加者は隣の人と話し始める。
これらを踏まえて会議に臨めば、会議の流れを臨む方向に進めていくことが出来るのである。
3.予告話法
1時間あれば終わると言われ、実際にやってみると2時間かかってしまった経験はないだろうか。
逆に2時間で終わると言われ、実際には1時間で終わってしまうこともある。
これらは引き受けた側にとって、感情が全く変わってくるのだ。
お願いごとをおおげさに予告することを「予告話法」という。
手がかかることをあらかじめ伝えることで覚悟して取り組み、本当に大変だったとしても不満は最小限におさえられる。
さらに予定より早く終われば、自分は仕事が出来ると思い、次へつながるのだ。
4.あえてつまらない話題を
なにか意見はありませんかと促しても誰も発言しないことがある。
下手に目立ちたくないという空気がその場を支配して、さらに発言しにくい雰囲気が生み出されてしまう。
そんな空気を断ち切るにはトップバッターの発言が重要だ。
え?そんな発言でいいの?というようなあえてつまらない意見を言ってみるのも手だ。
ハードルを下げることで、自然に発言しやすい雰囲気になるので議論が活発になる。
その結果、会議をうまくコントロール出来るようになるだろう。
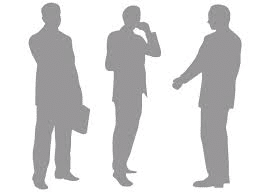
ビジネスの中ではトークも重要となる。
心理学の観点から、トークのポイントも押さえておこう。
第10話 目次
1.カドを立てないで「ノー」
2.上司に助け舟
3.口だけ上司
4.ポジティブな言葉
1.カドを立てないで「ノー」
交渉中にどうしても断らなければならない時は、口を真一文字に結ぶと良い。
こうすることで「拒否」の意志がより伝わるのだ。
明らかに断りたいと思っていても、ストレートに「嫌です」「やりません」というのも大人げないし、「検討します」と濁しても意志は伝えわらない。
ビジネスの場面ではあいまいな表現は、相手に押し切られてしまうこともあるのだ。
口を真一文字に結ぶのは万国共通のしぐさで、表情ははっきりさせた方が良いのである。
口元が相手に与える印象は、かなり大きいのだ。
2.上司に助け舟
ミーティングなどで上司が怒っているときは、自分に向けられたわけでもなくても近づきにくいものである。
しかし、怒った後の上司というものは、怒りすぎたかな…などといろいろ考えているものである。
逆に弱気になっていたり遠慮がちになっていることが多い。
こんな時はその気持ちを汲み取って、積極的に話しかけると良い。
この状況でよくぞ話しかけてくれたと感謝され、絆が深まるのだ。
上司に助け舟を出してやろう。
3.口だけ上司
有能な人だけが上司になるとは限らない。
中には口うるさいが、自分は責任逃ればかりで全く手に負えない人もいる。
そういう場合は幼稚な子どもだと思って接するのが良い。
こちらが親のような気持ちになってあしらえば、必要以上に腹を立てることもなくなるのだ。
専門的な知識は浅いくせに専門家気取りをする上司には、「最近の傾向は〇〇らしいですよ」とさりげなくフォローすると良い。
自分の味方と思わせておいた方が有利で、評価も良くなるだろう。
4.ポジティブな言葉
ポジティブな言葉は人の心や行動を前向きにする。
○○するなと禁止口調になるよりも、○○しようという提案に置き換えて、なるべくネガティブな言葉は口にしない方が、物事は良い結果につながる。
例えば接待の際に「相手を退屈させるなよ、変なことを言うなよ」と言われると、自分の言動が不愉快にさせてしまうのではないかと、萎縮してしまう。
それよりも「うんと楽しませてくれ、自分も楽しむんだぞ」と言われればのびのびと臨むことが出来るのである。
相手が前向きになれる言葉のチョイスを考えていきたいものである。
第11話 目次
1.信頼を得られるチャンスに変える
2.タイミングの法則
3.コントラスト効果
4.おいしい物言い
1.信頼を得られるチャンスに変える
上司がわざわざ自分の所まで出向いて来た時には、頼まれた仕事を必ず引き受けた方が良い。
自分の席まで呼び寄せる上司はプライドが高く、自分の方が上であることを誇示したがる人が多い。
その上司があえて出向いてくるということは、無意識に罪悪感をもっていることが考えられる。
そんな時に出される指示は嫌な仕事の可能性が高いというわけだ。
上司が頼みにくい仕事をお願いしているわけだから、無駄口叩かずに引き受けることで信頼を得られるチャンスとなる。
2.タイミングの法則
部下のミスがあった時は、週末の退社前に注意しよう。
休日をはさむことで、冷静に受け止め気持ちを切り替える時間を与えられる。
これが月曜日なら、落ち込んだ気分のまま1週間過ごすことになるのだ。
また、部下に限らず相手に苦言を呈する場合は、言った後に距離をおけるタイミングを選ぼう。
言われた方も血がのぼってもクールダウン出来る時間をもてるのだ。
3.コントラスト効果
人は何かを見た時に無意識に先に見たものと比較する。
最初に悪いもの①を見せ、次に良いもの②を見せることで、②を本来の価値以上に評価してしまう。
コワモテの男性がお年寄りに席を譲っているのを見て、好感がもてるのはそういうことだ。
普段はマイナス評価されがちな人が、イメージと反対の行動をとると逆にプラス評価されることがある。
これを「コントラスト効果」という。
人を動かす時によく使われているのである。
4.おいしい物言い
会議で意見を言う人と言わない人では、当然のことながら意見を述べた人の方が周囲からの評価は高くなる。
しかし、問題はタイミングだ。
前半と後半のどちらで発言したほうが良いかというと、断然後半である。
議論が白熱すると、最初に発言しても印象が薄れてしまうのだ。
しかも、あとに聞いた情報の方が人には強く印象が残るのだ。
ちなみに会議が終わりかけた時に、一言良いでしょうかと発言する手もある。
最後に集約するような意見を言うことで、おいしいところをもっていくことが出来るのだ。
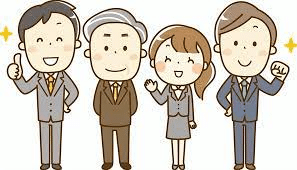
相手の気持ちを理解するためには心理学を活用する必要がある。
うまく相手の気持ちを取り込めるようにテクニックを学ぼう。
第12話 目次
1.運命共同体
2.ポジティブな暗示
3.タダの方が聞いてもらえる
4.わかる部下の気持ち
1.運命共同体
契約を結ぶ際に、この人と一緒に仕事をしたいと思わせる効果的な言葉がある。
それは「運命共同体」という言葉だ。
何があっても最後まで責任を負いますという意味になる。
大きなリスクの伴う仕事に着手する場合、誰しも失敗したら困るという不安がつきまとう。
「運命共同体」と言われると、この人なら何か問題が起きても誠心誠意対応してくれると安心感が生まれるのだ。
さらに責任感が強いというイメージも植えつけ、契約成立に持ち込める可能性が高まるのだ。
2.ポジティブな暗示
仕事を任せる時に「間違えないように気をつけろよ」と注意したり、失敗した部下に「次はミスしないようにがんばれよ」と言う人がいる。
実はこの手のセリフはミスを誘発するのだ。
なぜならネガティブな暗示をかけてしまうからである。
失敗を減らしたいならポジティブな暗示をかけると良い。
「なんでも勉強だ。もっと失敗していいぞ。」と失敗を奨励するような言い方をするのだ。
これで部下がリラックス出来れば、迷惑を被ることもなくなるだろう。
3.タダの方が聞いてもらえる
人を動かすには見返りが必要かと思えば、実はそうでもないというデータがある。
アメリカの実験で、報酬を分け与えたグループでは、報酬差で働き具合に大きな違いが出ることはなく、むしろ無報酬のグループの方が積極的に協力したというデータがある。
報酬という対価を発生させると、相手はその金額を意識し値踏みする。
ちょっとした頼みごとであれば、タダの方が気持ちよく引き受けてくれる可能性が高いというわけだ。
4.わかる部下の気持ち
部下は上司に対してそれなりに気を使った態度をとる。
だが、本心から上司に敬意を払っているかはわからない。
上司から名前を呼ばれた時に機敏に反応する人は、敬意の念を抱いていることだろう。
動作が機敏であるほど、尊敬の度合いは強いとみていい。
こうしたふるまいをされると、相手は気分がよくなり、その人に対する好感度は上がるのだ。
ちなみに自分の席に座ったまま部下を呼びつける上司は、主導権を握っていないと不安なため、テリトリーから出られないのだ。

消費者の購買意欲を掻き立てるにも心理学が使われる。
心理学を学んで売り上げアップにつなげよう。
第13話 目次
1.トリックで安く見せる
2.段ボールカット陳列
3.ネーミング次第
4.マル秘テクニック
1.トリックで安く見せる
お得感を与えるには、数字のもつイメージをうまく利用した価格に設定すると良い。
「8」という数字は、それだけで商品を安く見せる数字なのだ。
値段が980円で20円のおつりが返ってくるのと、同じ1000円を出してなにも返ってこないのとでは、お得感に大きな違いがある。
逆に1~4の数字はほとんど使われない。
100円にわざわざ10円上乗せしたような印象があるからだ。
買う方にしてみればお得感からほど遠くなってしまうのである。
2.段ボールカット陳列
商品が棚に並べられることなく、段ボールの箱をカットしてそのまま陳列しているのを見かけることがある。
これはカットケース陳列とか段ボールカット陳列と呼ばれる、れっきとした陳列テクニックだ。
一般消費者は注意→関心→欲求→記憶→行動と5つの段階を経て商品を購入するという。
段ボールカット陳列は、コストをカットしているという印象を与え、最初のステップでもある注意と関心をもたせるにはもってこいの演出なのである。
3.ネーミング次第
創業10周年に感謝して割り引きセールなんて広告をよく見かけるが、どうして安いのかを端的にアピールするのは欠かせない集客戦略となる。
ただし、単に安ければいいというわけではない。
値段の正統性を理解してもらえるようなセールを開催するのがオススメである。
あまりに安すぎても何か裏があるのではと思ってしまうのが、消費者心理である。
消費者のニーズを満たし、安心して購入出来る状況を作ることが大事。
わかりやすくて、いくら安くなっているかがひと目でわかれば、客の信用を勝ち取れるのである。
4.マル秘テクニック
例えば二人の人がいた場合、新密度は距離を見ればわかってしまう。
二人の距離が近ければ近いほど、親しい間柄と言えるのだ。
「パーソナル・スペース」によって、他人に踏み込んでほしくない距離がわかるのだ。
店で商品が並んでいると、妙に近づいて話しかけてくる店員がいる。
これはパーソナル・スペースを逆手に取った戦略なのだ。
手を伸ばせば届くくらいの距離というのは親近感をアピールする効果があるため、相手に好感をもってもらいやすい。
そこでつい商品を買ってしまうのだ。

売り上げを上げるため仕掛けもたくさんある。
どうやったら消費者の心をつかめるのか、心理学の観点から考えていこう。
第14章 目次
1.赤線で修正する
2.小出し作戦
3.噴水とシャワーのダブル効果
4.ハイトーンボイス
1.赤線で修正する
赤の二重線で修正された値札には、消費者の購買意欲をあおる心理トリックがある。
値札に定価と割引価格の両方が表示されていると、その違いが一目瞭然になり、客に与えるインパクトが大きくなり割安感が増す。
「コスト認知変化説」というが、商品がいくらという点ではなく、どれだけ安くなっているのかという点に集中してしまうのだ。
買いたいもの意外の物も思わず買ってしまうというのは、値札の効果が大きく影響するのである。
2.小出し作戦
効果なものを売ろうとしてうまくいかない場合は、小出しにしてみると良い。
例えば図鑑を買ったとして5巻で3千円だったとする。
届いた箱にいまなら残りの20巻全巻買うと10000円というチラシが入っていたら、どうだろうか。
普通に買えば、全巻そろえるのに15000円のところ、今なら12000円で手に入るとなれば、買いたくなるのだ。
せっかくここまでそろえたのだから、思いきって全巻揃えようという消費者の心理を利用した小出し作戦なのである。
3.噴水とシャワーのダブル効果
買い物客をお目当てのフロアだけでなく、他の階にも誘導したいなら、噴水とシャワーのダブル効果が有効だ。
デパートの1階が化粧品売場で占められているのは活気のある店に足を向かせるためだ。
女性たちでにぎわっているデパートにやってきた買い物客は、上の階にも昇っていくのである。
下のフロアから上のフロアへ客の流れを作ることを「噴水効果」と言う。
最上階の特設コーナーから下に降りていくことを「シャワー効果」という。
客の流れを作ることは売上げアップにつながるのだ。
4.ハイトーンボイス
客を買う気にさせたい時は、いつもよりハイトーンで話すと良い。
高い声には人の気持ちを高揚させ、購買意欲をあおる効果があると言われている。
高い声は元気で活気があり、それにつられてついノリで買わせてしまうのだ。
語尾が上へ長く伸びるのは客に対するへりくだった表現になり、財布の紐を緩めさせてしまう。
お買い得で~すと語尾が長く上へ伸びる声は、客の購買意欲をあおるのに最適なのだ。

長々と心理学について学んできたが、ついに最終話となった。
人の心理を突いていくことは、奥が深くおもしろい。
最終話 目次
1.人をイライラさせない時間
2.マイナス分を強調
3.顕示的消費
4.無意識のうちに行動をおこさせる
1.人をイライラさせない時間
長すぎず、かと言って短すぎないちょうどいい時間は3分間と言われている。
カップラーメンも3分だが、実は技術的に1分でも5分にでも出来るのだという。
1分だと箸や飲みものを準備するには短すぎる。
5分だとじっと待つには長すぎる。
3分だと人がイライラせずに待つにはちょうど良いのである。
本のタイトルを見ても3分でわかる~みたいなものも多いが、心理的効果を狙ったものなのだ。
ちなみに私は5分をよく使っている(笑)
2.マイナス分を強調
同じ水の量を違う形のコップに入れた時に、容量の大きいコップの方が量を少なく感じる。
これは器に対して水の量が少なく感じるからだ。
人は実際の数字よりも、その周辺にある他の要素と比較して、その割合でよくも悪くも判断してしまうことが多い。
これを逆手にとれば、客の消費行動を刺激することが出来る。
今なら1万円オフなどと、元の値段から大幅にマイナスしたことを強調すれば、高額な商品でもお得感を演出出来るのである。
3.顕示的消費
女性をターゲットとした商品開発を考える時、覚えておきたいのが「顕示的消費行動」と呼ばれるものである。
人は外見や肩書きで他人を評価しがちだ。
ブランド品を身につけていれば、オシャレという評価が得られる。
そのブランド品を買うという行為は、地位や財産を誇示したいという「顕示的消費」と呼ばれている。
ちなみに男性よりも女性に強く見られると言われていて、見栄を張りたい、見せびらかしたいという気持ちを上手くくすぐることが出来れば、少し高価な物でも商品を受け入れる傾向がある。
4.無意識のうちに行動をおこさせる
ハイクラスで高品質など、特別感を出されるとつい手に入れる価値があるものだと思い込んでしまう。
たいしてほしくないものでも、魅力的に見えてくるのだ。
このような心地良いイメージを引き出す言葉は、無意識のうちに行動を起こさせる「カチッ・サー現象」のスイッチになる。
カチッ・サー現象というのは心理用語で、テープレコーダーのスイッチを入れると自動でサーッというノイズが流れてくることに由良している。
聞くだけで人の心に働きかける言葉は、相手を操る魔法のスイッチになるのだ。

■まとめ■
ビジネスを行う上では心理学が欠かせないことがわかった。
人間関係の中で使われていたり、交渉や購買効果、上司と部下の関係性など幅広く使われている。
心理学のテクニックを知っているだけで、確実に良好な人間関係になったり、売り上げとして結果が出るようになるだろう。
心理学は本当に奥が深く、まだまだ知識としてたくさん学んでいきたいと思う。
最近注目されている「行動経済学」も心理学の要素がかなり含まれているので、これからのビジネスに心理学は欠かせないものとなっていくことだろう。
今後もビジネスに役立つ心理学の深さを学んでいきたいと思う。
心理学を深く学びたい方・心理学を絡めたビジネスを始めたい方・副業をしたい方、相談に乗りますよ。
まずはLINEに登録してね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
