
誰も教えてくれない!驚くほど変わる 障害児の食事のコツ
こんにちは。
えりくです。
前回は睡眠について
お話させていただきましたが
たくさんの反響をいただきました。
今回は睡眠と同じくらい
相談が多い食事についてです。
障害児の子育てで
食事の悩みを抱えている人は
多いようです。
偏食をなくしていきたくないですか。
集中して食事して
もらいたくないですか。
苦労して作った食事を
食べてもらいたいですよね。
食事についてはかなり
悩みの種だらけだと思います。

悩みをずばり解決する
noteになっております。
若干斬新な切り口で
育児書などに載っていない
実践例になっております。
ではご覧ください。
1.はじめに
![]()

食事は生きていく上で
なくてはならないものです。
障害があるお子さんだと
偏りがかなりありますよね。
偏りを無くすことは無理ですが
改善することは出来ます。
根気のいることですが
ポイントを押さえて
時間をかけていきましょう。
私が受ける相談で多い悩み例
✅偏食がかなりある
✅すぐに席をたってしまう
✅集中できない
✅食具をうまく使えない
✅咀嚼がうまくできない
無理やり改善しようとしても
余計悪化していきます。
一人ひとりに合わせて
少しづつステップアップ
していくことが大切なんですよね。
それでは解決策を
一つひとつ見ていきましょう。
2.偏食の原因
![]()

偏食には様々な原因があると
言われています。
原因をしっかりと把握した上で
対応する必要がありますね。

咀嚼がうまくいかなかったり
飲み込みが難しい子がいます。
嚙む力が弱く繊維質の物など
口に残るものを嫌がる傾向が
あります。
食べる意欲があったとしても
誤飲や窒息の危険があるので
注意が必要です。

障害のある子は感覚が過敏な子が
多いです。
固いものが苦手であったり
揚げ物が口に刺さると言って
食べない子もいます。

発達にばらつきがあるため
集中出来ずに立ち歩いてしまい
食事が進まないことがあります。
食べることに対して全く
興味がない子もいます。
見た目が嫌だったり
形が変わると嫌になってしまう
こともあります。
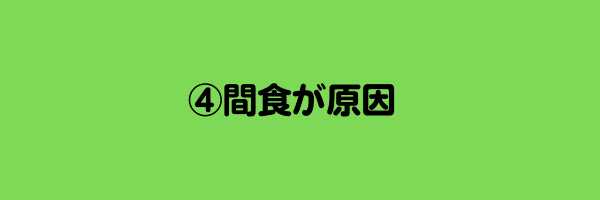
おやつの食べ過ぎで
お腹が空かないことが
多いようです。
障害を持つ子は
必要エネルギーが
少ないとも言われています。
好きなおやつばかり食べて
食事を食べない子は多いですね。
3.偏食の改善法
![]()

相談に来る親御さんは
まず何からすればよいか
わからない方が多いです。
偏食の改善に向けて
どのように対応すればよいか
具体的に見ていきましょう。

食具は使えるのか
困っていることはなにかを
まずは把握しましょう。
チェックリストを
作ってみるとわかりやすいですね。
摂食状況や食材区分などを
仕分けしてみて、なにを好むのか
何を全く食べないのかを
分けて考えてみましょう。
偏食の傾向を掴むことが大事です。
偏食傾向を掴んだら
よく食べるものは多めに出すとか
苦手な物は無理なくスモールステップで
進めていくという対応でいきましょう。

口腔機能の発達はどうか
身体的に座ることはできるのかを
見極めていきましょう。
口腔機能が弱い場合には
口腔機能をアップさせる
食事の形体が必要になっていきます。
咀嚼がしっかりできているか
喉までの送り込みができているか
嚥下機能はどうかなど
細かく見ていく必要があります。
これらは複合していることが多いので
細かい発達の部分をしっかりと
把握する必要があります。
身体機能に合わせた形体に
していく必要がありますね。
また発育の上でしっかりと
座ることが出来るのかも
見極めましょう。
座れないのに座らせるだけで
子どもにも負担になります。

気持ちを大事にすることが
一番大事なことです。
楽しい雰囲気で食事が出来ているか
食べたいという欲求はあるのかなど
子どもの内面を探る必要はありますね。
食べることは生きることです。
食事の時間が苦痛で仕方ないでは
一向によくはなりません。
雰囲気作りや家族と一緒に
食事を楽しむことから
始めてみましょう。
私が小学校の頃は給食を食べ終わるまで
残されているなんてこともありました。
あれはトラウマ第一位でしょうね。
そういう対応は
百害あって一利なしです。
4.集中して食事する
![]()

集中して食事をするためには
まわりにある気になるものを隠す
というのは模範解答です。
しかし私が相談を受ける子どもで
実際に隠して成功した事例は
約5割でしたね。
相談を受けた方へ実際に
アドバイスしている
集中して取り組むために使っている技を
今回は特別に伝授します。

子どもはごっこあそびが好きですよね。
好きなぬいぐるみや
キャラクターのカードなどと
一緒に食べるようにします。
ごっこあそびの延長と捉えて
食べさせる真似をしたりすると
意外と集中して食べられるように
なりますよ。
お母さん気分になるんでしょうね。
知らないうちに完食という子も
いましたね。
そんなあそび食べなんてと
思う方もいるかもしれませんが、
座る時間が長くなるし
気持ちも高まるんですよ。
すぐに立ち歩いて
ほとんど残すよりましだと
思いませんか。
これは是非試してみて
ほしいと思います。

保育園の食育活動もそうですが
自分たちで作った時の食欲は
ものすごいものがあります。
これは魔法ですね。
実際に食材に触るだけでも
気持ちが変わりますよ。
子どもにとって実体験って
本当に大事なんだと思います。
毎日は出来ないにしても
休みの日に簡単なおやつを
作ってみるから始めても良いでしょう。
ちなみにうちの息子は
片づけの手伝いを始めてから
完食する日が増えました。
目的をもつということは
大事なことなんですね。
最後の片づけまでが食事という
ルーティンを作ることも大事です。

体調や気分によっては全く食べないと
いう日もあるかもしれませんね。
考えてみてください。
人間は腹が減ったら飯を食う
という生き物です。
食欲は欲求なんです。
人に食べろと命令される
筋合いはないんですよ。
食べさせなきゃと大人が焦って
がんばりすぎちゃうことが
ありますよね。
それは単純に大人の
食べてほしいという欲求を
満たそうとしているだけなんですよ。
1食くらい抜いても死にはしない
くらいの気持ちで
時には諦めてみましょう。
強制されると大人になって
偏食が残ることがありますから。

これは私の経験談です。
母親に昔よく言われたのは
離乳食の時にめちゃくちゃ
やらせたということ。
手づかみの時期は食材の感触を
確かめています。
手で確かめ、口に入れて確かめ
動物的本能が表れているのです。
この時期に汚れるからやめなさい
精神でいると偏食が出やすい
傾向があります。
たかが掃除くらいの気持ちで
思いきりやらせてみると
食に触れる経験となり
食べる量も増えていきます。
小さいうちからの体験が大事なんですね。
ちなみに私はそばアレルギーで
そば以外食べられないものはないです。
5.食具について
![]()

いつから箸を持たせたらいいんですか
訓練箸は使った方がいいですか
などの質問もよくあります。
食具の使い方も段階があります。
スプーンの使い方では
まずは上手持ちで持ちますよね。
そこから下手持ちになり
鉛筆持ちへと移行します。

発達段階と子どもの握力によって
持ち方が進化していくわけです。
握力が育っていけば
鉛筆持ちに移行するんです。
なぜなら持ちやすいから。
身体的に育っていれば
自然と移行するのが
人間の力なのです。
しかし大人は訓練させようとする。
なぜだかわかります?
まわりの子と比較するからです。
子育てに焦るんですよね。
だから人間の適切な発達を
無視した便利な物が
続々と登場していくんですね。
こんなこと言ったら
炎上するかもしれませんが。
個人的には訓練箸は
おススメしません。
なぜなら食事は
家族のだんらんの場なのです。
子どもの発達を捉えて
食事中に会話しながら
箸の使い方も教えていくことが
重要なんですよね。
特に障害を持つ子は
集中しづらいし
やらせようとしても
難しいことが多いんです。
だからゆっくり丁寧に
関わっていくことが
大事なんですね。
ちなみにうちの息子は
大人が使っている箸を真似して
器用に使っていました。
スプーンもまだろくに
使えないんですけどね。
発達段階を完全に
無視してますね(笑)
6.まとめ
![]()

食事についての悩みが最近多いので
今回は私の経験もふまえて
まとめてみました。
子育ては一人ひとりの
発達段階を把握した上で
対応する必要があります。
特に障害をもつお子さんの場合は
連携機関と情報共有しながら
進めていく必要がありますね。
私に相談来る方には
カンファレンスシートや
サポートブックを作成し
より具体的な支援をしています。
子どもの将来を見据えた支援が
必要ですよね。
悩んだり迷った場合は
いつでもご相談くださいね。
子育ては一人ではできません。
いつでも力になりますよ。
↑ ↑ ↑
こちらからご登録くださいね。
次回もお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

