
透析患者の災害対策とは。
3月11日(水)が透析日だった旦那、病院で「透析患者の災害対策」というプリントを渡されたそうだ。
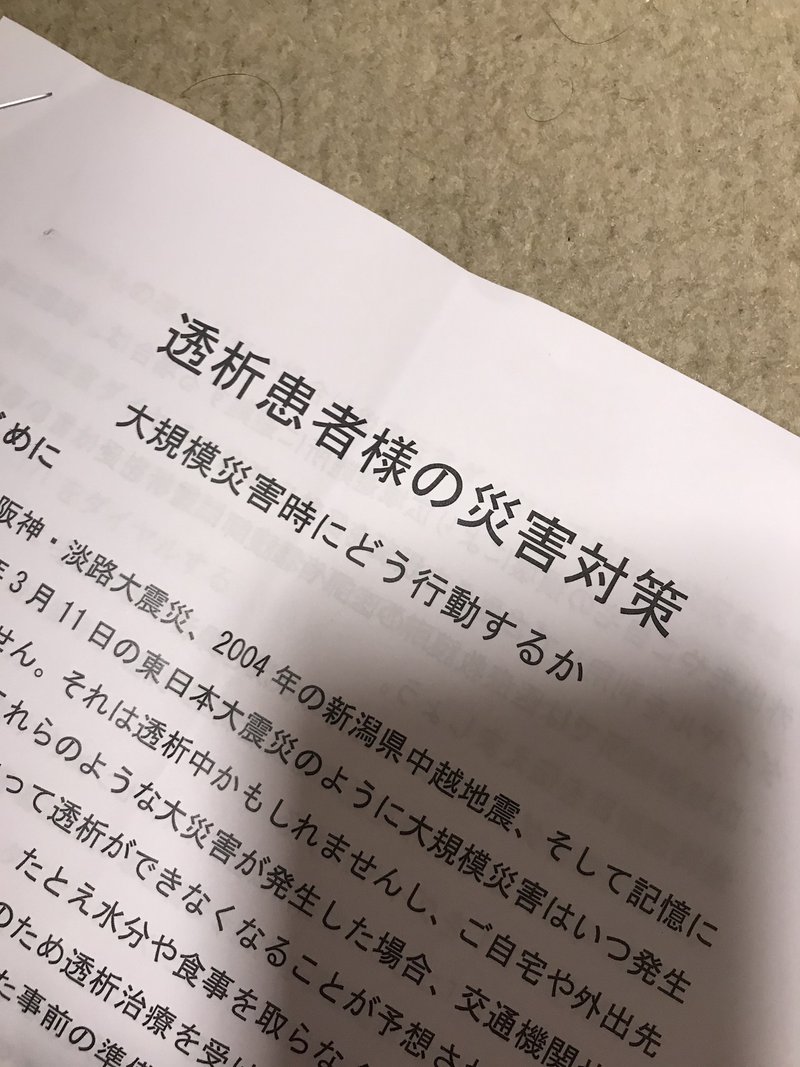
災害が起こったら私のダンナは途端に「災害弱者」となる。電気が止まり、水が来なくなり、ライフラインが停止することで、万一病院が機能しなくなったら透析ができなくなる。透析を行うには他の医療同様に電気と水は必須。透析が何日にもわたってできないということは、命の危険があるということだ。
日本赤十字社の「災害時要援護者ガイドライン」では、以下のような人を要配慮者として明記している。
病気や障害などにより薬や医療器具を要する者、バリアフリー化されていない避難所などで介助を要する者、感染症への抵抗力が弱く避難所で病気にかかりやすい者、被災により精神的障害が増幅される者
透析患者だけではなく、定期的な治療の必要がある人や、薬や注射、医療器具が毎日必要な人も要配慮者になるのだろう。
透析を受けている人は、普段から災害に備えてある程度の「備蓄」をしておくことが大切だと思う。いわゆる非常用持ち出し品のほかに、透析患者が必要と思われるものをピックアップしてみた。
透析条件カード(ドライウエイト、ダイアライザーの種類、抗凝固剤の種類などが明記されたカード)身体障害者手帳・健康保険証・特定疾病療養証のコピー、糖尿病・血圧の薬、リン・カリウムを下げる薬、お薬手帳、滅菌ガーゼ、消毒用アルコール、大判の絆創膏、サージカルテープ
自分がいつも行っている透析病院が被害を受けていて機能していなければ、透析を1日おきに行うことができない可能性がある。もしかしたら、機能している他の病院で透析をしてもらうかもしれない。その場合、自分の透析条件を書いたものがあると安心だ。
透析病院でも簡単なカードを作ってくれるが、ウチは透析条件の他に義足やライナーの重さ、かかっている病院と診療科、健康保険証番号などの情報を1枚のカードにまとめている。個人情報てんこ盛り状態である。
また、透析患者は免疫力が落ちている場合が多いらしいので、できるだけ清潔な状態を保てるようにマスクやガーゼ、アルコールなども常備しておいた方がいい。ダンナの場合は透析で針を刺す箇所や足の断端(切断した切り口)を清潔にしておかないといけないので、これらは必須。
ある程度の食糧の備蓄も大切。災害時は透析の回数や時間に制限が出ることも考えられるそうで、最悪の場合は数日間透析が受けられないこともある。こういった状況になると、自身で食事管理をすることが重要になってくるのだ。
塩分・カリウムの多い食品は控える・・・塩分1日3~4g
エネルギー(カロリー)は確保する・・・1日1200~1400kCal程度
水分量を抑える・・・1日300~400ml
災害時でも必要なカロリーは摂りつつ、塩分水分を控える。備蓄している食料ってインスタントやレトルト、お菓子類が多いので塩分やたんぱく質との闘いは大変そうだが、何とか工夫して乗り切るしかない。
そんなわけで、我が家では適度な食料と水、カセットコンロのガスボンベは普段から買い置きをしておいて、適当に食べたり使ったりしてその分を補充するようにしている。その他、滅菌ガーゼや水を浄化するグッズ、ハッカ油、アルコール、ウエットティッシュなど清潔を保てるものは常備。飲んでいる薬は私の分も含めて3日分を1セットにして、いつもバッグに入れて持ち歩くようにしている。
あとは寝ている時に地震が起こっても、すぐに義足が履けるように枕元に義足とライナーを置いている。これは入院中に同室だった義足ユーザーの人から教わった。さらに、ライナーの上につける靴下のような断端袋、杖などもわかりやすい場所に置くようにした。
いつ、どこで災害に遭うかわからない現代。人の助けを借りなければいけないこともあるかもしれないが、透析患者や定期的に治療を受けなければならない病気を持っている人とその家族は、自分たちなりにできる備えをしておくことが大切だ。モノの備えと、ココロの備えと。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
