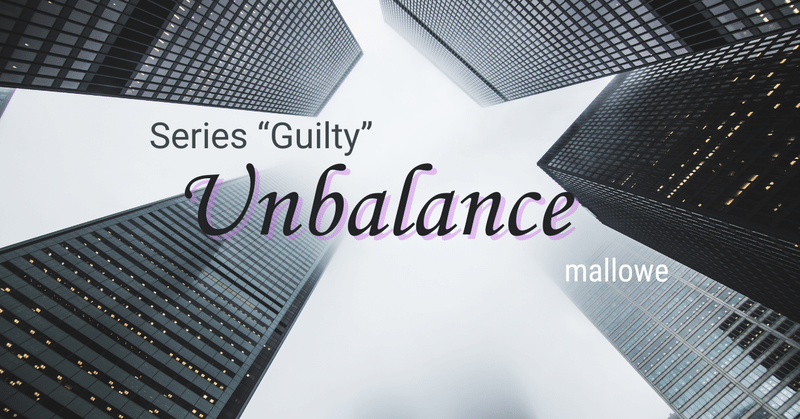
【シリーズ連載・Guilty】Unbalance #5
~紗都香
夫がリヤド出張から戻って来た。
結婚して4年。これまで不在時も帰宅時も特に何とも思わなかった。私がある程度遊んでいる事は夫も承知の上だし、遊び相手はあくまでも暇つぶし。深入りする事なんてなかった。
けれど今は違った。もどかしい。そして、妙に後ろめたい。これまで散々遊んでおきながら。
それは遼太郎くんが、遊びの域を逸脱し始めた事をはっきりと示している。
あんな生意気な若造に、まんまとしてやられてるってわけ。
悔しさはいつしか、快感に変わっていた。
リビングで寛ぐ夫。そのソファで先週、私は遼太郎くんに抱かれていた。
着火したように身体が熱くなる。遼太郎くんは私にこうなって欲しかったのだろうか。
たぶん、そうだ。
私たちは共犯者なんだという思いが、この後ろめたさから救ってくれる気がした。
「どうだった、リヤド」
思わず目を逸らしながらそんな言葉を掛ける。
「リヤドだかアブダビだかドーハだか、わからなくなるな」
「失礼ね」
「まぁ退屈な街だよ。しばらくはごめんだな」
「もうしばらくは出張なしなの?」
思わず、突っかかる。
「さすがにもう老体だ。少しはのんびりさせてもらいたいよ」
「まだ53歳でしょ。老体なんて早すぎる。それに滞在先がどこであろうと、あなただったらのんびり過ごしているんだとばかり」
「さすがに仕事で行っているんだ。ずーっとのんびり出来るわけじゃない。それにほら、イスラム教の国だろう。ラマダンが重なると羽目も外しにくいからな。いいな、お前は俺がいない間、パーティ三昧だったんだろ」
そう、夫の認識はあくまでも “パーティ遊び” 。
「まるで私だけ留守を謳歌していたみたいな言い方ね。仕事だってしているのよ」
「そりゃわかってるよ。別にいいんだよ、留守の間も気にせずやってもらって。妙な奴、連れ込んだりしなければ」
ヒヤリとした。まるで見透かされたみたい。
「妙な奴ってどういうこと?」
「まぁまぁ。それより夏休みの行き先、決めておいてくれよ。お前の休みに合わせられそうだから。のんびり出来る所、頼むよ。たまには国内でもいいな」
「息子さんたちは、いいの?」
「もう下の子も大学に上がったんだ。勝手に遊びに行くだろ。気にしなくていい」
バツイチの夫は前妻との間に2人の息子がいる。私は会ったことはないが。
そんなことより、夏休み…そんなものはどうでもよかった。南国の風よりも、避暑地の太陽よりも、遼太郎くんが恋しかった。
ー 暗い部屋。白くぼんやりと浮かび上がる身体。
やがて光り輝くように明確な輪郭を描き出す。
ウイスキーグラスを傾け、白い喉仏が上下する。開けた白いシャツから覗く首筋、鎖骨。口からこぼれた液体が胸から腹の筋肉を伝う。
手の甲で口元を拭い、舌舐めずりをし、蔑んだ目で微笑む彼の姿…が脳裏をよぎった ー。
頭を振る。
夫がシャワーを浴びに立ったところへ自分の社用スマホを取り出し、遼太郎くんの番号をタップした。そう遅くはない時間。仕事中か、帰宅途中か、家の近所の "冷蔵庫" で晩酌中か。
4回呼び出し、繋がった。しかし最初の言葉が出てこない。
『…もしもし? 九園さん?』
「遼太郎くん…」
『…どうされましたか』
私が "遼太郎くん" と呼んだことで仕事の案件ではないことは明らかに伝わったはずだが、まだ家ではないのか、ビジネス口調に少々苛ついた。
「ね、遼太郎くん。次、一番早いタイミングだったら、いつ会える?」
『珍しいですね、そんなことわざわざ連絡してくるとは』
「水曜日はどう?」
『水曜は毎週、道場へ通っていまして』
「木曜でも金曜日でもいいわ」
『両日とも取引先との接待が入っています』
「じゃあ土曜日は?」
『九園さん、必死ですね』
笑いを含んだ声だ。苛立ちが増す。
「じゃあ空いている日を教えてよ!」
『随分高圧的ですね。今どこですか』
「家よ」
『旦那さん、帰ってきてるんじゃなかったんでしたっけ』
「今は入浴中だから、聞かれる心配はないわ」
『大胆なことしますね。そのスリリングが楽しくて仕方ないんでしょう。でもそういう危ないことはしない方がいいですよ』
「遼太郎くん!」
思わず荒らげてしまった声に、バスルームの方を振り返る。シャワーの音は続いている…大丈夫だ。
「…お願い…あなたの都合のいい時、いつでもいいから」
『俺以外にもたくさんいるんでしょう? "野暮な男たち" が。暇は潰してもらえないんですか?』
「あなたを選んでいるのよ」
『遊び相手に本気になったらアウトなの、九園さんが一番心得ているのでは?』
反射的に電話を切った。怒りに反して身体はもどかしさで千切れるようだった。
するとすぐに折り返し掛かってくる。
「いいわよ、もう。その "野暮な連中" だって、私の…」
『日曜なら空いていますけど』
被せてきた言葉にハッと息を呑む。
「…日曜日…何時にどこなら…?」
『さすがに紗都香さんの家は無理ですね』
***
日曜、10:36 a.m. 小雨。
待ち合わせの渋谷駅に現れた彼は、白いパーカーのフードを被り、ジーンズの裾を少し濡らしていた。傘は持っていない。
私服姿を見るのは初めてだった。男性にありがちな妙なチェーンなどアクセサリーは一切に身に着けていない。
むしろ彼がそんな凡庸な服装をするなんて、意外だった。
「遼太郎くん、天気予報チェックしてないの? 今日は雨降るって言ってたよ」
「…」
照れくさいのか、フードを目深に被って俯く。スーツを着ていないとスイッチ・オフなのか。
そんな姿の彼とこれから向かうところの事を考えると、こちらも妙に照れくさく思わず苦笑いを浮かべてしまったが、Jazz Clubが香って来た時、笑みが消えた。それを察したかのように彼は私の手から傘を取ると、私の腰を抱いて交差点を渡り出した。
トップからミドルノートへ移ろう香り。
目眩がしそうだった。
*
私たちは円山町にあるホテルの一室に入った。白を基調にした明るく、小綺麗な部屋。当然、窓はないのだが。
入るとすぐに背後から彼が抱き竦めて来た。言葉の通り、息が一瞬詰まる。
鼻腔を突く彼の匂い。熱い吐息が漏れる。
そのままベッドになだれ込み、私は彼のパーカーの下から手を滑らせた。彼も同じように、私のシャツの下に手を入れ、互いを弄り合った。
「なんて言って家を出てきたの?」
耳たぶに唇を寄せながら彼が尋ねる。仕事時と違い、サラリとおろした前髪が眩しい。
「…ジムと、買い物」
「シャワーを浴びても、違和感ないように、か。本当にバレずに済むのかな」
そう言いながら彼は私の耳の後ろや首筋に、唇を、頬を擦りつけてくる。甘える猫のように。
「わざとマーキングでもしてるの?」
「ふっ…マーキングね…」
やはり、彼は夫に対して妬いている、と思った。私は得意げになって続けた。
「ね、どうして "日曜なら会える" って、わざわざ掛け直してくれたの?」
「会いたいって言ったのそっちじゃないか」
「忙しそうだったじゃない」
「だから日曜日ならって言ったんだろ。勝手に電話を切るからさ」
両手で彼の頬を包んで見つめると、彼は笑みを浮かべた。
「遼太郎くんも会いたいって思ってくれたってこと、本当に嬉しい」
少女のような言葉。少し前の私であれば、こんな言葉、男に使うことはなかった。鼻で笑って一蹴されるのがオチだからだ。
けれど今は、本当に素直にその言葉が出てきて、自分でも驚いた。彼はそれにキスで応える。なんだかまるで本当の恋人同士のようだった。
夢にまで出てくる、艷やかで美しい彼の身体。
甘く蕩けるような口づけの後は、スッと目つきが変わる。
私を狂わせる、そのアンバランスな目に。
*
「うぁー。さすがに腹減った」
仰向けに寝転んで彼は言った。もう午後3時を回っている。私も全く同じだ。普段と違うシチュエーションのためか、それ専用のスペースのためか、4時間近く絡み続けていたことになる。何度も剣を振り上げられる彼は、さすがの若さゆえのバイタリティだが、受けた自分もあっぱれだなと苦笑いした。
彼はテーブルの上にあるメニューを手に取ると「カラオケBOXと同じだな」と、放り投げた。
「最近のカラオケBOXはそれなりに料理も凝ってるわよ」
「ふーん、行かないから知らない」
「付き合いで行ったりしないの?」
「行かないね。頭下げられたって」
「さすが遼太郎くんね。じゃあ、どこか外で食べて帰る?」
「時間、平気なの?」
「まだ平気よ」
私はベッドを降り、バスルームに入った。すると彼もついて来て「一緒に入ろ」なんて言う。
「恥ずかしいわ」
「嘘だろ? 慣れてるくせに」
「そういう遼太郎くんこそ慣れっこなんでしょう」
彼はシャワーをひねる。自分のこととなると、答えない。まぁ私もはぐらかしたけれど。
彼は湯温を見てから私の腕を引いて抱き寄せた。2人して頭からシャワーを浴びる。そして舌を出し、舐め合う。私の身体をまさぐる彼の手。結局また始まってしまう。彼の剣はとどまることを知らない。
その後、彼は入念に私の身体を洗ってくれた。
結局、ホテルを出たのは午後5時過ぎだった。彼は私の肩を抱き寄せ、来た時と同じように傘を差してくれた。
「ちょっと、連絡だけ入れさせて」
メッセージで夫に夕食の旨を尋ねると、電話が掛かってくる。文字を打つのが面倒くさいのだ。遼太郎くんが面白がって顔を寄せて来て邪魔しようとするのを慌てて制する。
帰国後も仕事で慌ただしくしていた夫は、今日がようやくゆったり過ごせるからと、手料理楽しみに待っていたと言う。流石に気が引けた。
「遼太郎くん、私は軽く済ませるにとどめておくわ」
「無理しないでいいよ。さっさと真っ直ぐ帰りなよ」
「でも」
「遅くなっちゃったもんな。俺、一人で飯食うから。旦那さんのところへ帰ってあげて」
唇を噛み、思わず彼を抱き締めた。
「やっぱりあなたと一緒に食事するわ。一人にさせたくない」
「ダメだよ。俺は平気だから」
「…あなたが好きよ」
「…」
「だからどうということはないけど、あなたを失うのは怖い」
「紗都香さん」
「また、会って。こんな風に」
約束がないと、怖かった。しかし彼は何も答えない。すがるように見上げると、彼はキスをして来た。温かくとろけるような舌の感触に嬉しさと一緒に寂しさがないまぜになって身体中に広がる。
やがて彼は私の手に傘を押し戻すと「じゃあ」と言ってフードを被り、駅とは反対方向の坂を駆け上がっていった。
彼もきっと、私と同じ…とまではいかずとも、私のことをある程度は想い、考えてくれていると、そう信じていた。
#6へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
