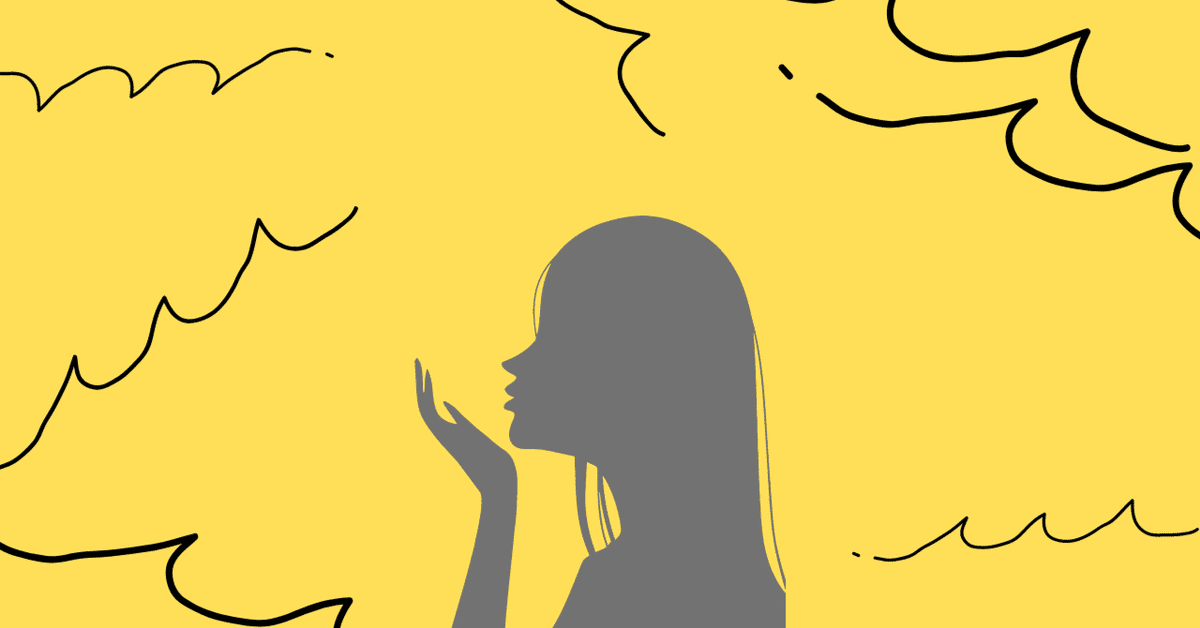
女性の健康課題の解決を女性だけに任せたくない理由
こんにちは。FUJIYAMA BRIDGE LABの石岡です。
婦人科へのアクセシビリティ向上と女性の自己決定をサポートするサービスの開発を行っています。
私たちが開発を行っているサービスは、生理や更年期など女性特有の健康課題の解決を目指しています。今回は、そのサービスの費用の出し手を誰に設定するのかということについて、考えをまとめたいと思います。
女に生まれた罰金…?と感じた出来事
生理に関する出費について私が考えた出来事をまずお話できればと思います。
私は20代半ばに生理が重くなり、婦人科で低用量ピルを処方してもらって症状が改善しました。それ自体はとても嬉しいことですが、処方してもらったピルを薬局で待っている時に、ふと考えたことがありました。
「3ヶ月に1回婦人科に行ってるけど、そのピル代にナプキン代…。いつも当たり前のように払ってるけど、なんか女性だけ負担するのっておかしくない?女に生まれた罰金じゃん…!」
たぶん機嫌が悪い日だったのだと思います笑
でも、自分では決められない「性別」によって出費が増えるのはなんだか納得行かない…という気持ちになったのは今でもよく覚えています。ナプキンは軽減税率の対象にもなっておらず、しっかり10%課税されています。生活必需品なのに!
私は保険適用の低用量ピルが体に合いましたが、人によっては保険が効かない低用量ピルを飲んでいたり、経血量が多くナプキンの消費が多かったりする人もいます。お金の負担に限らず、婦人科での待ち時間、生理用品を買いに行く手間、かさばるナプキンを持ち運ぶストレス、経血漏れの心配など、心理的ストレスまで広げると女性にかかる負担はもっと大きいように感じます。
生理に関する金銭的負担だけでも、もう少し社会全体でカバーできたらいいのにな、と感じた瞬間だったのです。
それではどんなビジネスモデル?
そんな出来事があったので、私が作るサービスでは、できれば女性個人からお金をいただきたくないと考えていました。開発中のサービスは、働く女性をターゲットにしているため、企業にアプローチするのがいいのではないかと思っています。お金の出し手が企業であり、その企業に属する女性が、福利厚生としてサービスを享受できるという形です。
となると、エンドユーザーである企業で働く女性の課題解決になるのはもちろん、お金の出し手である企業の課題解決も同時に行えるサービスでないといけない!
我ながら難しい選択をしてしまったと感じます…。
でもどうにかこの形を実現する方法がないか探索を進めていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
