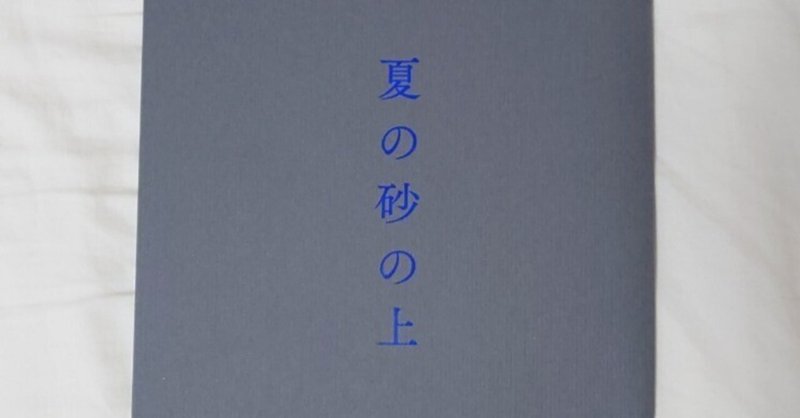
『夏の砂の上』感想
世田谷パブリックシアターで『夏の砂の上』を観た。およそ1年3ヶ月ぶりの田中圭の主演舞台。個人的にも久しぶりの観劇だ。短い感想を残しておきたい。
舞台は長崎。小浦治は一人息子を5歳で亡くし、勤め先の造船所が潰れ、妻に出て行かれた。坂の上の家で一人で暮らしている。雨の降らない暑い夏のある日、妹の阿佐子が娘の優子を連れて治の家へやって来る。阿佐子は博多で店を始めるから、夏の間に優子を預かってほしいという。16歳の優子を追い返すわけにもいかず、治は仕方なくつかの間の二人暮らしを始める。
とても地味な作品である。シンプルな衣装と舞台装置、ぽつぽつと紡がれる会話。特に治は「うん」とか「そう」とか、相槌ばかりだ。何かを語りかけるわけでもなく、疑問を投げかけるわけでもなく、あるいは観客に何かを委ねるようでもない。ただそこにある、というのが初めてこの作品に触れたときの感想だ。
ただそこにある寂しさ
田中圭が演じる治は寂しさそのものと言いたくなるような中年男だ。治の身には様々な「困難」が降りかかる。けれど彼はそれらに対して何もしない。正しく言えば何もしないのではなく、ただ暮らしている。治のあり方はこの作品のあり方そのものだと思う。
ドラマのお作法で言えば、主人公にはなるべく多くの困難に直面させるべきだという。たくさんの困難と向き合い、葛藤し、負けては打ち勝ち、どうにかこうにか乗り越えてゆく様子を目撃して、観客は心打たれ涙するものだ。
だが、治はそれらを乗り越えた先の希望を見出したりしない。小さな葛藤はある。静かな怒りもある。時には声を荒らげて、ちゃぶ台を叩くくらいの。
雨が降らない日が続き、水が出ないと告げる優子に、治は「辛抱だ」という。それは大変だ、早く水を汲みに行こうとは言わない。市役所に言えば水が出るようにしてくれるらしいと他人に教えられて初めて、そうか、じゃあ行ってみようか(それでもたぶん行かないのだ)、である。
彼はその困難を自ら取り除こうともせず、拒絶もせず、かといって受け入れるわけでもない。諦観、というのが近いだろうか。そう表現すると何だか孤高の人のようでかっこよく聞こえてしまうが、治の場合はどちらかというとかなしい中年だ。
たとえば私だったら、蛇口を捻って水が出ないことにいちいち腹を立てる。飲み水はもちろん、トイレだって流せない。食器も洗えない。役所は何をしてるんだ、と。しかし治は内心少しだけムッとして、でも次の瞬間には「しばらくの辛抱だ」と諦めて、ただの寂しい中年男に戻っている。きっと何かを失くすことに慣れてしまったのだろう。私が小さなことに腹を立てるのは、まだ手に入れるもののほうが多いからだ。もういくつか歳を重ね、失うもののほうが多くなったら、それはようやく大人になったということなのかもしれない。
治と周囲の人たちとでは、台詞のテンポも違っている。治以外の人々は、かつてあったことを忘れて、忘れたようなふりをして、前へ前へ進んでゆく。それでも治はたった一人で、自分の足元の砂が乾いて干上がるのをただ眺めている。そのうち砂が濡れていた跡もなくなって、風が砂をすっかりさらっていってもまだそこにいる。
渇きと雨
さまざまなものを失った治のもとへ突然やってきた優子の存在は、じりじりと日照りが続く空っぽの砂場に叩きつけられた夏の夕立のようだった。ひと夏の共同生活において、2人の間に特別な会話や交流があったようには見えない。それでも、治にとっての優子は薄れつつある亡き息子のとのつながりを思い出させる水となり、母の都合に振り回され生きてきた優子にとってもまた、乾ききってただそこにいるだけの治の存在は心地よかったのだと思う。
戯曲の台詞を表面的になぞれば、治は感情が抜け落ちてしまった男にも見える。だが実のところそういうわけではない。たしかに分かりづらいけれど、はっきり表に見せるわけではないけれど、本当のところではみっともなく怒っても泣いてもいる。そして亡き息子や優子に向ける目は優しい。
印刷された戯曲の文字を追うだけでは気付かなかった感情の色に、私は客席で気付いた。これが生きた役者が台詞を喋る、芝居の醍醐味なのだと改めて思う。治の人間らしさ、ややこしさ、可愛らしさが入り交じるのは田中圭だからなのだろうか。あと、山田杏奈の声。とにかく声が素敵だなと思った。
脱線ついでに蛇足だが、ラストで一度優子が戻ってくるところで、優子は本当は「行くな」と言ってほしかっただろうなと思う。ラブストーリーか何かだったら絶対言うところだ。治だから言わないけど。窓からの陽射しが眩しくて目を眇めても、そっと指の足りない手をかざすだけの治だから。
音について
これは何人かのフォロワーさんも言っていたが、もう少し小さな劇場だったらきっともっと良かったのに、と思うことがある。音だ。
蝉の声、鏡の割れる音、仏壇の鐘の音、机を叩く音、雨の音。それらを板の軋む音まで聞こえるくらいの小さな箱で聞いたらどんな景色が広がっただろう。木造の古い家は、たいていどこもかしこも薄っぺらくて、がたがたぴしぴしぎしぎしといつもうるさいイメージがある。SePTは結構広くて天井が高いから、そういう生活音は掻き消えてしまうし、そこに効果音が足されても何だか滑稽だ。
(もちろん劇場が小さくなるとチケット合戦がさらに激化するので、トラムだったらよかったのに、などとは言わない……)
ちなみに照明は個人的にすごく好きだった。治の白いタンクトップに光が反射するのも、後ろの色が時間の経過をわかりやすく表していて、それでいて美しいのも(そして私のように観劇に不慣れな人にもやさしい)。
おわりに
今回の私の観劇体験は「観察」に近かった。特に共感するポイントも、大きくうねるような感情もない。
ただそこに取り残されるようにぽつんと、小さなちゃぶ台の前に座る治の姿はとにかく寂しい。治が特別なわけではない。私も含めてこの世を生きるみんながそれぞれの坂の上で、あるかどうかもわからない砂の上でひとりだ。
それからここで「ナガサキ」の言葉の意味に触れることは避けた。避けるというか、私がそのことをわざわざ翻訳するまでもなく、治がかつて息子と暮らしたように、それは間違いなくあった。
あと10年か20年かしてこの戯曲に出会い直したらきっと違うものを観ると思う。
もしよかったら「スキ」をぽちっとしていただけると励みになります(アカウントをお持ちでなくても押せます)。 いただいたサポートは他の方へのサポート、もしくはちょっと頑張りたいときのおやつ代にさせていただきます。

