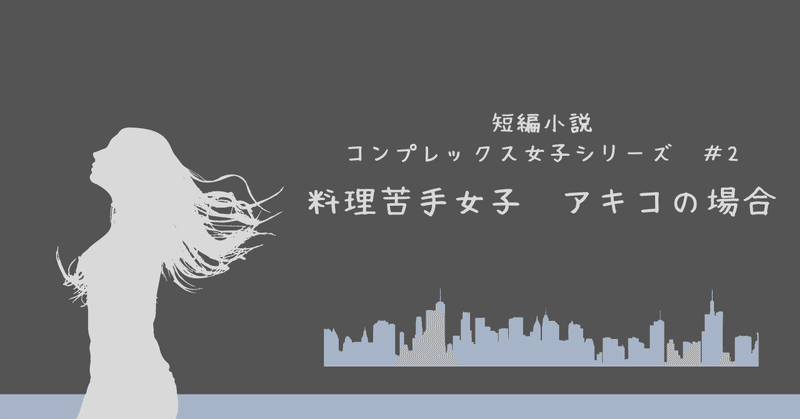
【コンプレックス女子たちの行進】第2話ー料理苦手女子 アキコの場合ー
第2話 料理苦手女子 アキコの場合
「おまえの飯は食えたものではない」
そんな捨て台詞を吐いて、アキコの婚約者は出て行った。入籍をするまえに、お互いの生活ペースを知りたいねという話になり、同棲を始めた。
同棲する前の付き合っている間は、違和感というものに気が付かなかった。共同生活をしていくうちに、少しずつ歯車が合わなくなっていた。
最初は少しテンポが合わないなと思った。
でもそれは、他人同士が初めて共同生活をするのだし、少しずつチューニングを合わせていくものだろうと深くは考えなかった。
やっぱりおかしいなとアキコが思い始めたのは、
お互いが仕事から帰ってきて、食卓を共にすると、婚約者が明らかに不機嫌になっていると気付いてからだ。
たまにだったら、仕事が疲れているんだろうなと思い過ごすことができるのだが、これが毎度毎度となるとどうもおかしい。
それから、婚約者は飲み会があるから、仕事で遅くなるからと先に晩御飯食べといてと連絡することが多くなり、一緒に食卓を囲む回数が少なくなってきた。
食卓のすれ違いは、その他のすれ違いにも広がっていく。
一緒の寝室で眠っているのだが、
ふたりで一緒に眠りにつくというタイミングも減っていく。
それぞれが別々のタイミングでベッドに入り、起床時間もバラバラ。
「おやよう」も「おやすみ」も「いってきます」も「おかえりなさい」も
その挨拶さえも毎日の生活で、交わされることがなくなっていった。
気付いたときにはアキコと婚約者との間には、取返しが付かない隔たりが出来ていた。
なぜこんなにうまくいかなかったのだろう。
同棲するまえは、ふたりでデートするのも楽しく、どちらかの家でお泊りするのも楽しかった。
一緒にいるのが当然だし、これからもふたりで手を取り合って人生を歩んでいくものだろうと思っていた。
それはアキコだけでなく、婚約者もそのはずだったと思う。
だからこそ、プロポーズをしてくれたのだろうし、両家の挨拶も済ませている。
あとは、正式に籍をいれるまでのカウントダウンだと思っていたのにまさか別れることになるなんて。
別れてから、一緒に住んでいた部屋を解約した。
数カ月しかその部屋で過ごすことができなかった。
ふたり暮らしから、またひとりぼっちで住むための場所に引っ越した。
婚約者がいなくなってから、台所に立つ気力がわかなかった。
自分の食事を用意するのもおっくうで、というか、食欲がそもそもわかなくて、反比例するようにお酒の量が増えた。
ひとりぼっちの部屋に帰るのがしんどくて、会社帰り、自宅の最寄り駅の商店街にあるひとりでもふらりと入りやすい居酒屋「タチドマリ」でお酒をひっかけてから帰るのが習慣になった。「タチドマリ」はテーブル席だけではなく、カウンターも少しあり、そこではアキコのように、ひとりで食事やお酒を飲んでいる客もいた。店員も慣れ慣れしいわけでもなく、かといって冷たいわけでもなく、ちょうどよい距離間が心地よかった。アキコが来店するとどうぞと言って、カウンターに案内してくれた。
そんな生活を半年ばかりしていた。
季節はめぐり、12月になった。
いつものとおり「タチドマリ」のカウンター席で、お酒をちびちび飲みながら、スマホでSNSを見ていた。
すると、タイムラインに「結婚しました」という元婚約者の結婚報告の投稿がされていた。そこには元婚約者とその相手の女性の2ショット写真が映っていた。
アキコはショックを受け、「どうして」「あなたひとりだけが幸せになっている」「わたしはこんなにみじめなのに」「っていうか、私と暮らしていたときからその女と関係を深めていたの?」と様々な感情が渦のように押しよせ、涙が出てきた。
お酒が入っていて少し酔っていたからだろう、涙が一粒落ちてからは、それがトリガーとなり、涙がとめどなく流れでてきた。目に涙がたまり、涙として落ちなかった部分は鼻の中に流れこみ、鼻をすすった。カウンター席は調理スペースの前だったが、調理スペースとカウンター席の間は少し高くなっていて、ちょっとした壁になっているから、普通に座っているならば、調理スペースにいる店員と目が合うことはなかった。
真正面から誰かに見られる心配もないこともあったのだろう、アキコは流れるにまかせて、涙を流し続け、なるべく音が大きくならないように気をつけながらも鼻をすすった。
店内は音楽が流れていたし、テーブル席もそこそこ埋まってていて、客たちも談笑していてガヤガヤしていたから、だれもアキコを気に留めることもないだろう。
そう思っていたが。
「ねえ、すすり泣きが気になるんだけど」
しばらくすると少し離れたカウンターで座っていた男性客がアキコに話しかけた。
「ごめんなさい」
謝るアキコの声は涙声でゆらいでいた。
男はまいったなぁという表情をして尋ねた。
「いや、うん、謝らせたかったわけではなくて……。さっきから酒ばかり飲んでいるけど、食べないの?」
「あまりお腹がすかなくて……」
「いつも食べてないよね?」
「えっ?」
また驚いて、アキコが男の顔を見ると
男は少し気まずかったのか、頭をぽりぽりと掻きながら
「あ、いや、俺もよくこの店にくるからさ、お姉さんいつもいるなと思ってたから……」
「……すみません、気づいていなくて」
「うん、まあ、いつもひとりの世界に入ってる感じだから、そうだろうね」
男は、カウンターの上部にある黒板の、「本日のおすすめ」とかかれたメニューを見て
「あれとか、おいしいよ。旬だしね~」
話の流れから男とアキコはカウンターに並んで食べ物を頼み、一緒に食べることになった。
話をきくと、男は「タチドマリ」の料理人のひとりが友人で家も近所だからということでよくお店に来ているらしく、また男自身もレストランのシェフだという。
「ここ、結構素材にこだわってるんだよ、友達の地元の漁港からとれた新鮮な魚が届いて、それがすごくうまいんだよ」
ちょうどタイミングを見計らったように、店員が、ぶりの刺身を持ってきた。
男が「タチドマリ」のメニューのすばらしさ、この料理がおいしいなどという話を聞いていると、あまり食欲もなかったアキコも食べてみたいと思うようになった。
ぶりは脂がのっていて、つやつやと光り、それを眺めていると、アキコの箸が自然と動いた。
「おーいいね!」男が嬉しそうに言う。
ぶりを口の中にいれると驚くようなとろける食感。
「……お、いしい」
「でしょ?」
また涙があふれてきた。
「…え、え、また泣いてる。美味しすぎて泣いてる? それは料理人も嬉しいことだろうね」
男の言うように、ぶりの美味しさで泣いているわけではなかった。
もちろんぶりは美味しかったけれど、それよりも様々な感情が胸からぐっとこみ上げてきたからだった。
消化しようとも消化できずずっと体の中で「どうしてこうなってしまったんのだろう」という後悔、いち早く立ち直りたいという焦り、孤独な時間を持つことで痛みが引いていくのをただ待っているもどかしさ、「やっぱり誰かに優しくされたい」という願望。
様々なものが涙として溢れたのだった。
男はアキコを気にかけつつも、他にも注文して目の前に提供された料理をもくもくと食べた。アキコもそれに倣うようにもくもくと食べた。
めずらしく、いつもより食べている気がする。
いつもお酒と一緒にちょっとしたつまみを食べるだけだったからこそ気が付かなかったけれど、男が言う通り、「タチドマリ」の料理は美味しかった。
もくもくと食べていると、アキコと男が座っているカウンター席の近くにあるテーブル席の賑やかな笑い声が聞こえてきた。
仲間うちで忘年会をやろうと小グループで集まったのであろう、同年代の男性3人と女性1人という4人グループが仲良く談笑していた。
男性のひとりが
「ケイコは最近どうなの?」と尋ねた。
ケイコと呼ばれた女性は「いや、だから、さっき散々仕事の話したじゃない」と返すと
「いやいや、そうじゃなくて、男関係の話」
「言わせないでよね。仕事以外にネタなんてないわよ」
「またまたぁ~、隠れてよろしくやってるんでしょうよ」とひやかす声
「まあ、でも、まじめな話、そろそろ現実とタイムリミットみたほうがよいよなぁ」
「自分たちはもう結婚してるからって、余計なお世話だよ」
ケイコと呼ばれた女性は少ししてから、席を立ち、つかつかとお手洗いにいった。
「いや、おまえ、その言い方デリカシーなさすぎるぞ」
「確かに言い方ストレートすぎたけど、やっぱさ、家に帰って奥さんがいてるのはいいものじゃん」
「まぁーな、確かに。子どもも癒しだしな」
男性たちはそう話し合っていた。
そんな、テーブル席の声が聞こえていたのかわからないけれど、男はアキコに尋ねる。
「ここの店は居心地がいいけど、そんなに頻繁に寄り道をして帰ってたら心配をする人いるんじゃないの?」
「……心配してくれるはずの人がいなくなっちゃったんですよね」
涙が流れ落ちきり、アキコは少し落ち着きを取り戻していた。
「そうなの?」
「さっきね、別れた婚約者が、別な人と結婚したってことをSNSで知ったんですよ」
「あぁ、なるほど、それで」
「もう過ぎてしまったことだし、さっさと立ち直らなきゃなんですけどね、私はずっとグタグタどこにも行けずなんですよね」
男はうーんと少し考えたあと、
「んー、まあ、俺うまく言えないけれど…。まさかなことは人生どこでも起きてしまうこともあるから、防ぎようないこともあるし、今は、目の前の美味しい料理のことだけを考えてたらいいじゃない?」と答えた。
「そうですね、少し溜め込み疲れてたのかもしれないです」
「うん、目の前の料理を味おう。今感じているおいしさは真実だから」
男とは、そのあと、とりとめのない話をして、別れた。別れ際、お互いの名前を教えあった。男の名はリョウタというらしい。
アキコはひとりで住む部屋に帰ったが、いつもより少し気持ちがすっきりしていた。話し相手がいたことが救いだったのかもしれない。
それから、アキコはタチドマリでたびたびリョウタと会い食事を共にするようになった。
リョウタと親しい関係になるのはそれほど時間がかからなかった。
あるとき、タチドマリでいつものように食事をしたあと、リョウタの家に誘われた。
道中、アキコの手を握ったリョウタの手は力強く、肉厚さを感じられた。途中絡められた指先も太くしっかりしたものであったが、同時にどこか繊細さも感じられた。
シェフの手とはこんな感じなんだという発見をしながら、リョウタの家にたどりついた。
「ごめん、そんなに片付いてない」
玄関から短い廊下を抜けるとリビングダイニングスペースと少し広めのアイランドキッチンがあった。
ダイニングテーブルには、何かを書きかけているのか、メモの紙が散らばっていた。リビングにあるソファには、脱ぎっぱなしになった衣服が雑然と置かれていた。
ソファ前のローテーブルには、マグやら読みかけの雑誌が置きっぱなしになっている。
確かにリョウタの言うように片付いているわけではない。
奥にはベッドルームがあり、掛布団やシーツがしわしわになっていて、床には脱ぎっぱなしになったパジャマが丸まっていた。
リョウタは「すぐにかたす」からと言って、雑然としたものを片付け始めた。
アキコはダイニングテーブルにあるメモの紙を見た。
そこには、簡単な料理のイメージイラストと、材料と工程の走り書きがされており、何かのレシピのようだった。何度も書いては消し書いては消しているのだろう、紙はくしゃっとなり、修正の二重線が引かれ、別の素材や工程のメモが追記されている部分もあった。
「あ、それは、ちょっとはずかしいな…」
アキコが、メモ紙を見ていることに気づき、リョウタは急いでそのメモ紙をまとめて、近くにあった引き出しに仕舞った。
リョウタは頭をポリポリ掻きながら
「……まだできてないレシピのアイディアの走り書きなんだよね。なんだか手紙を読まれているようで照れくさい」
それから、また、部屋の片づけに戻った。
アキコは、キッチンに移動した。キッチンは他のスペースとは異なり、整然としており、コンロからシンクまでぴかぴかだった。
「キッチンは使ってないの?」
意外だったからアキコが尋ねると、奥のベッドルームを片付けていたリョウタが「まさかっ、この部屋の中で一番過ごしている場所だよ」と答えた。
「へぇ、驚いた。一番きれいだから」
「まぁ、キッチンだけはちゃんと綺麗にするよね。それを生業にしているわけだしね」
「ふーん」
「あ、ソファかたづけたし、座ってて」
それからリョウタはコーヒーをいれるからといって、キッチンに行った。
アキコがソファで座って待っていると、しばらくして、電動ミルのガーっという音がし、やかんの蓋がカタカタと音を立てた。
しばしの沈黙の後、やかんからドリッパーに湯が注がれる音とともに、香ばしいコーヒーの匂いが漂ってきた。
アキコの場所からはリョウタの手元は見えないが、コーヒードリッパーに目を落とす伏し目がちになっているリョウタはどこか色気があった。
コーヒーを淹れ終えたリョウタはアキコの隣に座った。
「はい、どうぞ」
差し出されたコーヒーを飲む。
「おいしい」
「ありがとう。これもね、友達の自家焙煎珈琲豆やさんおすすめのでね……」
おいしいという言葉を聞くとリョウタはいつもにっこり微笑み、その食べ物飲み物のエピソードを聞かせてくれる。素材がどうだとか、友人のだれだれがつくったものだとか、調理方法をこうすることでより美味しくなるのだとかを教えてくれる。
「いいね、リョウタは料理が大好きで食べることも飲むこともたくさんの喜びがあって…」
「アキコは料理好きじゃないの?」
「好きじゃないというか、下手くそなんだよね。元婚約者もおまえの料理はまずいって言って出てったからねー。もう自信喪失しちゃって、しばらくキッチンに立ってない」
「失礼なやつだね。人が作ってくれた料理をそんな風に言うやつは。ちなみにソイツは、アキコに料理を作らなかったの?」
「うん、俺、料理作れないから、アキコがやってよって感じだったの」
「ありえないね。料理を作るひとへの敬意が足りない。けしからんよ」
「でもね、私もそこまで料理得意じゃないから……。レシピ見て作ってたんだけど、工程間違ったり、他の同時並行で作業したら、焦がしちゃったりとか。びくびくして火加減を見てたら、焼き具合がわからなくて、生焼けになっちゃったり。そりゃ、愛想つかれるよねと。まあ、料理だけじゃなく、お互いすれ違ってたっていうのもあるんだけど…」
怒りが止まらないようで、リョウタは続ける。
「だいたい、まずいって言葉ですませるのが解像度が低いんだよ。もう少し塩気がほしいとか、火加減をどうしてほしいとか、そういう風に言わないそいつがだめだ。それに、自分で料理をするわけじゃないのに、批判だけする。文句があるのなら、自分が作ってから言えよっていう。俺に言わしてみれば」
「…うん、ありがとう。なぐさめてくれて」
「人はね、食べずに生きていくことはできないわけで。料理をつくるっていうのは、食べる人が明日も生きていけるように、エネルギーをつくってるわけじゃん。そういう優しさが料理の中には含まれているわけだよ。その優しさを当たり前のものとして感謝できないのがだめだよ」
「ありがとう。そういう風に言ってくれて嬉しい。すっきりした」
「あと、料理のコツなら、俺がいくらでもアドバイスできるよ」
「そうだね、頼ろうかな」
「そうだそうだ、頼れ頼れ!」
「ふふふ」
アキコとリョウタはしばらく笑いあった。そして、笑いが落ち着いたタイミングでリョウタはアキコにキスをした。
ベッドルームに行き、抱き合った。リョウタはがっしりとしていて、力強く体温も高かった。包み込まれていると、これまで凍えてかじかんでいたものが、じんわり温まっていくようであった。こんな安心感はしばらく感じていなかったものだった。
心地の良い眠りについていると
隣で寝ていたリョウタがゴソゴソと起き上がる気配で、アキコも目覚めた。
まだ薄暗く、日が昇る前だった。
「あ、ごめん、起こしちゃった?ちょっと仕込みに行かないとなんだよね。ゆっくり寝ていてくれてもいいし、それか、ちょっと早いけど朝ごはん一緒に食べる?」
「うん」
リョウタはキッチンにたち、フライパンに火を付けて、ベーコンを手早く焼いた。
アキコも何か手伝ったほうがいいのかもと思って、リョウタのそばに近寄った。
「あ、じゃあ、そのトースターに食パンセットしてくれる?」
それから、ベーコンを焼いたあと、リョウタはボウルで卵をたっぷりかきまぜたものを空いたフライパンに卵液を流し込む。菜箸でぐるぐう手早くかき混ぜ、頃合いをみて、腕のスナップを聞かせながら、卵を巻いていく。そして、白い皿の上に黄色くふわふわしたオムレツが乗せられた。
手さばきがみごとで、アキコがおぉっという。
「いいね~」
リョウタとアキコが一緒にダイニングテーブルに並んで座った。
「「いただきます」」
出来上がった、オムレツはナイフとフォークで中を開けるトロッと半熟のたまごがあふれ出した。食べると口の中でふわとろが広がる
「ホテルの朝食みたい。幸せ」
「いいね~、幸せとは何よりだ」
朝食を済ませて、手早くキッチンを片付けたあと、リョウタは家を出ていく。
「まだ寝てていいからね~」
お腹がいっぱいになった多幸感に包まれながらも、リョウタの匂いがまだ残る、ベッドの中でアキコはまどろんだ。
しばらく感じることができなかった満たされた感情だった。
……「料理苦手女子 アキコの場合」のお話はここまで。
次はタチドマリにいたケイコの物語に続く。
いいなあと思ったらぜひポチっとしていただけると喜びます。更新の励みになります。また今後も読んでいただけるとうれしいです。
