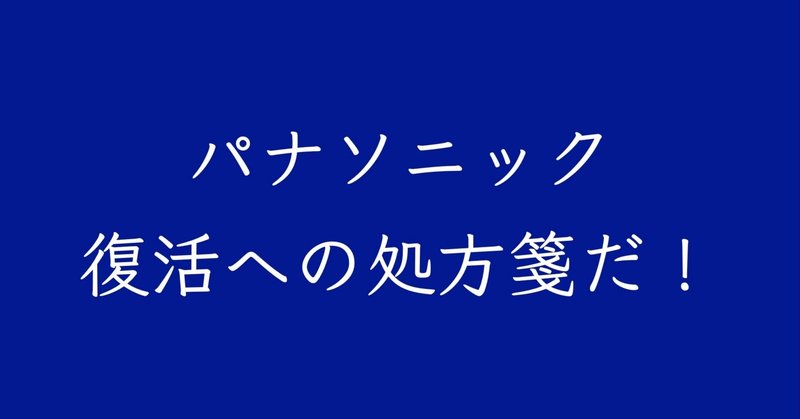
パナソニック復活への処方箋
○月△日
以前、パナソニックへの処方箋を示すと書いて、放置していました(ボクのサピエンス全史(第六章:水道哲学は捨て去れ))。そろそろ書きましょう。
その他、元パナソニック社員として、それなりに書きたいことがあって、いくつか記事にしています。
ソニーはなぜ復活できるのか 愉快なるヘンタイを育めるから
パナソニックの凋落を世界史と日本史から俯瞰する
素直になるには素直になれなくて
さて、とは言いつつ、この会社にできることは限られています。現実的にできることじゃないと、処方箋の意味がありません。
まずイノベーション(革新)は起こせないでしょう。残念ながら、そういう教育を受けてません。起こせる風土がありません。起こせた人もいません。
そもそも松下電器、もしくはパナソニックを就職先として選択する時点で「守り」の意識が高い人たちが大多数です。そんな人たちからはイノベーション、つまり「革新」は起きないでしょう。
というか100年を越える歴史がありますが、業界を一変させた革新事例は一つもありませんでした。会社が掲げる毎年の経営方針に「革新」という言葉が何度も盛り込まれていましたけど、「革新」できたことは、ボクの在籍中28年間には一度もありませんでした。決してゲームチェンジをしたり、新たな土俵を見つけて一番乗りなどはしてこなかったのです。
旧”松下電工”については意見を保留します。反論の余地があるので。
ちなみにパナソニックは近年、旧”松下電器産業”とは別会社の”松下電工”、当時の社名は”パナソニック電工”を吸収しました。これら2つの会社は、同じ起源でありながら、別企業(それぞれが上場企業)としての歴史が約60年と長く、文化風土がかなり違った会社でした。それについて、いずれ書くかもしれません。
革新=イノベーション、ならぬインベンション、つまり発明ならできる会社でした。メーカーなので当たり前です。発明と言っても、ほとんどが改良・工夫です。その改良を最も得意としてきました。
どこよりも小さいとか、どこよりも軽いとか、静かとか、省エネとか、そういう数字競争ならお手の物だったのです。2−3番手として後から乗りこんで、先の人の真似をする。
「真似シタ」とも揶揄されました。他社の真似をして、先人より良いもの、より数字を凌駕するものを作ることなら得意だったのです。そうして大概の土俵で1番になりました。
しかし、後から土俵へやってきたけど、1番どころか、全く歯が立たなかった事例があります。ゲーム機とスマートフォンです。これらを商品化し販売していたことさえ、ほとんど知られていないかもしれません。
これらは、あっという間に駆逐され、市場から消滅しましたので。
どうして生き残れなかったのでしょう。
これらは、そこに数字競争が無かったからと考えています。どのスペックを上げたら他社を凌駕して勝てるのか、そんな数字競争の世界があれば何とかなったのでしょうが、ゲーム機やスマホにとって、数字スペックは二の次でした。
他社が出しているから自分らもゲーム機とスマホを真似をしながら世に出した。
では次はどうすればいいのだ。どの数字を高めたら勝てるのだ。
と、オロオロしている間に取り残されてしまったのです。
さて、そういう会社です。今ある製品の数字競争しかできません。
逆に言うと数字競争なら勝てるのです。なので数字競争に持ち込む戦略で勝っていくことしかないと考えています。
では新しい価値が模索されている現代で、数字競争というレッドオーシャン見え見えの世界で生き残れるでしょうか。
一つだけ生き残れそうな数字戦略があります。それは、圧倒的な「品質」つまり「堅牢」「高耐久」です。とにかく壊れない、長く使える、それがパナソニックなのだというブランドにするという戦略です。もちろん世界を相手に。
価格が1.5倍高くても2倍長持ちし、2倍高くても3倍長持ちさせる。得意な数字競争です。それを選ぶ消費者はいるはずです。
高耐久は環境の訴求ができるからです。製品が2倍長持ちすれば、その製品が廃棄される量として、従来よりも半分となり環境負荷が下がります。環境意識の高い人たち、ミニマリストなどに指示されるでしょう。
また高齢者にとっても安心できる戦略です。70歳で家電を買い替えたお年寄りにとって、10年持たない製品寿命では不安です。
家電のコモディティ化(雑貨化)が進んで低価格競争となっている中で、中途半端に高くて中途半端な品質ではダメです。圧倒的に高耐久に寄せるのです。パナソニックだけ違う世界にいるんだと思わせるのです。そんな信頼を得るのです。おそらくそれができるのは世界でパナソニックだけでしょう。
全商品をすぐに高耐久とするのは難しいでしょう。最初は一般と高耐久タイプの並立になるはずです。そしていずれそのノウハウは蓄積され転用され、一般向け商品も耐久性が向上していくと思います。廉価版のエンポリオであっても、他社に比べたらずっと高耐久高品質イメージを目指すのです。つまりジョルジオ・アルマーニを作って、ベースをエンポリオ・アルマーニにするという戦略です。
また長く使ってもらうのであれば、機能はシンプルにして、より使いやすさを追い求めないといけないでしょう。デザインも飽きのこないものにする必要があります。残すべき機能とは何か、使いやすさとは何か、飽きのこないデザインとは何かを追求することになります。つまり商品企画力やデザイン力も上げないといけません。
本当に消費者が求めているのは何か、数字以外の何かを、今まで以上に深く考えるようになります。自分たちで大変な負荷をかけているから必然です。
その深く考えることが、脳を鍛え、次の価値を生み出すことになるかもしれません。つまりイノベーションを生み出すトレーニングになるのです。ブランド力と信頼を得ながら、自分たちも鍛えられ、新たな価値を生み出す力を手に入れるのです。
あと、新製品発売のサイクルは長くなります。市場の支持を得られれば、今までのように1−2年おきに新製品を出さなくてもいいはずです。目先のマイナーチェンジ(実は何も進歩していないことがほとんど)は意味がなくなります。
4−5年ごとのメジャーチェンジでよいなら、本質的な技術開発にリソースを注力することができます。(現場は、毎年の消費者の目先を変えるだけの些細な開発競争に疲弊していました)
製品寿命が長くなれば、買い替えサイクルも長くなって、自分の首を締める行為だという反論意見があります(実際ありました。つまり在籍時代に既に何度か提案していたのです)。不誠実な意見です。売上が落ちても、シェアと信頼を獲得すればいいのです。
以上がボクの考える処方箋です。
しかし、実はもうひとつ、忘れてはいけない重要な、ある施策があります。これを高耐久と同時に遂行する必要があります。
それは、例えこの高耐久を目指さないとしても、イノベーションを起こすには必須の方策と考えているものです。つまりこの会社がイノベーションを起こせなかった原因の核心を突いたものです。革新の核心です。本当の処方箋はこちらかも。
要点だけ書こう。「フェールセーフネットを準備しなさい」だ。
まさしく現場で実体験に基づいた理論なので、それなりの信頼性はありますよ。
さあさあ、詳しく知りたきゃ訪ねておいで。
コンサル料は安くしてあげるよ。それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
