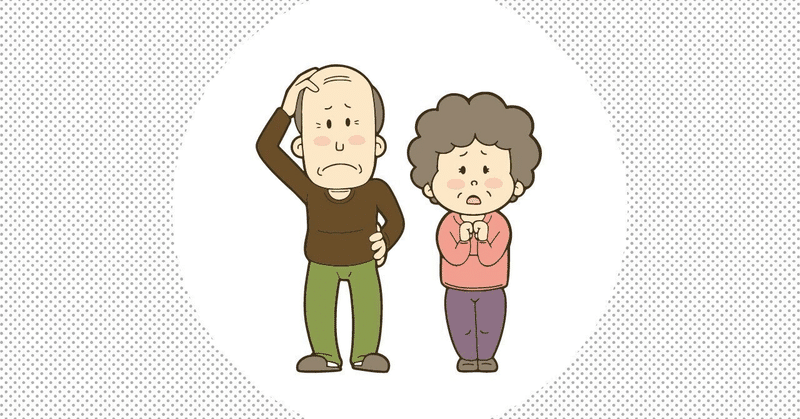
介護の利用者負担は「介護を必要とする」から起きる
今回はこの記事を見ていきましょう。
介護の利用者負担2割の拡大、議論膠着 所得上位20%→30%が焦点 物価高騰などで判断難航
【記事の概要】
・65歳以上の第1号保険料について、高所得者を上げて低所得者を下げる案を改めて提示。
・2割負担の対象者を拡大することの是非を論点とし、後期高齢者医療制度では「所得上位30%」とより広く設定されていることを紹介。
・対象者を「所得上位30%」まで広げるよう促す声がある一方で慎重論も少なくない。
・急激な物価高騰や他産業の賃上げなどで状況が複雑化したほか、「異次元の少子化対策」の財源論も含めて幅広く検討する必要性が生じたこともあり、結論が今年末まで先送りされた経緯がある。
・今後の衆議院解散、総選挙を踏まえると政治状況によって判断の難しい問題となっている。
【所感】根本原因と向き合わない限り、誰かの負担は必要
おそらく多くの方が「2割負担はイヤ〜😨」と思われたことでしょう。
「異次元の少子化対策」によって社会保障費から2兆円削って補填する話は、以前記事に取り上げました📝
「子どもの未来を守るか、高齢者の今を守るか」という二択を迫られている状況で、
「子どもと大人なら、大人の方が財産に余裕があるだろう」
と、介護の利用者負担2割を拡大させる話になったと見られます。
そもそも医療を必要とする現状を改善していけば(すなわち医療費を緩やかに削減できれば)子どもと高齢者を天秤にかけずに済むわけですが、
「今の日本で『健康』でいることは難しい」
というのは、食や医療の問題、第一次産業、近代史等と向き合うことで見えてきます😔
もしかしたら「要介護状態になる」こと自体それらと関係があるかもしれず、表面上の負担額の議論も必要ですが、「根本原因は何か」を分析することも同じように必要だと思います。
どうあっても『財源が足りずに誰かの負担が必要となる現実』は今すぐには変えられず、「どれだけ負担するか」の議論は問題の先延ばしになるのですから。
より「生きる意味を求められる時代」へ
「人が老いる以上、介護は誰しも必要となる」とよく言われますが、それは
「0歳における平均余命」の『平均寿命』
が年々伸びているのと比較して
「介護が必要な人の割合(国民生活基礎調査 1986~1998年)、もしくは手助けや見守りが必要な人の割合(2001~2010 年)」の『介護不要寿命』
これが男女ともほぼ横ばいであることから、
「平均寿命が伸びるほど介護を必要とする期間が増えている」
という統計上の事実をもって言うことができます😧

加えて
「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」の『健康寿命』
は平均寿命と並行する動きをとっており、
「現行の健康対策は『人を健やかにするもの』というより『人を生き永らえさせるもの』ではないか」
と見ることができます。
ひるがえってそれは
現代は全ての人に「(自分が)生きる意味とは何か」の答えを持つことが求められる時代である
とも言えます。
なぜなら「主体的には生きられない期間」の中で
「なぜ自分は生きているのか、あるいは生かされているか」
の答えを持ち続けられることが自分の心身を健康に保つ基盤となるからです。
(そしてその意味を「たすけ、まもる」のが本来の『介護』です)
これは、介護現場に長く立つ人ならば誰もが『人生の最期』を見て、天寿を全うされるまでの過程と深く関わっているはずですから、よくわかることかと思います。
この他にも介護ブログや読書ブログを運営しています。
今回の記事に共感してもらえたり、興味を持ってもらえたなら、ぜひご覧ください☺️
またnoteのメンバーシップではダイエットコーチングを行なっております。併せてご覧下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
