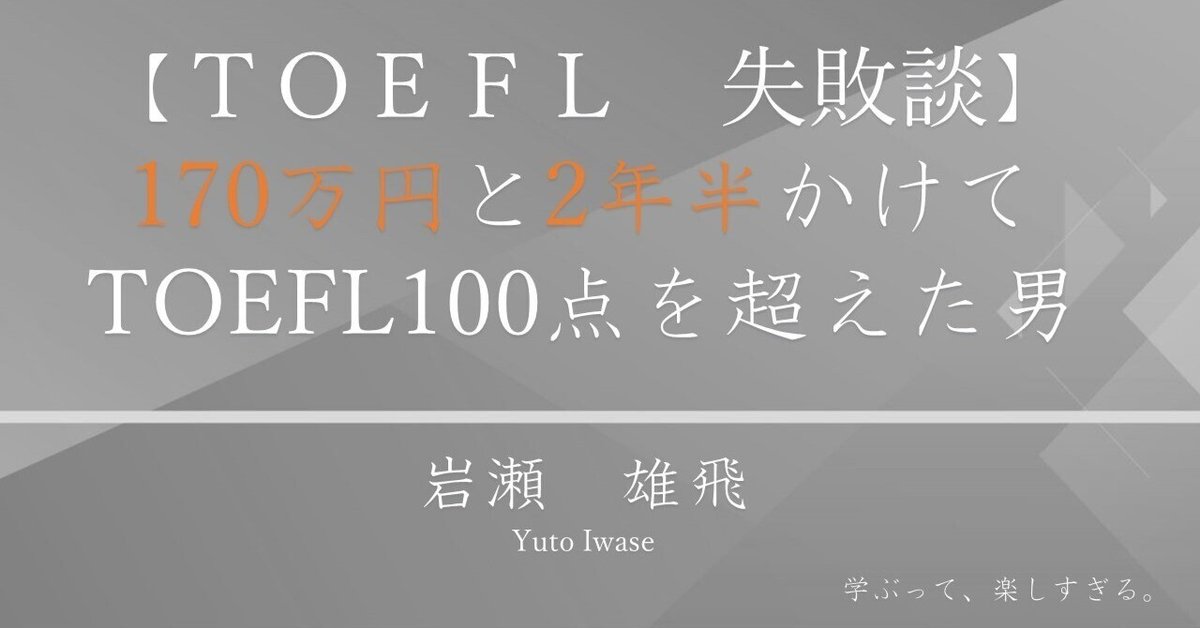
【TOEFL 4つの失敗談】170万円と2年半かけてTOEFL100点を超えた男
「学ぶって、楽しすぎる。」-弁護士の岩瀬雄飛です。
本noteでは学ぶことの面白さや学習のノウハウ等を発信するとともに、自分が学んだことの記録を発信しています。
今日のテーマは「TOEFL 失敗談」。
私は2021年3月からTOEFLの勉強をはじめ、2024年10月末日に目標であった100点をなんとか超えることができた。その期間なんと2年半である。また、それまでに要したお金を計算すると、少なく見積もっても170万円を超えていた(TOEFL受験費用、スクール、家庭教師、英会話、テキスト代等)。
おそらく、正しい方法で学習すれば、時間でいえば1年、お金でいえば100万円は出費を抑えられただろう。同じ失敗を繰り返さないために、読者の皆様が私の失敗談から教訓を得ていただけると幸いある。
失敗談① TOEFL受けすぎた
私が100点を超えたのは28回目のことである(1回目は70点強)。初試験の日から単純に期間で割っても1か月に1回は受けており、2週連続で受けることもあった。
しかし、当然であるが短期間で点数は大きく変わらない。そのため、短期間のうちに何度もTOEFLを受ける必要はなく、それは時間とお金の無駄である。しかし、頭では分かっていても、特に期限が近付いてくると、マグレでもいいから100点超えたいと、回数を重ねるようになってしまっていた。
TOEFLには各セクションの最高点を合計した点数であるMy Best Scoreが導入されている。しかし、多くの大学ではこのMy Best Scoreは正式なスコアとして扱ってくれず、1回の試験で各セクションの点数を揃える必要がある。
これがとても難しい。Speakingができた回に限ってListeningや Writingの点数が低いということはよくあるからである。点数を揃えるために何回も受ける(TOEFL界隈では「ガチャを回す」という)のは、すべてのセクションが高水準で安定的にとれるようになってからで十分である。それまでは場慣れやモチベーション維持のため、3か月に1度受験すれば十分であったであろう。
失敗談② 目標の設定の仕方が悪かった
2021年3月、私は、「1年半以内に、TOEFL100点を超える」という目標で勉強をはじめた。2022年秋までにTOEFL100点をとれば2023年の秋学期から米国留学を開始することができるからである。
しかし、多くの人が経験したことがあると思うが、最初に立てた目標は実現しないことが多い。大学受験において、早慶を目指していたが、秋くらいにMARCHに志望校を変更し、実際MARCHを受けたが合格できず、滑り止めの日東駒専に入学した、というケースはよくある事例であると思われる。
早慶を目指すのであれば、少なくとも1年前の春の時点では東大を目指すべきである。実際には国立と私立では出題傾向や試験科目が全く異なるが、努力量の観点でいえば、東大に合格する努力量があれば早慶合格にはおつりがくる。
私の場合は、「1年以内に、TOEFL105点を超える」という目標を立てるべきであった。この目標を実現するための努力をしていれば、それよりも容易な「1年半以内に、TOEFL100点を超える」は達成できたであろう。
また、デッドラインを目標としていたのも筋が悪い。1年半以内というのは、その翌年に留学するための期限であるし、TOEFL100点も各主要なロースクールが要求しているミニマムのスコアである。
このようにギリギリのラインを目標とした場合、条件が少し変わっただけで実現は難しくなる。例えば1週間体調不良で勉強できなかった、たまたま最後の試験の直前と仕事の繁忙期が重なった、等である。また、2023年7月からはTOEFL新形式が始まったように、試験側の条件が変わり、その対策を追加で行う必要が生じることもある。
失敗談③ 社会人の勉強法をしなかった
私が予備試験に合格したのはロースクール3年生のとき、司法試験に合格したのはロースクール卒業後である(当時は現在と異なり、ロースクール最終学年で受験することができなかった)。そのため、TOEFLは私が社会人になってから初めての重い試験であった。
仕事をしていると可処分時間はもちろん、可処分エネルギーも学生のときとは大きく異なる(後者については老いも関係する。)。やはり社会人には社会人なりの勉強法が必要であろう。自分は無意識のうちに学生のときと同じような勉強法を続けてしまったため目標の実現まで時間がかかってしまった。
具体的には、「重要な点に絞る」「スキマ時間をもっと有効活用する」等である。学生にはあって社会人にはない「時間」をどのようにカバーするかが社会人の学習には必要であると思う。
失敗談④ 戦略の立て方が悪かった
TOEFLはReading、Listening、Speaking、Writingが各30点の、合計120点の試験である。日本人の多くは、SpeakingやWritingよりもReadingとListeningが得意であるため、この2科目で満点に近づけることが王道である。
しかし、私はListeningの勉強を軽視していた。特に理由があるわけではなく、単純に私がListeningが苦手だったため学習を避けていただけである。その結果、Speakingでは話したくても話す内容が理解できていない、Writingでは書きたくても書く内容が理解できていないということが頻発した。ListeningはReading以外のすべてのセクションで必要となるスキルであるので、Listeningのスキルを伸ばすことはTOEFL攻略において必須の課題である。
他方で、Speakingを重視しすぎたことも敗因である。私は、司法試験の成功体験を踏まえ、多くの日本人が苦手なSpeakingに注力した。しかし、そもそも「相対的な」試験ではないTOEFLにおいて他人との差別化は不要であった。TOEFLは自分ができたかどうかのみで判定され、他の人の点数によって自分の点数が変動することは基本的にはない(たまに点数調整が行われることはある。)。
また、私も日本人であり、例に漏れずなかなかSpeakingの点数は上がらなかった。Speakingについては「Speakingのせいで100点を超えられなかった」ということがないように、守るセクションとしてとらえるべきであった。
終わりに
私自身、今回TOEFLで得た教訓を次回の学習に活かしたいと思う。学習に時間とお金を費やすこと自体は価値のある投資ではあるが、余分な時間とお金を費やすことはもはや浪費である。その分の時間とお金は他の学習に充てるべきである。読者の皆様が私と同じ失敗を繰り返さないことを祈っている。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
