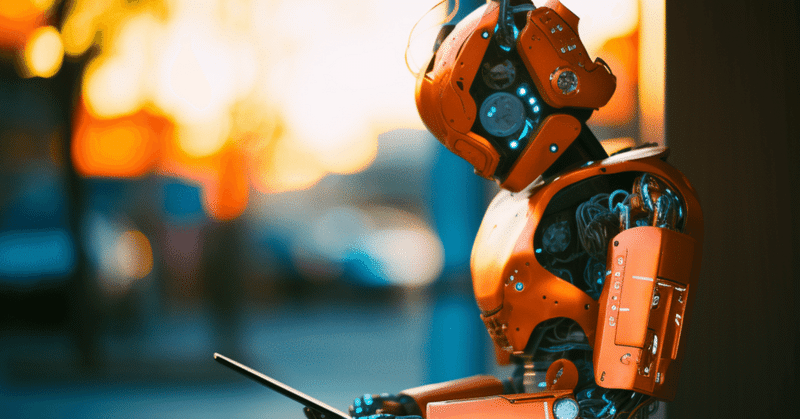
芸術あるいは「穏やかな日常」
自分をうまく受け入れるための言葉を知らない女が、あるとき、薄墨色の粘土に出会った。はじめのうち、女は手慰みに粘土をこね、ねじり、曲げ、歪め、固め、ほどいた。粘土のじっとりした重い感触を手のひらで何度も重ねて嗅ぎとるうちに、そう、女は手のひらで嗅ぐのだ、女はなぜか遠い故郷のことを思い出していた。幼い日々。はじめて意識した天井の模様。四角い電灯からぶら下がっていたビニールの紐。
父さん。母さん。兄さん。声を聴かせて。どうか教えて。わたしはいったい今までなにをしてきたの?本当はね、なんにも欲しくなんかなかったし、今だって欲しいものなんて何もない。父さん。母さん。兄さん。今はね、ただカップ麺が食べたいな。そういえばむかしのテレビでカップ麺のコマーシャルがあった。すてきな音楽が流れていた。あれ、なんて曲だっけ?
女は故郷からずっと離れた田舎町の福祉施設で暮らしていた。彼女は、AはあくまでもAであり、AがA’であったり、あるいはまったく別のBである場合さえある世の中の在り方に馴染めなかった。言葉というものが世界を構成しているのだということをうまく取り入れることが出来なかった。女の眼には、リンゴは常に小動物のように違って見えるのだ。赤いとき、丸いとき、突起が飛びてているとき、笑うとき、齧るとき、黒いとき、いろんなリンゴがあるというのに、スーパーに並んでいるのはいつも大人しく絵に描かれたリンゴだ。不思議なのは自分なのか世界なのか。女にはほんとうによくわからないのだった。
時々、施設長が女を手伝いいっしょに粘土をこねた。施設長はもうじき65を迎える老人で彼の逞しいぶ厚い肉体には明らかな衰えが見え隠れするものの、まだ彼の意識は絶えず世界を観察していた。老人がおもしろいと思うのは世界の輪郭、形、色であった。そこに解釈をはさむことを彼はあまり良しとしなかった。おもしろいと思うことのみを選んできた結果、老人はいくつかを失い、孤独を背負ってこの施設を営むことに決めたのだ。
ある日。なにやら不意打ちのように女の手のひらに10センチほどの細長い柱が生まれた。女は驚いたように初めての粘土細工をまじまじと見つめた。こうしようと意図して生まれた形状ではなかった。それは偶然に、もたらされたある種のギフトであった。もちろん女は神という言葉を使い慣れていないから、はじめての粘土細工は奇怪な毛虫のように女の手のひらの中でうごめいた。けれど、それはどこからどう見ても、今までこねてきた粘土の単なる塊ではなかった。女は、たぶん自分が作ったのだろう、細長い粘土細工をショートカットの硬い髪の中に埋もれた耳にあててみた。粘土細工から音楽が聴こえる。ずっと昔に兄さんが聴いていた流行歌だ。
施設長は女が生み出した粘土細工を光にあててみた。LEDの白い灯りの内側で粘土細工が呼吸をする。
「いいものを作ったね。咲さん」
咲さんは女の名だ。施設長はそういうと、咲さんの白髪交じりの頭をなぜた。咲さんはころころと笑い、「これ、わたしが作ったの?」と施設長にたずねた。「そうだよ。咲さんの作品だよ」
女は10センチほどの細長い柱に小さな頭をつけることを思いついた、綿棒を用いてその頭に懐かしい兄さんの顔を彫ってみた。
ひとびとの小さな努力の積み重ねの結果、穏やかな日常が訪れる。いっぱいのお茶と卵チャーハン、ほうれん草が高かったから小松菜の青菜炒めにしよう。施設長はまかないの智くんにそういった。智くんもまた咲さんといっしょにこの施設で暮らす知的障がい者のひとりだ。智くんは紙の音をきくことが好きで、毎日、チラシや画用紙、折り紙や包装紙、ありとあらゆる紙類をたたみ、広げ、伸ばし、丸め、また広げることで時間を費やした。紙がぐにゅぐにゅすると智くんは不愉快そうにそれをあたりにまき散らして怒鳴るのだ。ぐにゅぐにゅする。施設長は智くんの頭をなぜ、紙を拾い、ていねいに伸ばすとまたそれを智くんに与えた。
「智くんには料理の才能があるね」
なんどか一緒に包丁を使い、フライパンで野菜や肉類を炒め、塩や胡椒、醤油、砂糖、みりんなどで味をつけ、あるいは鍋に味噌をとくうちに、智くんは素朴で美味しい食事を作るようになった。施設長に褒められると智くんはエプロンの端を握ってうんうんと何度も頷くのだった。
咲さんは10センチほどの細長い、先端に顔のついた人形を一日にきまって10個作るようになった。10までの数字がわかるから。というのが咲さんが10個より多くを作らない理由だった。同時に10個より少なくを作らない理由でもあった。施設長は咲さんの作品を福祉施設の玄関にぎっしりと並べた。智くんがよくひとつをつまんでこれ僕のに似ていると言った。施設長は「そうかい。そうかもしれないね」といい、智くんの頭を撫ぜた。僕のといって智くんが下着に手を入れようとすると施設長は智くんのその手をやさしくつかんで「智くんは紙の音を聞くんだよね」とほほ笑むのだった。
何年かが経った。施設長と、智くんの両親と咲さんの兄の尽力により、咲さんの夥しい数の粘土細工と智くんが生み出したさまざまな紙で出来た唐突な塊の展示会が都会の一角で開かれることになった。ガラスウィンドウの向こうでびっしり並ぶ粘土細工はどれひとつ同じものはない。みな揃って10センチほどの円柱の上に丸い頭が乗っかっているだけのシンプルな形をしてるというのに、すべてがどこか違っているのだ。智くんの手が生み出した紙の塊は多くのひとびとにそれまで知らなかった「かたち」を見せた。すべての「かたち」を大量生産する社会の中、智くんの「かたち」は不気味にひとびとの心をえぐるのだ。見たことのない「かたち」はウィンドウの中で重なり、ぶら下がり、飛び、またおとなしく縮こまる。
自治体の職員さん、福祉に携わる職務をこつこつをこなす方々、孤独を背負った施設長と智くん咲さん、その仲間たち、かれらを遠方から支援し案じ続ける家族。ひとびとは穏やかな日常を得るため、それぞれの時間と能力を大事に大切に消費する。穏やかな日常は決して安易に得られるものではない。だから、穏やかな日常を、かれらから奪おうとする行為は何者であれ、決して許すべきではない。地球上のどのような場所であれ、肥沃であれ極貧であれ、人々のささやかな営みを蹂躙する行為は断じてあってはならない。
平和とは戦争と戦争のあいまに、あるいは戦争の脇でひっそりと息をするだけの沈黙なのか。戦後処理が終わっていないのは日本だけではない。多くの知性が前の戦争を超えられず、次の戦争を見据えている。ないのか、他に進むべき道は。「穏やかな日常」という牧歌を守り抜く術は我々の手には永久に与えられないのか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

