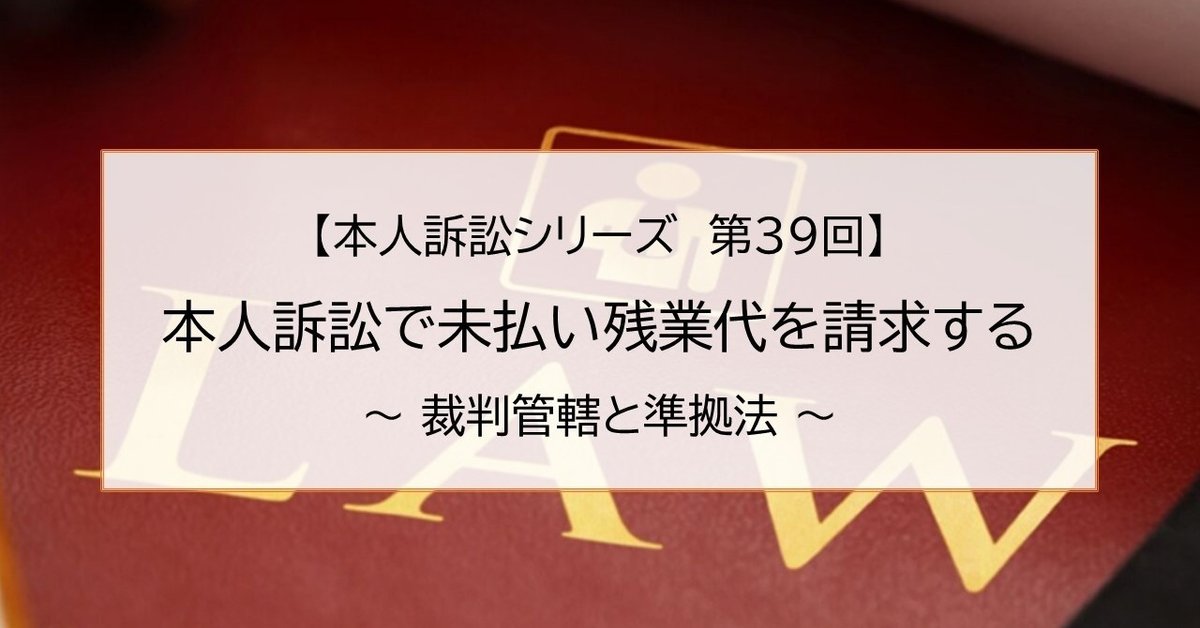
裁判管轄と準拠法の話し
今回と次回のnoteは証拠説明書をいったんはなれて少し堅い話を。まず、「裁判管轄」と「準拠法」についてです。
労働審判の管轄については第8回noteで解説しましたが、今回はちょっと特殊な私の実体験に絡めてです。というのも、私の本人訴訟のきっかけは、ある日本企業のフィリピン共和国マニラ首都圏にある現地法人への出向・駐在だったのです。
雇用契約の当事者は元従業員の私と元雇主の日本法人。私の就労場所はその日本法人のフィリピン子会社があるマニラ首都圏。つまり、日本に居住している私と日本法人の間で民事上の争いが発生しているわけですが、その争いの根源はフィリピンでの私の勤務に関する法律行為。日本とフィリピンという二つの国が登場しているのです。
そうした中、裁判をどこの国で行うかという裁判管轄。私はすでにフィリピンから帰国して日本に住んでいるわけですから、日本の裁判所に事件を持ち込むことは自然です。民事訴訟法第4条に「普通裁判籍による管轄」が定められていますが、ここに規定された裁判籍のいずれかが日本にあれば、日本の裁判所に管轄があることは認められるはずです。一方、会社の住所地は大阪府ですから、日本の裁判所に管轄権があることは当然認められます。後は、民事訴訟法や労働審判法にそって管轄を決めるだけの話(労働審判の管轄は第8回note参照)。裁判管轄については、日本とフィリピンの二つの国が登場するからといって問題はなさそうです。
そこで、事件を持ち込まれた日本の裁判所は、日本とフィリピンのどちらの法律を適用して事件を審理するのかという問題が出てきます。争いの元は、フィリピンでの私の勤務に関係する法律行為なわけなのですから。つまり、準拠法の問題です。
準拠法とは、契約内容を履行しないなど契約に関して争いが生じたとき、その効力・解釈にどの国の法律が適用されるのかを明示するもの。日本には「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」と言います)という法律があります。国際私法と呼ばれるもので、私と日本法人の間のフィリピンを舞台とする争いのように、渉外事件に適用する私法(=準拠法)を指定する法律です。国家間の法の抵触を解決する法律であることから、抵触法とも呼ばれるようです。
裁判管轄が日本の裁判所であれば、国際私法は強行法規ですから、当事者が適用を望むか否かにかかわらず、通則法は適用されることになります。通則法第7条には「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による」と定められています。つまり、準拠法の指定について、まず、当事者である私と日本法人が自治的に決定するという原則です。
続いて、同法第8条1項には「前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による」とされています。つまり、当事者が自治的に準拠法を決定しない場合、「最密接関係地」の法律を準拠法とするということです。また、同法第12条2項では「労務を提供すべき地」の法律を「最密接関係地」の法律として推定しているのです。
では、私のケースはどうだったかと言えば。
まず、雇用契約書には準拠法についての取り決めは何もありません。一方、「最密接関係地」は紛れもなくフィリピンでしょう。数回東京などへ出張しましたが、就業場所はフィリピン子会社のオフィスでした。つまり、「労務を提供すべき地」はフィリピンです。となれば、通則法に基づけば、私と日本法人に適用される準拠法はフィリピン法ということになりそうです。
しかし、ここで、私と日本法人の間で準拠法についての「黙示の合意」があったか否か、あったとすればそれは日本法かフィリピン法か、を明らかにする必要があります。これは、画一的に行為の「最密接関係地」の法律を準拠法にしてしまうと、個々の事件の特性に即さないという弊害が出る可能性があるからのようです。この「黙示の合意」とは、雇用契約書などで使用される言語、当事者の国籍や住所、性質や目的物など契約をとりまく諸事情から当事者の意思を推定するものです。
その点、私の雇用契約書から使用言語、国籍や住所がわかります。給与支給明細書からは、日本の所得税や雇用保険料が控除されていることがわかります(本当は、日本の居住者でないわたしの賃金から所得税が控除されているのはおかしいのですが・・・)。私の給与は、日本法人から私名義の日本の銀行口座に日本円で直接振り込まれていました。そもそも、私は日本でその日本法人の求人に応募して、日本でその日本法人の代表取締役の面接を受け、日本法人に採用されています。さらには、私のフィリピン現地法人での業務も、日本法人代表取締役からの直接の指揮命令系統のもと行っていました。フィリピン子会社の事業も、その親会社である日本法人が受注した業務の再受託が8割を占めていました。
私としては、これだけの事実が揃っていれば、準拠法を日本法とすることについて、私と日本法人の間には「黙示の合意」があったと言えるのではないかと考えるところでした。
しかし、任意交渉の時に私の代理人に付いてくれた弁護士は、それだけでは日本法の適用があるとは自信を持って言い切れないとの見解。「労務を提供すべき地」の法律が「最密接関係地」の法律であって、それが準拠法になるという通則法上の原則。その原則を覆うだけの「黙示の合意」を主張できるか、そこがポイントであろうということでした(結局、結論を出す前に、その弁護士は私の代理人を辞任しました→経緯は第33回、第34回note参照)。
裁判管轄が日本であるにもかかわらず準拠法がフィリピン法となれば、しろうとの私としてはますます厄介なことになるところでした。おそらく理論的には、このようなことも起こり得るのでしょう。しかし、私は、日本の法律でさえしろうと。ましてや、フィリピンの法律など理解できるわけがありません。英語ならまだしも、タガログ語で書かれていようものなら、もはや手の施しようもありません。また、未払い残業代は日本の労働基準法にしたがって算出。もし準拠法がフィリピン法で、フィリピンの労働法に基づいて未払い残業代を算出するとなれば、いろいろ変わってきたことでしょう。さらに、任意交渉で相手方の代理人を務めた弁護士はフィリピンの労働法にも詳しいらしく、フィリピンに進出した日系企業向けにWEBサイトで法律コラムを書いていたのです。
私は、労働審判申立書のなかで準拠法は日本法である旨を主張、まずは相手方がどのように反論してくるのかを待ちました。私は、労働審判でも同じ弁護士が相手方の代理人に選任されて、準拠法をフィリピン法と主張してくるなら相当面倒なことになると思っていました。ただ、その一方で、相手方としても、フィリピン法を準拠法とすることには実際には骨が折れるでしょうし、弁護士費用も割高になってくるかもしれません。それに、労働審判は話し合いで紛争を解決する場。準拠法など法律論のような議論を持ち出すのは、いささか不向きだとも思いました。準拠法については、私は、争点にならないことを強く望んでいたのです。結果オーライですが、相手方も準拠法については争点にはしてきませんでした。
ここまで長いnoteをお読みいただきありがとうございます!今回は「裁判管轄」と「準拠法」ということで、ちょっと堅苦しくニッチでマニアックな内容だったかもしれません。ご容赦ください。次回も証拠説明書を離れて、「労働基準監督署と属地主義」について述べていきたいと思います。
街中利公
本noteは、『実録 落ちこぼれビジネスマンのしろうと労働裁判 労働審判編: 訴訟は自分でできる』(街中利公 著、Kindle版、2018年10月)にそって執筆するものです。
免責事項: noteの内容は、私の実体験や実体験からの知識や個人的見解を読者の皆さまが本人訴訟を提起する際に役立つように提供させていただくものです。内容には誤りがないように注意を払っていますが、法律の専門家ではない私の実体験にもとづく限り、誤った情報は一切含まれていない、私の知識はすべて正しい、私の見解はすべて適切である、とまでは言い切ることができません。ゆえに、本noteで知り得た情報を使用した方がいかなる損害を被ったとしても、私には一切の責任はなく、その責任は使用者にあるものとさせていただきます。ご了承願います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
