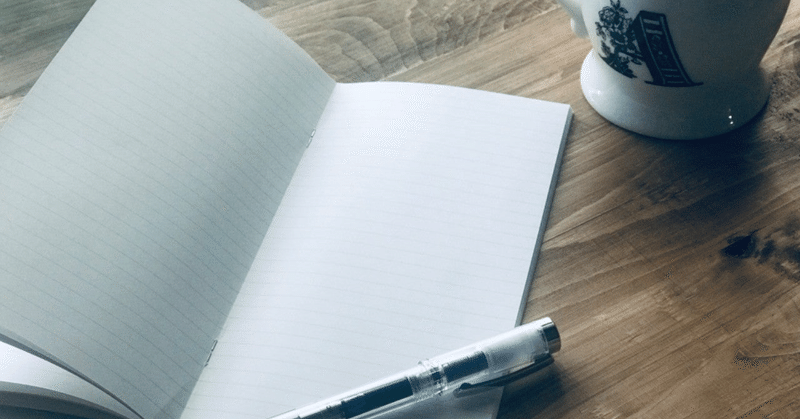
大3の春、初めての研究Ⅱ
わたくし研究の話をこすりすぎています。だから、この場でいつもより鮮明・詳細に述べ、もう2023年に置いていこうと思います。
第1節 試行錯誤
6月末、私たちはそれまで約4か月間取り組んできた研究をまとめはじめていた。なぜなら、7月上旬に開催される学術学会でポスター発表を行うからだ。私たちにとっての一番大きな問い・実態・考察・結論すべてを、一枚のポスターにする。そしてそれを用いて、著名な研究者や先輩、他の出場者に見解を述べるのだ。
…と簡単に言っているが、そこに至るまでが尋常じゃないほど大変だった。学会があと数日後に迫っているというのに、「そもそも私たちの研究の軸はなんだ!」「何を言いたいのか?」それがまだブレブレだった。材料は十分持ち合わせているはずなのに、どうも美味しく調理できなかったのだ。
6月26日のゼミでは、指導教員と院生による訪問診療(=各グループを循環して相談に乗ってくださるシステム。贅沢!)が行われた。しかし、それを以てしても授業時間内に議論が終わらなかった。そのため、我々は延長戦に突入した。(中略)指導教員からご助言をいただきつつ、院生にはホワイトボードが真っ黒になるほど大幅な交通整理をしていただき、ついに!方向性が定まった。やっとスタートラインに立つことができた瞬間だった。ちょっとだけ、美味しい匂いが漂ってきた気がした。※料理で例えるのは難しいことが分かった。私にはセンスがないらしい。以降、やらない。
決定した流れに沿って、今度はポスターを作成していく。これまた、かなりの労力を要した。全体の流れを示すスライド一枚を二日でなんとか作り終え、その突っ込みどころしかないであろうものを、朝4時に院生に送り付けた(語弊を招きそうだが、この非常識な時間帯と連絡頻度の多さを傍から見たら、この表現が適しているのではないかと思う)。そして、いただいたアドバイスを基に構成や考えを練り直したり、紹介していただいた文献を読み漁ったりして、私たちの研究を見つめなおした。
そして遂に、複数枚のスライド作成にとりかかる。学会はもう目の前。できた暫定版スライドを、指導教員と院生のお二方に校正・校閲してもらった(なお、その依頼LINEはこれまた朝4時半)。すると、示したいものが示し切れていないこと、問題意識が伝わらないこと、図がわかりにくいことなど、超重要なことが明らかになった。それらすべてを余すところなく修正し、なんとか、なんとか、一枚のポスターにすることができた。
第2節 発表とその振り返り
ポスターは完成した。さあ、あとは発表練習するのみだ!
しかし、発表練習の段階までたどり着いてもなお、悩みはなくならなかった。限られた時間で最大限に研究を伝える必要があるが、どこを主張し、どこを省くことが望ましいのか、分からなかった。それだけでなく、練習していくうちに自分たちの結論に問題がある予感がしてきて、焦りが生じ、一体なにを発表すればいいのか分からなくなっていった。そこで急遽、指導教員に(アポと言えるのか分からないくらい急な)アポをとり、研究室で相談に乗っていただくことにした。研究室では、ホワイトボードや仮印刷したポスターを用いて研究の要旨をまとめ、特出すべき内容を全員で確認・把握した。
一つ解決すると、また一つ問題が生じる。…進まない。結局、学会前日までほぼ毎日研究室に通った。ある時は留学生の院生に発表を聞いてもらい、質問とご助言をいただいた。“質問に答えられない”という状況によって先行き不安に襲われたが、初めて聞く人を相手に発表するとても良い機会だった。またある時は、モジモジしたら罰金(通称:1モジモジは400円)と自分たちを奮い立たせながら、一人ずつ指導教員の前で発表した。その後も何度も何度も、練習した。私たちの主張に一貫性があるか。本当に言いたいことが言えているのか。初めて聞いた人にも通じる流れになっているか。その都度確認しながら。
しかし、それでもなお私たちの悩みは底なしであった。「環境管理型権力を手放しに肯定することの何が問題なのか」という、まだ聞かれてもいない質問について考えて頭をパンクさせ、再び院生を頼る。…正直、”学会ではそんな質問来ないでくれ”と心から願うくらいには、頭にブチ込むのが難しかった。でも、たとえ当日尋ねられないとしても、学問をするうえで知っておく必要があると思ったから、教えていただいて本当によかった。
お二方の力を借りながら、4人でとことん話し合いながら、なんとか研究を完結させた。そして、とうとう本番を迎えた。練習しすぎたおかげで発表内容に大きな問題は生じなかったが、私個人の“自信がなくなると声が小さくなる”性質により、説得力に欠ける発表をしてしまった回もあったように思う。何はともあれ、学会は無事終了した。
学会を経た率直な感想は、「おお、研究者たちも学生の研究に関心を持ってくれるのか」という驚きが大きい。てっきり、各分野に精通した彼らにコテンパンにやられるものだと思っていたため、彼らが指摘や質問をしてくださるだけでなく、「新しいね」「ここから○○にも○○にも広がりそうだね」「似た研究にこういうものがあるから参考にしてみてもいいかも」と、議論を深める方向にもっていってくれたのが嬉しかった。もちろん、「それを用いるならあれを読まないと」とか「私の分野ではこの前提すら成り立たないよ」とご指摘をいただくこともあった。でも全然へこまなかった。私が学んでいる分野の学際性に触れる貴重な体験だったし、学問の場では“学生だから”と大目に見てもらうのでなく、対等に権利があるのだと知ることができたから。
第3節 研究後の気持ち
半年も前のことをこんなにも熱を持って語ることができるのは、グループ研究が私にとってすごく重要な出来事だったからだ。研究によって考え方が、学問への向き合い方が大きく変化し、大学生活が突然濃いものになった。
最近、社会学系の授業がすごく楽しい。特にTAをさせていただいている授業は、なにも考えずに受けていた(ごめんなさい)2年前とは全く違った意味で聞こえてくる。学び直す有難い時間だ。きっと2年前にも、授業の中には沢山のメッセージが散りばめられていたのだろうと思う。それに当時気が付かなかったことが悔やまれるが、今気づくことができたのは幸いなことだ。
有り余るエネルギーは、ゼミの発表(準備)にも注がれた。アーリとラースンは何を言いたいの?を頑張って考えていたら、輪読の楽しさに気づいてしまったような気がする。また、今学期は先輩の卒論ゼミにもお邪魔させていただいた。どのように論が展開されていくのか?そもそも20ページなんてどうしたら到達するのか?近くで学ばせていただいた。これは来年私も頑張らなくては…という気持ちになった。ほかにも、今まで本なんて読まなかったのに本を買って読んでみちゃったり、論文を収集してPCにストックしてみちゃったり。研究を発端とした“熱”は、色々なところに影響しているのである。
ここまで自分が研究にどのように向き合って、それがどのように今に繋がっているのか、その全貌を述べてきたが、すべては指導教員と院生と、そしてゼミ生のおかげだ!ありがとうございました。それぞれに対する感謝をここで述べようと思ったけれど、照れくさいのでやめておく。
一年を振り返るつもりが、上半期分を書いただけで年が明けてしまいそうだ。もう、あきらめる(笑)。2023年が充実していた、ということは後世の私に残せただろう。一年あっという間だった。さ、2024年も頑張ろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
