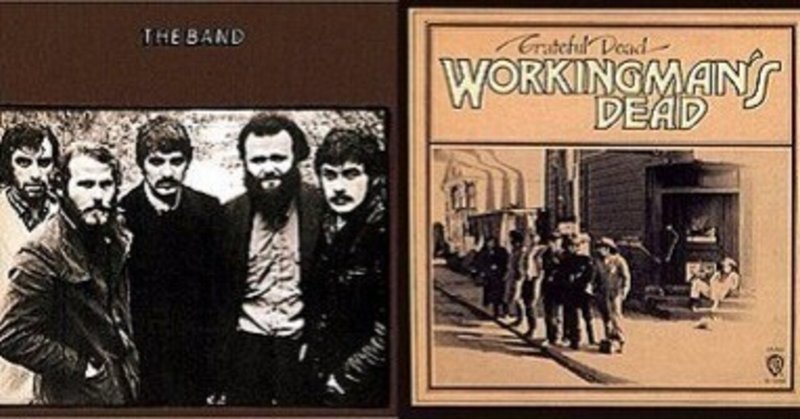
南部への憧憬を抱いた作家とそれぞれのアメリカーナ
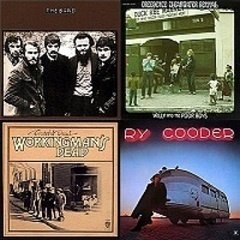
今回、ご紹介するのは、アメリカーナ系のロックです。
アメリカーナ・ミュージックは、アメリカ合衆国における白人音楽のルーツであるフォーク/カントリー/ブルーグラスや黒人音楽のルーツであるブルース/R&B/ゴスペルといった各音楽ジャンルの伝統的なスタイルが融合されたサウンドを特徴としています。
60年代後半から70年代半ばに掛け、多くの作家が同ジャンルの生誕地である米国南部の音楽へと向かいました。
メンフィスに帰還したエルヴィス・プレスリーは、『フロム・エルヴィス・イン・メンフィス』を発表し、ナッシュビル巡礼後のボブ・ディランは、『セルフ・ポートレート』や『新しい夜明け』を上梓し、自身と米国の音楽的なルーツの探求と模索があり、彼と深い関わりを持つザ・バンドもロビー・ロバートソンの牽引により同様の傾向がみられました。
70年代、多様化と産業化という二つの流れが進むロック・シーンにおいて、ルーツ志向のロックは、ある意味、時代の流れからの遡行ともいえるわけですが、カウンター・カルチャーの中心地にいた彼らには、その疲弊やある種の反動があり、そして、50年代のロックンローラー達から洗礼を受けたロックンロール世代が抱く南部への憧憬からアメリカーナへ向かった、と筆者は考察しています。
シーンの各作家たちがそれぞれのアメリカーナを追い求め、その結果、数々の大変味わい深い名作が生まれ、ルーツ・ロックとしての同ジャンルは、一つの完成をみる事となりました。
ちなみに、その後オルタナ・ロックの台頭以降、主にカントリー・ロックのシーン/分野から派生した新たなアメリカーナも成立しており、同ジャンルは、21世紀以降においてもスタイル/形式を変化させつつ、非常に重要なジャンルとして位置付けられています。
アメリカ人ミュージシャンが国家の歴史的/社会的なアイデンティティを見つめ直す際、米国南部の音楽は、その最良の道標となり、アメリカーナという名の豊穣な音楽文化は、我々音楽リスナーにも改めて深い感銘を与えてくれます。

『The Band』/The Band(1969)
作品評価★★★★★(5stars)
ニューヨーク郊外ビッグ・ピンクの地下室を離れ、ロサンゼルス中心部のハリウッド・ヒルズの邸宅へ移動したカナダ人を中心とする5人組は、名伯楽/ジョン・サイモンとの調練から米国の豊かな音楽遺産を一つの作品に刻印させる事に成功した。
通称ブラウン・アルバムと呼ばれる19世紀の米国史にまつわる今作は、南北戦争におけるプワー・ホワイトを主要テーマに、酒好きの労働者である男と妻や幼い恋人や売春婦たちとのドラマが映し出され、情感溢れる歌と演奏を聞かせる彼らは、管楽器から弦楽器までマルチに熟しつつ、豊沃な南部音楽を豊潤なルーツ・ロックへ凝縮/蒸留させてみせた。
帰路の途についたザ・バンドは、後にサウンドの魔術師として脚光を浴びるトッド・ラングレン監修の下、ロバートソンによる内なる不安の披瀝と共に、物憂げな虹色が浮かび上がる一枚を描き出したが、それは、緩やかに崩れ落ちるアメリカや彼ら自身の姿をも暗喩していたのである。

『Willy and the Poor Boys』/Creedence Clearwater Revival(1969)
作品評価★★★★(4stars)
前身バンドであるゴリウォッグスでの下積みのキャリアを経て、スワンプ・ロックの先駆をなすCCRとして改めて再出発した彼らは、目を見張る創作意欲から存在感を示し、ラジオ・オンエアとの相性の良さもあり、その知名度は、広大な米国の国土を跨いで浸透した。
伸び盛りなバンドの勢いが反映された同年発表の2枚のアルバムを経て、架空のジャグ・バンドに扮したジャケットが印象的な今作は、コンセプチュアルな構成と社会的な題材を併有しており、トラディショナル色を滲ませた彼らは、その忠実的なロックンロールをらしく躍動させた。
チャート制覇と満を持してのウッドストック出演によってピークへ達したCCRは、驚くべき事に、その翌年にはキャリアを決定付ける2枚の作品を更に重ね、英ロイヤル・アルバート・ホールでの熱演が示す国際的な成功もあり、ロックの一時代を最も精力的に駆け抜けてみせた。

『Workingman’s Dead』/Greatful Dead(1970)
作品評価★★★★(4stars)
ブルーグラスや前衛音楽やジャズなどを愛好するミュージシャンたちから構成されたこの伝説的なサンフランシスコの一団は、ヒッピーのアジールであるベイエリアで共同生活を送り、アシッドなジャム・セッションに明け暮れ、まさにカウンター・カルチャーの体現者としてカルト的な支持を集めていた。
グレイトフル・デッドの今作は、舞台裏で支えるオウズリー・スタンリーやリック・ターナーらの供給物資を活用した実験作から一転し、ルーツを再訪する作風となり、デッド特有の有機性をハーモニーでも活かし、ジェリー・ガルシアの叙情性やロバート・ハンターの文学性を伝承歌的な楽曲群へと昇華させ、一つの短編集として丁寧に纏め上げた。
矢継ぎ早に放たれた同年の姉妹作によって黄金期へ突入した彼らは、真骨頂であるライヴにおいて社会学的にも興味深いデッド・ヘッズと呼ばれる一種のコミューンを形成しつつ、莫大な軍事支出と共に、PAシステムの革新的技術の嚆矢として知られるウォール・オヴ・サウンドを完成させていく。
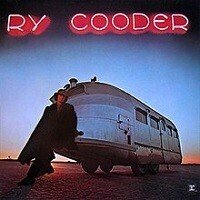
『Ry Cooder』/Ry Cooder(1970)
作品評価★★★★(4stars)
西海岸から南部音楽への案内役の一人を担うこの若きボトルネック・ギタリストは、ワーナー所属のミュージシャンやビーフハートやストーンズらとのセッションを通じ、その独創的なスライドの腕を磨き、南部音楽回帰への機が熟すと同時に、シーンの表舞台に現れた。
ヴァン・ダイク・パークスとレニー・ワロンカーがプロデュースを務めたライ・クーダーの処女作は、バーバンク・サウンドによる華々しい編曲の下、ブルース/フォークの巨人たちが遺した演奏スタイルを継承すると共に、それを踏まえた独自の奏法の確立させた一枚となった。
初期三部作を通じての大恐慌時代への探訪と共に、その作家性をユニークなギター・サウンドによって構築したライは、以後も幅広い親交と技法の吸収を重ねていくが、それは、アメリカーナの境界を越えたある種の学術的な民俗音楽の探求でさえあったと言えよう。
それでは、今日ご紹介したアルバムの中から筆者が印象的だった楽曲を♪
ちなみに、筆者は、00年代のインディ・ロック世代なのですが、オールタイム・ベストで一枚を挙げるとするならば、昔から『The Band』を選んでおります。
まぁ、そんな大それた質問、面接以外では受けたことないですが(笑)
あと、10代後半の時、放課後に通ったタワレコで紙ジャケ盤をジャケ買いした思い出もあるなー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
