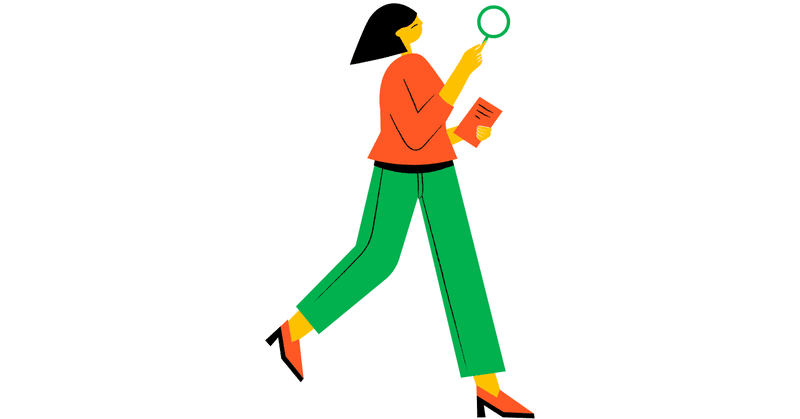
【小説】ヒマする美容師の副業 水ねだり魔女(後編)
すれ違いざまに男が耳元でささやいた。
「俺と沖縄に行かないか」
「行く、行くわ沖縄。でも、明日まで待って」
「どこで待ってればいい?」
「駅ビル5階のカフェ、本屋さんの隣だからすぐわかるわ。9時半までには必ず」
明日まで待ってもらったのはおばあちゃんの顔が浮かんだせい。あたしを頼ってくれているおばあちゃんにきちんとさよならを言いたかった。
翌朝、
「少しだけ旅行することになったの。しばらく帰れないけど心配しないで」と伝え、念のため同じことを大きな文字で書いて冷蔵庫に貼った。あたしと入れ違いにパートから帰ってくる母親が見つけたらどういう反応をするのか一瞬考えたけど、あの人のことだ、ふーんと言うだけな気がした。
「じゃあ行ってくるね。おばあちゃんも元気にしててね」と声をかけて出ようとしたとき
「お昼は楽々亭のヒレカツ弁当をお願いします」といつものちょっと照れた調子でおばあちゃんは言った。しばらく帰れませんと言ったばかりなのに無邪気にランチの注文をしてきたおばあちゃん。やっぱりすぐに忘れるおばあちゃん。
それでもあたしはいつものようにバスに乗りこみ駅に向かった。駅ビルのなかの24時間営業している本屋さんに行くのはあたしが外に出るための数少ない口実のひとつだ。本を見ながら店内を歩いていると生きてるって実感できるけど時間の観念が飛ぶのでアラーム設定は忘れない。あたしは家計管理担当という職権を濫用して書籍代を確保していた。来る日も来る日も舐めるように本の表紙やタイトルを見て歩き、今日の一冊を決めてセルフレジに向かうときの一瞬だけどスキップをしてしまうほどの胸の昂ぶりがある限り、明日までは生き延びられると確信できた。
でも今朝は違う。本のことも忘れてカフェを目指すあたしの心拍数は爆上がりだ。息するのも忘れて通路からカフェを覗き込む。奥の奥まで見渡せる構造になっており、何度も何度も探したけど男の姿は見えない。ウソだと叫びそうになるのを堪えて時計を見る。9時19分だ。まだ時間はある。あたしが早すぎただけだ。でもカフェには入れそうになかった。あたしは十分に挙動不審な人になっていて、あの男のためにもこれ以上目立ちたくはなかった。だから本屋の通路側で本を見るふりをしながら男を待った。全神経はカフェの出入口に向けられ動悸はいっそう早まり喉はカラカラで、そうしているうちにも9時半という刻限が必ず訪れることがこの世の終わりのように恐ろしかった。
賢明なる読み手もしくは聴き手の皆さんはあたしがこれ以上語らなくてもあの男が決して現れないことにお気付きかもしれない。あたしが男と沖縄に行っていれば書き出しから全く違う物語になっていたからね。
この世の不幸を一身に背負ったような境遇で育った女の子でしたが、20歳のとき白馬の王子様が迎えに来てくれて死ぬまで幸せに暮らしました。めでたしめでたし。
デパートですれ違っただけの男の言葉を信じて待ち合わせ場所に行くなんてイカれてるといわれてもその通りですというしかないけど、沖縄に行こうと誘われてあたしは心底うれしかった。今よりもマシなところで暮らしたいとホントは願っているのを瞬時に見透かしたあの男にそのままついていけばよかった。それなのにあたしはあたしの帰りを待っているおばあちゃんを思い出してしまって、そしてあたしがおばあちゃんを捨てられなかったようにあの男にも捨てられない何かがあったのだろうから最初からどうにもならない話だったのだ。そんなに簡単にどこかへ行けるのならデパートなんかをうろつくわけないのだ。
そういうわけで沖縄行きは今のところ実現していない。あたしは朝が来ればバスに乗って駅ビルの本屋に行き隣のカフェでコーヒーを飲む生活を続けているけど変化はあった。たった一度話しただけの男と会話するようになった、もちろん頭の中でだけど。読んだばかりの本の話とか、おばあちゃんと母親がまたケンカしたこととか、話したいことが次から次にあふれてくる。そしてときおり店内に視線を走らせてはあの男をさがす。誰も知らないあたしだけの拡張されたカフェタイムは格段に楽しさを増してきている。
バス停前の美容室の人がさりげなさを装ってあたしを見ているのは知っているけど気づかないふりして毎朝バスに乗る黒ずくめの女の子の役を演じている。なぜ黒ずくめなのかというと、母親が黒い服しか買ってこないからだ。服の買い方がよくわかってないあたしとしては似たような体型の母親の服を着るのが最適解なのだと思い込んでいたけど、もしかしたらあたし基準で買ってきてくれているのかもしれない。母親が買ってくる服を真っ先に着るのはいつもあたしなのだから。あたしが自分では気付けないでいる服の好みを母親はわかっている?
美容師さんに聞かれるままにおしゃべりしていたら、鏡にはあたしの知らない女の子が映っていた。いつも伸びっぱなしで、あまりにも長くなるとおばあちゃんに裁ちばさみで切ってもらっていた女の子はもういない。鏡にはショートカットの自分で言うのも照れるけど、かわいい女の子がいて見慣れなさすぎて凝視してしまう。そこに昨日ソファを勧めてくれた女の人がやってきた。
「あら、見違えたわ。ショート似合うわね。あのね、これ、衝動買いしてしまった服なんだけど、よかったら着てみてくれない」
「パーティションの向こうで着てみる?」と美容師さんも勧めてきたので試着しているとふたりが小声で話しているのが聞こえてきた。
「あの子のために買ってきたんだろ?」
「違うわよ」
「ウソだけは相変わらずヘタだな。そうやっていいやつだと信じさせる。まいったな」
「よく似合ってる。着てくれる人が見つかって良かった」
女の人はよほどうれしいらしく満面の笑みだ。ウソがヘタな人のホンモノの笑顔にあたしもつられる。
鏡には見慣れぬヘアスタイルと装いの女の子が映っている。右隣にはカットしてくれた美容師さん、左隣には服をくれた女の人。みんな笑っていて、年恰好からもホンモノの家族みたいに見えた。こんなおとうさんとおかあさんがいてくれたら世界は全然違って見えるんだなとあたしはひとり勝手に衝撃を受けていた。
「わたしはカオリっていうの。あなたは?」
「ユウリです」
「じゃあ、ユウちゃんって呼ばせてもらおうかな。ユウちゃんさ、明日の今頃、またここに来れる? 実はね、クローゼットを片付けているんだけど一回も着てない服とかあるんだよね。気にいるものがあればもらってくれないかしら」
あたしは明日もこのカオリさんとこの美容室で会えることがわかって飛び上がるくらいうれしかった。
その勢いであたしはもっとこの店に来る口実が欲しくなっていた。
「おばあちゃんがいるんですけど、カットをお願いできますか? 同じ話ばかりするけどニコニコしていてかわいいんです。あたしがそばにいれば大丈夫なんで」
「もちろん喜んで。予定が決まったら連絡して」
そう言って美容師さんはショップカードを渡してくれた。
美容室 Life is beautiful 代表 伊藤 高史
ジョークのような店の名前だと思ったが口には出さなかった。
正午が迫っていた。カオリさんと伊藤さんに
「本当にありがとうございました。では明日」と言って外に出た。
朝はまぶしかった日差しはすでに陰り今にも雨が降ってきそうな重い雲に押しつぶされそうだったけれど、あたしはスキップを始めていた。同時に笑いが込み上げてきた。落とし穴にはまりこんでいて一生出れないと思い込んでいたけど膝をちょっとだけ引き上げたらあっけなく外に出ていたことがおかしくてたまらない。落とし穴なんて最初からなかったのだ。スキップしながら笑っているのでおなかはよじれ息も上がってきた。なのにスキップをやめられない。
楽々亭のヒレカツ弁当がグラングランと揺れているけど、かまわずにスキップを続ける。家が見えてきた。おばあちゃん、今帰ったよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
