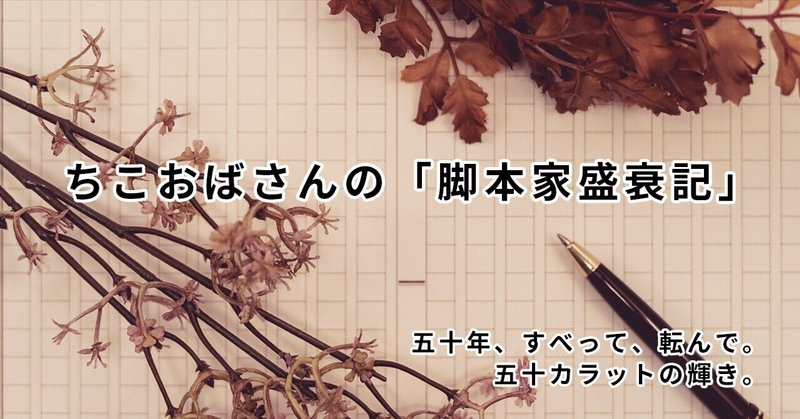
「達人には遠くて。CDデビュー?!」
(前回より)わたしは制作会社を出て、六本木に向かう通りを歩いた。バス停に辿りつく前に、涙がぽろぽろこぼれた。
ちなみにこの時のドラマのタイトルは「わたしは泣かない」だった。
第二回「達人には遠くて」
一週間後、わたしは台本を全直しして、提出した。六十枚×五日分を丸々書き直したのだ。次の打ち合わせはさくさくっと進んだ。いくつかの改定は求められたが、ケガは軽かった。Yプロデューサーは「ガッツがありますね」と云って下さった。Oさんは「若さってすごいわね」とニコニコ笑って下さった。
どうやって書きなおしたかは、まるで覚えていない。ただ、必死だった。必死で三百枚の原稿を書き飛ばした。
しかし、この時のハードルの越え方が、わたしの後のライター生活を決めた部分がある。一週間というタイムリミットの中で、構成だのキャラクターだのを改めて考える余裕はなかった。頭はほっておいても回っていたから、それをただ書いた。書き殴った。
この体ごとぶつかって行く感覚こそが、のちにプロとして書いていく上での礎になった気がする。
けれど、この「考えないで走り抜け」的な、云わば、その場しのぎの「馬鹿力」で勝負するというやり方が、通用しなくなる時がやがて来る。
二時間のサスペンスドラマを書くようになった頃だ。書いていて、「長い」と思う。この辺で終わりかな、と思った当たりから「ラストの山場」が始まる。この部分から先、ラストのシークエンスを書くのは相当な力仕事だ。
やはり、乗り切るには、きちんとした構成を立てる必要があった。構成の考え方については、まだまだ、コツとか妙案を掴んでないので、ここでは「時間」で説明したい。
二時間ドラマを仕上げるのに、大体「一か月」かけていた。それでも、あがりがよかったことはあまりなく、書き出し当初はなかなか苦戦をした。大直しをくらうこともあった。うーん、難しいなあ、と思案に暮れていた頃。
当時、親しくさせて頂いてた年下の女性ライターのMさんと飲んでいて「わたしは大体、二か月もらって書くかな」と言われた。衝撃だった。同じ番組を書いていて、彼女は「執筆」に倍時間をかけているのだ。わたしの認識としては、彼女のサスペンスは、謎も人間ドラマも十全に描けている傑作だった。わたしの二倍、面白いと言ってもいい。
まさか「時間」がそのまま、作品に出るわけではなかろうが、打てる手として、とりあえず、わたしも一本仕上げるのに、二か月かけることにした。
そして、執筆の手順を改めて考えた。
まず、ざっくりした二時間のプロットを書く。それから、倍の長さの同じくプロットを書く。そこから、軽く第一稿を書く。これに三週間ほどかける。ここからが未知のゾーンだ。そこから、また、プロットに戻る。戻ってストーリーつを要約し、テーマを再考する。これを何回か繰り返す。それから、要約したプロットを眺めつつ、第二稿を書く。余計な身がそがれ、台本の骨が見えて来る。言いたいこと、伝えたいこと、など、書かねばならないポイントが浮かびあがる。そこまでしてから、第三稿を書き、軽く直してから「第一稿」として、提出する。
こうして二か月間、試行錯誤をするのだが、二か月あっても足らないくらいだった。それに、台本を書くことは、ライターの一人遊びではない。並走してくれるプロデューサーがいてくれるこその仕事だ。
「いつ、あがります?」「そうですね。二か月ほど、もらえれば」ここで大抵、「二か月もかかるの?」と無言の返答が響く。こちらも「時間をかけた分だけ、いいもの、書きますから」と胸の中で返答する。だから、二か月分の圧を背負っての執筆になるのだ。
こんな試行錯誤をしていた頃、テレビ界では二時間ドラマがとても多数つくられていた。サスペンス人気が高かったのだ。今は、月に二、三本、あるかなしだろうか。けれど、何度か試みた「二時間ドラマの作法」は決して、無駄になるものではないと思う。
ついでにひとつ。執筆時間だけで、上級、中級というのは違うのだが、こんな例もある。
映画の脚本家として著名なK氏は、「ぼくはそうだなあ。一本書くのに、大体一年かなあ」とのんびりおっしゃった。様々な賞も手にされてる方の話。
上には上がある。
あまり、固い話ばかりになってしまっても、楽しくないだろうから、少々、ふざけた話題にも触れてみる。それはテレビ局への出入りが通館証なしで出来た、ある種、テレビ界も牧歌的だったころのお話。
二十代の後半だった。先輩の女性ライターと組んでゴールデンの連ドラの執筆をしないかとの話が来た。プロデューサーは数字はとれなくとも、若者に絶大な役者さんを使って、ギリギリに攻めた作品を作っていたSさんだった。Sさんはその先輩のNさんを連ドラの書けるライターを育て上げようとされてたらしく、わたしはまあ、お供というか、お助け要員だった。だから、そんなに緊張しないで、番組に入った。
テレビ局の喫茶店で、Sさんと向き合い、今回のドラマについて話した。この時は私、一人だったと思う。「ちこ、テーマはどうする?」と問われ、わたしはぼんやりしていた。当時は、というか、今もだけど、わたしは頭の回転がそんなに速くない。何かを問われたら、返答までに少し、時間がかかる。「テーマ?」ふーむ、と考え、「青春ですかね」とバカな答え方をしたら、「いや、これだな」と云って、S氏は空中に人差し指で、〇を書かれた。ぽかんである。なんだろう。と、のろのろ考えていると、一言、宣った。
「無、だ」
無がテーマ。不可解だ。判断停止だ。びっくりだ。驚きすぎで、リアクションが取れない。あれから、数十年経つが、今もあの発言の真意は不明だ。
この話には、後日談というか、おとぼけエピソードがある。
そのS氏が、何と、わたしとNさんに連続ドラマの主題歌を歌わせると言い出したのである。歌謡界にピンクレディやキャンディーズが大人気だった頃だ。前述したように、わたしは賢くないので、「どんな衣装にするんだろう」と、恐ろしいことに「乗り気」で考えた。思慮分別のあるNさんは、「Sったら、また、困ったことを言いだしたな」と思ってたそうである。
もちろん、連ドラの執筆が始まったら、歌のワンフレーズを歌う間もないほどの修羅場が待ち受けていたのだが。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
