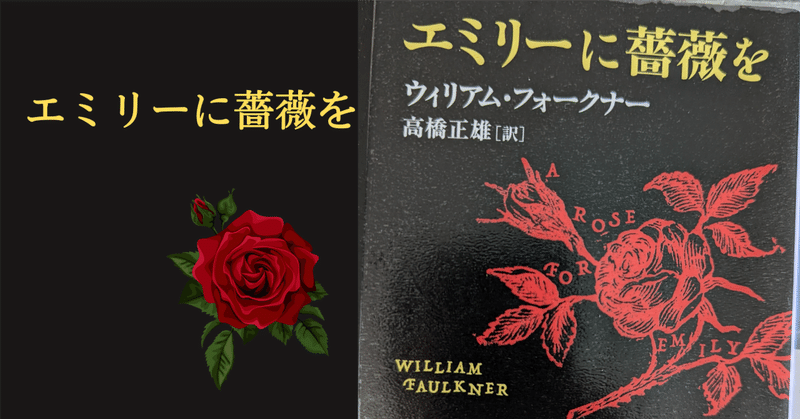
当時の時代背景を感じる【エミリーに薔薇を】ウィリアム・フォークナー著 高橋正雄訳
「エミリーは、町とっての
しきたり、義務、心労の種でした。」
しきたり?義務?
そもそもエミリーは人物なのか。
それとも何かを象徴するものなのか
疑問がわきました。
エミリーのお葬式から始まりました。
生前のエミリーについてのエピソードで
話が展開されます。
この作品は、
2022年9月25日メロディアスライブラリーで紹介。
著者はウィリアム・フォークナーですが、
ノーベル文学賞を取りました。
彼自身をこの放送で初めて知りました。
彼はアメリカ南部の出身で、
『エミリーに薔薇を』以外の他の短編集も
舞台はアメリカの南部でした。
・社会背景
『エミリーに薔薇を』の時代は1894年。
南北戦争から29年が経過しました。
戦争の結果、奴隷制は廃止されましたが、
エミリーには黒人の使いの人がいました。
いくら法律で決まっても、人々の意識はそう簡単に変わるものではないと感じました。
時代背景を考えると高校生の時に読んだ
『風と共に去りぬ』を思い出しました。
この話は、南北戦争か舞台です。
当時読んだ時は、「アメリカにもこんな時代があったのか」と思いました。
アメリカは進んでる印象がありましたが、どこの国も最初から進んでたわけではないのかと学びました。
世界史の授業で、南北戦争について習い、
奴隷制度が廃止になったのは知ってました。
小説として読むと、当時生きてた人たちの生活の様子や考え方が伺い知れました。
・昔の小説に書いてあること
この本に限らず、昔出た小説は
後ろの方にこんな注釈が書いてあります。
「現代では不適格になった差別用語が出てきていますが、著者が故人であることと、当時の時代、背景を考えてそのまま表現にしてます」と。
原作の翻訳にも「黒んぼ」という表現が
頻繁に出てきます。
今では差別用語のため、使用できません。
当時の様子をより表すために、
そのままにしているようです。
・感想
「これってどういう状況?」
高校生の時に『風と共に去りぬ』を読んだ時も、同じ感想を持ちました。
一度読んだだけではイメージできず、
放送日までに2回読みました。
メロディアスライブラリーの放送で解説があり、
やっと状況が理解できたくらいです。
他の短編集も理解に苦労しました。
読んでてわかったのは、
裕福な人が黒人の人に
家のことをやらせていたことです。
日本で例えると
お金持ちの人が家事をやってくれる女中さんを
雇ってるイメージかと思いました。
『エミリーに薔薇を』は、
ミステリー風に話が展開していると思いました。
一時期、一緒にドライブに行ってた
工事の現場監督の人が突然かけなくなったり、
ある時、薬局に毒薬を買いに行ったりしました。
話の最後でやっと
「現場監督の彼は死んだんだな」と
気づいたぐらいです。
ラジオ放送でもなければ、
この本を手に取ることはなかったと思います。
今のアメリカの南部の人たちはどういう価値観なのかは、はっきり分かりませんが、黒人奴隷制の影響は少なからず受けていると感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
