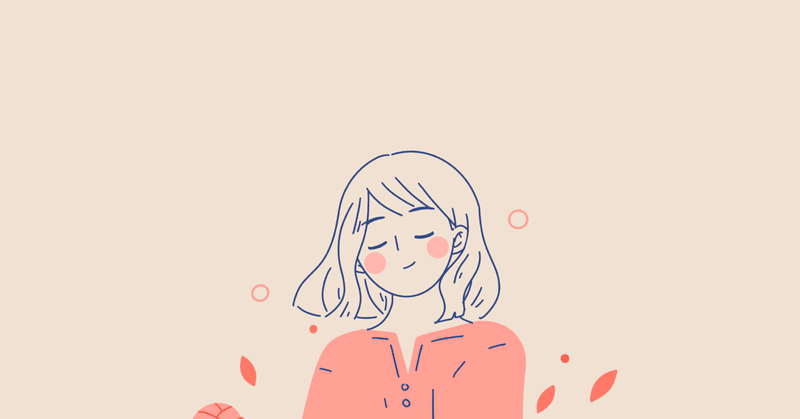
Tさんと私と鍵と
以前にも子どものころ鍵っ子だったと書きました。優しくしてくれる大人がいたと書きました。今回はその思い出を綴りたいと思います。
何年生の時かはうろ覚えなのですが、小学校2・3年生のころだったと思います。帰宅方向が同じで家も近いので、学校ではさして仲が良かったわけではなかったけれど、一緒に帰る同級生に『Tさん』という子がいました。その日私は憂鬱でした。帰りの準備をしているときに、家の鍵を忘れたことに気がついたのです。家には誰もいないので、建物の入り口で母の帰りを待つことになります。その頃、通勤に1時間以上かけて会社勤めをしていた母の帰りは夜7時を過ぎることもある上に、今のように携帯電話もなかったですから連絡をとるすべもありません。よほど暗い顔をしていたのでしょう、一緒に帰っていたTさんが心配して事情をたずねました。鍵を忘れて家に入れないことを伝えると、「それならうちに遊びにおいでよ」と誘ってくれました。
渡に船とばかりに、好意に甘えてお宅にお邪魔すると、Tさんのお母様も大学院の研究員か何か、両親共働きで不在でした。戸建てのおうちには小学校高学年のお兄さんと、おじいさん、おばあさんがいました。おばあさんは急に遊びに来た私にもいやな顔一つせず、Tさんに叱言を言うでもなく、私を優しく迎え入れ、和室つづきのリビングに通してくれました。Tさんから事情を聞くとおばあさんは母が帰宅するまでうちで待っていていいよといい、テーブルに出ていたお菓子を薦めてくれました。テレビを見たり、おばあさんの作るチラシ紙細工を真似てカゴを折ったりして過しました。Tさんのおばあさんは柚木麻子著の『マジカルグランマ』に“出てこない”マジカルグランマのようなおばあさんでした。全体的に小柄で丸っこく、パーマをかけた柔らかな白髪をしていたと記憶しています。ただ、記憶の中でどんどんとマジカルグランマ化していった可能性は否定できませんが。
自宅の留守電に、私の所在をTさんのおばあさんが残してくれたにもかかわらず、6時を過ぎても母は迎えに来ません。夕ご飯どきまで人の家にいるのが初めてだった私はだんだんと居心地が悪くなり、ずいぶんそわそわとしていたのでしょう。おばあさんは「大丈夫よ、ご飯食べていきなさい」と私の分まで配膳をしてくれました。Tさんのおばあさんのご飯は、ひとりひとり豆皿にそれぞれのおかずがキレイによそい分けられていて、大皿にもられた料理しかしらない私の目には、それはそれは素敵に見えました。
夕食が終わって、7時を過ぎても母はまだ来ませんでした。お風呂ができているから、とTさんと一緒に入るように勧められ、ここまで来たら楽しんでやるくらいの大きな気持ちにもなってきて、私は一緒に風呂場に行きました。翡翠色を基調としたタイル張りのお風呂だったと思います。浴槽にはおもちゃまで浮かべられており、上海でも自宅のユニットバスでもシャワーしか浴びたことのなかった私は、ここで初めてお風呂に浸かる体験をしました。まず驚いたのは息苦しさです。お湯の温度と水圧で肺が圧迫され息がうまく吸えないのです。それに慣れてくると次に興味津々になったのは水の中で自分の手や脚が歪んで見えることでした。手の向きを変えることで細長くなったり、丸く短くなったりするのです。しばらくそれに夢中になっているうちに、息苦しさがぶり返して出ようとすると、もう少し入ってなくてはいけなんだとTさんに諭され、2人で数を数えました。
お風呂を出て、Tさんのパジャマに着替えさせてもらっている頃、母が玄関に現れました。留守電に気がつくのが遅くなり、心配していたそうで、表情に慌てた様子が見えました。Tさんのおばあさんは母をなだめると、また鍵を忘れることがあれば、うちに来てもらって大丈夫ですからと念をおしました。このときは社交辞令だったかもしれませんが、私は聞き逃しませんでした。今思い返せば、自分で自覚していた以上に淋しかったのでしょうね。私はことあるごとに「鍵を忘れる」ようになって、Tさん宅の呼び鈴をならすようになりました。私の無遠慮な上がり込みには母が一番参ったようで、迎えに来るたびに平身低頭でお詫びを言い、3度目には父と一緒に迎えに来て自宅の合鍵をTさんのおばあさんに手渡しました。それでも私は、ときどき「鍵を忘れ」てTさん宅におばあさんに会いに通い、Tさんとゲームをしたりして遊び、お茶菓子をいただいて、合鍵を手にとぼとぼと帰宅したのでした。
数年前に、良い思い出も多く、何より校舎自体に愛着があって娘を母校に通わせたいと思い、その頃住んでいた地域の近くに引っ越しました。自分達が住んでいた社宅の前を車で通ることもたまにあります。Tさんのお家の前の道も通ることがあります。おばあさんがご存命かどうか知る勇気がなく、呼び鈴は鳴らせませんでした。当時の鍵っ子は今に比べると珍しく、家に帰って出迎えてくれる人のいるお宅に羨ましさはあったけれど、自分は淋しい、自分はかわいそうだ、そんな風には全く考えていませんでした。子供は強く、順応力も高いものです。優しく接してくれた恩のある大人たちも、ひとりで偉いねと言ってくれこそすれ、私をかわいそうな子としては扱いませんでした。今も別にかわいそうだったとは思っていません。だけれど、母になり、自分の子供が同じ年頃になり、今あの下校路を通るとき、無性にあの頃の自分を抱きしめてやりたくなります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
