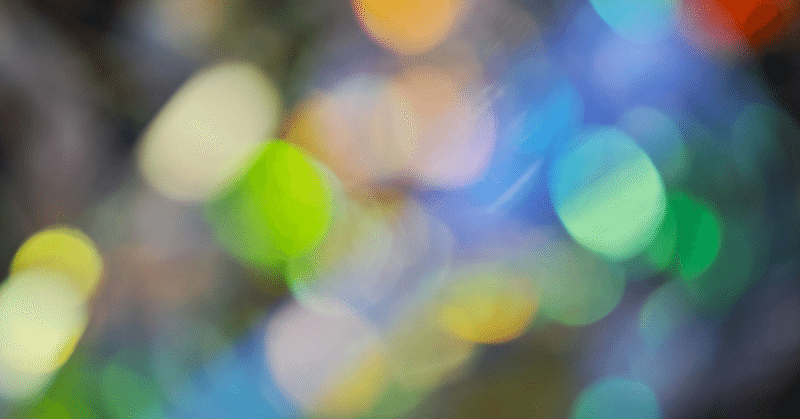
発達障がい|人生のターニングポイントと自己受容
人生の大きなターニングポイントは高1の夏だった。
春からの入学の高校にいっぱい期待していたし、、意気込んでいたが、コロナで休校(これだけで鬱になってもおかしくない変化)。
いままでの人生で培った元気になる方法(プールや図書館)が使えず、ほんとにしんどかった。
あのときは、私ばかりでなく、たくさんの人がしんどかったと思う。
6月から始まった高校。やる気にあふれた私に、学校は「毎日三時間勉強しましょう」なんて言ってきた。
みんなはどうやら、それを聞いても「そんなのするわけねえよ」と思っていたようだが、私はそれを真に受け、「三時間勉強しなくては…!」と思い詰めた。
本音と建て前の違いがわからないPDDの特性がはっきりと表れていたと思う。
しかし、新しい生活に、コロナで変わった社会、いろんなものが重なる中、毎日三時間なんて、できるわけがなかった。
「やらなきゃいけないのにできない!」と大パニックを起こす。
理想の学校生活とどんどんかけ離れていき、学校もいけない、勉強もできない、どうしたらいいんだ! と大パニックの連続だった。
人生で一番パニックが多い時期だったんじゃないだろうか。
夏休みに、ほんとうにどうしようもなくなってどん底を見た。
母にドライブに連れて行ってもらい、よくそこで話していたのだが、その日は全くなんの結論も見えず、朝方まで車の中で泣き叫んでいた。
あそこで、自分の底を見たと思った。
(その説はほんとうにお世話になりました。おかあさま)
あそこで、いろんなものを捨てられたのだと思う。
期待通りにいってほしい、という願望や、どうして自分はこんなにだめなんだ、と自分を責める気持ちや、こんなにだめだと見捨てられるかもしれない、という不安、それら諸々を。
それまでの私は白黒思考だったから、そのときの状況は、ほんとうに真っ黒で人生終わりだと思っていた。
でも、真っ黒だと思っていた状況になっても、意外と人間は死なないし、家族に捨てられもしなかったし、いじめられることもなかった。
意外と、大丈夫なんだ、と気づけた。
それともうひとつ、こんなに苦しんでいる私、それだけ頑張っているんだな、と気づけたのが大きかった。
それまでは、「苦しんでいる」というのは自分がだめな証だと思っていた。でも、苦しんでいる=頑張っている、ともいえるのでは…? と思えたのが、そのときだった。
自分の頑張りを自分で認められるようになったのが、あの瞬間だったのだと思う。
それと同時に、自分はこんなもんだ、と諦められた部分もあったのだろう。
「もっと頑張らなくちゃいけない」というのは「もっと頑張れるはずだ」という期待もあったんだと思う。
でも、「いや、私の頑張りはこんなものだ」とある意味諦めること。
それがあのときの私にとって、大きな大きなことだった。
その後、二学期からはなんとかやってたけど、それは環境要因ももちろん大きかったけど、やっぱり、あそこで諦めれたからだと思う。
自分の弱さを認めたとも言いかえられる。
よく言えば自己受容、悪く言えば諦観。こんなもんだ、という。
でもそれがあのときの私には必要だった。
今でも忘れられない、一晩中泣き続けたあの夏。
泣きすぎて目も頭も痛いし、顔はパキパキになるし、人生終わりだと思った。
でもあの時期に、思考の転換をできていなかったら、もっと辛かったのかな、と思う。
頑張ってくれてありがとう、諦めてくれてありがとう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
