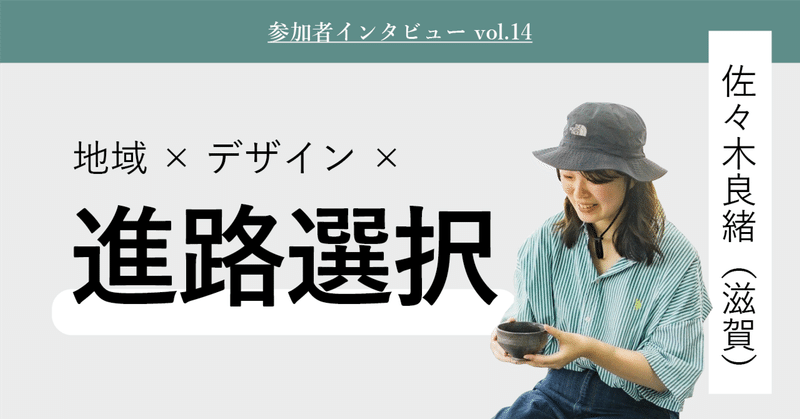
LDSを経て、人生の進路がストンと決まった|佐々木良緒さん(滋賀 / 20代)
LIVE DESIGN School の23年度メンバー同士が、根掘り葉掘りするインタビュー企画! 各地で活動するメンバーたちが日々考えていること、そして、LDSの参加を経て見えてきた展望とは...?
プロフィール
岡山県出身。滋賀県の成安造形大学、地域実践領域に所属。旧志賀町地域を中心に、グラフィックデザインから、マルシェ運営、エコツーリズムの企画運営、世界湖沼会議での発表など、様々な側面から地域と関わっている。大学では「てんてこのんき」というライフスタイルの研究を進めている。2024年春から大分県耶馬溪に移住。デザイナーとして勤務予定。
てんてこのんきとは
てんてこ、てんてこ、のんきに、ゆるやか、自分のペースで、自分ごと。
「てんてこ舞い」という言葉があります。元々は祭囃子や里神楽で、小太鼓の音に合わせて休む暇なく舞う様を忙しい状態を表す言葉になりました。
「てんてこのんき」は「てんてこてんてこ」と里神楽の小太鼓の音のように、あわただしく暮らしながらも、心はいつもゆるやかで、「のんき」でいられる。そんな暮らしや生き方を目指しています。さまざまな「場所、ひと、もの、こと」の視点や取り組みを通して、「これからの暮らしのあり方」を模索します。
農家の娘として生まれ「農的暮らし」の中で育った私が、大学進学の一人暮らしを機に、暮らしについて興味を持ち研究を進め、「てんてこのんき」という言葉を作りました。lifeworkとして「てんてこのんき」的な暮らしや生き方を考察し、さまざまな方法で、実験的に活動しています。
━━ LIVE DESIGN Schoolへの参加のきっかけについて教えてください。
京都の工芸イベント「DIALOGUE」でリードデザイナーの新山直広さんのトークショーを聞いたことがきっかけです。活動に興味があったのでお話する機会をいただいて、そこで「ちょうどいい学校が来年からある!」とご紹介いただきました。
実はリードデザイナーであり九州拠点の福田まやさんは以前から知り合いで、ホームページを見たら福田さんがいたので驚きましたね。また、おもデザ本も読んでいて、自分もこういうふうになりたい!と漠然と思っていたので、この学校に入ったら、地域のデザインについて学べるんじゃないか、という思いで入ったのがきっかけです。
━━ 実際の印象と、想像してた印象で何かギャップはありましたか。
もっと硬い学校かなと思ってました!
開校式も東京で、実は、少し緊張していて(笑)。でも、いざ始まりフィールドワークや、オンラインプログラムに参加していくと、運営の出雲路本制作所の皆さんはすごく温かくて、ゆるいけど、良いところを拾っていく。そのリズム感、空気感が、すごく心地よくて思っていたよりもすっと馴染むことができる学校だなと思いました。
━━ 佐々木さんは何度かフィールドワークに参加されていますが、参加されてみていかがでしょうか。
オンラインプログラムも充実していると思いますが、フィールドワークは特にこのスクールそのもの、重要なポイントだなと感じました。
地域とデザインをテーマとしている学校ですし、そこで会う人、匂い、味も、全ての環境的要素を3日間ぐらいで一気に感じて、学んでいる。文章であったりオンラインの言葉から得るものもすごくあるんですけれど、フィールドワークでの学びは感覚的な部分ですよね。五感から「いいな!」と感じる瞬間。地元のおじちゃんのちょっとした一言や表情からすごくリアルに“ここで生きて、ここでデザインしてるんだ”と感じるんです。私にはもう衝撃というか。うわーいいなって思います。
あとは、参加者の皆さんと話せるのもフィールドワークの良い部分で、皆さん面白く、魅力的な方ばかり。皆んなが先生という感じがすごくしています。移動中のバスの中とかでも活動の内容で盛り上がったり、本当に全員が全員で学び合っているんですよね。
━━ 特に印象に残ってる言葉はありますか
どの回も良いので、選ぶのは難しいですが、特に尊敬している福田さんの回が印象的ですね。福田さんが話された「いろんな視点で見る」という考え方にとても共感しました。デザイナーだけでなく、農家や生産者など、様々な職業の方々や幅広い年代の人々からの色々な視点があるからこそ、生まれるものがあるというお話です。
私は学生時代、様々な人の視点から1つの地域を旅するエコツーリズムや、規格外の野菜や流通できなかった商品を活用する仕組みについて考えてきました。例えば、漁師や農家の方々と協力し、料理人が直接仕入れて加工し、マルシェで提供するような取り組みです。このプロセスでは、40代、50代の男性の方の参加が多かったのですが皆さん私の発言を本気で拾ってくれて、流通とは何なのか?を同じ立場ですごい議論しました。
異なる意見や視点がぶつかり合うことで新しいものが生まれるという実感もありますし、デザイナーだけが発見するのではなく、全てのスタッフが同じ立場で発言できて作り上げる状況が私は理想的だなと思っています。いろんな人の視点で拾い上げたり、積み集め合わせた企画であったりとか、そういうデザインをしたいと思っているので、福田さんの言葉はすごく印象に残ってます。
━━ 佐々木さんはLIVE DESIGN Schoolを通して福田さんの会社に就職が決まりましたが、どのような経緯だったのでしょうか。
LIVE DESIGN Schoolの開校式で久しぶりに再会したときに、実は地域のデザインの仕事をしたい、という話をしていたら、福田さんが私のWebサイトを見てくれました。だったら一緒に何かやろうよ、と誘ってくださって、アルバイトから始まりました。
当時は将来にすごく悩んでいて、東京の会社に行くか、地域に行くか、どの選択をしても、学べることはあるだろうとは思っていましたが、自分が今どうしたいのかに迷い、ずっといろんな人に、相談していました(笑)。
長い期間悩んでしまっていたのですが、九州のフィールドワークのときに、福田さんから「東京でも地方でもどちらでも学べることが必ずある。自分で決めたらいいけど私は席を空けてるよ」と言ってくださって・・・。すごく嬉しかったです。
また、フィールドワークで実際に九州に行ってみたら、もうとても魅力的でした。福田さんの仕事してる環境を肌で感じて、いいなってなったんですよね。帰ってきてから決断して、福田さんに行かせてくださいと、お伝えしました。
でも、福田さんの言葉もありますが、地域のデザイナーになろうと思ったきっかけの一番は、耶馬溪という場所が、暮らしと仕事が密接に関わっていることです。私が本当にやりたいことって何だろうと言ったら、もちろん仕事の面ではデザインなのですが、「てんてこのんき」という活動も続けたいですし、暮らしもすごく重視して生きていきたいと思ったので、そこが決めてですね。
将来は、自分の選んだ場所で独立をしたいっていう思いはずっと持っていて、いつか独立してLIVE DESIGN Schoolのリードデザイナーの方々のようになりたいなって憧れています。
━━ ズバリ、LIVE DESIGN Schoolに参加して良かったでしょうか。
良かったとしか言えないですね(笑)。人生の岐路が決まりました。参加しなかったら福田さんと再会する機会もなかったと思います。
実は、デザイナーになるかどうか、3年生の前期まで悩んでいたんです。一次産業や、職人さんとして働くことに惹かれる自分もいて。デザイナーってある意味俯瞰する立場なので、決めきれてない部分がありました。
でも、LIVE DESIGN Schoolに入ったら、“デザイナー”と、分ける必要性もないということに気づいたんです。一次産業に近づいているリードデザイナーの方を見て、あんな風になりたいなって思いました。スクールを通して、デザイナーになりたいという言葉が自分の中にすっと入ってきましたね。
「こうなりたいんだな」とリードデザイナーの皆さんを見てストンと落ちた感じがして、自分のなりたい姿が見つかり、参加することができてとても良かったです。
(聞き手|尾崎友紀さん)
地域で必要とされる「広義のデザイン」について、各地のデザイナー陣と参加者どうしが学び合う場として始まったLIVE DESIGN School。現在、24年度のエントリーを受付中です!デザイナー(志望)はもちろん、イラストレーター / 大学生 / 行政職員 / 地域おこし協力隊 / 販売員 / 製紙業 / 百姓!などなど多様な肩書きの方にエントリーいただいています。詳細はこちらから!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
