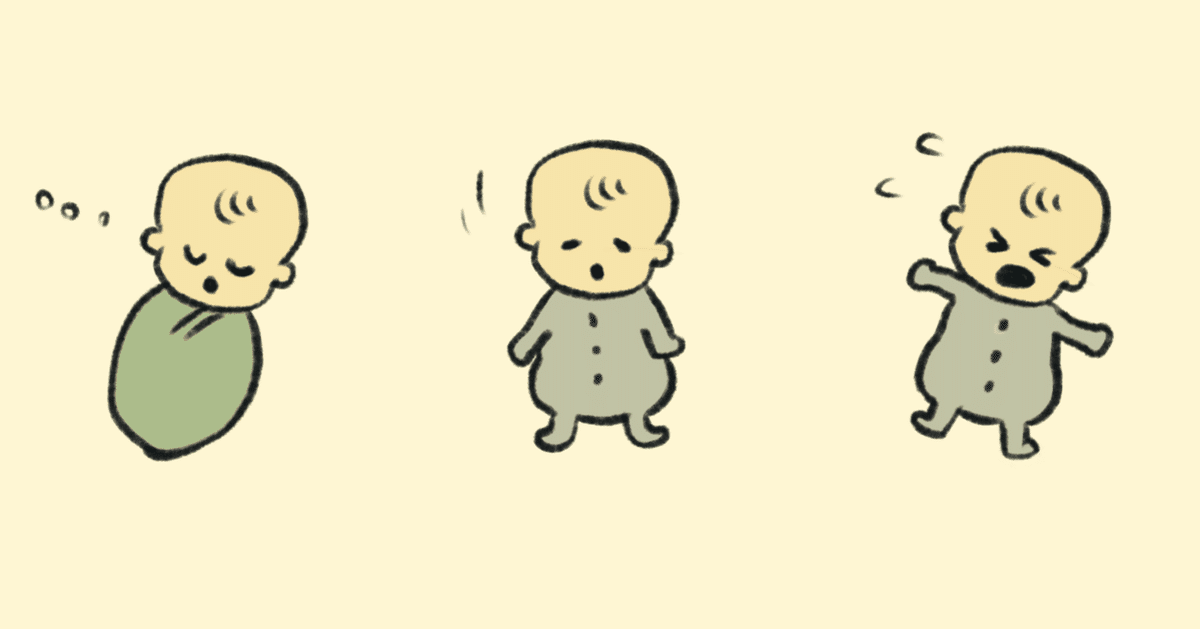
うちのこ洗脳SS-18「紅恭也、童心に還る」-本編
【承前】
あらすじとまえがき
・ダブルクロスの悪落ち済みキャラクターである紅恭也は、本編後のオラクルに転移する。
・これから彼は胡乱エルフどもにひどいことをされる。
・本編はシリアスが一切ない。
俺の名は紅恭也。明らかに元いた世界ではない宇宙船の一室で、今、天井から伸びる蔓によって後ろ手に縛られ、膝をつかされている。
目の前には、二人の敵がいる。
片方は金髪で隻眼、マッチョで酒臭い女。竹ひごをおやつのようにばりばり食べている。
もう片方は割烹着のちんちくりん。顔に青筋を浮かべ、恐ろしい笑顔でこちらを見ている。
「さて」
割烹着の少女が切り出す。
「お前はそこのツーズーを斬ろうとした。間違いないかゆ」
怒りに震える手で、胸を小突く。
「ああそうだとも。楯突くやつは全員この刀で……」
「ハムにすゆ」
割り込まれる。
割烹着の少女が大上段に構えたポテトマッシャーを、ツーズーが全力で抑えている。
「どうどう! ララモイ落ち着け!」
「離せツーズー! 親友を害すゆ奴は先手を打ってハムに限ゆ」
「無事だから! アタシ無事だから! な!」
十秒ほど力比べが続き、やがてララモイと呼ばれた少女はため息を付いて矛を収めた。
……“ハムにすゆ”の、背筋が寒くなるような響きには突っ込まないことにした。
仕切り直す。
「言っておくが、情報を素直に渡すつもりはないぞ」
結局の所、彼女らが推定で敵であることはまだ揺らいでいない。
「そうか」
ツーズーは、了解を取らず俺のポケットを弄り始める。
「なんかあゆか」
「おっ、手帳出てきたわ」
「げっ」
燃やしておけばよかった。
「あー、何だこの文字。アタシには読めん。ララモイ、読めるか?」
「ふむ。あー、日本語ゆね。九十九堂とか、なことかの言葉ゆ。内容は……「所有者紅恭也……【ファルスハーツ構成員手帳】」……?」
二人は顔を見合わせる。
そして。
「ハムにすゆ!」
「落ち着け!」
今度は好奇心をむき出しに襲いかかるララモイを、またツーズーが止めていた。
「こいつダークファルスの関係者ゆ! ハムにしてポテサラに入れて食べゆ!」
「ダークファルスを食おうとするな!」
止めているツーズーの腕には縄のような筋肉が浮かび、ララモイの矮躯を止めるに当たり恐ろしい力が加わっていると分かる。
「ダーカー肉が食卓に出ゆんだから今更ゆ!」
「やめろ!」
暫くの押し問答。
三十秒も経つ頃には、二人のエルフの息は上がっていた。
再度、仕切り直し。
「ハーッ……。とにかく、こいつからはまず情報を引き出す。少なくとも抵抗が無駄だとわかってはいるようだからな」
「妥協すゆ。代わりに我がポテサラ魔法の礎にすゆ」
ゼーゼー息を切らしながら、俺を置き去りにして会話が進んでいく。
「今回はヒトの心に作用すゆポテサラ魔法を使ゆ。ぐずぐずにすゆ」
「ほー。それで心をグズグズにしてどうするんだ」
ツーズーが促す。
「グズグズにすゆのは反抗心ゆ。上手く決まれば、卵を割って親を見たひな鳥みたいになゆ」
彼女は身振りを交え、説明する。
「ララモイ、たまに本気でえげつねえこと考えるよな」
引いている。そんな術を俺に掛けるつもりなのか。
「まずは精神抵抗を限界まで下げゆ」
「あっ、うちが呼ばれたってそういうこと?」
いつの間にか、星の光も見捨てた暗がりから、影を練ってできたかのような女性が半身を出している。
「シャドウリング、期待しているぞ」
「種族名で呼ぶのやめて。ツィールって名前で呼んで」
言いながらも、手に持ったダガーが妖しく揺らめいていく。
「こっちのルールに従うなら……ミラージュとかどう?」
「うゆ。悪くなゆ」
ララモイが頷くと、ツィールはしゃがみ込み、縛られた俺の手を弄る。
「じゃあチクッとするよ。ごめんね」
そして彼女は謝罪し、手のひらを浅く裂いたようだった。
「っ……」
痛みとともに、意識がぼんやりとし始める。
「決まったみたい」
「ありがとゆ。せっかくなので暫く見てくかゆ?」
邪悪な笑みのララモイ。ツィールは承諾する。
「だって美少年好きだし」
「お前のヘキはわからん……」
ツーズーは呆れていた。
頭を抱えるツーズーをよそに、ララモイがポーチから何かを取り出す。
「うわあ」
ひと目見た瞬間、ツィールが飛び退いた。
ふわふわした意識でソレをどうにか視認したところ、どうやらピンク色をした複雑な文様のシールのようであった。
「ゆふふ、信仰エルフの即席アセンションパッチゆ」
名前からしてロクでもなさそうだ。
【砂漠のオアシス酒場にて】
「南部地域のエルフ氏族を教えて欲しゆ」
軽装にターバンを被ったララモイは、カウンターにどうにか座るなりマスターに切り出した。
「なんだ、ポテサラエルフとは珍しい。その話ならカウンターの端に座ってるアイツが詳しいぜ」
見ると、シャツの胸元を開けたドラコニアンの男が空のグラスを指し、ニヤつきながらこちらを覗いている。
「ったく。常連さん、何が飲みたい」
デーツのアラックとのことだったので、アタシたちも同じものを頼んだ。
「ありがとよ。それで、ここいらの氏族はデーツとブドウが大勢力だ。ここの酒も、半分は奴らとの交易品だよ。マイナーなところでは信仰エルフがいるな」
「そいつら、まさか信仰を食うのか?」
男はグラスに口をつけ、続ける。
「ああ、まあ……かつてはそうだった、が正しいな。昔の奴らは慎ましくプリーストに就き、穏やかに神に向かう信仰の恩恵に預かっていた。だが、人口が増えてくると神託が下ったのさ。『俺の信仰をネコババするのやめろ』とな」
「世知辛ゆ。ポテサラあゆか」
あいよ、とマスター。
「まあそれで奴らは自分の食性について研究したんだが、あることがわかった。ヒトに向けられる、憧憬や畏怖、愛情あたりの感情ならなんでも食える、と。そこからのムーブは早かったよ。その秀麗な容姿を活かし花街に向かい、上級娼婦となった奴は数しれず。さらに強欲な奴らは『アイドル』養成所を開き、信仰を受ける御神体になろうとする同族にあらゆる手を尽くして教育……そして技術開発だ。努力って良いよな」
「ゆゆ、食事中にする話じゃなゆ」
……まあ、過程はどうあれ上手く行ってるから良いだろ、と彼は言った。
「なあ、その話聞いてて思うんだが……」
アタシは切り出す。
「そいつら、中部では『サキュバス』って呼ばれてないか?」
「ララモイ……お前まだそれ持ってたのか……」
ツーズーもしかめ面をしている。
「ゆふふ。術式は分かったゆから、何枚でも作れゆ」
おお、神よ……と唸るツーズーを横目に、ツィールが割り込む。
「やっぱりそれ……貼るんだよね? 下腹部に」
「うゆ」
返答とともに、こちらを見る。
沈黙。
「剥こっか!」
「剥ゆ」
◆◆
「ひどい……」
いざやるとなったら、彼女たちは早かった。
学ランのブレザーとワイシャツは完全に前を開けられ、シールを貼りやすいようインナーはたくし上げられている。
下半身の方もベルトが床に落ち、パンツが見えている状態だ。
「ゆふふ。魔術の進歩には犠牲がつきものゆ」
「いっそ殺してくれ……」
羞恥で真っ赤になりながら懇願するも、まるで意に介していない。
……それはそうと、ララモイが脇腹の傷を見るや否や、バッグの瓶から出したポテトサラダを傷口へパテのように塗りつけたときは正気を疑った。
むにゃむにゃと呪文を唱えたら傷が塞がったのを見て、今度は俺自身の正気を疑った。
「つか……」
ツーズーが割り込む。
「お前、ちゃんと飯食ってるか? 戦闘員にしちゃ細すぎる」
彼女はあくまで戦士の立場から俺を見ているらしい。
「こんなもんじゃないの?」とツィール。
バンブーエルフの戦士は、ツィールちゃんは軽装だからな、と前置きして続ける。
「さっき戦って分かったが、力の源泉が異能とはいえ、型としては力で敵を押し切っていくスタイルなンだよ。だが、戦術が搦め手多用でミスマッチが起きてる」
「へー」
「まあ、外部からみた感想だ。そんでどうなんだ、いつも何食ってる」
敵にすら余裕を持って接する彼女に腹を立てながら、正直に答える。
「チョコレートとか……シュークリームとか……コーラとか……」
彼女の余裕が消えた。
「……」
笑みもだ。
「お前、偏食しすぎ。早死するぞ」
「ねえ、それバンブーエルフが言って良いことじゃないよね?」
「ヒューマンとエルフでは消化酵素が違うンだよ」
「そっかあ」
こちらの反応を待たず、今度はララモイが悪い声を上げる。
「魔力充填終わったゆ」
見ると、悍ましくてらてらと桃色に輝くシールを掲げていた。
「今からこれを貼ゆ。魔力切れまで効果は持続すゆ」
言いながら、ペリペリとカバーを剥いでいく。
「ねえ、本当にやるの……?」
ツィールは本気でこちらを心配している。まるで一度同じ目にあったかのようだった。
「くっ……俺はどんな拷問にも屈しな……ない……?」
「ミラージュがキマってて意思が揺らいできてるんだよな。まあ多分死なんから頑張ってくれ。最悪死んでもこっちのルールじゃムーン一発で生き返る。キャスト化してもいい」
ツーズーは苦笑いしながら促す。
救いはなさそうだ。
「じゃあ貼ゆ」
ララモイの、シールを持ったもちもちとした手が右下腹部に触れた途端、異変が起こった。
「がぁッ……? あああッ……!」
気持ちいい。
というより、脳がキャパシティ以上の快楽信号を送っている……!?
「ああああああッ――!?」
シールによる快楽信号を逃しきれず、体がビクビクと痙攣し始める。
「ほーら、まだ貼り始めたばっかだゆ。動くなゆ」
喉を嗄らすことも厭わず叫ぶ。
快楽が、暴力的な快楽が逃げることなく、体内を反射している。
「今、ぽてちの魔力でおまえの感覚を増幅してゆ。終わった時が楽しみゆ」
「――――ッ! ――!」
ペタペタと貼り付けが進めば進むほど、気持ちいいというよりも度を越して苦しくなっていく。
ふと窓を見ると、濃紫色のロングヘアーを揺らす少女が、舐めるような眼差しで俺を凝視している。
アヤメだ。一緒にこの世界に来ていたらしい。
悲鳴の中に「助けてくれ」と懇願を混ぜると、気づいた彼女はスケッチブックに何やら書き、窓越しに俺に見せた。
「キョウヤくんの悲鳴もっと聞きたいから耐えて♡」
ダメだ、完全に衝動に従っている。俺とシラカのことそういう目で見てたのは気づいてたけど……!
「ちなみに外の奴らもララモイがしっかり蔓で拘束してるから、助けは来ないぞ」
ツーズーが無慈悲な宣告を下すとともに、俺は抵抗を諦めた……。
……さて。
「貼り付け終わったゆ。生きてゆか?」
「はひ……はは……」
過酷なシール貼りを終え、俺の下腹部はシールの文様に沿い、卑猥に輝いていた。
これではまるで淫紋である。
部屋を循環するそよ風にすら反応するほど肉体が敏感になっており、シラカに見られたら殺されるんじゃないか、と思えるほど無様に喘いでいた。
実のところそのシラカは、アヤメに続いて外で目覚め、真っ赤な顔を隠しながらこちらをチラチラと見ていたりするのだが。
「許してぇ……何でも言うからぁ……」
あまりの衝撃に心はほとんど折れてしまっていて、思考もままならない。
「ふむゆ。頃合いかゆ」
ララモイは何度か俺の体を叩いて具合を確かめ、納得したかのように頷く。
「ララモイさん助けてぇ……」
再度の懇願。しかし。
「これならポテサラ魔法も通るかゆ」
忘れていた。
彼女の目的は、最初からポテサラ魔法の人体実験だったのだ。
「じゃあお前の脳みそに直接魔法をかけゆ」
そう言って、ララモイは処刑人の足取りで近づく。
両手を広げ、俺に覆いかぶさり、蒸したイモのような香りとともに、頭を抱きかかえ――
そして、最後の理性的な思考は、露と消えた。
◆◆
私、砂原海白花(サワラミ・シラカ)。電撃使い!
宿敵との最終決戦で事故って、それで異世界に飛ばされたら、目の前には半裸に剥かれ卑劣な拷問を受ける想い人の姿が! 突撃しようにもとんでもなく硬い蔓にぐるぐる巻きにされて絶体絶命! どうしよう!
「うへへ……いーなあ……。青少年が羞恥で身を捩るの、本当好き……私このためだけに生きてる……」
チームメンバーのアヤメは恍惚としながら拷問光景を貪っていて、役に立たない! 私の方もレネゲイドの調子が悪くて何も出来ないから、正視できないけど様子を見守るくらいしかできてない!
「あっ、割烹着の子がキョウヤにハグしてる」
「実況やめてよー」
見ると、ララモイがキョウヤの頭に抱きつき、後頭部を優しくさすっている。
「あれさ、ぱふぱふだよね?」
「……うん。“私と同じで”絶壁だけど」
実際に何が起こっているかはともかくとして、相当に嫉妬を煽られる光景ではあった。
「『よしよし……』とか言ってない?」
「きーこーえーなーいー!」
耳をふさごうにも私の手は拘束されていた。
「あっ、終わった」
しばらくすると、ララモイはハグをほどき、キョウヤから距離をとった。
そのキョウヤの第一声はこうであった。
「ままぁ?」
その一声は室内を凍りつかせたようで、特にララモイは固まってしまっている。
「……まま?」
伺うようにツーズー。
「効いてゆ感触はあゆが……」
近寄って触れようとしたものの。
「ちがう! ままちがう!」
彼は、拘束されながらも身をよじって抵抗した。
それでも、ララモイは彼の頭を数回タッチし、結論を出す。
「……効きすぎゆね。一時的に赤ちゃんまで戻ってゆ」
ため息をつき、ララモイはしょんぼりと数歩下がった。
「まあそれはそうと……」
無垢を体現したかのような、トロンとした目で視線をさまよわせるキョウヤに対し、ツィールは頬を抱き、目線を合わせて投げかける。
「いくつか質問しよっか」
「んうー」
戸惑い。だが、抵抗はしていない。
「『ダークファルス』って知ってる?」
「わかんない!」
即答だ。実際私もわかんない。
「へー、それはよかった。だったら、『ファルスハーツ』ってなに?」
「れねげいどをつかってじぶんのねがいをかなえるそしき!」
ヒトの扱いに差があるな、とツーズーがぼやく。
「じゃあ次。『レネゲイド』ってなに?」
「わかんない!」
「まじかゆ」
己の領域を極め、未知すら切り拓く元凶は、「そんなもんよく戦闘に使えゆな……」と漏らしつつも、成り行きを見守る。
「うんうん。それじゃあ……きみの願いはなに?」
「ままをまもるの!」
「そっかあ」
一呼吸の間。
「そしたら最後に。この中に、きみのママはいる?」
「おそと!」
……んん?
「外……?」
ツィールが、ゆっくりと立ち上がりながら、こちらに振り向く。
歓喜に頬をほころばせた想い人と、目が合う。
「ままぁ!」
マジかー……。
ちなみに、アヤメは腹を抱えて笑い転げていた。
自由な足で、思いっきり蹴ってやった。
……
「それで……どうすんの? この赤ちゃんみたいなキョウヤを」
拘束を解かれ、室内。
六人も居ると狭い。
「多分二時間も経てば治ゆ。後遺症も大体一週間だと思ゆ」
ポテサラエルフの大魔術師は、申し訳無さそうに告げた。
「ふふ……『ママァ!』って……痛った小突くのやめて」
未だに笑いが止まらないアヤメを制裁しながら、どうせだからということで私もキョウヤに質問することにした。
「ねー、キョウヤー」
「んんあー?」
甘ったるい、と書いても足りないくらい糖度の高い声で、キョウヤが反応する。
「ママのこと、好き?」
「好きぃ……」
普段からは考えられない反応だった。
「へー……」
「今のシラカの顔もだいぶヤバい」
さっき蹴ったところをもう一度、蹴る。
そして続ける。
「ママもキョウヤのこと好きー」
「ままぁ……!」
うーん、プラトニック。ツィールが茶々を入れる。
「ゆゆ」
とても申し訳無さそうに、ララモイが割り込む。
「……ちなみに拷問術ゆから、今のは術が解けたら全部覚えてゆ」
「……うぇ?」
「うむ。ララモイが開発する術は、基本的にたちが悪いと思ったほうが良い」
固まる私、それでもニコニコと微笑むキョウヤ。
「私、明日からどういう顔してこいつと会えばいいの……?」
「……なんとかなゆ」
「まますきぃ……」
「キョウヤは黙ってて……」
◆◆
エピローグ!
結局の所、あの後俺たち三人は、まず研究室に入れられ、レネゲイドがなにかを徹底的に解析された。
その結果、オラクルの技術で言う『フォトン』で干渉することができると判明した。
暫くは要経過観察だけど、大きな問題が起こらない限りは、オラクルの市民として生活を送っていいらしい。
そして、オラクルでの朝が来る。
「……眠い」
そりゃそうだ。昨日の夜ふかしは、拷問がセットだったのだ。これはいくら若くても堪える。
「キョウヤ、あーさーだーよー!」
隣のルームから、シラカとアヤメが起こしにやってきた。
なんであいつらはそんなに元気なんだ。
「わかった、わかったから今起きるよ、マ――シラカ」
危ないところだった。
吹き出すアヤメがボディブローを受けている気もするが、気にしない。
過程はともかく、俺たちはたどり着いたのだ。
何もかもが片付いた、平和な世界に!
〈完〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
