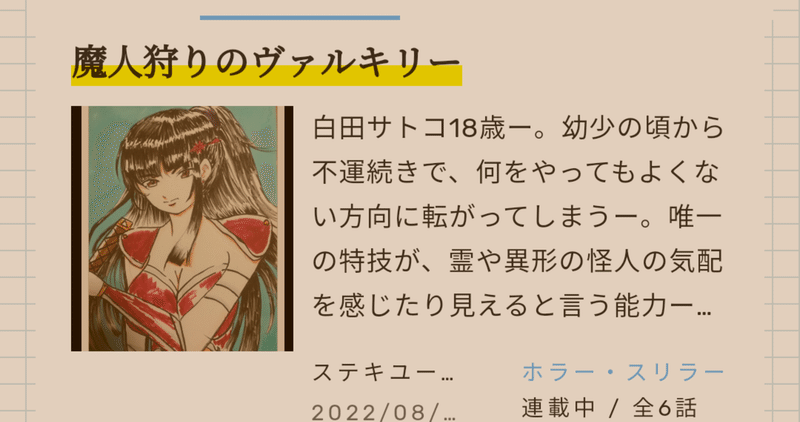
ステキブンゲイで、小説書いてます。(魔人狩りのヴァルキリー)
第九話 哀愁のレコード ③
マネキンは、口から赤い光線を放った。黒須は鎖を締める手をキツくし、一瞬で彼を地面に押し倒した。マネキンは黄色い禍々しい悲鳴を発した。口から次々と光線を放ち続けている。
「悪いが、お前の呪いは私には効かないよ。もう全て読めているんだ。」
黒須は冷淡で冷ややかな眼差しををマネキンに向けた。マネキンはうつ伏せになり、バタバタもがいている。マネキンに亀裂が生じた。そして、木の幹の様にメリメリ音を立てていく。その亀裂は深くなり、青磁色の光を放ち粉々に粉砕されてしまった。鎖は青磁色の光を放つと、消失した。黒須が左手を上げると、押し入れの扉が開き案山子がふわりと浮遊し、青磁色の光を発しながら黒須の側までやってきた。そして、黒須はぶつぶつと呪文を唱えると、案山子はぱっくり口を開いた。その光は案山子の中に吸い込まれていき案山子は口を閉じたのだった。
黒須は全身汗だくになっていた。彼女はどっと疲れて、その場にへたり込んでいた。案山子はカランと音を立ててその場に倒れた。黒須はゼエゼエしながら老婦の様子を伺った。老婦は静かに寝ているようだった。
すると、突然窓が開き奇術師風の優男が姿を現した。彼は窓の淵に立っている。
「やあ、君がまさかそこまで苦戦するとはね…」
男は高めの優しい声で話しかける。
「やはり、お前が仕組んだのかー?涼白…死者は道具じゃないぞ。指図め、自分の使えそうなドールを物色していたと言う事か?」
クロスは涼白を睨みつける。
「僕はただ実験していたに過ぎないのさ。魂の質量を測るためにね。強く質の良い魂だけを選別し、僕に従えさせる。僕は最近ら忙しいもんでね…道具が欲しいと思っただけなんだよ。」
涼白はトランプをパチパチ鳴らす。彼は#飄々__ひょうひょう__#とした感じの掴めない青年である。
「お前ー、何しに来たんだ?まさか、それだけの用ではないだろうな?」
クロスは鎌を構えた。彼の不敵な笑みからざわざわとする悪魔の様な不気味なオーラを感じ取ったのだった。
「白田サトコ…知ってるよね?」
涼白は目を細め、淡々と話した。
「…何で、お前、彼女を知ってるんだ!?」
黒須の鎌を持つ手は強くなる。
「僕は彼女の居場所を突き止めたんだ。マネキン君が教えてくれたよ。」
涼白のその言葉に、黒須は魚の様に目を大きく開き瞳を不安定に震わせていた。
ーどういう事だ…?白田サトコから霊力は全て抜き取り、霊が近寄らないように術式を与えた筈なのだが…。ー
黒須が動揺しているのを見て、涼白はにんまり不敵な笑みを浮かべた。
「あの娘の霊力は尋常じゃない様だね…実は、僕は情報通でね、あの娘の事はとっくに調べがついているのさ。」
涼白は悠々としながら得意げに話す。
「ーで、お前に何が出来るんだ…?あの娘には何も効きやしないぜ。」
黒須は、鋭い眼光で涼白を睨みつける。鎌を構え攻撃の大勢に入るが、全身の力は吸い取られたかのように重く倦怠感が下の大学。
「君は自分の力を過信しているみたいだね。でも、僕は君の術なんて簡単に読めるのだよ。」
ー!?ー
「『どうして?』って顔だね…君には言ってなかったようだね。僕の本当の力をー。」
「…だから何だっていうんだ…白田サトコとお前になんの関係があるんだよ?アイツはもうただの人間なんだぜ?」
「僕はね、彼女にずっと興味を持っていたんだよ。君はまだ知らないようだね。彼女の中に眠っている、真実をー。」
「…真実だとー?」
黒須は鎌を構える手を緩めた。
「君が何であの娘に思い入れがあるか知ってるよ…あのアオイって娘と瓜二つなんだろう?あの頃をかつてのアオイと自分と重ねて見ていたのかい?」
「…お前、何でアオイの事を…?」
「だから、前にも言ったろう…僕は情報通だって…実は僕は君と取引をしたいんだよ。」
涼白は、優しい眼差しで黒須を見ている。その言動に、黒須は苛ついている。
「…さっきから、調子の良い事をベラベラと…!今からその舌を切り取ってやろうか…!?」
黒須は、重たい身体をしきりにバタバタ動かす。
「白田サトコが僕のドールとなったあかつきには、君の恨みを僕が全て晴らしてやろう。」
涼白は、得意げに話す。
「…聞けるわけねぇだろ!そんな事…!!!」
黒須は荒い息を上げると、涼白目掛けて全力で走り込み、彼を斬りつけようとする。
「いやあ、君は実にわかり易いね。では、返事を待ってるよ。」
黒須の鎌が当たった瞬間ー、涼白の身体は淡い薔薇色の光に包まれ薔薇の花弁を放ち、消失した。
「待て!!!」
黒須は病室の外をくまなく見渡したが彼の姿はどこにもなく、ただカーテンが風に煽られているのだった。黒須は、軽く舌打ちをした。
それはバブルが絶頂の頃だったー。とある小さなコンサートホールの舞台の中央で、高校生位の青年がライブを催していた。彼はノリノリになりハスキーボイスでエレキギターを鳴らし、観客を沸かせていた。観客席は満員であり、女性ファン達が内輪やネオンを振りながら黄色い声援を送り続けていた。
「進一ー!!!」
5人で結成されたグループで、皆歳が若く才能を思う存分に爆発させていた。その中でも一番目だっていたのは、進一という青年であった。彼は長身の黒髪に、眉目秀麗で中性的な顔だちをしており、その甘いマスクと歌声に女性は心を鷲掴みにされたのだった。
辻山進一は、汗だくになりながらもテンポ良くリズムを刻んでいった。
ライブが終わると、女性ファン達がワラワラと進一達に群がってきた。進一は甘いマスクで笑みを浮かべ手を振ると、一人ひとりにサインを書いて渡していた。
進一が仲間と次の打合せを終え、会場を後にした時ー、一人の女が出迎えていた。赤いトレンチコートに赤いルージュの口紅をしていた。その女は進一の恋人であるようだ。進一は仲間と別れ、女と帰る事にした。
進一は絶頂だった。彼の歌唱力やギターの才覚はグループの中で軍を抜いており、その上美貌に恵まれていた。そして、彼の周りは常に色んな女が群がっていたのだった。その上、彼は女好きであり、有頂天になっていたのだ。
仲間はそんな彼を何度も諌めたが、彼は次第に傲慢になっていき、仲間を見下すようになっていった。次々と進一の側から離れて行く様になっていった。
進一は、仲間の事を観向きもせず酒と女に溺れ堕落する様になっていった。美貌の天使は次第に堕天使へと豹変する様になっていったのだった。
そんなある日の事ー。長年恋人だと思っていた女が自分に愛想をつかして去ってしまった。彼女は、他に男が居たのだ。
それは進一の自業自得であるが、彼は納得がいかなかった。
ー対した事のない女達は自分に簡単に振り向いてくれるのに、何で長年本気で愛した女は自分に振り向かないのだろうー?
そして進一は、彼女対して身勝手な強い憎しみを抱くようになった。彼の心の中の悪魔は力を増幅させ、禍々しい黒い感情に支配されてしまっていた。彼は、家から電動のドリルを持ち出し、彼女を付け狙い背後から突き刺し殺害したのだ。そして、彼はそれでは満足がいかなかった。赤いトレンチコートを着た黒髪でルージュの口紅をつけた女を見る度に、片想いの記憶が蘇ったのだ。そして彼は甘いマスクと持ち前の雄弁さで次々と女に手を出し、殺戮する様になったのだった。彼は頭の回転が速く、偽装工作はお手のものであったのだ。
そんなある日の事ー。警察は現場にあった遺留品の指紋から犯人が進一であると突き止めた。彼がうっかりつけてしまったのだった。警察は、彼のアパートを取り囲む様になる。そして進一は力尽き、首を吊り自ら命を断ってしまう。
それから突然異変が起き、次々と女性の不審死体が決まったエリアで見つかるようになる。
死体の共通点は、赤いトレンチコートの黒髪で赤いルージュの口紅をした若い女ばかりであった。その被害者達の遺体には、胸や腹をドリルの様な物で深々と貫通されえぐられた痕があったのだった。
警察達は犯人を探し、それは都市伝説として語り継がれていくのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
