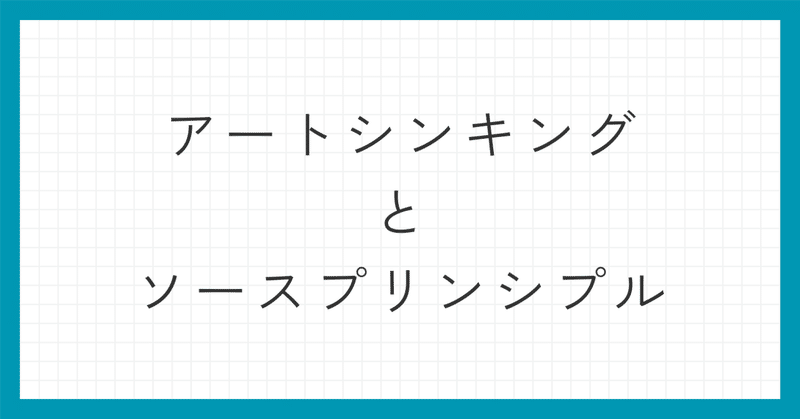
アートシンキングとソースプリンシプルの接点について考えてみた
はじめに
この記事はソースプリンシプルについて知っている方向けの記事になっちゃいました。知らないよ、という方は先にこちらの記事を読んでいただく方がスムーズかと思います。
私は一時期、アートシンキングにハマり、関連本14冊を読み、同じと違いを浮かび上がらせるといったマニアックな探究をしていました。
最近、とあるインタビュー記事でソースプリンシプル提唱者であるピーターカーニックの発言を見た時に「なぜ今アートシンキングが求められているか?」の理由がそのまま「なぜ今ソースプリンシプルが求められているか?」に置き換えられそうと思えたので、今回はそれをネタに記事を書こうと思います。
きっかけとなったピーターカーニックの発言とは?
Leadermorphosisというポッドキャストがあります。
こちらは、ホストのLisa Gillが「新しい働き方」「指導方法」などの最先端にいる世界中の実践者、作家、思想家との話をお届けするものです。過去には、「ティール組織」著者のフレデリック・ラルーも出演したことがあります。
Lisa Gillのプロフィール(ポッドキャストから引用)
リサは、セルフマネジメントチームとの取り組みが評価され、Thinkers50 Radar 2020 に選ばれており、『Moose Heads on the Table: Stories About Self-Manageing Organisation fromスウェーデン』(2020)の著者でもあります。彼女は組織自己管理コーチ、タフ・リーダーシップ・トレーニングのトレーナー、そしてReimaginaireの創設者です。
あるときゲストとして「ソースプリンシプル」提唱者のピーター・カーニックが出演したのですが、その中でパーソナリティのリサギルの話に対して以下のようにピーターが話しました。ここでピーターのいう「この種のコラボレーション」とは、ソースプリンシプルに基づくコラボレーションのことを指しています。
『この種のコラボレーションは、繰り返しになりますが、私たちが学んだことのないものであり、たとえば従来の教育パラダイムで教育されていないからです。
コラボレーションに関して私たちが学んできたことは、生産ラインのようなものです。左側から半分生、または 4 分の 1 生産された製品を受け取ると、直線的なプロセスが進行し、それに対して何かをして右側に渡すことになります。
この直線的なプロセスは、通常、私たちがコラボレーションと呼ぶものですが、それは現在必要とされている「何をすべきかを正確に指示される必要がない、創造的で革新的な人同士でのコラボレーション」には全く不十分です』
上記の「コラボレーションに関して私たちが学んできたことは、生産ラインのようなもの〜」という箇所について、後で出てくる「工場パラダイム」が効果的だった時代に生み出されたものだと思えたのです。また、ピーターのいう従来の教育パラダイムとは、「工場といった、ある意味で1つの正解(
製品)を素早く出し続けるプロセス」で活躍できる能力を学ぶことを目的としているものと言えます。
アートシンキングとの接地点とは?
前提として、アートシンキングと言っても、明確な定義があるわけではなく、それぞれの方がそれぞれの立場からそれぞれの思う範囲を「アートシンキング」として語っていると私は捉えています。
そのため、ここでいうアートシンキングとは、私が読んだ中で一番オススメの2冊(一番なのに2つw)の1冊である『ハウ・トゥ アート・シンキング 閉塞感を打ち破る自分起点の思考法』に書かれていた内容だけを指します。言い換えれば、著者である若宮和男さんのレンズで観たアートシンキングということです。
この書籍では、時代の変化に適応するためにパラダイムを「工場」から「アート」へ変える必要があるという背景のもとで方法論としてアートシンキングを紹介しているのですが、方法論をそのままソースプリンシプルに置き換えても成立するなぁと思えました。
こちらの本に感化され、図解したものがあるので「該当する箇所」を紹介します。



いかがでしょうか。シンプル化することによって文脈が削ぎ落とされる弊害がありますが、大枠をつかむにはとても理解しやすいパラダイムの分け方だと思いました。
私たちを取り囲む働く環境はまだまだ工場パラダイム前提になっている(がゆえにシステム不全を起こしている)というのは身に覚えがあるのではないでしょうか。
さいごに
著者である若宮和男さんのレンズを通して紹介されている「アートシンキング」の内容からはソースプリンシプルとの共通性が多数感じられるので、久しぶりに読み直したいと思いましたし、今の時点での記憶や当時私が図解化した範囲では、今回の記事の文脈でいうコラボレーション(協働)についてどう書かれているのか分からないので、その観点で見ていきたいと思いました。
また、この記事では肝心のアートシンキングとソースプリンシプルについてそれぞれが何か?についてほぼ説明していませんので、気になる方はぜひ以下の記事を読んでもらえたらと思います。
若宮さんのいうアートシンキングを図解化しようと試みたものがこちら。
14冊についてまとめたものがこちら。
ソースプリンシプルについてはこちら。
こちらもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
