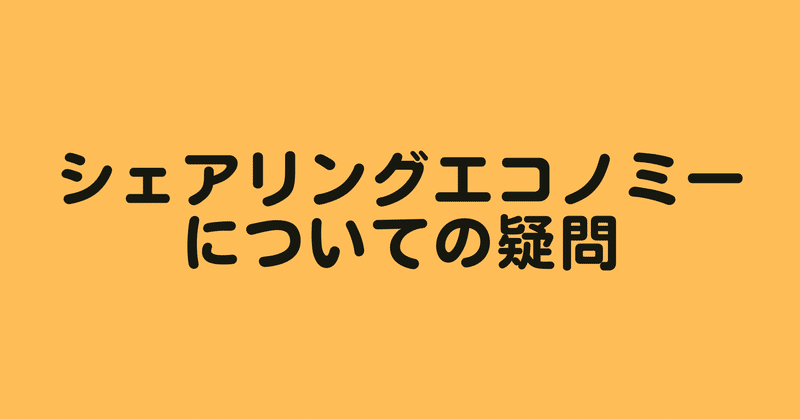
シェアリングエコノミーの普及は日本の国際的競争力に貢献するのか?
はじめに
実は最近私はシェアリングエコノミーが広がることの意義・価値について漠然と疑問を感じていました。
なので、今日はこのテーマを考察します。
シェアリングエコノミーとは?
場所・乗り物・モノ・人・お金などの遊休資産をインターネット上のプラットフォームを介して個人間で貸借や売買、交換することでシェアしていく新しい経済の動き
一般社団法人シェアリングエコノミー協会HPより引用
シェアリングエコノミー通称シェアエコは、サービスを主に5つに分類できるそうです。
空間(airbnb、SPACEMARKETなど)
モノ(mercari、ジモティー、airClosetなど)
スキル(coconala、AsMama、タスカジ、TABICAなど)
移動(UBER、nottecoなど)
お金(Makuake、READYFOR?など)
一般社団法人シェアリングエコノミー協会HP参照
私とシェアエコ
そんなシェアエコと私についてですが、正直実際にサービスを使った経験は少ないです。
レンタルスペースのSpayceeやSPACEMARKET
民泊のAirbnb
写真素材のshutterstock
クラウドファウンディングのReadyfor(支援者として)
印刷のラクスル
共同生活のシェアハウス(サービスは未利用。友人が経営する物件のみ)
古本屋のBOOK・OFF/ネットOFF、Amazonの古本購入サービス
(【2020年1月版】シェアリングエコノミー完全比較ランキング300選参照)
なぜ利用経験が少ないのか、過去にどういう思いで使ったのかなどは掘り下げると面白そうなので別立てで書いてみたいと思います。
なぜシェアエコに疑問を感じたのか?
それは、世界の中の日本という視点で捉えたときに生じました。
私は去年の秋から冬にかけて経済、政治、環境問題などをインプットしてきました。
その中で、世界の中での日本の現状を知ることになりました。
経済 → GDPは下がっている。デフレになって30年近く。しかし、デフレ
下で行うべき政府の政策は行われていない。
政治 → 軍事面とセットという意味でアメリカ傘下と言っても過言ではな
い。
環境 → 石炭火力発電を推進する姿勢を崩さないことで国際社会での評価
が下がり続けている。
もちろん、各業界ごとといったミクロで捉えるとそれぞれの分野で尽力し続けている個人・法人はたくさん存在するでしょうし、個人的にも知っています。
しかし、ファクトベースで俯瞰してみると世界の中での日本の存在感・影響力は弱まる一方だと思えてしまいます。
こういった状況の中でシェアエコがもたらしているものは個人単位でみると以下のメリットがあります。
・提供者
自分の喜び、不要なものがお金に変わる。
副業体験ができる。
新しい繋がりが得られる。
・利用者
欲しいモノ・経験が安く手に入る。
手に入らないと思っていたモノ・経験が手に入る。
新しい繋がりが得られる。
これらは、すごくいいことだと思えますし、だからこそ、思考停止になってしまいがちです。
一方で、俯瞰した目線でみると低コストでのやりとりが増えたり、もっと安く手に入れるには?という思考を助長し消費自体が減るのではないか。
そして、それが増えていくと、GDPという側面での国際競争力がますます下がるのではないか。と思ったのです。
つまり、シェアエコの普及は、世界の中での日本の存在感・影響力を高めることに繋がるよりもむしろ下げていくことに繋がるのではないかと思ってしまったのです。(国内での満足度・充実度は高くなっていくが、世界の中での国としては沈んでいっているイメージ)
だから、調べたり考えてみた。
とはいえ、私はシェアエコの関係者それぞれの立場においてのメリット・デメリットについて考えたことがないためそれらを並べた上で自分なりの結論を出してみることにしました。
シェアエコの関係者を大きく3つに分けました。
1)個人
さらに提供者・利用者に分けられる。
2)法人
3)政府
※地方自治体はここに含みます。
それぞれのメリット・デメリットを出していきます。
個人
提供者
メリット
販売体験ができる
収入が得られる
新しい繋がりが得られる
生産者人格が芽生える
自分の喜び・不要なものがお金に変わる体験ができる
デメリット
収入が不安定(プラットフォーム依存)
個人事業リテラシーがないと発注側にいいように使われて疲弊する
利用者
メリット
欲しいモノ・経験が安く手に入る。
手に入らないと思っていたモノ・経験が手に入る。
新しい繋がりができる
興味関心、価値観が近い人
デメリット
提供されるモノ・サービスの品質は不確実である
法人
メリット
死んでいた資産・資源を利活用でき、売り上げアップになる
新しい繋がり、関係性ができる
デメリット
自社の商品・サービスと競合するシェアサービスがあると売れなくなる
政府
メリット
利用されず負債になっていた法人・個人の資産が現金化される
赤字運営の公共施設が黒字化、運用されるようになる
就業支援、福祉サービス、観光促進の黒字化・質の向上に繋がる
自治体の課題解決に繋がる
デメリット
市場価格等で買う機会が減るため個人の消費額が減る。
→本当に減ったのかは要検証
現時点では、個人間取引の売り上げは計上されないため、GDPという指
標で数字が下がる(政府は2018年から改善に向けて動いている模様)
→参照記事その1・その2
また、上記の分類に当てはめることはできませんが、経済面で起こりうる事象について書くと、
シェアサービスが流行るほど、社会の需要と供給のマッチングの精度が上がるので、社会全体の無駄が減る。「本来の価値以上の価格」で売ることが難しい時代になる。
シェアリングエコノミーとは?本当のメリット・デメリット計20選より引用
があります。
また、上記に伴って、これまで大量生産・大量消費前提のビジネスモデルで進めてきた企業にとっては売り上げ減どころか、存続の危機も訪れます。
そうなることで、企業は「無駄・ゴミを出さないように」という視点で事業、商品を設計していくことになり、シェアエコの普及は結果としてサステナブルな社会づくりに寄与することになると言えるかもしれません。
まとめ
上記のように書き出してみて思ったこと。
(1)個人間取引の反映は急務
シェアエコが普及したとしても個人間取引の数字がGDPに反映されなければ、国際競争力へは繋がらないと思いました。(2018年から政府がこちらに取り組んでいるようです。)
(2)他国も含めた新しい国家の幸福度を表す指標づくりまで昇華できるかGDPという指標そのものの限界説も以前から叫ばれています。
以前、日本では、ブータンの国とセットで知られたGNH(国民総幸福量)が有名かもしれませんが、こちらは調べてみると人口あたりのGDPが含まれているのですね。
2019年度のランキングを見るとブータンはなんと95位。。。
日本は58位です。。。
トップ10のうち8国がヨーロッパの国(もっといえば北欧の国が5カ国ランクイン)であり、ニュージーランドとカナダが頑張っています。
アメリカ、中国、ロシアなどの大国のランキングはトップ10圏外です。
落合陽一氏の書籍「2030年の世界地図」によればSDGsの評価指標はヨーロッパ諸国がランキング上位になりやすいものと書かれていましたが、
この指標も「北欧すごい!」「ヨーロッパいけてる!」というブランディング(国際的影響力に当てはまる)に寄与するものと言えます。
また、最近知ったのですが世界寄付指数(人助け・寄付・ボランティアの3指標で評価)といったGDP以外の指標もあります。
こちらの記事では、2009年に始まったこの調査の10年間分を集計した総合ランキングが紹介されていました。
ここでは、日本の総合順位は126カ国中107位でした。
また、トップ10にミャンマー(2位)・ニュージーランド(3位)・オーストラリア(4位)・スリランカ(9位)・インドネシア(10位)と東南アジア、オセアニアの諸国がランクインしているのが印象的でした。
これらの国は、この順位を誉れとしていたり、国際的に活用しているのか(そもそもできるものなのか不明ですが)は分かりませんが、ランキングの構成国が異なるという意味では違った指標を打ち出すことができているのかもしれません。
一方で、こちらの記事によると、例えば寄付の項目については「過去1ヶ月以内に寄付をしたかどうか」という条件で調査されているそうです。
日本人の場合は寄付文化がないと言われることが多いですが、例えば災害時や歳末助け合い募金などに寄付している人が多いのではないか。
しかし、そのタイミングを外した1ヶ月以内になると数値は必然低くならざるをえないのではないかというようなことを書かれていました。
こちらを読んだ時に、確かにどういう人向けにどういうタイミングでどんな内容を調査したものなのかまで遡らないと、一方的にランキングが低いとミスリードされてしまう可能性は高いと思いました。
色んな指標はあれど、少なくともこれらのランキングにおいては日本が上位に位置しているものはありません。(私の情報は少し検索した程度なのでもし知っている方がいれば教えて欲しいです。)
もちろん、捏造はいけませんが
・世界の人の真の幸福に繋がる
・日本が実際にその要素を持てているがまだ、あるいは十分に可視化されていない
といった要素を指標化し、その指標に他国を巻き込んでいく動きをとっていけば国際的影響力・存在感の増大に寄与することができるはずです。
シェアエコが作り出す従来の枠組みとは異なる人と組織の繋がり、そこで交換されている価値、生み出されている価値は、もしかしたらそういう指標づくりに昇華できるかもしれない。
シェアエコを普及させていくことがそういうチャンスだと捉えると意義・価値を感じることができました。
(3)止まっているよりも動いた方がいいはず
政府のメリットに記載した利用されず負債になっていた法人・個人の資産が現金化されること。これは言い換えれば止まっていた資源が循環することだと言えます。
この循環については、政府や経済などを自然と見立てた場合、価値があることだと思います。
しかし、そこにどんな価値があるのか?については勉強不足のため分かりません。
組織が腐る、経済、政府が腐るとはどういう意味なのか?逆に、組織、生命、政府が活き活きとしているというのはどういうことなのか。そのために何が必要なのか。
このあたりについては発酵や、東洋医学の気血水の話などメタファーとして捉えられそうなテーマは浮かんでいますが、学んでいないため、今後のテーマということにしておきます。
さいごに
消費者1人1人の姿勢が未来に影響している
今回、日本の国際競争力を高める手段としてのシェアエコについて考えてみました。
しかし、話が広大なため個人としてどうすればいいのか?というと迷ってしまうと思います。
私はこのことを考えた時にサステナビリティや環境問題に積極的に取り組んでいる、映像作家であり、クリエイティブディレクターでもある、リチャード・グレハン氏の話が浮かびました。
彼はこんなことを言っていました。
「消費生活の中で何を買うか選ぼう。その選択は、自分がどんな未来に投票していきたいかの表明だ。」
素晴らしい言葉だと思います。
こちらについて考えてみることがこの記事を読んだ後にすぐに取り組めることなのではないでしょうか。
例えば、本記事ではシェアエコの普及が間接的に、企業へのサステナビリティ教育になりうると書きました。
実際に企業がサステナブル、サーキュラーに事業を考え、無駄のない事業づくりが実現するか、その動きが加速するかは私たち1人1人の選択が大きいでしょう。
つまり、私たちは常に購買行動を通じて何かしらの未来づくりに貢献しているのです。
(余談ですが、個人的にはSDGs・サステナビリティといったテーマでの
ランキングはヨーロッパ優位でひっくり返せないと思えるので別な指標を日本が打ち出せたらいいな、そうしたいなと思っています。高齢者対策指標とかいいかも。)
「じゃぁ、どんな未来づくりに投票したいの?」この問いについて考えることは同時に、自分がこの社会に存在し所属しているということでもあると思えます。
ぜひ考えてみて欲しいなと思います。
追伸:なぜ国際競争力を高めることが大事だと思っているのか?
そもそも今回の課題設定には、前提に国際競争力を高めることが大事だという私の考えがあります。
国際競争力とは言い換えると、交渉の際の武器と言えるかもしれません。
なぜこれが大事だと思っているのかというと、もし、超大国(アメリカ、中国、ロシア)に軍事を振りかざされると自由も選択も自治も一気に失われると思っているからです。
(しかし、戦争を起こすよりも経済発展してもらえる方が損失が少ない・利益が大きいからこそ戦争を起こしていないという側面があります。)
そしてそれらの国には日本の価値観、常識、ルールは通用しないと思っています。(日本はどこかで自分たちだけで通用するルールを通したい欲求が強いのではないかと思うことがあります。しかもそれに気づいていない。)
だからこそ、以下の2つは絶対に押さえておくべきポイントだと思ってます。
・国としてのできる限りの自立(エネルギー・食料の自給率、軍備・自衛)を果たす努力はし続けるべき。
・できる限りwin-winの交渉を可能にするための影響力・存在感を保つ、上げ続けるべき。
つまり、自衛のために国際競争力の向上を念頭に置くことは重要だと思っているのです。
とはいえ、このあたりについてもまだまだ知見が足りないので引き続き学んでいきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
