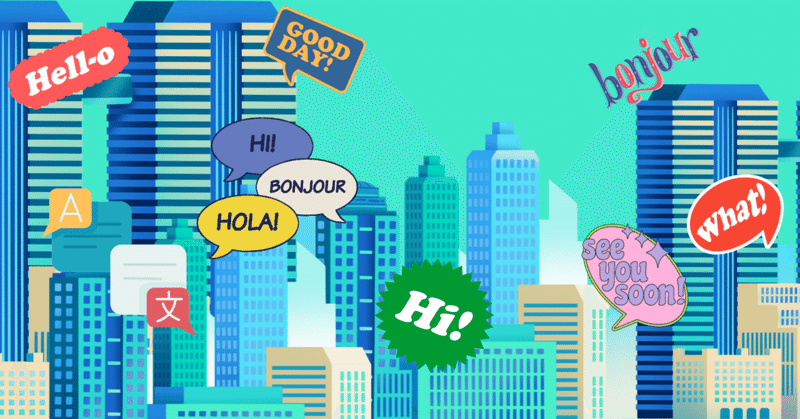
英語がペラペラじゃない人が、外資系企業で働きたいと思ったら
私が大学生のころ、人気の就職先といえば「ゴリゴリの外資系企業」だった。マッキンゼーやボスコン、P&Gやジョンソンエンドジョンソンなどがそれにあたった。
最近の学生はどんな就職先を好むのだろう?
外資系と一口にいっても、業界や職種によって様々なので一概に言えることは少ない。
ただ、もしこれから外資系企業で働きたいという方が、新卒・中途問わずいるとして、恐らく最初に抱くのは「英語ダイジョウブかな…」という不安なのではないかと思う。
なお、私は10年以上外資系企業に勤めているが、もともとネイティブの英語話者ではない。
英検も持ってない。TOEICは、大昔に880点を取得して以来一度も受けていない。下がっている気しかしないのでもう受けないことにしている。
それでも外資系企業で英語を使って仕事ができているのには理由がある。それは、英語が公用語になっている会社でキャリアをスタートしたから。これに尽きる。
私が新卒で務めた会社は、日本法人でもすべてのメールおよび会議が英語で行われる環境だった。
最初は正直面食らった。何言ってんのかまったく分からなかったからだ。
でも、これから初めて外資系企業に勤めようとする人、特に英語がネイティブなわけじゃないという方には、叶うならこのタイプの企業に入ることをおすすめする。
なぜなら、公用語になっているということはつまり、全員がその公用語を問題なく扱えるようになる必要があるので、そのためのトレーニングが充実している可能性が高いからだ。
実際、私が勤めていたこの会社では、特に新卒者に対しては綿密な英語教育が行われた。
そして、同じような英語教育を受けた人だらけで構成される組織の会話がどのようになるかというと、一定の型を使った会話になるのだ。
つまり、全社員が
「私はAだと思います。理由は3つあります。1,2,3・・・」
という形で自分の意見を述べる。
だれも好き勝手に
「私は昔こういう経験をしたので、Bかな~と思ったんですが、今回はAもいいなーと思って。1つの理由はこうで~、あ、2みたいな理由も考えられますよね~」
みたいな発言をしないのだ。
これはある意味ビジネス上のマナーともいえるかもしれないが、英語という(全員が慣れているわけではない)共通言語を使用しなければいけないという制限がかかることで、より強固なルールとなる。
話を遮る時、誰かの発言に反対したい時、逆に強く同意したい時、全員が特定のフレーズを口にする。これは非ネイティブにとってとてもよいシステムだった。
その結果、どの国のどんなバックグラウンドの誰が発言しようが、内容はシンプルかつ同一教育を受けている全員にとってわかりやすい形になり、英語を使って仕事ができる環境が整うのである。
また個人的には、ビジネス英語の方が日常会話より簡単だと思う。
日常会話のようにジョークが入ったり、あっちこっちに話が飛ぶ会話は苦手だ。
英語を使った会食やランチに呼ばれると、お腹が痛くなりたい、と思う。英語のプレゼンなら平気なのに。
ごく個人的な経験談でしかないので、どこまで汎用性があるかは不明だが、1社目で身につけた型を使いまわして2社目で問題なく仕事をしている私のような人が実在はしているので、ひとつの参考にしていただけたら嬉しい。
そして仮に、冒頭に述べたような環境が整った会社にいなくても、自分で型をある程度身につけられさえすれば、少なくとも英語で言いたいことは言えるようになるのだと思う。
(周りが同じ型を使うかは分からないにしても…)
やはり何事も渦中に飛び込んだ方が学びは早い。留学などもそうだが、英語を使うしかない環境に身を置くことこそ、近道だろう。
そして、「守破離」と言う考え方もまた真実。
一度型さえ身につけてしまえれば、あとは周囲のネイティブの言い回しを盗むもよし、自分なりのアレンジを加えるもよし。
自由演技で楽しめるようになることだろうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
