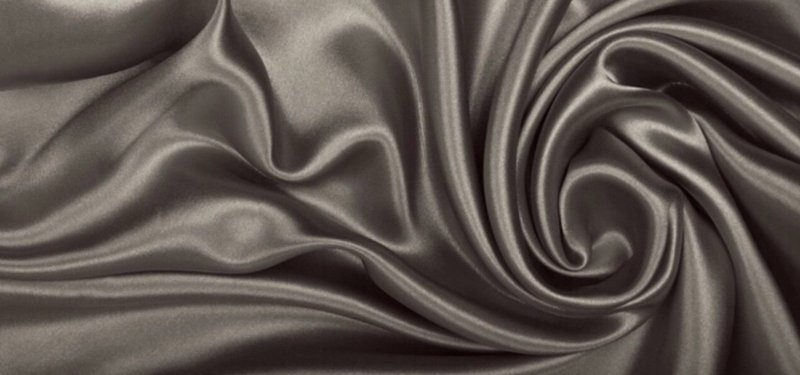
小説『あれもこれもそれも』1. ⑧
*過去の話はコチラから*
小説『あれもこれもそれも』
story1. 呪術的な日常 ⑧
「ねえ、芳彦は誰かを憎んだことってある?」
「えっ、憎む……ないんじゃないかな、多分。そんなことある?」
「そうだよねえ、普通ないよね」
バイトが早めに終わって、芳彦が寝てしまう前に僕もベッドに潜り込むことができた。今日、常連客に言われたことを自分なりに噛み砕いてみたが、自分の中に〝憎しみ〟という感情はどうしても見当たらない。もしかしたら僕は負の感情の認定基準が高いのかもと思ったので、具体例がないかどうか恋人に尋ねてみたのだ。しかしやはり彼だけではなく、誰に聞いてみたところで答えはみな同じような気がした。
「嫌いになったり、生理的に受け付けない人はたまにいるけどさ、憎しみってなかなかの熱量だよね。その感情に至るまでに、深い親交とか強い期待とかがないと起こらない気がするよ」
芳彦は愛憎という言葉を的確に表現する。そして多分『僕らには分からない感情かもしれないね』とほのめかしてもいる。少なくとも彼と僕は、現実……というか男女の恋愛を前提とした世界においては、人間関係の熱量を上げないようにして生きてきた。どうせ違う世界にいるんだから、と。こういった生き方はよく指摘されるように、傷つくことを恐れているからなのかもしれない。人を憎むようになる以前に、人に対する感情の熱量の上げ方そのものを、どこかに置き忘れてきたのかもしれない。
今日も携帯アプリを介してセックスに誘うメッセージが何通も届いていた。液晶の中には、そこかしこに〈ヤリモク〉〈サクッと〉〈後腐れなく〉という、予防線を張ったような言葉が並べられていた。きっとこんな言葉からは、憎しみなんて生まれようもない。
……ともかく、憎むには何か順序らしきものが必要そうだ。もし常連客が言ったように、僕が健斗を憎んでいるとしたら、いったいどんな順序があったというのだろう。これだけ考えているのに全く分からなくて苛々する。頭蓋骨を引き抜いて、ひっくり返して振ってみて、それでも、心当たりになるものは何一つ落ちてきそうにない。
「あっ」
唐突に声をあげたのは恋人の方だ。
「それに近いもので嫉妬なら分かるよ。サラブレッド女優が天才女優に嫉妬して『憎い、あの子が憎いわ』とかいう漫画なかったっけ?」
芳彦のテンションが急に上がり、それと一緒に掛け布団も一瞬跳ね上がった。冷房の風が布団の下に潜り込んできて、ひんやりとして気持ちよかった。芳彦、きっとまたくだらない茶番でも始めるんだろうな。と、仕方なく彼の方を向くと、案の定、漫画の登場人物の物真似を交えながら1人でけしゃけしゃと笑っている。
「はいはい、世代違いです」
「でも分かるでしょ。ち・な・み・に、あの漫画は今も続いているんだからね」
一連の茶番が僕を思いやるユーモアだと分かっていながら、今日はどうも乗る気になれない。脳は常連客の言葉を反復し、心は確実にその空き容量を少なくしていった。たとえば『好き』と言われると、その言葉が意識に重層して、心の領域にまで積もるようになって、いつしか本当に好きになってしまうことがある。感覚は近いのだが、負の言葉の影響力はそれを遥かに越えていて、まったく手に負えない。百歩譲って、僕が健斗ことを嫌いでもいい。しかし〝嫌う〟と〝憎む〟の間の距離は、近づいたり離れたりしてなかなか定まらない。
「……誰かに何か言われたの? 考えても分からないことはそのまま別の誰かに投げちゃうって手もあるよ」
彼はそう言って、僕の頭に手のひらを乗せてくる。だから芳彦に投げてみたのに。詳しく聞いてこようともしないし、ふざけてばかりじゃん。頭上の手だって中途半端に大きくて、それも僕を苛つかせた。手を払いのけ頭を懐に差し込んで、額を芳彦の鎖骨に押しつけぐりぐりしてやった。「いててて」と言いながらも、彼は笑って僕の肩を抱き寄せた。
僕は大学に行くと、オフィスアワーに呪術の教授の研究室を訪れた。実際の専門は文化人類学で、呪術でないことは分かっていたが、今のところ彼のことはそうとしか呼びようがなかった。アポイントを入れずに訪室したことを怒られたが、シラバスに連絡先の記載がなかったことを告げると「では本題に移ろう」なんて言って、はぐらかされた。僕は意を決して聞いてみた。
「人を呪うという行為の源泉はなんでしょうか?」
過去の話はコチラから
ご支援頂いたお気持ちの分、作品に昇華したいと思います!
