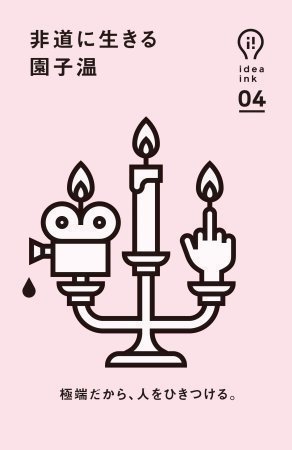激烈過る表現論-『非道に生きる』(映画監督・園子温) これは一種の起業家論だ
『ヒミズ』や『冷たい熱帯魚』など、激烈な作品で有名な園子温監督の著書『非道に生きる』は200万ボルトぐらいのエネルギーを急速充電できる一冊です。既存の映画スタイルをぶち壊す爽快感と、自分の欲望を真っすぐに突き詰める潔さ。そして、創造するバイタリティ。起業家になっても成功できるような人ですね。心のど真ん中に突き刺さりました。
(以下抜粋)
もしも映画に文法があるのなら、そんなものぶっ壊してしまえ。もしもまだわずかに「映画的」なるものが自分に潜んでいるとすれば、それもぶっ壊してしまえ。映画がバレエや歌舞伎や能や日本画や、そんな伝統芸能に成り下がったのなら、とっとと捨ててやる。そんな気持ちで映画を撮ってきた。
自分の才能とやらを後生大事に守っているうちは、つまらない映画監督にしかれない。下水道に叩き落されて、ドブの水を浴びるほど飲んで、才能の欠片もないとせせら笑われているときに、燃え立つような「やる気が」が出て、めまいがするくらい憎しみが湧き立つ。その「刹那」に行きたい。
誰しもメジャーになるまではインディーズなりの戦い方というものがあります。自主映画を作っていたころの僕にとっては、作品の内容や価値よりも「いかに自分の名前を売り込むか」ということのほうが大切だった。というのも、どれだけすごい映画を撮っても、試写にも来ない、観客は来ない、誰にも知られない、では作っても無駄だからです。だから「こいつは一体何者なんだ?」と思わせる仕掛けをいかに作るかということばかり考えてきました。
たとえ資金が乏しくても一生懸命やればどんな映画だって確実にヒットさせられる。
もちろん普通にやってても当たるはずがない。
・まず場所によってまくチラシをまったく変える。
・マンションの「燃えるごみ」置き場のバケツのふたの裏側にチラシを貼ったり、電車の壁面の広告を(よっぱらいのふりをして)チラシに差し替えたり、本屋で売れている雑誌に勝手にチラシを挟み込んだりと
そもそもたいていの映画は映画しか意識していないように思います。テレビのバラエティや AVも意識しないで「映画的」と言われる得体のしれないものだけを探る人が多い。映画にかかわる人は目に見えるものすべてをライベルだと思わないと成長しないように思います。テレビドラマでも Avでもアートでも、いま窓の外に見える風景でも、すべて映画と同じレベルに存在している。「映画は映画だ」と、何か独立したものととらえているようではだめ。だから僕は「映画的」や「映画史」といった言葉が好きではない。
ロック音楽にしても、「ロック的」「ロック史」と言い出したとたんに、ロックというものがすごく閉じたカテゴリーになってシーンが終わるんだと思います。透
最低最悪の映画になったとしても、自分の欲望を映画に焼き付ければいい。そうすれば欲求不満がたまらないんじゃないか。映画について初めてしっかり目覚めた感覚を味わいました。いわば「撮るべき映画」から「撮りたい映画」へのシフトです。
自主映画を撮っていたときは、タルコフスキーやゴダールの作品を真面目に研究するあまり自己分裂して、自分の欲望や人生の喜びがどこか遠いところに行ってしまっていた。おそらく、他人からほめられたい、評価されたいおいう自意識のせいだと思います。でも幼いころはポルノやエクソシストを見て飛び散るゲロに興奮していた。だから自分が映画から受け取っていた原始的な感動を開放して、好きなものを何でも混ぜ込んでしまえばよかったんです。もしもお前がおっぱいが好きなら、そのことを包み隠さず露わにせよ、という啓示といってもいい。
「この映画を傑作にする」などと思わない態度。「これを撮ったら死んでもいい」なんて思ったらン荷が重すぎて精神的にもビジネス的にも必ず行き詰ってしまう。むしろ「とにかく進めば、その先のステップがある」くらいに考えたほうがいい。未来における作品の制度よりも、未来のために自分の今を大事にする。何事も常に「次」への足掛かりでしかなく、永遠の過程なのです。
演技は最初のシーンの最初のカットが一番大切で、そこで追い込んで心構えをきっちり確率させておけば、後の演技はだんだんよくなる一方です。それまで何テイクも延々と同じことをやらせました。
僕の現場ではまず、この場面ではどうしたいのか、役者に自由に動いてもらいます。それを見たうえで、僕が照明や撮影などのプランをその場でスピーディに立てていく。役者に判断を預けると、与えられた自由の中でもがいて新しい芝居を見つけてくれることがって面白いのです。
みんなが言いたいほうだい言える空間にしておくことが、事前に考えてもいなかった発想を呼び寄せたり、つらい撮影現場でのガス抜きの役割を担ったりします。
映画に込めるべきは「情報」ではなく「情緒」ですy。整理整頓された言葉を仕入れたいだけなら、本を読めばいいし報道をみればいいい。セリフのボキャブラリーにしろ、シーンの持つ意味にしろ、映画の中の言葉は市井の人々の肉声でいいのです。
出来事の追想ではなく、出来後 tの真っただ中にいるときの気持ちや情感を、貧弱な言葉でもいいからそれでつづること。
そもそも何かしらの極端さや過激さを求めなければ表現など面白くありません。日本人が無前提にしんぼうしている「日本映画の王道」は眉唾もので、いい映画を撮るための「伝統のスキル」が安定してあるかのように、ある種の傾向の作品ばかりを評価してきました。当然ながら、そんな環境からは、既存のテクニックを更新し、新しいことに意欲的に取り組むカメラマンも技術者も生まれません。
現代の品文化は無色透明といっていいほど色がない、というのが僕の印象です。日本文化から今の時代の空気感を強く感じることはほとんどありません。
なので、時代に合わせるという問題設定をすること自体が、とても難しい時代になっています。
この問題に対しる僕の戦略はありません。戦略を立てる対象が曖昧模糊としているときには、もう四方八方にハリネズミのごとくとがるしかない。リサーチやマーケティング、とにかくそうした類のものから作品を発想しないこと。それが自分の「戦略」といえば戦略です。次に何が飛び出すかわからないように努力したほうがいい。
「時代を先回りして読む」ことが不要な時代。そこでもっと突っ込んだ話をするなら、表現者は自分で時代を作るぐらいの気持ちでいればいい。具体的には「量より質」ではなく、「質より量」で勝負することです。自分の作品が認められない、と時代を嘆くのではなく、自分の作品を無視することができないくらいに量産して時代に認めさせればいいのです。
以前の作家が複数人で作っていたのと同じ分量を、自分自身で作る。そうやって、自分の作品が受け入れられるコンテクストを自分自身で生み出せばいい。
一本の映画製作のために時間をかけすぎると、出演者の選択をストーリーの展開に気をもむ時間ができてしまう。そうした実務的な弊害もあります。時間も予算も限られた「愛のむきだし」を作ったときには、自分のことなんかかまう暇はなかった。だからよかったんだと思います。「ハリウッドにでも行って新人からやり直したい」くらいの気持ちでもって、若いころの無鉄砲さへと自分をけしかけたい。今ここであえて大量生産を標ぼうするのは、自分のつまらない自我をぶち壊したいからでもあるのです。
しかしどんな逆境においても、自分に嘘をつかないように心掛けてきました。実のところ、僕が知っている多くの「偉大になりたいけれど、なれない人」はどこかで自分を騙していいる人たちでした。僕は取材やインタビューでも恥ずかしいことも丸ごと言えてしまえる作家でありたちお思います。自分をよく見せようとするのは、僕の偉大さのアーカイブにはない。
これから映画を作っていく人たちは、自分が面白いと思うものを見つめなおしてほしいと思います。どんなカレーであれ、美味しければ人を惹きつける。それと同じように、人は面白い作品を無視できないという基本に立ち返ってみてほしいのです。
他人が面白がるものをまねるのが人の常ですが、自分が本当に面白がっていないなら意味がない。自分が面白いと思えば、少なくとも一人は面白がっていることになる。つまり自分という人間一人は少なくとも自分のことを面白がっている。ゼッタに確実は「一人目のお客さん」だと思うのです。たとえ他の奴がマスターベーションだのナルシストだのと言ったところで、兵器のへいちゃらで自分が面白いと思うものだけを追求すること。それが非道の生き方です。
同じ考え方をするために生きるのなら、生まれなくてもよかったとさえ思います。
少しでも面白くないと自分が思うことは一切やらない。それを他人が「非道」と呼ぼうが知ったことじゃない。自分が面白がっているかどうかなんて、そもそも子供のころは一発でわかるもんもです。
映画をみても他人のレビューなんか読まない。他人があざ笑おうが、面白ければずっとその映画を評価し続ける。自分の映画の評判だってどうだっていい。僕が面白いんだからそれでいい。それがもっとも確実に面白いものを発見できる方法です。本で読んだり、先生から教わった「面白さ」あんてどうせ既成概念そのものだし、教われば教わるほど、どんどん普通の考え方をする奴になってしまう。
とにかく自分を疑わないこと、面白いと思ったことを断念しない。自分を信用しない自分なんて悲しすぎる。自分が自分のより良き理解者であること。でないと、自分は自分と無関係になってしまいます。
サポート頂いたお金は全額書籍購入費に充てさせてもらいます。