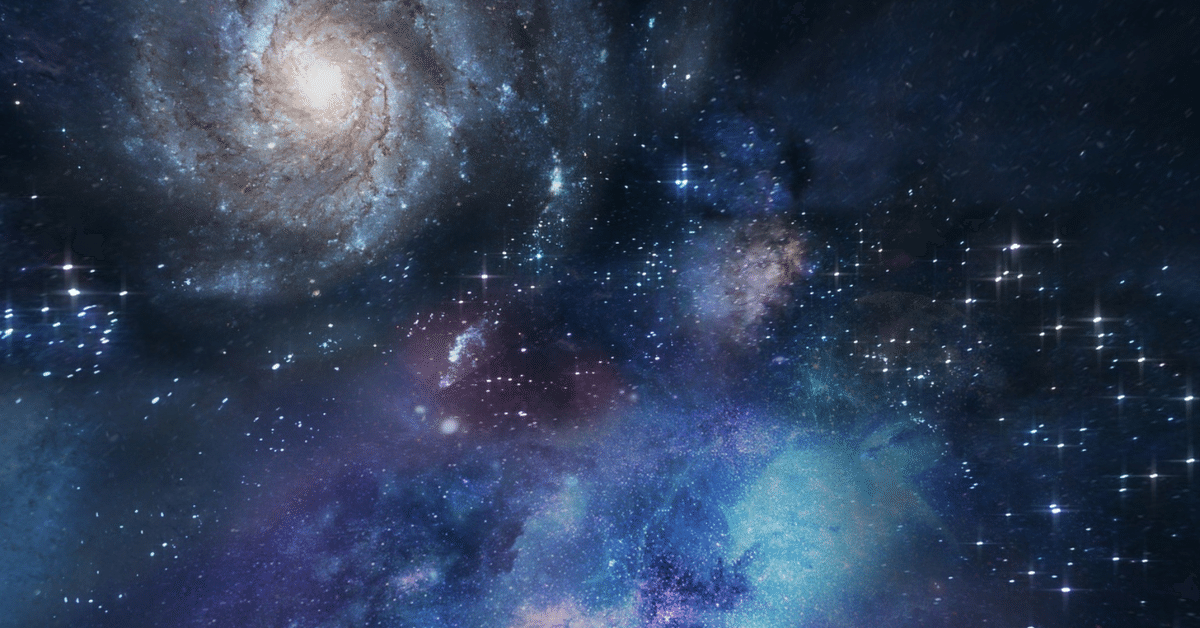
科学があれば哲学は要らないのか 『メタ哲学入門』第3章まとめ
「メタ哲学」は、哲学の分野の一種です。主に三つの問いを扱います。すなわち、①哲学とは何か ②どのように哲学をすべきか ③なぜ哲学をすべきなのか の三つです。これらの問題は、哲学に関心をもつ私たちにとって、どれも非常に重要です。ケンブリッジ大学出版局から刊行されている『メタ哲学入門』を下敷きに、メタ哲学初心者のレートムと勉強しましょう。
お世話になっております、レートムです。
この記事では「自然科学がこれほど発達している現代において、哲学の仕事は残されているのか」という疑問に対する、メタ哲学なりの応答をまとめています。
いま私はPCを使って、noteというプラットフォームで記事を執筆しています。
文字だけではなく音声でもお楽しみいただきたいので、Twitterのスペース機能を使って同様の内容を配信しています。
その意味で、私はもちろんこの記事を読んでいる皆さん(そして配信を聞いている皆さん)は、コンピュータ科学の恩恵を受けていると言えます。
一介の初学者でしかない私がこうして気軽にコンテンツを発信できているのは、科学の飛躍的な発展のおかげだということです。
それに比べて哲学はどうでしょう。
コンピュータ科学だけではなく、数学や物理学など他のあらゆる科学が日進月歩の成長を遂げているなか、哲学の発展・進歩という話になると、どこか心もとない気持ちになるのではないでしょうか。
例えば、かつては典型的な哲学の研究対象とされていた私たちの心についても、心理学や神経科学が非常に多くのことを解き明かしてくれています。
仕事ができる人のところにより多くの仕事が集まるのは必然ですから、このままでは哲学は全ての仕事を他の科学に奪われてしまうかもしれません。
哲学の勉強をこれからも続けることは、ひょっとして無駄なのでしょうか?
私たちは哲学書を捨てて白衣に着替え、実験や観察を通じてこの世界を解き明かす方向へとシフトすべきなのでしょうか?
この記事が扱うのはこういった問題です。
ただしあらかじめお伝えしておくと、「哲学にはまだするべき仕事が残されている」というのがこの記事のさしあたりの結論となります。
すでに哲学書を売り払い白衣を購入してしまった方々も、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。
皆さんにとってこの記事が、哲学を始めるモチベーションや、もっと好きになるためのきっかけとなれば幸いです。
哲学はもう必要ないという考え:助産師説・残余物説
まず初めに、私たちが取り組む問題を明確にしておきましょう。
すなわち「自然科学がこれほど発達している現代において、哲学の仕事は残されているのか」という問題です。
この主張を代表する人物として、「車椅子の物理学者」として知られるスティーヴン・ホーキング氏が挙げられます。
彼は次のように述べています。
哲学は現代科学(とりわけ物理学)の発展に追いついていない。知識の探究における発見の光は、科学者が手にしているのだ。
冒頭でもお伝えしたとおり、現代科学の発展する速度と哲学のそれには、大きな開きがあるように思われます。
しかもホーキング氏によれば、かつては自然科学で解決することが困難だった問題(例えば「なぜ宇宙が存在するのか」など)も、進化を遂げた科学ではすでに対処可能だというのです。
このように、哲学で扱う問題は徐々に自然科学へと吸収されていくのだという考えは、メタ哲学における「助産師説・残余物説」として知られています。
前々回の記事では、この「助産師説・残余物説」を次のように紹介しました。
つまり哲学とは、そこから多様な科学が生まれてきた源泉であるという意味で「助産師」であり、研究の主題に関する知識がまだ明確でないため科学とは呼べないという意味で「残余物」なのです。
かつて「哲学」とされていた分野のなかに、現在では物理学・天文学に分類されるであろうものが含まれていたことはよく知られています。
哲学とは未熟な学問であり、研究が進んだ暁には自然科学の一部として確立されるのだ──これが「助産師説・残余物説」の考えです。
ホーキング氏の主張は、かろうじて「残余物」としてその役割を残していた哲学も、今や綺麗さっぱりお役御免になったのだというものだと言えます。
しかもこの考えは、自然科学の側からのみ提出されているものではありません。
哲学者の中にも、こうした考えを支持している人々はいます。
アメリカの哲学者であるウィルフリド・セラーズもその一人です。
世界を記述・説明するという側面において、科学は万物の尺度であり、存在するものについては存在するとし、存在しないものについては存在しないとするのだ。
たしかにセラーズも主張するとおり、現代に生きる私たちのほとんどは、科学的に実証されないもの(例えば霊魂や天使など)の存在を認めないという立場に立っています。
こうした立場は「存在論的自然主義」と呼ばれています。何が存在するのかは成熟した自然科学によって決定されるのだとする立場です。
そして、こうした「万物の尺度」としての科学の立場は、科学が世界を客観的に──観点から独立に──説明できるという事実とも関係しています。
したがって私たちが取り組むべき問題は、「〈科学による客観的な説明だけが世界をあるがままに記述しているのであって、哲学による説明が入り込む余地はない〉というのは本当か」という形で表すことができます。
これに対して私たちは、「たしかに科学は重要だけれど、哲学的な説明の重要性はなくならない」と応答します。
次の節で詳しく説明しましょう。
二種類の自然主義を区別して考える:存在論的自然主義と方法論的自然主義
先ほど「存在論的自然主義」という言葉が登場しました。これは、〈何が存在するのかは成熟した自然科学によって決定されるのだ〉とする立場のことでした。
実は、この考えと「哲学はすでに終わってしまった学問であり、あとのことは自然科学に全てを任せるべきだ」という考えにはギャップが存在します。
後者の考えは「方法論的自然主義」と呼ばれるものです。その名のとおり、「この世界を探究するための方法は自然科学を措いて他にない」と考える立場です。
存在論的自然主義と方法論的自然主義は別物だということを明確にするために、ケンブリッジ大学の天体物理学者であるA・S・エディントンの「二つのテーブル」の話を例に出しましょう(Eddington, A. S. 1928. The Nature of the Physical World. Cambridge: Cambridge University Press. xi-xiv.)。
エディントンは、私たちに馴染みの普通のテーブルと、彼が科学的テーブルと呼ぶものを区別します。
私たちに馴染みのテーブルとは、私たちがコーヒーカップなどを置くために使う、何らかの色をもったアレのことです。
それに対して「科学的テーブル」とは、客観的視点から眺めたときのテーブルの姿のことを指しています。
それは一体どのような姿をしているのでしょうか?
まず、「コーヒーカップを置くためのものだ」というのは、インスタントコーヒーにしろミルで豆を挽くにしろ、コーヒーを飲む文化をもった私たちに対して現れる性質です。
テーブルをいくらよく調べてみたとしても、「コーヒーカップを置くためのもの」ということは判明しません。
また「何らかの色をもっている」ということさえ、客観的な性質とは言えません。
例えば、色覚異常をもつ方々が見ている世界と私たちの見ている世界ではその色合いが全く異なることは有名な話です。
そのため「色」とは、あくまでも自分の感覚器官である目を通したときに見えるものに過ぎません。
そのためテーブルについての客観的な記述に色は登場せず、「そのテーブルはしかじかの波長の光を反射している」というべきでしょう。
「方法論的自然主義」が主張するような客観的な世界の捉え方は、まさにこういった類のものです。
確かにこうした記述が妥当であることは間違いないでしょう。しかし私たちは、この記述のみで満足することができるでしょうか?
どうも怪しいように思われます。
むしろこの世界について隈なく説明するためには、「私たちがそれらをどのように経験しているか」──私たちはテーブルを何のために使用しているのか、私たちはテーブルをどのようなものとして眺めているのか──という視点が不可欠なのではないでしょうか。
ここで重要なのは、私たちの日常的なものの眺め方のなかには、「存在論的自然主義」が否定していた非科学的な存在者たち──霊魂や天使──は一切登場しないということです。
つまり、私たちは「存在論的自然主義」を採用しているのです。
そしていま明らかとなったのは、そこから必ず「方法論的自然主義」を支持しなくてはいけないわけではないということです。
もっと言えば、私たちが生きているこの世界を適切に描写するには、私たちの視点から見た世界を描写するためのもう一つ別の方法が必要だということです。
ではここで言われている「もう一つの方法」とは何でしょうか。
それが、〈人文科学としての哲学〉です。
人文科学としての哲学
誰しも一度は耳にしたことのある「人文科学」という言葉ですが、念のため復習しておきましょう。
事の始まりは、自然科学が大きく発達した16世紀にまで遡ることができます。
これにより、観察や実験といった方法を使って世界を解き明かそうとするムーブメントが興りました。
ここで研究の対象となる「世界」のなかには、他ならぬ私たち人間も含まれています。
一方で、こうした動向に対立する学問も存在しました。
それが、当時哲学とも密接な関連を有していた神学です。
神学は、〈人間は単なる自然の一部ではなく、世界に対して独特の関係を結んでいる〉という考えに立つことで、自然科学の意見に反論しました。
こうした考えを共有する複数の学問分野(哲学も含みます)が、まとめて「人文科学」と呼ばれるようになったのです。
そのため人文科学では、私たち人間にとってこの世界がどう経験されているかが重視されます。
ここで改めて、人文科学(哲学)と自然科学の違いを考えてみましょう。
二つの違いを明らかにすることで、両者が「世界を正確に記述・説明する」という目的にそれぞれ別々の仕方で役立っていること──それゆえどちらも不可欠だということ──がもっとはっきりするでしょう。
二つの違いは、それが〈誰にとっての世界を説明しているのか〉ということを基準に理解することができます。
すでにご紹介したエディントンのテーブルを例に説明しましょう。
人文科学(哲学)は、「私たちから見た世界」を説明することを目的とした分野だと言えます。
例えばエディントンが述べるような私たちに馴染みのテーブルは、用途や色をもった対象でした。
そして「物を置くため」という用途や「オレンジ、赤、茶色」といった色合いは、テーブルを使用し眺める私たちに依存した性質です。
それに対して徹底した自然科学は、「特定の誰かの目線に立たない」客観的な説明を目的とした分野です。
エディントンのいう科学的なテーブル像では、私たちに依存した性質は度外視されるため、テーブルの用途や色については扱いません。
これら二つの観点は、この世界を余すところなく描き切るためにはどちらも不可欠なものです。
そして二つの観点はほぼそのまま、人文科学と自然科学という二つの学問分野に重なっています。
そのため、自然科学がどれほど発達したとしても、哲学を人文科学の一種と考えるなら、そこにはなお固有の探究領域が残されていると言えるのではないでしょうか。
今回のまとめ
・〈哲学とは何か〉という問いについて、自然科学の発展に伴って哲学に固有の問題は失われつつある(あるいは失われてしまった)のだという考えも存在する
・哲学者であっても非科学的な対象は考慮に入れないという意味で、自然科学の成果を高く評価している(〈存在論的自然主義〉)
・一方で、科学がこの世界を適切に説明する唯一の方法だという考え(〈方法論的自然主義〉)には異論の余地があり、哲学による探究も世界の重要な一側面を捉えるものとして不可欠である
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
