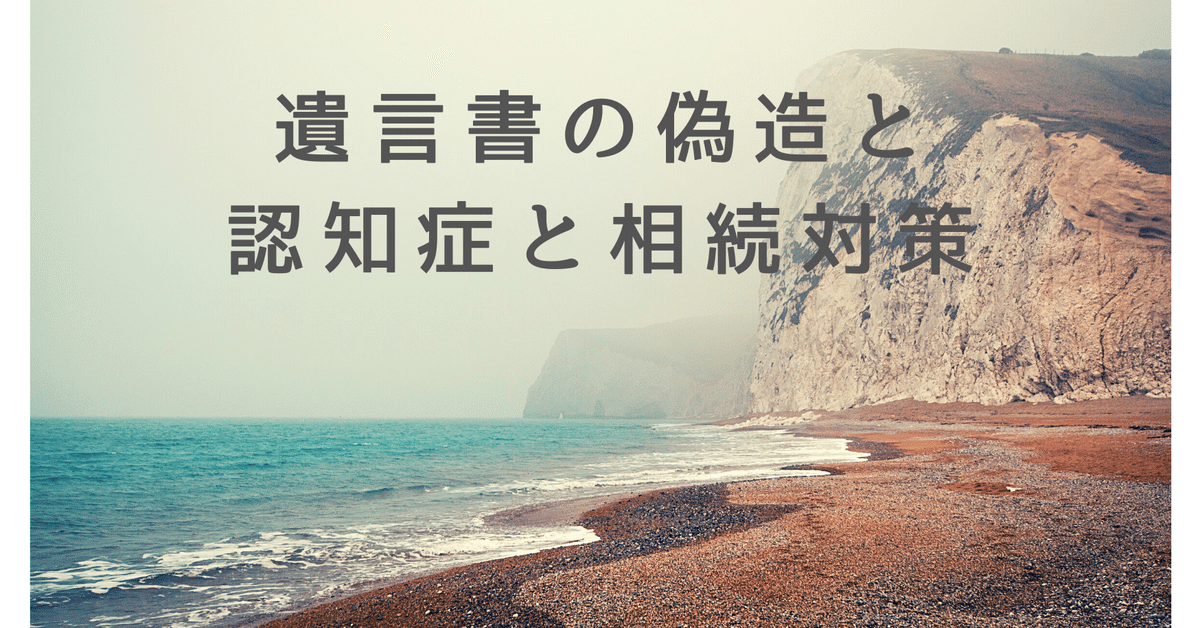
遺言書の偽造と認知症と相続対策
こんにちは!相続コンサルタントの髙山です。
先日、知人のAさんが「認知症の人の相続をするのに遺言書が作成されていた、文字も書けないのに、裁判も」という相談をされた話しを聞きました。
話の内容によっては髙山さんにお願いしたいと言われましたが、「ここまでくるともう弁護士案件ですよ、非弁行為をするわけにもいかないし」とお断りしました。
・文字を書けないのに書いてある
・本人の筆跡ではない(代筆)
など、相続あるあるの話しにちょっと驚きました。(あからさま)
偽造が疑われた場合
一般的には以下のとおり
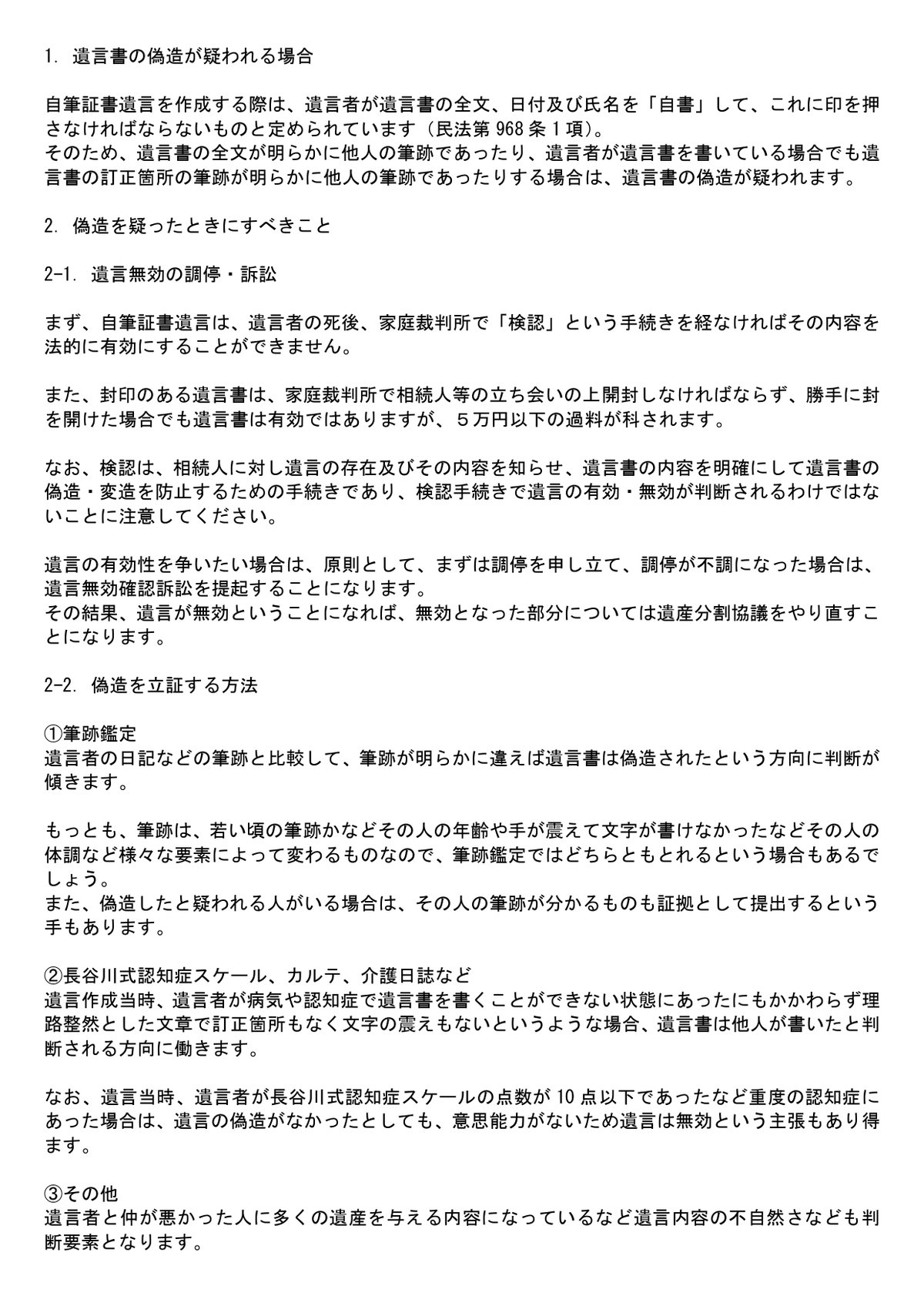
認知症になったら
「認知症=遺言書が書けない」ではありません。
作成するときの本人の意思能力や行為能力の有無が大事になってきます。
医師の診断書、介護記録、家族の証言等から総合的に判断されます。
意思能力を証明するために、心療内科を受診して「意思能力に問題なし」という診断書を取得するのも一つの方法になるでしょう。
遺言書の効力
遺言書は最高の生前対策と言われています。
それは遺言書で多くの相続問題を解決することができるからでしょう。
・相続トラブルの回避
「想い」が伝わり感情面での対立が減る
・相続人の負担を軽減
相続手続きや費用負担が減る、遺産分割協議書が戸籍の種類が不要や減る
・渡したい人に財産を渡せる
相続人以外のお世話になった人へも可能
・その他
遺産分割の禁止の定め、内縁の妻と子の認知、後見人の指定、相続分の指定などなど
早めの相続対策を
認知症と診断されたら基本的には相続対策はできなくなり、意思能力のない中で行われた法律行為は無効になります。
厚生労働省の発表によると認知症を患う人は2025年には700万人を超え、これは65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症という計算になります。(10年前より1.5倍増加)
そして認知症の前段階である「軽度認知障害(MCI)」を合わせると、高齢者の4人に1人が認知症またはその予備軍になります。
このような状況だからこそ、早めに相続対策に取り組むことが重要になってくるのではないのでしょうか。
相続対策には生前贈与など色々ありますが、最強の相続対策は「家族が仲良く暮らすこと」です。
そして円満に相続するポイントは
・家族会議で合意の形成
・現状把握を専門家に依頼
・ひとりでコソコソすすめない
になります。
相続コンサルタントは家族会議の司会進行をして主張の調整を行います。
家族会議について少しでも気なる方はお声がけください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
