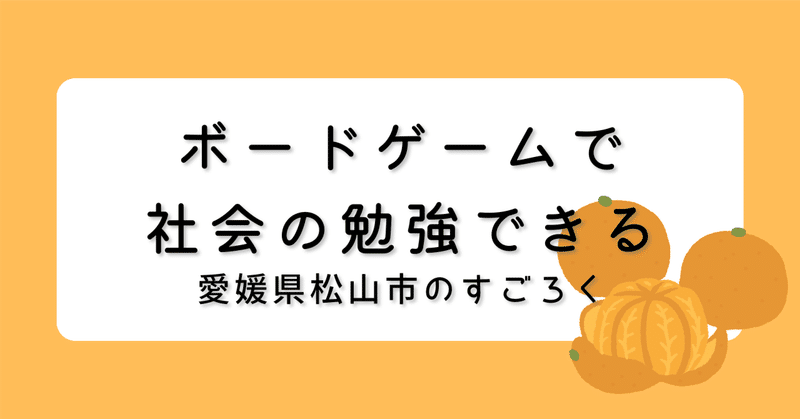
楽しく学ぶを目標にすごろくを作ってみた
教育関係で探求学習をテーマにした子どもの居場所づくりに地域のNPO法人さんと関わらせてもらってます。そこは方針として「女性の社会参画」とか「ジェンダーギャップ解消」といったことをテーマに活動しているのですが、私もちょこちょこ加わってまして。
そして12月初旬に仕事や暮らしに関するイベントを三越地下のブースで開催しました。
そのイベントで先ほどの探求学習の塾(?)PRのためのイベント企画やら中身を考えたのですが、これが結構楽しんでもらえたので、そしてもったいないので誰かに見てほしい。というか買ってほしい(図々しい)
と思ってちょっと出してみました。
イベントでは親子で参加できて面白い!楽しい!しかもランキング出されるんか!と色々仕掛けを用意して盛り上がりました。
イベント用に作るだけではもったいなくて
イベントだけに作るにはもったいなくて、なんや勘やでベースを作るのに10時間ぐらいこれに費やしてます。(マジかよ)
探求学習がテーマの活動なので、表面的なことを考えるだけではいけないのよ。
とはいえこれだけでは何やってるかわけがわからないと思うので端的にまとめると、「子どもたちに教科学習以外の体験をさせる場」を作っています。
なんでボードゲームにしたのか?というと、三越だし、イベントターゲットが家族連れなので親子だろうと・・・。そして親子で知恵熱でる遊びやった方が面白いだろうと。さらに言えば地域のNPOがやってるので地域のことを子供達が知ってくれれば楽しみながら学べるだろうと。
色々な思いがありました。
で定常的に活動している場所の名前は「まちのがっこう+」です。ここでの活動はフィールドワークと課題発見とその解決をしたり、小学生を対象に活動していますが、低学年は地域探索がメイン、高学年は経済活動がメインのカリキュラムになってます。
なので地域情報×経済的視点を養うボードゲームがいいなと最初に考えた。
そして活動場所が愛媛県松山市の中心街なので、子供達が参加するフィールドをボードゲームに落とし込むことにした。
実は松山市には路面電車があり女子一人旅全国一位を獲得した、お手軽旅ができる街でもある。
本当に一泊二日あれば大体のことはできる。近郊に自然もある。
松山市の中心街を回るのであれば大体1日1万円もあればお土産と体験で十分なのである。
ということで手持ち金を1万円として路面電車の旅のボードゲームを作ることにした。
ボードゲームの内容
プレイヤーは最大6人まで。そしてゴールは自己申告制というトリッキーな内容です。所持金が最初に1万円渡されますが、路面電車の乗車券を購入するので大人は1000円引かれ、子供は400円引かれます。
「最初に乗車券分は引いといてよ。」とよく言われましたが、リアルな旅ではそうではないのでリアルに寄せました笑
路面電車は山内線みたいに外回りと内回りがあります。松山市駅をスタートしてサイコロを振って進路を選択します。
プレイヤーは県外から来たトラベルプランナーという名目で路面電車の旅をスタートさせます。
各マスにはイベントかお土産があります。お土産は愛媛限定のものもあれば関係ないものもあります。イベントでは愛媛の地元民なら「あ〜ね」となるようなトピックを用意しています。
例えば、
道後温泉では旅行客と仲良くなってお小遣いをもらう
駐輪禁止の場所に停めて違反の罰金
通勤ラッシュのエリア
などがイベントとしてあります。そしてお土産では、
紅まどんな
鍋焼きうどん
鯛めし
などなど。愛媛の有名なものがわかるようになっています。
どうすれば勝つことができるか?というところですが、愛媛ならではのお土産・体験・運・戦略思考があれば勝てます。トラベルプランナーなので愛媛を満喫しないと旅のプランなんて考えられませんよね。
なので勝ちパターンは愛媛のお土産をフルで集めるということです。ちなみに先に誰かが獲得したお土産は同じマスを踏んでも獲得できない。ということで早い者勝ち要素もあります。
最終的にどういうふうに順位をつけるかですが、お土産の金額の×2~4が最終資産となります。さらにゴール手前でロープウェイ券が売られているので、それを買うと、最終資産の1.2倍が最終となります。
なので手持ち金額からどんどんお土産を買って、早めにゴールしたら良いということにもなります。(※他の人の動向にもよります)
手持ち金が1000円から500円を切った段階で、ゴールへ向かうか申告を考えます。
というのも・・・ロープウェイ券は参加人数の約半分の枚数しか発行されないというルール付きです。
なので路面電車でぐるぐる回って、お土産を買っても良いけれどもロープウェイ券で1.2倍を取るもよし・・・なかなか計算力を使わせるゲームです。
実際には電卓を用意しておくと良いです。
イベントの時も大人の方がのめり込んでました。選択肢が色々見える分大人の方が考えながら進めていましたね。
本当はもっと作りたい
本当は楽しみながら学べる知育玩具を色々と作ってみたいのだけれど、時間があまりないのと、お金に余裕がないのでこういった趣味に近い活動がなかなかできない。
次に作りたいなあと思っているのは、
山脈系→日本の山脈がわかるボードゲーム、プレイヤーは登山家
各地域の産業がわかる系
各地域の歴史がわかる系
地域社会とかは楽しみながらじゃないと覚えられないのではない?というのが自論で。暗記の内容は薄っぺらいものと思ってます。
やっぱり旅行に行った時に自分の知識・思い出と擦り合わせる感動があった方がいいなと思う人です。
そして自分が楽しみながらでないと地理や社会は本当に覚えられないな・・・という記憶があるからです。
コロナ禍で経験が不足しがちだし、不登校の子はフリースクールで学べる場と学べないところの格差が激しいし。
いろんなところで活用したいものです。
うーん、営業力が欲しい笑
社会の教員免許持ってます
ちなみに社会の教員免許を持ってます。
でもオンラインの家庭教師では数学を教えています。
すごい珍紛漢紛(チンプンカンプン)ですね。
社会全般が苦手でコンプレックスがあったので、それが一番大きなところですが、シンプルに知ってみたいと思ったのもあります。社会は本当に先生トーク力の良し悪しが顕著に出る教科だと思ってます。
特に自主的に社会を捉えるかどうかが社会の教科を知れるかのポイントにもなりますが、社会課題をそう捉えて行動している生徒さんはとても少ないです。主任者教育というのがあるのですが、社会問題を自分ごとと捉えてもらうための教育のことです。
みんながみんな政治家や国家公務員などになるわけでもないのですが、流石に投票にも興味がないというのは伝える側の不足を感じています。
切り口は今回ボードゲームでしたけど、身近な地域を経験で感じ取ってもらうのが主任者教育の初めの一歩でもあるんじゃないかな?と思います。
でも子供たちみんながそんな大層なものになることを望んでるんじゃなくて、自分で選んで考えて行動しましょう。をゲームの中でも経験できてもらえると嬉しいですね。
ダウンロード
こちらからダウンロードできます。
ルール表も記載しています。
内容物
ボードゲームのボードA3
お土産表
金種表
ルール表
各マスのお土産一覧表
ルールは足りない、わからない!が出てきたら勝手に足してOKです。
わからなかったらコメントやメッセージくれると喜びます。
駒とサイコロは用意してね!
100均で揃います。
駒は自分で作っても良いし、めんどくさがりな人はお弁当のデザインピックの尖ったところをニッパーとかで切れば完成します。
ボードゲームのデータはA3の2枚分です。
こちらはコンビニのカラー印刷を使うと良いです。2枚をうまく貼り合わせるとA2サイズになるので、一般的なボードゲームのサイズとなります。
金種表は正直多すぎるぐらい用意しています。切るのも大変なので、各金種が5~15枚ずつあれば事足りるかなと思います。
至らない点が多いけれど、こういうのもっと作りたいなと思います。
もっと画像でみたいという人はインスタの活動記録を見てください。ボードゲームの様子も投稿しています!
https://sites.google.com/view/machinogakkou-plus/instagram?authuser=0
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
