
羊角の蛇神像 私の中学生日記⑮
ぼくは窓ガラスを破る
私たちの寮に、不穏な空気が立ち込めていた。
Aくんは私のことをひどく憎んでいるようだった。
私の一挙一動に感じる彼の苛立ちは、ヒリヒリとした重い空気として私に伝わるのだった。
厳しく詰め寄るようなこともあった。
寮には居室が3つあった。6畳か8畳ほどの和室の、1番手前が私の部屋だった。
奥の部屋ほど寮長先生たち家族の居住スペースは遠くなる。
先輩たちが奥の部屋に集まって、何かを話したりしている気配を感じる夜があった。
Wくんは日に日に弱っているようだった。
3年生たちから呼び捨てにされ、こき使われ、常に萎縮しているようだった。
私も憔悴していたのだろうか。夜の眠りが浅くなっていたのかも知れない。
本館の休み時間、私は机に突っ伏して仮眠をとっていた。
すると、私の頭を誰かが小突いてきた。
私が顔を上げると教室から走り去るBくんの後姿が見えた。
その悪戯が、何度か繰り返された。
Bくんは、その頃でも私に直接ひどいことを言ったり、したりすることは無かった。
私たちの関係性において、それは子どもじみたただの戯れだったと思う。
しかし、私は強い眠気に襲われていたこともあり、気持ちが荒んでいた。
今度やられたら、窓ガラスを割ってやる。
私はそう、自分に暗示をかけるように想った。
そうして私はその通りに廊下側の窓ガラスを拳で割ったのだった。
後悔など微塵も感じなかった。
あれは私の声無き悲鳴だったのかも知れない。

ぼくは正義を言い訳にする
希少なまじめ枠(非非行もしくは不登校)である私の器物損壊について咎める先生はいなかった。
むしろ、先生たちは戸惑っているようだった。
寮の状況について先生たちは情報共有していたのだろうか。
保護観察で送致されるようなイレギュラーな子どもたちが引き起こすトラブルやいざこざには慣れっこ、という様子でもなかったと思う。
クラスメイトが、私の手に怪我が無いか心配してくれた。
私が割ったガラスは薄い磨りガラスだったので軽い力で破裂するように割れた。したがって、強く打ち抜くというよりも、スナップを効かせて割った。ガラスがあった面より奥に手を入れれば怪我のリスクは高まる。
ガラスを拳で割って怪我をするのは、ガラスの割れ目に触れてしまった場合と、枠に残ったガラスに触れた場合の2通りあり、いずれもガラス面よりも向こうで起こる怪我だ。
人生でガラスを割ったのはこの時だけだが、経験者として説いておく。
寮への短い帰路は、他寮で学年の違う人と情報交換や交流のできるわずかな時間だった。
隣の寮の先輩が私に告げた。
「ガラスのこと、Cが怒っとったで。『あいつ調子乗っとう』って言ってたで」
そんな、情報は要らないのである。
それを聞いたところで、どんな対応ができるだろう。
「寝ぼけていたんだ」と嘘をついて、わざわざAくんやCくんの前でBくんに謝罪して、服従する姿勢や先輩たちを敬う態度を示せば、うまくいくだろうか。
そんな風にうまく立ち回れる私ではない。
児相の習慣を持ち越して、上級生を呼び捨てにしたりなどしない。特攻服で暴走し、裏に刺繍の入った学ランで喧嘩をしまくるような恐ろしい人たちに対してさえ、うまくできなかった私なのだ。命に関わる自分の愚かさを呪いつつ、それでも私は私で良いはずだと思いたかった。
自分の心に嘘をついて、Wくんとの数週間の交流を無かったことにしたBくんと私はちがう。
恐怖に服従するくらいなら、私は孤独な異邦人で構わなかった。
しかし、能力(できるかどうか)と自己選択(するかしないか)は大きく異なるものだ。そして、そのふたつの違いよりも、結果の方が社会では重視されることを知っている。
私がくだらない正義を説いた所で、それは空気の読めない自分がついた強がりに過ぎない。
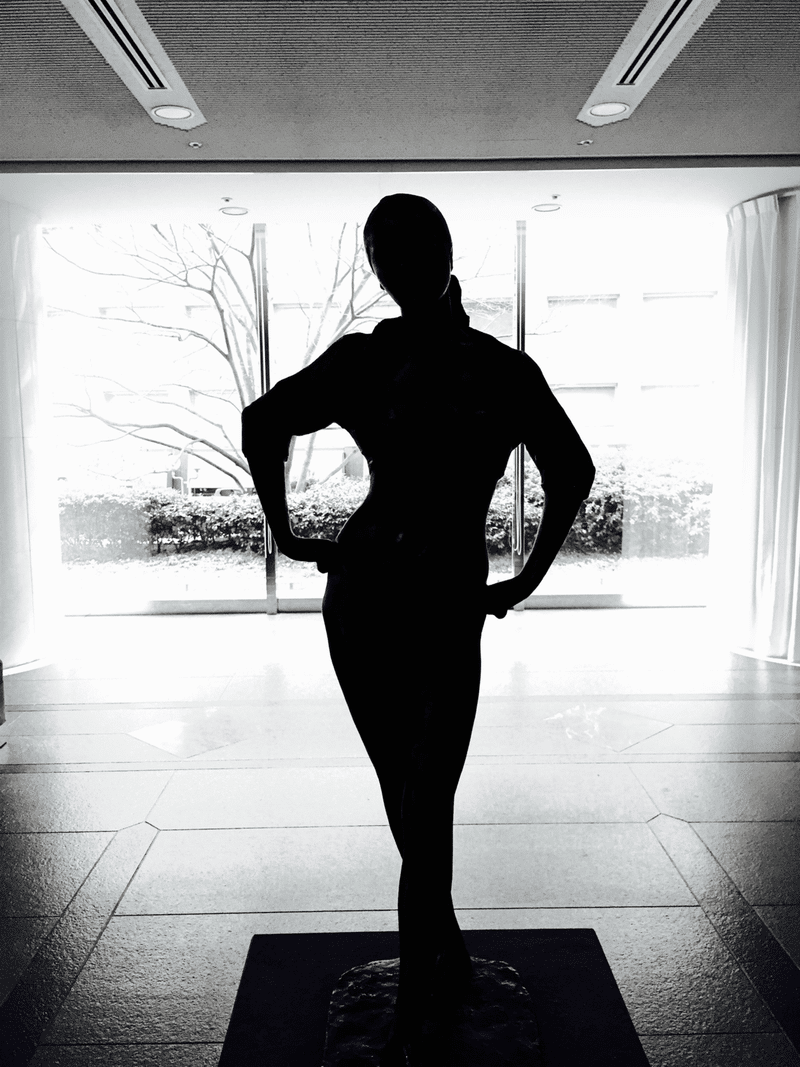
ぼくたちは母の前で泣く
何か、学園の行事に母が来てくれることになっていた。
本館で会う同級生や下級生が、行事のあとに家族と出掛けることをうれしそうに話していた。
私も出掛けられると思って楽しみにしていた。
行事が終わって、母が寮に来た。
母に連れ出してほしい旨を伝えたが、寮長先生が不思議そうな顔をして、今日はそういう予定は無いと言った。
本館で誰々が、今日は家族と出掛ける日だと言っていた、と抗議する口調で私は言ったと思う。
たぶん、それはその子の寮独自の話だろうと先生が言った。
とても楽しみにしていたので、中学2年生の私は幼い子どものように泣いた。
荒んだ寮の暮らしの中で、どれだけ母とのささやかな外出を心待ちにしていただろう。
母は子どもを慰めるように微笑んで、「お正月になったら帰れるから」と言った。
学園に暮らす私たちには「帰省」というものがあった。
長期休暇に、最大2週間まで家に帰ることができたが、無断外出をしたり、煙草などの悪事が見つかると罰として帰省期間が減るとか、全く帰れなくなるといったルールがあった。
少年法による保護観察はかくも厳格なのだった。
正月やお盆には、不祥事の無かった子どもたちの半分以上が帰省する。中には孤児や家庭の事情で帰宅できない子どももいた。
24時間、休みなく子どもと生活を共にする十景(寮長夫妻)も長期休暇には交代で1週間ばかりの休暇が与えられた。
帰省によって数の減った寮生たちは、休んでいない十景の寮に集められて、普段とは違う寮での暮らしを経験した。
これは「集中管理」と呼ばれていた。
話は前後するが、私は帰省の日数を減らされて集中管理で隣の寮で生活したことがあった。
まじめ枠の私だったが、不祥事を起こすことになるのであるが、それは少し先の話。
母が来た日のことを書いていて、思い出したことがある。
Bくんのことだ。
ある週末に、Bくんの母が面会に来たことがあった。
Bくんの母だと紹介されなくてもわかるほど親子はそっくりだった。
ふたりの会話の内容は勿論知らないが、母親と話し、帰る母親を見送りながら、Bくんは泣いていた。
私はBくんの家庭のことなどは知らない。
彼もその穏やかでお茶目な性格とは裏腹に、煙草やシンナーを吸い、刺繍の入った特攻服で山を攻めたりしていた不良少年だった。
Bくんに限らず、彼らはよく見えないバイクのハンドルを握り、バイクを吹かす「ボボボンボー」というような音を口で鳴らす、バーチャル暴走に興じていた。
青春とは、見えないギターをかき鳴らしたり、見えないバイクにまたがったりすることなのだ。
それで、そういう不良少年だったBくんにも家族がいて、誰も知らない背景があるのだ。世間に迷惑をかけた彼らだったが、ひとりひとりに様々な事情があったのだ。
子どもが非行に走ることを、意志が弱いと言い切るのは単純だと思う。
私は縁あって彼らと関わることができて、ひとりひとりの素朴な人柄に触れることができた。
子どもがどんな風に育つかは、環境による所が大きいのだ。
Bくんが何に対して涙していたのか知る由も無いが、大人になった今では、彼に何か手助けができなかっただろうかという風な、余計なお節介に心が乱れてしまう。
しかし、子どもだった私は、不思議そうに彼が泣いている様子を盗み見るだけだった。
彼も、戦っていたのだ。たぶん。
Bくんは、母親が見えなくなるまでその背中を見送っていた。
寮長先生が優しく微笑みながらBくんと並んでいた。

お鍋の夜に
これから書くことを、滑稽な笑い話だと思って読んでほしい。
ここに登場するのは、鍋をつつく5人の子どもたちと、出汁昆布とドレッシングの瓶である。
ある日の夕食は鍋だった。
ギスギスした空気でつつく鍋はどんな味だったろう。
Aくんの私への怒りは、日に日に増していくように感じられた。
私のように空気の読めない、とろくさい子どもを目の敵にすれば、ストレスは溜まる一方である。
私は殆ど四六時中、彼の冷たい視線と、その奥でたぎる怒りを感じていた。
そんな視線を感じながら、私は鍋から何かしらの具をお玉で掬って椀によそった。
「あつッ!」
私の隣でAくんが言った。
言いがかりだったのか、実際に出汁が跳ねたのかはわからない。
鍋が噴きこぼれるより早く、Aくんの怒りがあふれたのだった。
「熱いやろがワレ」か何か、ドスの効いた声でなじりながら彼は菜箸で鍋の底から出汁昆布をつまみあげ、それを私の手の甲に乗せた。
突然のことだった。
それはある種の音楽のように、完璧なテンポで心を奪う旋律を奏でただろう。
一瞬のようにも、長い時間のようにも感じられた。
あまりの熱さに、私は情けない悲鳴を上げた。
そうして、ばね仕掛けの勢いで立ち上がった私は、私の感情を置き去りにして勝手に動き出すのだった。
なおも悲鳴のように「ああああ!」と喚きながら、Aくんに体を向け、座ったままの彼の顔や頭を7〜8発は殴ったようだった。
あふれ出したのは私も一緒だった。
睨む者と睨まれる者の、心の擦り切れるような日々があり、嵐のように私たちのアンカーロープは切れたのだ。
ポカポカと、子どもが大人を殴るような滑稽な姿だったかも知れない。それでも半狂乱の中学生の拳骨を、微動だにせず顔面に受け続けるAくんのことを、改めて恐ろしいと思う。
手の甲の火傷の痛みが私の意識を現実に呼び戻した頃、Aくんはゆっくりと立ち上がった。
テーブルにあったのか、冷蔵庫から取り出したのか忘れてしまったが、目の据わった彼の手にはドレッシングの瓶が握られていた。
不穏な気配とは不釣り合いなピンク色が軽やかに舞った。
鋭さと重さ、性質の異なる痛みが、私の脳天で衝突事故を起こしたようだった。
そんな衝撃と共に、視界に電光のように閃くものがあった。
私はAくんにドレッシングの瓶で殴られていた。
殴られる度に、意識が白いもやのようなものに包まれた。
遠のく意識が、私の体に戻ってくるのを待たずに次の衝撃が頭上で弾けた。
何度目かで、考えることが不自由になった。
ぼんやりとする意識の片隅で、死の予感とは、こんな風に緩やかに体に満ちていくのだと、不思議な安らぎとともに感じた。
気がつくと、Aくんが握るドレッシングの瓶が割れていた。
私の頭で割れたのか、何かに打ちつけて割れたのかは知らない。知ったことではなかった。
瓶の割れた切先を私に向けて、何か、死にまつわる呪いの言葉を彼が静かに説いたように思う。つまり、これでお前を刺してやろうかとか、そういうことを。
寮長先生たちがやってきた。
Aくんは特に抗う様子も見せず、フレンチドレッシングかサウザンアイランドで汚れた手を洗ったと思う。

羊角の蛇神像⑯へ続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
