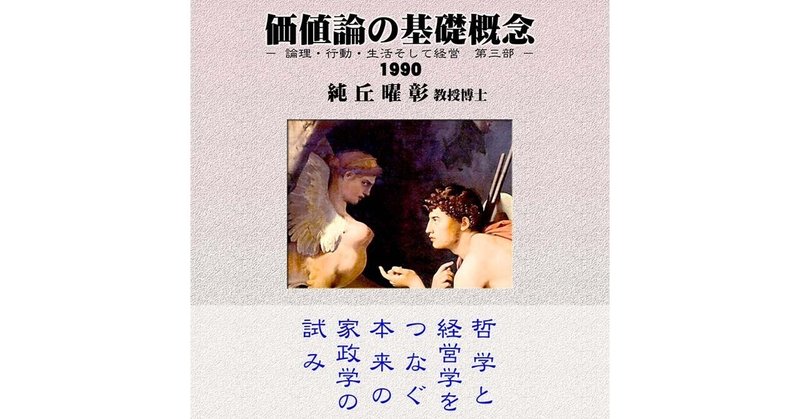
第一章 価値と適合性 3 可能状態と機能状態
〈意味〉は、ある類型概念の固有の機能を果たすことであるから、これは、機能を果たしうるが果たしていない状態と、果たしうるし果たしている状態とに区別することができる。たとえば、料理は、まだ食べられていない状態と、食べられている状態とがある。これらの状態をそれぞれ〈可能状態〉と〈機能状態〉と呼ぶことにする。これには、類型概念の〈可能状態〉と〈機能状態〉、特定対象の〈可能状態〉と〈機能状態〉を考えることができる4。
とりあえずは、同じ類型概念、同じ特定対象は、両状態において〈意味〉も〈価値〉も同じである、と考えるのがよいようにも思える。しかし、特定的な主体・状況においては、〈可能意味〉ないし〈可能価値〉と、〈機能意味〉ないし〈機能価値〉とを区別する必要もあるのではないか。というのは、主体・状況によっては、〈可能意味〉が完全に〈機能意味〉へ実現するとはかぎらないからであり、また、場合によっては、偶然的に〈可能意味〉以上の〈機能意味〉が出現することもあるからである5。
しかし、物事の〈可能状態〉が〈機能状態〉になるには、相応の条件の成立が必要となる。たとえば、いかにすぐれた(機能的な)犬小屋でも、犬がいない状況においては、〈可能状態〉にとどまる。犬がいてこそ、犬小屋も〈可能状態〉から〈機能状態〉へとその機能を発現する。すると、犬がいるにしても、いないにしても、犬小屋の〈意味〉は同じであるが、しかし、〈価値〉は異なるのであり、犬がいなければ、犬小屋にも〈価値〉はない、と言うべきなのだろうか。いや、犬がいない状況での特定の犬小屋の〈価値〉は、〈可能価値〉であり、特定の犬がいる状況での犬小屋の〈価値〉は、〈機能価値〉であって、両者を量的に比較することこそが、カテゴリー=ミステイクなのではないか。
特定対象の〈価値〉は、特定条件(主体・状況)において〈機能状態〉にあるとき、客観的に確定される。しかし、この特定対象の特定条件における〈機能価値〉のほかに、特定対象の特定条件における〈可能価値〉、類型概念の特定条件における〈機能価値〉と〈可能価値〉、さらに、特定対象の類型条件における〈機能価値〉と〈可能価値〉、類型概念の類型条件における〈機能価値〉と〈可能価値〉も考えることができる。これらの異なるカテゴリーにおける〈価値〉を混同し比較してしまうとき、我々は一般に誤謬に陥る。では、これらの〈価値カテゴリー〉の関係はどのようになっているのであろうか。
特定対象の〈価値〉が特定条件における〈機能状態〉において確定されるとはいえ、その〈機能状態〉において首尾一貫して同じ量的な〈価値〉を示し続けるとはかぎらず、むしろ時間的な経過にしたがって変化する方が一般的である。この変化の原因には、その特定対象の変化や特定条件の変化がある6。とすると、〈可能価値〉は、時間変化する〈機能価値〉の全体を含むものなのだろうか。
しかし、〈可能状態〉の段階では、〈機能価値〉を特定化する条件そのものも可能的なものにすぎず、したがって、その時々の特定条件も、その状態までは正確には特定化されえない。たとえば、タロウのための犬小屋は、タロウが大きくなってきゅうくつになったにしても、わずかの〈価値〉は残っているが、しかし、もしタロウがフィラリアかなにかで死んでしまったならば、わずかの〈価値〉すら持たなくなってしまう。それでいて、まだ子犬のタロウのためにその犬小屋を買おうかと迷っている時点では、いつタロウが死んでしまうかはわからない。
では、特定対象に関して各時点で可能な特定条件のすべての状態を想定し、そのそれぞれの状態における〈価値〉を勘案し、この〈価値〉のすべてを要素とする集合をもって、その時点の〈可能価値〉とし、このような各時点の〈可能価値〉のすべてを要素とする時間順序列集合を、その特定対象の〈可能価値〉とみなすのはどうであろうか。これも理論的には可能であるが、しかし、各時点の〈可能価値〉は、その前後の時点の〈可能価値〉と独立ではないのであり、この理解の方法は、この点の考慮に欠けている。つまり、実際にある時点にまで進めば、それ以降の可能な条件もその時点の具体的条件を根拠として展開するもののみに収束していくのであって、いつまでもすべての可能性が残存しているわけではない。そして、同じことが、そのような特定条件の状態によって確定される〈価値〉についても言える7。
一般に可能性が収束する、ということは、逆に、一般に現実性は拡散する、ということでもある。現実性は、時間順序列として樹状に分岐していくのであり、そして、これを、現実の可能性として理解する方が、各時点の現実の時間的関係も考慮しているという点において、先のような時間の切片における可能性の理解よりも優れていると思われる。このように考えるとき、〈価値〉を確定する特定条件も、その状態は時間順序列において樹状に分岐していくのであり、したがって、理論的には、このように分岐するすべての特定条件(主体・状況)の状態の時間順序列ごとに、個々の時点における対応する〈機能価値〉を時間順序列として対応させることができる。そして、このような〈機能価値〉の時間順序列のすべてを要素とする集合として、〈可能価値〉を理解することができる。ここにおいて、特定条件の状態の時間順序列の実現の可能性の比重は、〈機能価値〉の時間順序列の実現の可能性の比重でもあり、これを〈機能価値〉の時間順序列の集合である〈可能価値〉において考慮することができる8。
4 アリストテレースは、『形而上学』などにおいて〈デュナミス(可能態)〉と〈エネルゲィア(現行態)〉という概念を用いている。そして、ここでの意味の〈可能状態〉と〈現実状態〉は、このアリストテレースの概念を踏まえたものである。また、アリストテレースは、この二つの概念に、さらに〈エンテレケイア(完了態)〉という概念を考えることもある。しかし、〈意味〉における〈完了状態〉は、歴史化した実績のようなものであり、このような歴史的形成構造に関する問題については、この章では論じることはできない。
5 たとえば、同じ料理でも、満腹であればそれほどおいしくはなく、また、空腹であればよけいにおいしいものであろう。
6 たとえば、同じ機械でも、年月を経れば故障が増え、たとえその機械が変わりなく機能したとしても、世間の機械の進歩によって陳腐化してしまう。
7 たとえば、ある時点に早くもきゅうくつになってしまった犬小屋が、それ以降の時点にきゅうくつではなくなる、ということはありえない。
8 〈可能世界〉の問題については、D・ルイス、S・クリップキーなどの《量化様相論理学》関係の著作を参照せよ。本文でも論じているように〈可能世界〉的な発想は、理論的には興味深いものではあるが、我々の現実の行動や能力とはかけ離れているように思われる。むしろ、我々は、〈可能世界〉的な問題をとても簡便に処理する「秘密」の方法を日常的に公然と行っているのではないだろうか。しかし、この問題は、次の第5節で簡単に触れたが、より詳細には、主体や状況の歴史的相互関係構造に関するものであり、今回の論文の範囲を越えている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
