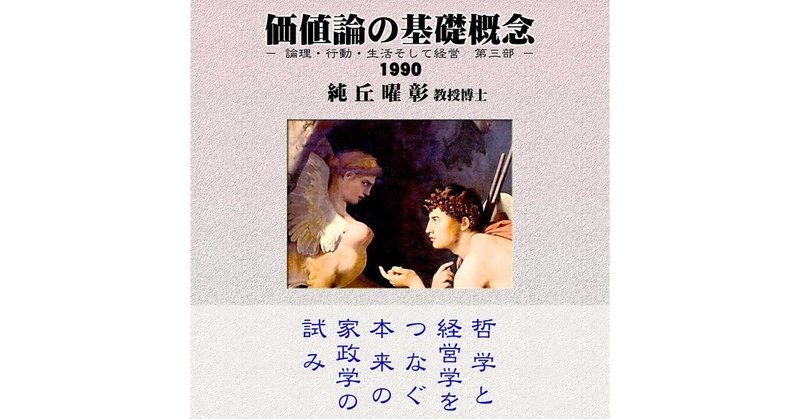
第一章 価値と適合性 10 意 義
このように〈背景事象〉は、別の物事の適合条件や不適合条件になる。この点から、物事は、〈背景事象〉として〈意義〉を持つ、と言える。つまり、〈意義〉とは、〈背景事象〉として他の物事を適合・不適合にさせる効果、ということである14。
〈意義〉は、状況の中においてのみ存在するものであって、つねに機能的である。さらに、それは状況の中において他の物事との相乗相殺によるところが少なくなく、因果連鎖的に、はるか先のことに影響することもある。逆に言えば、はるか昔のものが現在の状況で〈意義〉を発生してくることもある。たとえば、駅があるから町が発展し、町が発展するから駅が発展する、というのは、相乗的な〈意義〉であろうし、また、古代の遺跡が発見されることで、現代の一大観光地ができあがる、というのは、因果的な〈意義〉であろう。このような相乗相殺的な〈意義〉や因果連鎖的な〈意義〉は、そのほとんどがその物事の本来の〈意味〉ではない。そもそも〈意味〉は、あくまでその物事の類型において固有のものであるから、あまり具体的な多くの他の物事との関係まで含んではいない。
ある物事が〈意義〉を生じると主体が考える場合、その物事が状況適合的でなくても、不適合でさえないならば、それを無意味なままに、ある状況に導入することがある。これは、「布石」と呼ばれる。たとえば、車を持っていなくても、駐車場を借りておくことはでき、駐車場を借りてあることは、後に車を持つことを可能にする〈背景事象〉となる。状況は、ただ与えられているものではなく、このような「布石」を積み重ねていくことによって、主体的に構成することができる15。
しかし、だからといって、物事が〈背景事象〉として持つ〈意義〉のすべてが、このように意図的に主体的に状況に汲み込まれたものである、などと考えてはなるまい。先述のように、〈意義〉は、状況内の他の物事と相乗相殺的であり、因果連鎖的であるので、誰もが予想もしなかったような〈意義〉が派生してくることも少なくない。だが、〈意義〉は、物事に固定的なものではないので、逆に、その〈意義〉を持つ物事と相乗相殺的・因果連鎖的な他の物事をうまく導入してやることによって、その物事の〈意義〉を消滅転換させることもできる16。
主体は、状況に内在する複雑な〈意義〉を解読し、手持ちの物事の固有な〈意味〉を勘案して、それらの物事を最適に状況に織り込んでいく。ここにおいて、手持ちの物事を状況に織り込むこと自体が状況を変化させるという点が重要になる。順序を間違えると、手持ちの物事を生かすことができずに廃蔵することになり、逆に、状況にうまく織り込んでいくことができたならば、手持ちの物事をよりよく生かし、さらに、次々に新たな手持ちの物事を得ていくことができる。より多くの手持ちの物事があることの方が、よりよい状況を構成していく選択の幅があるが、しかし、手持ちの物事があることよりも、よい状況であることの方が本質的だろう17。
だが、主体が構成すべきよい状況とはいかなるものだろうか。この問題のために、次に、主体そのものを問題にしなければなるまい。
14 このような物事の〈意義〉は、その物事の〈意味〉であることもあるが、そうでないこともある。たとえば、免許証は、車の運転が規範的に適合であることを保証するという〈意味〉を持ち、したがって、それが検問などにおいてそのまま免許証の〈意義〉でもあるだろう。これに対して、たとえば、免許証は、そのほかにも、郵便物の受取などにおいて身元証明としても用いられることがある。が、しかし、これは、いかに反復的に機能しようとも、免許証の固有本質的な〈意味〉ではない。
15 ウィットゲンシュタインは『哲学探究』において、〈意味〉の問題を〈言語ゲーム〉という概念によって分析したが、生活や会話の適合性のモデルとして、とくに言葉のしりとりゲームを比較検討してみることは有効であろう。しりとりにおいては、その言葉は、直接的に次の言葉を規定するとともに、間接的に同じ言葉を使えないという規則を「歴史的」に累積する。直接的に物理的に適合性や不適合性を規定する効果は明白であるが、歴史的間接的な規定性や社会的規範的な規定性については、何を媒介とし、どこに蓄積しているのか、ということは大きな問題である。しかし、この問題はこの章では論じることはできない。
16 たとえば、赤字の子会社はやっかいものだが、しかし、合併して親会社の黒字を減らすのに利用することもできる。
17 言うまでもなく、ケインズの〈流動性選好〉は、流動性を趣旨とする貨幣に関すればこそ成り立つものであり、財貨一般に成り立つものではない。むしろ家政学的には、適合を支配できる状況の〈意義〉に対する固定権力と、選択を支配できる物事の意味に対する流動権力の比率および回転率、および、実績や信用などの簿外財産など、バランスシート的な理解が必要だろう。もちろん、したがって、このような資産に相当する〈権力〉に対し、資本に相当する権力源泉とそのバランスも、生活経営上の大きな問題となる。そして、これらは価格としてではなく〈価値〉としてのみ一元的に理解できるものであり、いわゆる会計学的な範囲を大きく越えるものであろう。このような主体の選好構造については、次章で詳細に考察していきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
