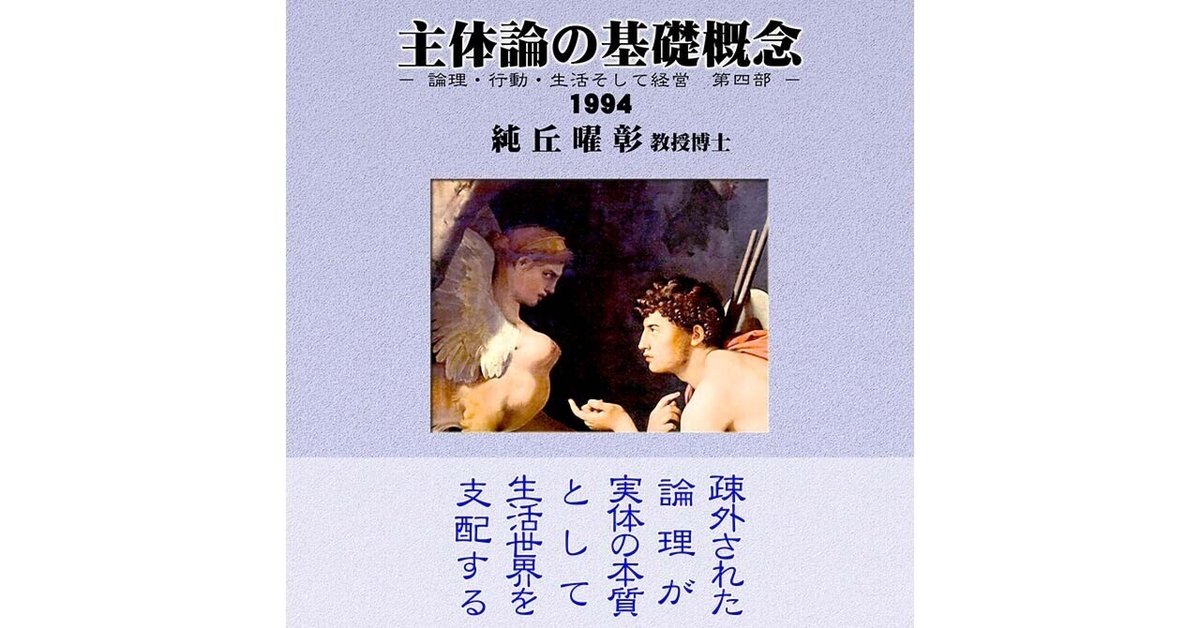
第一章 物事 4 〈法則〉と〈体系〉
一般類型的連関を、〈法則〉と呼ぶ。〈法則〉は、一般類型としての〈事〉を条件とし、一般類型としての〈事〉を帰結とするが、それらの一般類型に所属する特殊個別的な〈事〉にも、その〈法則〉が妥当する。というより、特殊個別的な〈事〉に妥当しないならば、それは〈法則〉ではないし、ある一群の特殊個別的な〈事〉になんの〈法則〉も共通に妥当しないならば、そもそもそれらを同じ一般類型的な〈事〉として同定することもできない。ある〈事〉と連関する〈事〉は、一般類型の〈法則〉として特定的であるが、その特定性は、あくまで一般類型としての形式的なものにすぎず、特殊個別としての具体的な〈事〉としては、かなりの幅があり、境界も曖昧なままであるかもしれない。
一般類型的な「自然連関」を、「自然法則」と呼ぶ。もっとも、「自然連関」においても、ある特殊個別的な〈事〉が条件であり、また、ある特殊個別的な〈事〉が条件であるということは、我々によって、それらの特殊個別的な〈事〉が一般類型的な〈事〉と認識されなければ、つまり、我々の人間的な関心において特定されなければ、そもそもどちらも〈事〉ではないし、したがって、〈連関〉でもない。この意味で、論理的には、それこそ、「自然連関」も含むすべての連関に関して、[〈法則〉を条件としてのみ〈連関〉を帰結とする]という連関が成り立っているのである。つまり、我々が〈事〉として一般類型的に特定するものの間でのみ、そして、それらの一般類型的な〈事〉の間に一般類型的な〈法則〉が成り立っている場合にのみ、そのそれぞれの一般類型である個別特殊的な〈事〉にも、〈連関〉が認識されうるのである。ちなみに、我々がある特殊個別的な状況にある一般類型的な〈事〉を発見し特定するというのは、なにか[頭や心の中で「概念」で把握する]というようなことではなく、[我々自身がそれらに同じ対処をする]ということである。[同じ対処である]ということは、[他者がその対処に同じ対処をする]ということであり、無限後退的に補証される。
一群の〈法則〉は、ある〈法則〉が他の〈法則〉の帰結を条件とすることによって、有限の一般類型としての〈事〉だけから構成されるものとなる。すなわち、それらの〈法則〉に沿っているかぎり、[それらの〈法則〉のいずれかが帰結とし、また、それらの〈法則〉のいずれかが条件とする一般類型としての〈事〉]しか発生しない。このような一群の〈法則〉は、〈閉鎖体系〉を構成している、と言う。〈閉鎖体系〉は、有限の種類の〈法則〉から構成される。〈閉鎖体系〉を構成するその内の一つの〈法則〉でも異なるならば、いかに他のすべての〈法則〉が同じであっても、別の〈閉鎖体系〉である。
〈現実脈絡〉にある〈閉鎖体系〉が成り立つ場合、それは、その〈現実脈絡〉が、その〈閉鎖体系〉に含まれる〈法則〉のいずれかのみをさまざまな順序で接続して形成されている、ということである。この場合、〈現実脈絡〉に登場しない〈法則〉があってもかまわない。なぜなら、そのような〈法則〉も、〈閉鎖体系〉が成り立つために不可欠なものだからである。
〈現実脈絡〉は、局所短期的には〈閉鎖体系〉が成り立っていることが少なくない。しかし、大所長期的には、一部の〈法則〉が異なったり、変わったりしている。先述のように、一つの法則でも異なるならば、それは別の〈閉鎖体系〉である。とはいえ、この異なったり、変わったりする〈法則〉が、たしかに〈閉鎖体系〉を構成するのに不可欠なものであるにしても、実際には〈現実脈絡〉にほとんど登場しないものであるならば、この相違は、発覚することなく、潜在したままで、あたかもそこに共通の〈閉鎖体系〉が成り立っているかのようであるかもしれない。
そもそも、異なったり、変わったりするというより、その問題については明確に決まっていない、〈法則〉が欠落している、ということもありうる。この場合、厳密には、その一群の〈法則〉は、体系として閉じていない。しかし、その問題が、めったに生じないものであり、いまだ生じていないものであるならば、現実的には〈体系〉を成立させていると言える。この〈現実体系〉は、それに含まれる一群の〈法則〉のみで〈現実脈絡〉が構成されている、というものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
