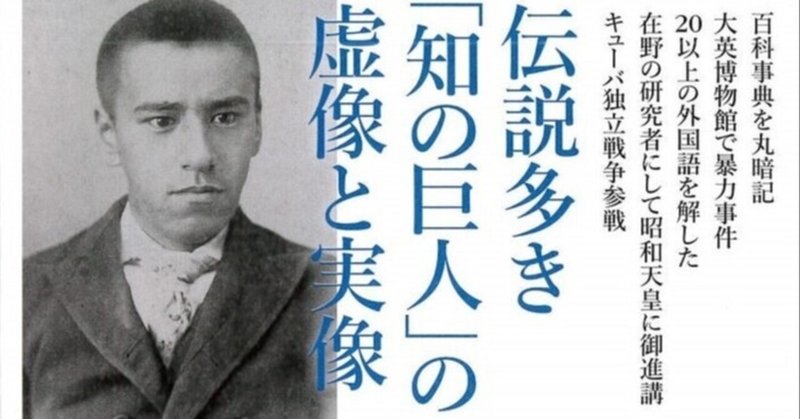
読書メモ「南方熊楠 日本人の可能性の極限」
引用ではない部分は(参考)(感想)など、わたし自身が書いたもの。まとまった感想というわけでもないので、あくまでもメモ。ちょうど2年前に書いたものです。下書きのまま寝かされていました・・・。
P101 大英博物館の円形図書館(図書閲覧室)
あの図書館のこと、よく言ってましたですよ、円形の。「あそこ行った時は、自分のいちばん望んでいたところに来たと思って嬉しかった」って言ってました。(「南方文枝さんに聞く」*文枝・・・熊楠の娘)
(参考)大英博物館WEBサイト。図書館としての機能は変わり、2000年には改修されたが、基本的なデザインは熊楠の頃とほぼ同じのよう。行きたい。
P138 熊楠をよく知る人物からの最高の賛辞
ロンドン大学事務総長 フレデリック・ディキンズより、熊楠の結婚祝いに添えられた手紙(抜粋)
君は東洋と西洋に関するかくも深い学識を持ち、人間世界と物質世界の率直で公平でしかも私心のない観察者です。(1908年1月8日の手紙、未公刊)
P206 熊楠が神社合祀に反対した理由
神社合祀は、第一に敬神思想を薄うし、第二、民の和融を妨げ、第三、地方の凋落を来たし、第 四、人情風俗を害し、第五、愛郷心と愛国心を減じ、第六、治安、民利を損じ、第七、史蹟、古伝を 亡ぼし、第八、学術上貴重の天然記念物を滅却す。(白井光太郎宛書簡 1912年2月9日「神社合祀に関する意見」原稿、南方熊楠全集7巻より)
P205-208 熊楠は「エコロジー」という語を日本で最初期に用い、重要視した
南方は、地域の植物生態系と関連しながら、 そこに生活する住民をふくめた、社会生態系という考えを、すでに持っていたもののようである。かれは、植物の生態系を破壊することに反対すると同時に、各小地域ごとの社会生態系を、権力による強制合併によって乱すことに反対した。(「南方熊楠」鶴見和子,講談社学術文庫)
P208 森そのものとなった熊楠
熊楠は、自然の神秘・驚異・美しさ・知恵あるいは言語化不可能な感覚を、五感全てで感じ取っていた。例えば「林中裸像」と呼ばれる、熊楠が大木の横で、腰巻一つで腕組みをして写っている写真が残っている。この写真は現在、熊楠の象徴的な姿を表すものとして、さまざまな書籍や資料で用いられている。そこからは、彼が森中において、身体全体でさまざまな情報を敏感に得ていた様子を見てとることができる。いわば身体全体が、森と交流する媒体そのものになっていたのだ。そのときの状態は、言語化不可能であり、まさに物我一如である。」(唐澤太輔)
(感想)五感だけでなく、第六感も発達していた熊楠は、森からすべてを受け取り、森と一つになっていたのではないかと思う。
(参考)「林中裸像」が表紙に使われた本(未読)
P210 国際的視点をもつ、稀有なグローカリスト
熊楠は、ディキンズを通じて海外の世論を喚起しようとした(日本の恥を晒すべきでないと考えた白井光太郎、柳田國男に反対され、思いとどまった)。
神社合祀という暴挙を、国境を越えた方法でくい止めようとしたのだ。つまり熊楠は、地域を「民際交流」(鶴見和子『南方熊楠』)によって救おうとしたのである。近い将来、自分のような発想や方法が当たり前になる日が来ることを、熊楠は明らかに予見していた。(唐澤太輔)
このことから唐澤氏は、熊楠を「世界でも稀有な資質を持つ人間」「グローカリスト」と表現している。
また熊楠は、田辺町およびその近隣地域を綿密に実地調査している。つまり熊楠は、神社合祀という問題に対して、グローバルかつローカルに考え行動したのである。一言で言えば、熊楠は国家の枠を超えた「グローカリスト」(グローバルとローカルの連動による、それらの乗り越えを目指す者)であったと言うことができるかもしれない。このように、熊楠は、当時世界でも稀有な資質を持つ人間だった。(唐澤太輔)
P216 「捕まっても、ただでは終わらない」
神社合祀反対運動中に投獄された獄中でも、熊楠は粘菌を発見している(ステモニチス・フスカの原形体)。これまで白色しかないと思われていたが、熊楠は深紅の個体を発見した。
P220 「粘菌」ではなく「菌虫」だ!
熊楠は「粘菌」という言葉を廃止したかった。(中略)そして「菌虫」=ミケトゾア(Myceto+zoa, 菌類+動物)の名前を採用したかった。熊楠は、粘菌の性質上、最も重要である捕食機能=動物的要素を無視したような「粘菌」という名前に疑問を感じざるを得なかったのだ。そして、ここで大胆にも熊楠は粘菌を「原始動物」だと主張している。(唐澤太輔)
(感想)当初、植物界の菌類に分類されていたため、「粘菌」とネーミングされてしまった不遇な動物(本当はアメーバの仲間)。とにかく不思議で、誤解を受けやすい、へんな生き物であることは間違いない。
P222-226 粘菌の生態から導き出した死生観
「生と死の世界を簡単に分断することなどできない」
「生命現象を観察する者の立場は絶対的なものではない」
(感想)全くその通り!生と死について、わたしは以下の文章を大学の卒論で取り上げた(20年くらい前のこと)。
死は生を引き立てる。生は死を引き立てる。
私は、今でも、これらのことに恐怖を抱いている。
たぶん、これからもそうであり続けるだろう。
嫌味で冷酷なばあさんになる予定の私は、
愛情で織られた布で、はねっ返りの恐怖を包み、それを重荷よろしく背負い込む。
そして、そこから小出しに見せびらかして、自慢する。
見える人にしか欲しがられない、大切な大切な宝物を。
(山田詠美「姫君」あとがきより)
そして「生命現象を観察する者の立場は絶対的なものではない」。これは、観察者効果や二重スリット実験の話。今でこそ認知されてきているが、このような見方は熊楠の時代にどれだけあったのだろうか?
P226 ミナカテルラ・ロンギフィラ(ミナカタホコリ)を発見
1916年4月、自宅の庭、柿の生木にて。粘菌が落ち葉や朽木ではなく生きた木から発見されることは珍しい。うちの柿の木も見てみたくなる。
その他、8種を新発見。2種は発見したものの分類上現在は認められていない?「イタモジホコリ」も熊楠が発見した。現在では研究実験でよく使われている。
P233 キャラメル箱の真相・・・実は桐箱も用意されていた
桐の箱も作っていたんですよ。けれど開きにくいということで、キャラメルの箱にしたんです。あの小さいキャラメル箱のことだと誤解されている方が多いのですが、そうではなく、問屋さんのところにある大きいやつです。箱の上に綺麗な天女の絵がついていました。父はよく粘菌入れとして愛用していましたが、もちろんこの日使ったのは新しく貰ったものですよ。(南方文枝・神坂次郎「父 熊楠の素顔」)
(感想)桐箱を用意する常識は持ち合わせていたようで、ほっとした。それでもやはり実用面からキャラメル箱を採用するところが、やっぱり好きだ。桐箱があまりにもピシッと閉まるので、緊張して開けるのに失敗するのが不安だったらしい。かわいい笑
P244 日本人の可能性の極限
熊楠の死後、柳田國男は以下のように述べている。
我が南方先生ばかりは、どこの隅を尋ねて見ても、是だけが世間並みといふものが、ちよつと捜しだせさうにも無いのである。七十何年の一生の殆と全部が、普通の人の為し得ないことのみを以て構成せられて居る。私などは是を日本人の可能性の極限かとも思ひ、又時としては更にそれよりもなほ一つ向かふかと思ふことさへある。(「南方熊楠」柳田國男)
(感想)晩年?性愛に対する考えの違い(熊楠の卑猥さに拒絶反応w)から疎遠になっていたらしい柳田國男は、それでも熊楠を最大評価していた。日本人の可能性の極限の、さらにもっと向こう側・・・誰も到達したことのないところ。ちなみに熊楠は、性愛の問題も民俗学上は非常に大事なことだ!と主張。わたしもそう思う。宮本常一の本で、そういう聞書があって面白い。(「忘れられた日本人」より『土佐源氏』)
(終わり)
これが初めての熊楠本ではないので、よく伝記で書かれていること等、既に知っていて新たなインパクトが特にないものは書かなかった。
あ・・・死後デスマスクをとって、遺言で脳を研究用に保存しているというのはインパクトあった。(阪大に保存)
夢、やりあて、南方曼荼羅については先に読んだ「南方熊楠の見た夢 パサージュに立つ者」に詳しい。著者は同じく唐澤太輔さん。
よろしければサポートをお願いします。クリエイティブな活動をしていくための費用とさせていただきます。
