
角砂糖同好会の終焉
食わず嫌いという言葉がある。
人生において一度だって口にしたことがない物を、その味も分からないのに嫌いだと判じて、死ぬまで口にしてなるものかと決め込む態度や人のことだ。
しかしながらそれは、あくまで言葉の上での正しい意味であり、世間で比喩されるような食わず嫌いの正しい実態とは異なるのではないだろうか。
大抵の場合。
そう言われるような人は人生で一度は”それ”を口にしていて、舌に合わなかったという懐古の印象を引き摺り、勝手に心の中でそう決め込んでいるだけなのである。
たとえば僕の場合は納豆やキュウリがそれにあたる。
食事の拒否権を得る前の幼少期は、親の顔を立てる為にも渋々と食べていたが、それから先は一度も口にしていない。
どんなに心から大好きな人だろうが、それらを食べた口で駆け寄ってくるようなことがあれば、ウィル・スミスさながらに批判も覚悟のビンタを僕は食らわせるだろう。同様に放送禁止用語を連発するに違いない。
けれど、それは意固地になっているだけとも言える。
だって よく言うだろう。
大人になればなんとなく食べれるようになった、とか。
理由とか理屈とかを超越して、本当になんとなく、意味らしい意味もなく苦手が苦手でなくなる。あの感覚。
しかし僕はあれが、なんだか、とても怖く感じる。
苦手な物を自然と呑み込めるようになった。
そんな新しい自分との邂逅に祝いの盃を交わす余裕なんてほとほとなく、自分の知らないところで自分がはっきりと変わってしまった実感というのは気持ちが悪い。
翻って大人になれど、やはり食べられなくて、苦手を苦手のまま過ごしていたと知るのもそれはそれで嫌だ。
そんなこと好き好んで知りたくない。
だから、僕もまた食わず嫌いだ。
自分のことなんて分からないままでいい。
考えたくもない。
変化してしまった自分を知る方が怖いのか、あるいは、変化していない自分を思い知る方が辛いのか──なんて。
けれどそれは残酷にも、
口にしてしまえば自ずと分かる事なのである。
角砂糖同好会を知っているだろうか?
いいや、誰も知っているはずがない。
そもそも僕と彼女とその他大勢の繋がりを、そんな名前で呼んでいたのはこの世で僕だけである。当の彼女も、このエッセイを読むまで露も知らないことだろう。
あれは遡ること数年前──上京して二年と半ばが過ぎた頃、より具体的には大学三回生の秋のことだ。
没個性な普通の人間であることに劣等感を患っていた僕は、学業の傍ら、個性ある変人に成るべく試行錯誤を繰り返していた。その一環として その時期は普段着を医療用の白衣に完全統一。こんな感じの格好で自宅と大学を往来し、健気なセルフプロデュースに勤しんでいた。

満員電車とかかなりしんどかった。
すわ岡部倫太郎のコスプレかと揶揄されたが、僕としてはそういうつもりはなかったし、白衣と岡部を記号的に結び付ける価値観にも腹が立って無性に不服だった。
さて、大学という社会は広いようで狭いものである。
夏季休暇明けの残暑の頃より。
暑苦しくも白衣に袖を通し、各ゼミで最前列の席を陣取って発言を執拗に繰り返している人間が悪目立ちをするのは必然だ。
だからそれに乗じてか、
物見遊山気分で僕に話しかけてくる人も何人かいた。
その内の一人。
男子だった。名前は覚えていない。どんな顔をしていたかも、どんな調子で話しかけられたのかも。
我ながら薄情な記憶力だ。
けれど、彼に言われた一言だけはよく覚えている。
「面白い集まりがあるから、都部も来ないか」
そんな漠然とした誘われ方をした。
面白い集まり。
決して見下すわけではないが、世俗に染まった大学生の言う ”面白い”の価値観に懐疑的だった僕である。
およそ数回に渡る その誘いを毅然と断っていた。
断っていたのだが。その日はなんとなく、誘いに乗ってやるか、と気まぐれに足を運ぶことにした。
辿り着いたのは、
学生に貸し出されている複数ある視聴覚室の内の一室。
中に這入ると、十人未満──だったと記憶している──の男女の姿があった。何度か見たことがある人もいた。
しかし直接の繋がりがある友人はいなかったので、挨拶もそこそこに、最前列の真ん中の席に座ることにした。
「それでは今日も鑑賞会を始めまーす!」
誰が言ったか、
そんな音頭が背後で取られた。
疎らな──拍手、拍手、拍手。
僕もそれに倣って、シンバルを叩く猿の玩具のように手をぱちぱちと無心で叩いた。
室内の照明が落ち、雑談の声も潜まって、プロジェクタスクリーンにその映像は表示される。
最初に映ったのは素性も知らぬ女性の顔。
その女性の胸部や臀部を舐め回すようなカットが挟まり、劇場映画とは異なる質感の日常的な場面が連続して、暗転と共に性的な文字列が並んだ題目が表示された──とどのつまり、僕の眼前で流れ始めたのはアダルトビデオだった。
盛大に困惑する僕という存在を他人事にして、
映像と時間は刻々と進行していく。
改めて その内容を細かに描写せずとも、そうした作品の基本的な段取りはなんとなく伝わるだろう。僕を除く男女はその段取りに様々な声を上げた。時に歓声し、時に指摘し、時にその性行為の有様を評定するのだ。
さながら応援上映である。
例えるならばアレがいちばん近い。
応援上映。
僕が東京に訪れて、初めてその文化に触れたのはマーベル・シネマティック・ユニバースの集大成とも言える『アベンジャーズ エンドゲーム』だった。

この映画を最速上映で見れた事を、未だに自慢に思っている。
映画本編もさることながら、その回に集まるのは”応援”上映を前提とする人々なので、程度の差こそあれど一体感があり中々に楽しい映像体験なのである。
けれど、その時とはあまりにも勝手が違う。
映像作品として売り出された性行為の導入や前戯や行為その物を、20歳前後の複数の男女が和気藹々としながら、事も無げに密室空間で鑑賞している。
気分は不思議の国に迷い込んだアリスである。
常識という名の白兎を見失った僕に出来ること。
それは不思議の国からの脱兎の如き逃走だ。
だって、そんなの──気持ちが悪いだろう。
僕は席を立って、愛想の挨拶もなく部屋を出た。
この部屋に、一秒だって、もう居たくはなかった。
そのまま立ち止まらず。
学内で500mlのスプライトを唯一販売している自販機まで歩いていき、購入。近くのベンチに座り込んで、不快に乾いた喉を潤すことにした。
それから数分して。
半分ほどのスプライトを、缶から胃へと移し替えた僕の名前を呼ぶ声があった。高さとしてはアルトだ。
声の方を見遣れば、先程まで視聴覚室にいた面々の内の二人の男女が駆け寄ってくる。
やばい!早く逃げなきゃ!
なんて、今すぐ自宅に帰りたい気持ちが山々にあったが、どことなく申し訳なさが滲む顔付きを備えた人間を無視して その場を去れるほど冷徹にはなれなかった。
それに、どんな理由があれ。
あの部屋に戻るつもりこそなかったが、何故あんなことをしているのかと、ミステリ好きとして純粋にその動機に好奇心をくすぐられたのはあるかもしれない。
あの時。どんな掛け合いを交わしたんだっけ。
もう覚えちゃいないが、大したことのない二.三言だったはずだ。上辺だけで中身も意味もない、そんな会話。
しかし結論として。
お詫びに近くの喫茶店で軽食を奢ると言われたので、それなら良いよと、僕は二人に着いていくことにした。
「ごめんね」
喫茶店に到着して、席に座るやいなや、
対面(といめん)の彼女に謝罪された。
その隣に座る男は無言だったけれど。
なんなら僕の方を見ていなくて、興味もない様子でスマートフォンを弄っていた。
彼女の謝罪を受けながら。
さしずめ彼女の付き添いを請け負った彼氏なのかなとか、まるで別のことを考えていたのを記憶している。
仮にそうだとして、あの異様な集まりに、恋人二人組で参加というのは大概に世も末だとも思ったが。
それに僕はもう気にしていなかった。
元より怒っているわけではなかったし、過ぎたことと割り切ろうと喫茶店への移動中に心に決めていたのだ。
そんな僕の内心など知らず、謝罪の言葉を続ける彼女に反応しようと思ったが名前を覚えていなかった。
何度か顔を合わせたことはある。
が、そうして話すのは初めてだった。
普通に困ったので、
「めいろさんって呼んでもいい?」
と聞いてみると
「え? なんで?」
なんて、困惑のトーンで返された。
なんでとか言われても困る。
とはいえ勿体ぶる必要もないので、
いつもカラーコンタクト付けてるから、
と、命名の理由を簡潔に答えた。
「なるほど? なるほどか。……もしかして、わたしの名前忘れてる? わたしの名前、⬛︎⬛︎⬛︎⬛︎って言うんだけど、そんな渾名で呼ばれたの初めてだよ。大抵はみーちゃんとかみー子とかみっちゃんとかだったし」
彼女は得心した様子を見せて、ひとまずは何か頼もうと場を仕切り出した。
横の男は本当に何の為に居るんだよ。
ともあれ始めてのお店である。
それも他人の奢りだ。
お品書きをじっくり見てから決めようかしら──なんて、うきうきで考える隙もなく、目の前の二人は珈琲を頼むとか言い出した。
嘘だろ。
コイツら、まさか珈琲が飲めるのかよ。
今も昔も僕は珈琲も紅茶も抹茶も酒類も炭酸水もまるで飲めない人間であり、この時期はそのことを強烈に気にしていた。恥ずかしく思っていたとでも言おうか。
なんなら珈琲を飲めるのは大人の証拠、
くらいには考えていた。
それにほぼ初対面みたいな同回生の前で、ちょっと見栄を張りたい気持ちもあり。じゃあ僕も同じ物を、なんて つい流れで言ってしまったのである。
ほどなくして三人分の珈琲が提供された。
その黑々とした香り深い液体に口を付け、嚥下する。
……苦すぎる。
飲めたもんじゃねぇ。
その動揺を表面化させる訳にはいかないので、涼しい顔でこの喫茶店の珈琲は中々美味しいねとか言った気がする。舐められたくねぇ。もうこうなると意地だった。
それに、一度出された物を残すのは失礼に当たる。
それは僕の美学に大きく反する行為だ。
机上の隅には、古めかしいデザインの硝子瓶があり、中には角砂糖がこんもりと詰められている──あれ欲しいな……とか考えていると、めいろさんが瓶をひょいと開けて、角砂糖を二個三個と自前の珈琲に入れ始めた。
「都部くんも入れる?」
もしかして彼女は良い人なのかもしれない。
そんなことを思った。
僕があの集まりのことを人知れず、 ”角砂糖同好会”と呼ぶようになったのは、この一幕がきっかけである。
彼女の誘いを受け入れて、僕も角砂糖を五個六個と投入した。それでもやっぱり苦かったが、それは先程とは違い、こんなの飲みきれないと思うほどではない。
「それでさ、あの淫乱な鑑賞会はどういうつもりなの?」
優雅なティータイムもそこそこに、遠回りは抜きにして、聞きたいことだけを聞くことにした。
「まあ、なんていうか、就活で参っちゃって」
簡潔な理由だった。
「だから みんなでやろうって決めてさ。二週に一回くらいの頻度で集まってああいうことしてる。変なことしてるな〜〜って。その辺はみんな分かってると思うよ。でもそうしなきゃ、なんかもう、やってらんないんだよね。なんだろう。自分が今 煮詰まってるってことを忘れられるような、そんな変な時間が欲しくてさ」
はたして。
その現実的な真相を前にして、僕が落胆しなかったかと言えば嘘になるけど、その動機はよく理解出来た。
ただし疑問は残る。
そんな就活に悩まされる者たちが集う互助サークルに、どうして僕が誘われたのだろうと。
「え、だって都部くんがそんな変な格好してんの就活でストレスが溜まってるからじゃないの……? 」
なんか みんな心配してくれていたらしかった。
有難いけど見当違いだ。
残念ながら、これはただの趣味である。
しかし彼女の神妙な顔を前にすると。
そんな馬鹿馬鹿しい真相を口にするのも気まずく、適当な形で首肯したのを覚えている。それに続けて、
「たまになら顔を出すよ」
なんて、愚かにも、僕はそう言ってしまったのである。
「きっっっっっっも!!」
一連の流れを読んだ彼女ちゃんによる感想は、
そんな端的で、的確な、何よりも鋭利な一言だった。
「一から十まで意味不明なんだけど。就活で荒んだ心を癒す為に皆でAVを見るって何? 普通に皆で遊ぶじゃ駄目なのそれ。不健全。不健全よ。凄く凄く気持ちが悪いわ。あのさぁ、そいつらが第一に頼るべきはセックスじゃなくてカウンセラーでしょうが」
都営新宿線本八幡行き──目的地へ向かう為の電車の中、吊革に掴まる僕の正面に座る彼女ちゃんは、そんな風に感情的に捲し立てた。
平日の半端な時間だからか。
席は相応に空いていて、座るには困らなかったけれど、彼女を放置する訳にもいかないので直立だった。
別に放置したとして彼女は幻覚なので、それで人的被害が出るわけでもないが、これは僕の納得の問題である。
「たしかに私を人間みたいに扱うなとはアンタに言ったけど、それはペット扱いしろって意味じゃないからね?」
彼女は、
僕の良心のメタファーを名乗る僕の幻覚である。
僕が喫茶店で珈琲をやむなく頼んだ時は、自分も率先して同じ注文をして、お子様舌なアンタと違って私は珈琲を飲めるんだぞと自己主張してくる。そんな存在だ。
ちなみに紅茶も抹茶も酒類も炭酸水もごくごく飲める。いちばん好きな飲み物はネクターらしい。どこ由来?
名前も渾名を付けるなと怒られたが、ないと不便なので、彼女(かのめ)ちゃんと僕は勝手に呼んでいる。
「──ま、いいや。そんなキモすぎな連中のことは刹那で忘れちゃお♡ 人生を豊かにするのは忘却よ。あぁ〜、やっぱり谷間の百合は最高だわ。バルザックの文章って大好き。バルザックの小説になら年中抱かれたいわね」
そんな妄言を宣う彼女の今日の髪型は、文学少女さながらに三つ編みである。ご丁寧に伊達眼鏡も掛けてる。
ハワイアンブルーの髪色が前衛的に存在を主張しているので、その大人しめな印象の髪型は全く似合ってない。
学生気取りなのか。夏用のセーラ服を身に纏っているが、スカートの丈が短くて不埒だ。彼女の体型で風紀を乱す格好をされても、僕としてはちっとも嬉しくない。
小説──昨夜から熱心に読んでいるようで、残りの頁数を鑑みるとようやく終盤に差し掛かるというところだった。谷間の百合。どんな小説? と聞いてみたら、今のアンタみたいな小説とだけ言われた。答えになってない。
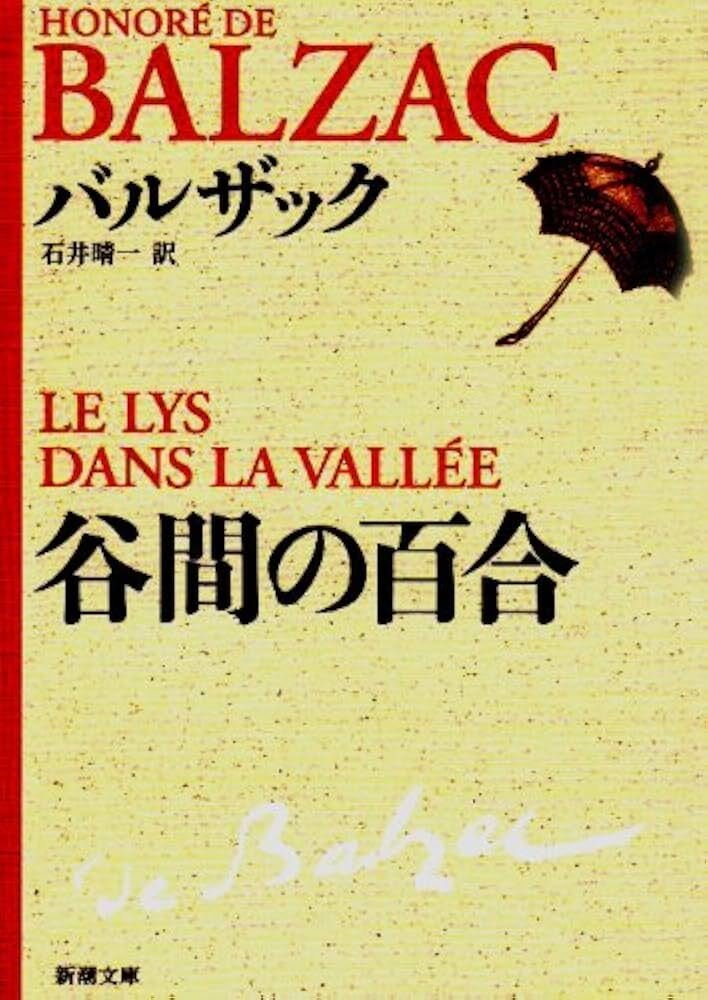
オノレ・ド・バルザックの名作長編小説。
「私は就活とかしたことないから分かんないけどさあ。唯一無二の自分なんて価値観が均されて、自分という存在がその他大勢の一人に過ぎないと思い知った、そんな学生のささやかな抵抗と考えれば美談なのかもね。どちらにせよ。底なしにキモイけど」
それに、と続けて。
彼女ちゃんは頁を捲る。
「そういう奇特な集団っていうのはね、存外、あっさりと崩壊するものよ。つまんないことでね」
なるほど、先見の明がある。
あくまでも過去の出来事なので、”先見”の明が正しい表現なのかは考えものだが、少なくともその見込みは当たっていた。
電車は遅延なく目的地へ向かう。
だから僕は、その場所への到着を大人しく待ち続ける。
無抵抗に揺られながら。
結論から言えば。
角砂糖同好会はそれから四ヶ月と持たずに、驚くほど呆気なく空中分解した。
ある時は同好会内で痴話喧嘩が勃発し、ある時は面子の恋人が苦情を飛ばして、ある時は教師に集まりが露見し、ある時はある時はある時は──そんな形で角砂糖同好会の面子は、さながら幽霊部員である僕と目立った問題を起こさなかった彼女を残すところとなった。
正直な話。
そうなれば、もう活動を継続する意味はない。
しかし。あれ以来めいろさんとは個別に交友関係を深めていて、たまに僕らが会う口実として、角砂糖同好会の活動はちょうど良かったというのはあるのだろう。
素直に会えよという話だが、僕が改まって人と会うことに億劫なのもあり、それがスタンダードだった。
僕の方から人に会いたいとか言うのは、
極めて稀なことなのである。
ところで僕とめいろさんの間に色事はなかった。
男女の友情は成立しないというが、僕は恋愛不全に陥っていたし、彼女も彼女で好きな男が居たので健全な距離感を維持することが出来ていたのである。
だから しばらくの間、
僕らは同好会の不健全な活動を健全に続けた。
免罪符代わりにアダルトビデオを実況し、その後は益体もない話をした。恋愛相談に乗ったり、逆に恋愛不全に悩む僕の悩みも聞いてもらったりしたのを覚えている。
昔々こういうことがあってさ、それから好きな人が出来ないんだ。人をちゃんと好きになれないんだ。怖いんだよ。ひょっとして自分は心の冷たい人間なんじゃないかって。たった一度。恋人に裏切られたくらいで、情けなくも、死ぬまでそれを引き摺り続けるのかなって。それが嫌なんだ。嫌なのに変われないんだ。この人の為に全部を捧げようなんて当たり前の感情なのに。そういう気持ちが抱けないんだ──そんな自分がどうしようもなく嫌いで、どこか遠くに、消えてしまいたいんだ。
とかなんとか。
”こういうこと” を、詳しく掘り下げる気はない。
それは僕の最も致命的な失敗体験であり、忘れ難いトラウマであり、僕の人格形成に関わる重要な一件なので、おいそれと語るには少しばかり暗く、そして重い。
思えば彼女ちゃんが見えるようになったのも、
あの一件からである。
話を戻そう。
要するにその話を打ち明けるくらいには、友人としての信用をめいろさんに寄せていたのだ。
僕がこの話をすると、
彼女は決まってこんなことを言った。
「大丈夫だよ。そんなことないよ。きっと立ち直れるよ」
それは、あまりにもありふれた慰めの言葉だ。
実態としては、まるで大丈夫じゃないし、そんなことあるし、立ち直れる保証なんかどこにもなかった。
それでも。
たとえ気休めだとしても。
そんな言葉をくれるのは嬉しかった。
そういう関係が数ヶ月に渡り脈々と続いた。
しかしこの関係は、角砂糖同好会と同様に、あまりにも呆気なく終わりを告げることとなる。
その日、彼女はいつものように持参した円盤を再生機器に挿入して、再生の準備を進めていた。
そうして会うのは、ほぼ一ヶ月振りだったと思う。
無事に例の男性と交際を開始したらしく、それで気を使って僕の方から連絡を絶っていたのだ。
しかし、
「そういう変な遠慮をされると気まずいからやめて」
と怒られたので、機会を作って、会うことになった。
その映像を再生するまで、二人でどんな話をしたかは覚えていない。きっと。良い意味でどうでもいい話だったと思う。よくある会話。ありふれた雑談。そういう話。
少なくとも、およそ二十分後に年単位の絶縁をすることになる友人と交わすような会話ではなかっただろう。
再生開始──されて、僕はすぐに違和感を覚えた。
その映像は市販の作品にしては画質が悪く、撮影もなんだか不得手な様子だ。端的に言えば素人臭い。かと思えば素人が売り出す作品にしても拙さが異様に目立つ。
やがて見知らぬ一室に被写体として映ったのは、
僕の隣に座るめいろさんその人だった。
愚鈍な僕といえど、流石に直感した。
これは彼女とその交際相手の情事の映像だと。
僕は映像をすかさず止めて、間髪入れずに問い詰めた。問い詰めたというより差し迫ったが正しいのだろうか。
恋愛相談、いくらでも聞こう。
惚気、話したくなることもあるだろう。
でも”これ”は、絶対に違う。
僕は友人としてこんなのは見たくない。
頭の中でそれらしい正論を探すが、しかしこういう時に限って、言葉がうまく出てこなかった。
とにかく。とにかくだ。
自分を大事にしてくれ、とか
そんな月並みなことを言った気がする。
「保健体育の教科書みたいなこと言うんだね」
そうかもしれなかった。
しかしそれでも、
これは君にとって大事なことだろうと訴えた。
「大事じゃないよ。だって……こんなの、ただの惰性だよ? 関係を維持したいからってみんなやってることだよ」
明確に彼女は苛立っていた。
語気も強くなり、僕を睨むようにして、言葉を続ける。
「じゃあさじゃあさ! わたしが半年くらい こういうことを彼としなかったとするよね!? そしたら、もう今のままじゃいられないんだよ。飽きられたり、冷められたり、彼は別の相手を選んだりするんだよ。恋愛なんてそんなもんだよ。それが普通なんだよ。そんなこと分かってるよ。分かった上でみんな恋愛してるんだよ」
めいろさんは、
堰を切ったように一人で抱えていた不満をぶちまける。
「それでもね。たまに、それをすごく馬鹿馬鹿しいって感じることもある──そんな悩みを、友達に一緒に笑い飛ばして欲しかった、そう考えることはそんなに変なこと?」
変じゃないかもしれない。
理屈は通っているのかもしれない。
しかしそれでも限度がある。
それが彼女の剥き出しになった本音に対する、
僕という人間の正直な感想だった。
「自分をそこそこに愛してくれる恋人がいて、一緒に馬鹿になれる友達もいる。わたしは恵まれてるのかもしれないね。でもどうしても考えちゃうんだよ。とても寂しい。ずっと満たされていない。そんな気がする。足りない。全然足りない。本当に欲しかったものはこれだっけって。ねぇ、わたしって一生こうなのかな。一生この埋まらない空洞と一緒なのかな。ただただ心から安心したいってさ、そんなに大変な高望みなのかな?」
大丈夫だよも、
そんなことないも、
きっと立ち直れるよも、
その時の僕は言わなかった。
そんなの分からない、としか言えなかった。
「……都部くんは冷たい人だよね。だからさ、そんな風に良い人の振りなんかしないでよ。本当は他人のことなんてなんとも思ってない癖に」
限界だ。
口論になる前に、僕はその場を離れ、帰ることにした。
このまま二人で会話を続けても不毛だと思ったし、なによりも二人とも頭を冷やすべきだと判断したからだ。
その冷却期間は数年に及ぶことになるとは、
この時は流石に予想だにしてなかったが。
去り際、ではないけれど。言い過ぎたと後悔したらしい彼女は、あの時 僕に向かってこんなことを言った。
それは、どう考えても今更な言葉だったけれど。
少なくとも彼女のことを嫌いにならず済む言葉だった。
「──そんな顔、させるつもりじゃなかったの」
彼女の名誉を守るため。
言っておくことがあるとすれば、この会話は一言一句と正確な記憶ではなく、似たような、意訳に等しい遣り取りがあったというだけの話だ。本来の遣り取りには個人名や友人を介した具体的な例が飛び交い、かような文章以上に僕もまた感情的になっていた。
意訳の嵐を”嘘偽りのないエッセイ”と称するのは抵抗があるが、ただそれでも僕と彼女の関係がほどなく断絶し、今日に至るまで没交渉だったという物事の終点はまるで変わらない。
つまり僕も彼女も、
相手が求める友達であることに失敗したのである。
当時の二人の年齢が21歳であることを鑑みれば、それは仕方の無い事だったのかもしれない。当時の僕らでは処理しきれない問題だった。大変ないざこざだった。
あの日、彼女があれだけ激昂した理由もついぞ思い至らず、僕は問題をそのままにしてしまった。
未熟なばかりに。
「まさか、今なら上手くやれるとか思ってる?」
神保町駅に到着し、目的地にして待ち合わせ場所であるCAFEラドリオに向かう道中のことだ。
彼女ちゃんがそんな風に絡んできた。
「彼女の悩みを受け入れて、言葉を上手く返して、今も仲良しこよしで友人を続けられてたって?」
小馬鹿にするような口調。
一笑に付すという表現が正しい、嘲笑混じりの言葉。
「馬鹿じゃないの」
それは心を感じさせない。
とても冷たい響きの声音だった。
「そういうの、傲慢っていうのよ。アンタの言葉にも、思考にも、なけなしの善意にだって何にも変えられない。たしかに人生は劇的かもしれないわね。でも劇じゃない。人生は人生でしかないの。人生は成るようにしか成らない。だから言葉を重ねることなんかに意味はない」
アンタの言葉に意味なんかない、と。
「あっさり聞き流されて、軽く受け止められて、それで終わりよ。みんなそう。アンタとは無関係の場所で立ち直って、アンタとは無関係の場所で生きていく」
それだけのことだ、と。
そして、その講釈の締めとばかりにこう断言する。
「誰も、誰一人だって、アンタなんかに期待してない」
……今日は、いつもより三割増しでご機嫌斜めだね。
なんか嫌なことでもあった?
「べっつに〜〜〜? ただね。昔 自分を傷つけたクソ女とわざわざ会う予定なんか作って、和解の振りなんかしようとしてる態度が気に食わないだけ」
和解の振りとは心外だった。
あれから時間もそれなりに経った。
少なくとも僕はもう気にしてないし、彼女もそういう姿勢だからこそ、今日という再会の日が成立したのだ。
「そこよ。”振りじゃない” ことが一番の問題だって言ってんのが分かんない?」
ひどく呆れた様子で、かぶりを振る彼女ちゃん。
三つ編みがだらしなく揺れるばかりで、まったくもってその姿はサマになってない。
「まあ好きにすれば。言っとくけど、私はアンタのそういうところが本当に嫌いだから」
彼女ちゃんは、
そんな捨て台詞を吐いて黙ってしまった。
疑問は尽きないが、今日に関してはもう口も聞いてくれない気配があったので、脳味噌を切替えることにする。
ラドリオの店内に這入ると、特に迷うことなく、店内の最奥の席に彼女の姿を見つけた。
数年振りに顔を合わせる彼女は大人っぽくなっていて、それは見目に限らず、服装や振る舞いにも同じことが言えた。ちなみにカラコンは付けてなかった。黒目だ。
少しがっかりである。
さて。
実際に顔を合わせるまではいささか緊張していたが、流石に年単位で時間を置くとやらかした過去も他人事である。思ったよりもすんなりと。昨日帰り道で別れたばかりの友人さながらの距離感を取り戻すことは出来た。
それから二時間、僕は注文も挟まず語り明かした。
良い意味でどうでもいい話をした。よくある会話。ありふれた雑談。まあ、なんというか、そういう話。
「──あ、そういえば好きな人が出来たよ」
「お、良かったじゃん。どんな子?」
「もう彼氏がいる子」
「えぇ…………」
そう言われためいろさんの顔は、
なかなかどうして味わい深かった。
映画の一作目で語り部がヒロインと円満に結ばれて終わったのに、続編であっさりそのヒロインと破局していて、なんなら別の交際相手を作ってるのを見た時とか。
僕もこんな感じの顔になる。
「災難だね。よかったら、わたしの友達とか紹介しようか?」
有難い申し出だった。
とはいえ僕は恋愛がしたいからその人を好きになったわけではないので、それでは意味がないことを説明した。
「そっか。なんだろう。上手くいくように応援はしてる。……していいのかなこれ。人の彼女さんなんだよね」
「ありがとね。そういう めいろさんは? 今って人生楽しい?」
「楽しいよ。毎日がそれなりに」
迷いのない即答だった。
それを純粋に嬉しいと思う程度には、自分が未だに彼女のことを友人として好いていることが嬉しかった。
「都部くんは……? どんな感じ? 生きてて楽しい?」
悪意のある聞き方のようだが、絶縁状態だったとはいえ彼女との付き合いも短くはないので、そこは単純に言葉足らずなだけだと判断する。
めいろさんも気になるのだろう。
昔の友達は、あれからどんな風に変わったのか。
しかし僕は答えに困ったので、ひとまずは何か頼もうと場を仕切ることにした。彼女も追加で頼むらしい。
「わたしはブレンドコーヒーで。……そういえばコーヒー好きだったよね。都部くんもこれにする?」
なにか勘違いをされている。
たしかに彼女の前で珈琲が苦手な姿を見せた覚えはないが、昔から好きだったと言われるような印象的な思い出を作った覚えはない。珈琲。珈琲ね。珈琲ですか。
僕は少し考え、きっと何かを誤魔化すような顔をして、その申し出をこんな風に断った。
「今はちょっと、珈琲は飲みたくないかな」
2024/7/20 都部京樹
執筆BGM
『ロマンス宣言』カネコアヤノ
『ただいま。』宇宙ネコ子
全体プレイリスト⇒https://open.spotify.com/playlist/4F2A0A5x6T5DZLZXDXuEoB?si=sUznb1seRHG-vcsgjQP-Mg&pi=a-r8eHXL5CRmyZ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
