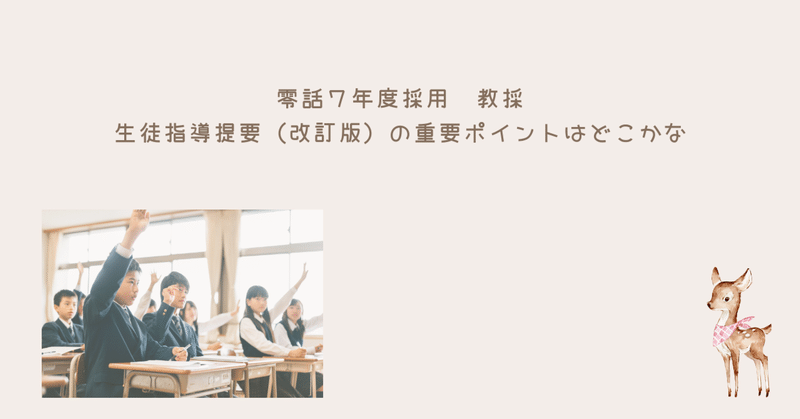
「生徒指導提要」はここをチェック令和7年度採用教採向け
生徒指導提要
教員採用試験を受験をする方にとって
知らない
という方はいらっしゃらないほど
認知度の高いもの
今回は
令和7年度に教採を受験される方は
どこを中心に確認をしたらよいだろう
ということについて
私はこう思うという
お話させて頂こうと思います
「生徒指導提要」とは
小学校段階から高等学校段階までの
生徒指導の理論・考え方や実際の
指導方法等について
時代の変化に即して網羅的にまとめ
生徒指導の実践に際し
教職員間や学校間で共通理解を図り
組織的・体系的な取組を進めることができるよう
生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として作成したものです
(生徒指導提要改訂版より引用して抜粋)
平成22年に初めて作成されたので
割と最近のものです
12年ぶりの改訂されたのが
令和4年12月です
ですので
令和6年度採用の方は
かなりていねいに勉強されたと思います
もちろん私も
サポートする立場として
重点をおいて確認しました
さて
その「生徒指導提要」は
今年はどこを勉強したらよいでしょうか
私の見立ては
次のようになりました
令和7年度採用試験はここを確認
①生徒指導の定義
②生徒指導の目的
③生徒指導の構造
この3点です
実はここは昨年度
指摘させて頂いたところと同じところです
同じなんだ・・
と思われるかもしれませんが
少し違いがあります
令和7年度教採で確認しておきたいところ
まず
生徒指導の定義と目的は
「基本」として
いつ受験しても重要ポイントです
生徒指導とは何か(定義)
何のためにするのか(目的)
ということを正しく知っておくことが
大切だからです
なんとなくわかっているかもしれません
こんな感じかなと思うかもしれません
ですが曖昧にせず
正確に知ることはとても大切ですね
生徒指導の定義
生徒指導の定義は
このようになっています
生徒指導の定義
生徒指導とは、児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。
生徒指導の目的
そして目的です
生徒指導の目的
生徒指導は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えることを目的とする。
生徒指導の構造
つぎに「生徒指導の構造」についてですが
はじめに
こちらの図をみてください

この図は「生徒指導提要(改訂版)」
に記されている図をもとにして
色分けして表してみました
2軸は時間軸
生徒指導の分類として
2軸は一番右の2つ
プロアクティブ
リアクティブ
のところです
時間を軸にしたものを指しています
児童生徒の課題への対応を「時間」
でみたものですね
生徒指導提要(改訂版)の文章を引用すると
このように解説されています
①常態的・先行的(プロアクティブ)生徒指導日常の生徒指導を基盤とする発達支持的生徒指導と組織的・計画的な課題未然防止教育は、積極的な先手型の常態的・先行的(プロアクティブ)生徒指導と言えます
②即応的・継続的(リアクティブ)生徒指導課題の予兆的段階や初期状態における指導・援助を行う課題早期発見対応と、深刻な課題への切れ目のない指導・援助を行う困難課題対応的生徒指導は、事後対応型の即応的・継続的(リアクティブ)生徒指導と言えます。
3類は生徒指導の課題性
3類は生徒指導の課題性を
高い・低い
で分類したものです
こちらも「生徒指導提要(改訂版)」の
本文で確認してみましょう
生徒指導の課題性(「高い」・「低い」)と課題への対応の種類から分類すると、図1のように以下の3類になります。
①発達支持的生徒指導全ての児童生徒の発達を支えます。
②課題予防的生徒指導全ての児童生徒を対象とした課題の未然防止教育と、課題の前兆行動が見られる一部の児童生徒を対象とした課題の早期発見と対応を含みます。
③困難課題対応的生徒指導深刻な課題を抱えている特定の児童生徒への指導・援助を行います。
このように記されています
生徒指導の4層
生徒指導の4層
じつはこの4層のところが一番重要です
なぜ重要かというと
ここが改訂されたところのひとつだからです
改定前の『生徒指導提要』(平成22年)では
3層構造だったものが
4層構造になりました
こちらも「生徒指導提要(改訂版)」をもとに
図を作成してみました
図1と色を対応させています

第1層「発達支持的生徒指導」
第2層「課題予防的生徒指導:課題未然防止教育」
第3層「課題予防的生徒指導:課題早期発見対応」一部の児童生徒を対象
第4層「困難課題対応的生徒指導」特定の生徒を対象
これを
生徒指導の重層的支援構造
といいます
生徒指導の重層的支援構造で特に重要なこと
生徒指導の重層的支援構造で特に重要なこと
それは
第1層のすべての児童生徒を対象とした
「発達支持的生徒指導」
第4期教育振興基本計画にも
その大切さが示されています
発達支持的生徒指導とは
発達支持的生徒指導は
特定の課題を意識することなく
全ての児童生徒を対象に
学校の教育目標の実現に向けて
教育課程内外の全ての教育活動において進められる
生徒指導の基盤となるもの
発達支持的というのは
児童生徒が自発的・主体的に
自らを発達させていくことが尊重されている
ということで
発達の過程を
学校や教職員が
どのように支えていくかという視点
であるということも重要です
児童生徒の
「個性の発見とよさや
可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支える」
ように働きかける
とも記されています
※この章で太字部分は
「生徒指導提要(改訂版)」
文部科学省令和4年12月
を引用し一部を抜粋したものです
この記事のまとめ
令和7年度教員採用試験を受験される方の
一次試験対策のひとつとして
私は
「生徒指導提要(改訂版)」の
生徒指導の重層的支援構造
その中でも
発達支持的生徒指導
を理解しておくといいのでは
というご提案をさせていただきました
「生徒指導提要(改訂版)」に限りませんが
正しく理解してもらいたい文章は
じっくり読まないとわかりにくかったりしますね
わかりにくいのは
まちがえのないように
ていねいに説明しているからなので
仕方がないのですが
やはりできるだけ効率的に勉強したいですよね
今回の説明がその一助となればうれしいです
*サポート*とてもうれしいです。 いただいたサポートは過去問等資料用書籍代 として使わせていただきます。
