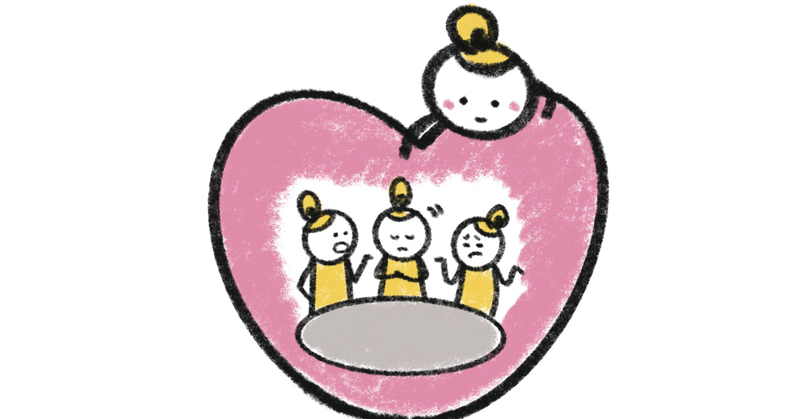
行政の相談員に"離婚してもふたり親”を知ってもらうために
こんにちは。しばはしです。
2022年6月、世田谷区5支所職員・相談員の方に向け、「ひとり親家庭への支援者向け研修プログラム」の研修を実施させていただくことになりました。
どのような経緯で実施に至ったかを、各地域でも研修の機会が実現できるようシェアします。
行政によるひとり親家庭支援の現状と課題
前出の記事で、行政によるひとり親家庭支援の現状と課題について触れました。
離婚したいと悩む時、身近で無料で相談できる行政相談員。相談者にとって心強い存在であり、かつファーストコンタクトでのアドバイスは影響力が高くもあります。
それゆえ、相談員の方に「離婚しても両親が子育てに関わっていく」という価値観を知っていただいたうえでアドバイスをしていただくか否かで、その相談者そしてその先にいるお子さんの未来が大きく変わっていきます。
私の居住エリアである世田谷区において、りむすび立ち上げの頃から面会交流相談会や相談員研修などを提案してきましたが、面会交流=DVのリスクなどというスタンスからなのか、なかなか実現にいたらず、世田谷区は離婚に向けた手続き的な相談会や養育費相談会がメインに行われてきました。
そんななか、ここに来て転機がありました。
世田谷区で研修が実現した経緯
世田谷区において、りむすびの取り組みを応援くださる区議会議員さんが少しずつ増えてきているなか、りむすび立ち上げ以前から離婚後の養育について関心を持ち共同養育普及に向けて取り組んでくださっている佐藤美樹区議会議員が、議会の一般質問において、"離婚家庭と関わる支援員が共同養育の視点を持つことの必要性"を投げかけてくださいました。これまでも何度か取り組んでくださっていましたが、今回、世田谷区の管轄部の担当者の方が必要性を理解してくださり実現にいたりました。
その前段階として、世田谷区のひとり親向けリーフレットにりむすびを掲載させていただけたのも佐藤議員によるご尽力のおかげでもあります。

実施に向けて研修担当の方と打ち合わせをさせていただいたのですが、高葛藤ケースへの介入には常に悩まれている様子であり、離婚前の夫婦の葛藤を下げるための支援のコツ、精神的DVの相手との面会交流についてどのようにアドバイスすればいいか等、具体的に知りたいというニーズがあることも受け取りました
2016年に大阪府で相談員研修をさせていただいた際には、
・離婚した後も子どもにとって親はふたりだという当たり前のことに今まで気づかなかった
・面会交流したくないという方に対して、"したほうがいい"と言いづらい
・子どもの気持ちを踏まえ、どのような声がけをすればいいか参考になった
といった声もいただいていたことから、研修をする意義をあらためて再認識するところです。
各地域で実現させるには
今回といいますか、これまでやってきた行政へのアプローチ。他にも方法はあると思いますので、あくまで参考までにですが、流れをざっくりお伝えしますと。。
①地方議員へ啓蒙
②地方議員から管轄部署の担当者を紹介してもらう
③地方議員が議会の一般質問で取り上げる
④管轄部署の担当者が行政の対応について回答する
⑤実施
という流れになります。
①②で関係性を構築することは時間も要します。特に②においては、せっかく理解促進できていた矢先に異動で担当者が変わるといったこともしばしば。
ポイントを総じていうならば
・議員や行政のお手を煩わせない
・個人的な困り事をなんとかしてくれ!ではなく、行政における必要性を伝える
・行政の現状を批判しない。不満をぶつけたり攻撃的な対応をしない
・かゆいところのお役に立てます!スタンスで具体的に提案する
・外部での実績を提示
といったところでしょうか
①については、当然ながらご自身の居住地の議員と親交を深めるのが◎です。選挙区の住民の声には親身になってくれやすいです。また、その議員さんがどの委員会に属されているか(子ども支援に関心があるか)や家族構成(お子さんがいるか)などをHPで見ておくとよいですね。
そして、「現状→課題提起→提案」です。仕事におけるクライアントへのプレゼンと一緒ですね。
当事者の方、特にお子さんと会うことが制限されている方は、お相手の居住地エリアの相談員に共同養育の知識を持ってほしい!と願う方も多いと思います。
ひとつの方法としてご参考にしていただければ幸いです。
*すでに具体的に動かれている方、これから動かれようとしている方などでお役に立てることがありましたらお声がけください*
よろしければサポートをお願いします。いただいたサポート費用は共同養育普及に活用させていただきます!
