
世界的ミスコンの舞台裏であったハラスメント、出場者の私が見たその一部始終
今回の note では「ミスコンにおけるハラスメント」について、記者の実体験や他の出場者への取材内容を基にまとめた記事をご紹介します。共同通信は他のコンテストにおいても同じような被害があるのではないかと考えています。もし「私も被害を受けた」「被害を受けている人を見た」という方がいらっしゃったら、可能な範囲で結構ですので、お話を聞かせてください。

■ この note で伝えたいこと
みなさん、こんにちは。
今回は記者の私が今年3月に書いたミスコンの実態に関する記事について、取材に至った経緯や、その中で伝えたかったことをお話ししたいと思います。少し長くなりますが、最後まで読んでいただければありがたいです。
この記事の中で取り上げた「ミス・アース」というコンテストは毎年90カ国以上が参加する世界規模のミスコンテストの一つです。開催目的の一つとして地球環境保護の促進を掲げ、公式ホームページにはパートナーとして国連機関の名前も掲載されているような大きな大会です。
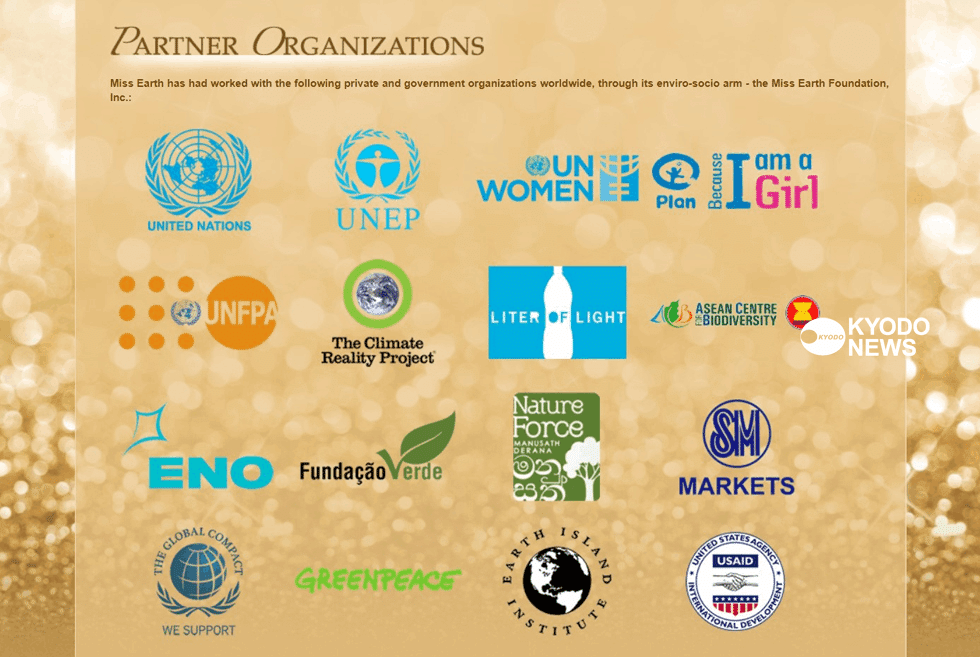
パートナー団体として「国連」や「国連女性機関」などが紹介されている
大学生の時にその地方大会に参加した私は、大会後のアフターパーティーで出場者がドレス姿のまま男性審査員たちの隣に座り、お酒の相手をさせられる場を目の当たりにしました。セクハラのような言葉をかけられた人もおり、開催趣旨と実態の大きな差に驚きました。
「ミスコンへの参加は素晴らしい経験だったが、パーティーのことは忘れたくても忘れられない」
「今後参加する人には同じ経験をしてほしくない」
その場にいた女性たちからこうした声を聴いた私は、自分が見聞きしたことを報道することで何かを変えられるのではないかと考えて記事を書きました。
記事は、共同通信に加盟する新聞社のウェブサイトやYahoo!ニュースなどのプラットフォームでも公開されています。コメント欄にはこちらが予期していなかった声も寄せられており、筆者の私にとっても学びになりました。
そして今、ミスコンに気軽に参加できるようになった時代だからこそ、他の大会でも同じような問題が起きているのではないかと思い、この note を書いています。
ミスコンを巡っては賛否さまざまな意見がありますが、少なくとも、今後出場する人たちにはもう不快な思いをしてほしくない、誰も被害を受けないようにしたいと考えています。
そんな問題意識を少しでも多くの方と共有するため、改めて私自身の経験をお伝えしたいと思います。
■ ビューティーキャンプ
私がミスコンに興味を持ったのは大学入学後、1人暮らしをするようになった頃でした。
自炊を始めたのをきっかけに「健康的な食事がしたい」と思うようになり、ミスコンの講師もしていたある栄養士の方の本を手に取りました。その本がとても面白く、以来ミスコンに関連する本をいくつも読みました。
特に印象に残ったのが林真理子さんの「ビューティーキャンプ」という1冊。ミスコン大会のファイナリストたちが2週間、食事や本格的な筋トレ、ウォーキングの指導などを受け、大会に臨む様子を描いた小説です。
そこに登場する女性たちが自分の人生や将来について悩みつつも前進し、内も外も美しい人間になっていくことに感動し、「私もそんな経験がしたい」と思うようになりました。
ミスコンの是非については賛否それぞれの意見があります。
「ルッキズムを助長する」という批判を受けて廃止する流れがある一方、外見以外のパーソナリティーを重視することを打ち出し、存続を図っている大会も多くあります。
ミスコン世界大会の優勝者には、その知名度やタイトル(「ミス○○」という肩書き)を生かし、環境保護やジェンダー平等などを訴えているオピニオンリーダーもいます。
もともとジェンダー問題に関心があった私は、ミスコンに対する評価が大きく分かれていることに興味を持ち「まずはこの目で実態を確かめたい」という思いで自らコンテストに応募することを決めました。
■ 「環境保全」掲げる世界的大会
前述した通り、私が参加した「ミス・アース」という大会は「人々の環境保全に対する意識を促進すること」を目的とする世界規模のコンテストです。世界大会の公式ウェブサイトでは、国連(United Nations)や国連女性機関(UN Women)がパートナー団体として掲載されています。

私は当時、農家の手伝いなどをしていたこともあり、自然とともに暮らす持続可能な生活を発信したいと考えていました。大会の目的は、そんな価値観とも一致していましたし、国連機関がパートナーになっているコンテストなら、有意義な活動ができるのではないかと期待していました。
実際、1カ月間ほどかけて行われたオンライントレーニングでは、メイクやウォーキングの練習に加え、環境問題に関する知識やスピーチの技術なども教わることができました。このコンテストでタイトルを得て社会を変えようという強い思いをもった他の出場者や講師との交流は、貴重な経験になったと思います。
しかし大会後のアフターパーティーは、そうした学びや大会が掲げる目的とはかけ離れたものでした。
■ 酒席でお酌「ホテルに誘われた…」
当時はコロナ禍で会食の自粛が呼びかけられていた時期なのに、当然のようにお酒が振る舞われ、コンテストの出場者はドレス姿のまま全員参加を求められました。賞をとった女性は男性審査員の横に座るよう指示され、中にはホテルの部屋に来るよう誘われたケースまでありました。

受賞した女性たちは審査員を務めたスポンサー企業の関係者の横に座るよう指示された
パーティーが終わってから出場者同士で話をしたところ、ある人は「スポンサー企業の男性から不快なことを言われた」と怒り、また別の人は「泣き寝入りしたくはないけど、どうしようもない」とおびえていました。
ショックだったのは、大会の運営スタッフがこの実態を目の当たりにしながら、男性審査員らの言動を容認していたことです。
問題視していないのか、あるいは外部に漏れることはないだろうと高をくくっているのか。いずれにしても馬鹿にされたような気持ちになり、悔しくなりました。そして、今後も同じようなことが繰り返され、誰かが傷つけられることだけは、なんとしても避けたいと強く思いました。
■ 出場者が語ってくれたこと
後日、私は自分が体験したことを信頼のおける複数の友だちに打ち明けました。
彼らは「あなたがコンテストに向けて楽しそうに特訓していたのを知っているから、悔しいし信じられない。もし声を上げたいなら、報道機関の記者に伝えたり、パートナーになっている国連に連絡したりしてはどうか」とアドバイスしてくれました。
しかし、そもそもミスコンに対して良くないイメージを持つ人も多い現状で、初対面の記者に率直な話をするのは簡単ではありません。仮に話すことができても、その内容を信じてもらえるのか、きちんと報道してもらえるのか。不安は拭えませんでした。

それならいっそのこと、自分自身の言葉でこの問題を世に問いたい。当時から記者を志望していた私は、この時に「私が体験したことは、私の手で記事にしよう」と決めました。
その翌年に共同通信に就職し、記者となった私は、今年3月の国際女性デー(3月8日)に合わせて記事を出そうと考え、1月ごろから当時の出場者らと連絡を取るようになりました。
ある女性は「あの日のことは忘れられない。日本社会の古い感覚がもっと早く変わってほしいと思っているから、私で良ければぜひ手伝いたい」と応えてくれました。
インタビュー取材で彼女が語った「今後も同じ思いをする女性たちがいるのは間違っていると思う。自分だけでは行動できなかったから、記事に協力できてうれしい」という言葉は特に印象に残っています。今に至るまで、その一言は取材者である私の励みになりました。
■ 「パートナーではない」国連からの回答
記事にする以上、私を含めた出場者側の一方的な主張だけを取り上げることはできません。大会の運営会社にも事実関係を確認しましたが「当事者の特定が著しく困難であり、ご指摘の各事項に関して事実関係の特定及び事実認定を行うことができません」とまさかのゼロ回答でした。
運営スタッフがパーティー会場にいたのは私もこの目で確認しましたし、賞をとった出場者に対し、男性審査員の隣に座るよう指示しているのも見ました。調べようと思えば、出場者や審査員が所属するスポンサー企業からも、事情を聴くことができるはずです。そうした調査をせずに「事実認定ができない」と回答するのは、非常に不誠実な対応だと思います。
取材で明らかになった事実もありました。私が最も驚いたのは、運営サイドがパートナーだとするUNWomenの広報担当者が「我々はミス・アースのパートナーではないし、ロゴの使用も認めていない」と主張したことでした。

世界的なミスコンテストと言われるミス・アースが、国連機関の名称とロゴを勝手に使用しているというのは、にわかに信じがたいことです。念のため、国連(United Nations)にもパートナー関係を調べるよう依頼しましたが、こちらも同様に「パートナーではない」との回答でした。
私自身、出場を決めた際は「国連機関と関わりがあるなら、きっと信頼できる大会なんだな」という印象を持っていたので、この回答をもらった時は本当に悔しくなりました(国連サイドの説明について、ミス・アース世界大会の運営会社にもメールで見解を求めましたが、この note を書いている5月下旬時点で返信はありません)。
運営サイドへの不信感はさらに募り、他の地方予選や世界大会の運営はどうなっているのだろうかと疑念を持つようになりました。
■ ハラスメントは容認できない
こうした取材内容をまとめた記事は3月下旬に配信され、大変多くの人の目に触れました。ただ、寄せられたコメントに目を通す中で、読者の方々に問題意識を共有していただくことの難しさも再認識しました。
「ミスコンは基本的に自己顕示欲が強い人が出るもの」
「参加している時点で、女性としての要素を有効利用したい下心がある」
こういった厳しい意見もありましたが、私がコンテストで知り合った女性たちにそうしたイメージには当てはまりません。出場者の真摯な思いは記事にも書いたつもりだったのですが、きちんと伝わらなかったのだろうと思います。筆者として、歯がゆい思いです。
日本の大学などで実施されてきたミスコンの中には、性差別やルッキズムを助長するとの指摘を受けて廃止になった例が複数あります。しかし歴史を振り返ると、国際的な大会はたびたび「女性蔑視の象徴だ」という批判を受けつつも、「外見だけではなく知性と内面も競うもの」に形を変え、存続してきた経緯があります。
私自身、オピニオンリーダーになって社会に貢献するという目標を掲げ、そのための手段として外見・内面を磨く努力をすることは、スポーツや芸術の大会にも通じる点があると思っています。
また、全てのコンテストに不適切な問題があるわけではありません。高い理想を持った方たちが純粋に競い合い、出場者をリスペクトした形で運営されている大会もあります。
私は自分自身が出場することで、そうしたミスコンの良さを知ったからこそ、一部ではハラスメントがあること、被害を受けている人がいる事実についてもきちんと報道したいと考えています。
ミスコンの是非についてさまざまな意見があったとしても、誰かが不快な思いをしたり、傷つけられたりすることは容認できません。
もし皆さんの中で、同じような体験をした、あるいは見聞きしたという方がいらっしゃったら、その内容を教えていただけないでしょうか。ささいなことでも結構です。以下のフォームから声を寄せていただければ幸いです。

