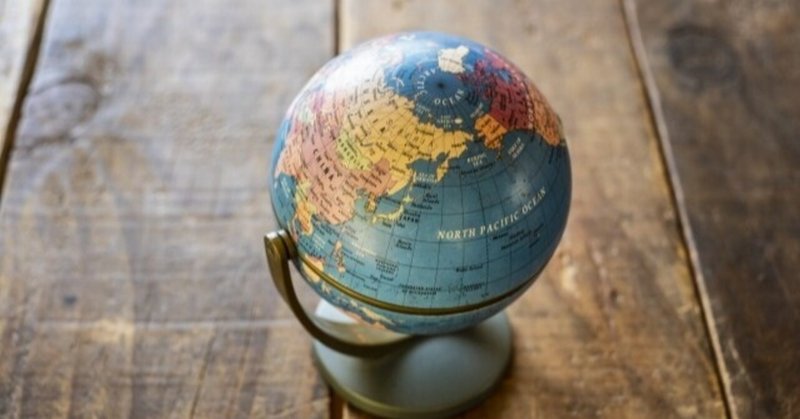
ハートランド・ロシアの動向を分かりやすくふまえて世界情勢をみてみる
最近ロシア近隣できな臭い動きが続いている。これは何を意味しているのだろうか。
ウクライナの国境にロシア軍が集結。
カザフスタンのデモに対してロシア軍が投入された。
現在、世界は米中覇権戦争を中心に動いているが、ユーラシア大陸の中心部・地政学的にいわゆる「ハートランド」を持つ大国ロシアを無視して世界情勢は語れない。
当ブログは素人の世界情勢ウォッチャーであるが、ロシアの動向には様々なツールを通して普段から注目している。それでも、まだまだロシアという国は謎に満ちている。
本日はウクライナとウズベキスタンの事例からハートランド・ロシアの意図を読み取ることで、混迷する世界情勢を照らす一灯となるよう記事をまとめてみる。(あくまで素人の記事です)
ロシアの目指す方向性
ロシアの起源は東スラブ人のロシア平原への定住に始まり、キエフ公国をルーツの一つに持つ。まさに「大陸の中央部=ハートランド」の人々だ。帝政ロシアの時代にユーラシア大陸の広範囲に支配域を持つ強国となり、ソヴィエト連邦を経て現在のロシア連邦に至る。
ソ連の崩壊後、西側諸国の一員として歩みを始めたロシアであったが、経済が自由化されても人々の生活は豊かにならず、新興財閥といわれる一部の超金持ちだけが豊かになる格差社会を生んだ。その新興財閥をやっつけて国民的人気を得たのがプーチン大統領という流れである。
ロシアはかつてG8に数えられ、自由・民主主義陣営の一員になりかけたものの、クリミア併合でG8から外され、経済制裁もくらっている。
つまり、ロシアにとっての優先順位は「強いロシアであること=地域覇権国家となること」>>「西側諸国の一員として発展すること」なのである。ソ連は崩壊しても、地域覇権国家であることは決してやめない。
それは、大陸最奥にあり難攻不落でありつつも貧しい土地である「ハートランド」を領土に持つ国の宿命なのかも知れない。G8に戻ることにもメリットはない。これがロシアの立場であるし、またプーチン大統領がその地位にとどまり続けるための正当性でもあるのである。
そして、地域覇権国家として絶対的な影響力を保持しておきたいのが、旧ソ連構成国である。ウクライナもカザフスタンも、旧ソ連構成国であり、ロシアからすれば子分のような存在だ。

ウクライナVSロシア
ところが、ウクライナにしてみたらロシアの子分というのが嫌なのである。
ウクライナというのもなかなか理解が難しい国で、ロシアとともにキエフ公国をルーツとする。「小ロシア」と呼ばれていた時代もあるほどの、ロシアとは兄弟分のような存在であるが、歴史の波に翻弄されるなかで、決してロシアに好印象を持っているというわけではないのが現実である。
特に2004年のオレンジ革命以後、ウクライナは脱ロシアを進めた。脱ロシアということは、西側諸国に接近するということである。ウクライナの究極の目標は、EUの一員となることだ。
しかし、ロシアからしてみれば、同様のルーツを持ち、舎弟のように思っている国が、帝政ロシア以降の不倶戴天の敵である欧州に接近するというのは許しがたいことである。
特にNATOは反ロシア軍事同盟であるから、NATOがウクライナに入り込むのは、はらわたを抉られるようなもので断じて看過できない。従って、ロシアはウクライナのNATO非加盟を求めて、ウクライナ国境の軍隊を集めて圧力をかけているのである。
ところが・・・
NATO、ロシアの拡大停止要求を拒否。
日本も見習ってほしいような強気の外交(欧・露ともに)。ロシアは実際にクリミアを編入したという前科があるから、少なくともウクライナ東部のロシア系民族が多い地域は併合しようと動くかもしれない。
米中覇権戦争のかたわら、ロシアと欧州の関係がかなりきな臭くなってきている。
カザフスタン
一方、カザフスタンはロシアの忠実な舎弟である。ソ連から独立後、共和制の国となったとされるが、ナザルバエフ大統領が27年にわたって大統領を務めるなど、かなり独裁的で権威主義的な国である。
旧ソ連構成国ではロシア以外では最大の面積を持つ大国で、資源も豊富である。西方からのNATO拡大を警戒するロシアにとって、南側に広く横たわるカザフスタンはいつまでも忠実な舎弟であってほしいだろう。
だが、そんなカザフスタンで大規模なデモが起こり、ロシアが軍を投入するという事態になっている。これはいったい何を意味するのだろうか?
報道ではデモの発端は資源価格(LPガス?)の高騰に国民の不満が爆発したということになっているが、すでに資源価格はもとに戻っているそうである。それにも関わらず、軍が出動するほどの大規模デモの背景には何があるのだろう?
大きくは、長く独裁政権が続いたナザルバエフ元大統領と、それを引き継いだトカエフ大統領に対する不満が鬱積していたというのが理由である。また、中国の一帯一路への不満(中国企業ばかりが儲ける)ということも背景にあるそうである。
こういう状況に、万一アメリカが介入してきたら、ロシアとしては極めて厄介である(アメリカとすれば、この地に親米政権を作ることに大きな戦略的価値があるように思える)。従って、ロシア軍を早期に投入して、忠実な舎弟のままでいてもらおうというのがロシアの意図であろう。

ロシア・ファクターで複雑化する世界情勢
ということで、米中覇権戦争が進行するさなか、ロシア周辺できな臭い動きが増してきている。ただあえてロシアの立場から言うならば、地域覇権国家を目指すロシアは、アメリカや欧州によって常に劣勢を強いられているのだ。そして欧米に対する反発心が、欧米の恐怖心を更に醸成するという悪循環になっている。
米中覇権戦争は、今や民主主義国家VS権威主義国家という世界を巻き込んだ対立に昇華しつつある。ロシアも中国と同じく権威主義国家の一翼とされ、2021年には民主主義国家が次第に劣勢となる様相がみられていた。
その巻き返しを狙ったのが、バイデン大統領による民主主義サミットだった。
劣勢に立たされる民主主義陣営、次第に勢力を増す権威主義陣営という構図の中で、今回のウクライナとカザフスタンの騒動はどのような結末を迎えるだろうか。ただ、ロシアとしてもEUやNATOに対して劣勢に押し込まれているというのもまた現実である。日本政府はウクライナやカザフスタンの騒動に巻き込まれる必要はないものの、うまく立ち回ってほしいものである。
(画像は写真ACから引用しています)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
