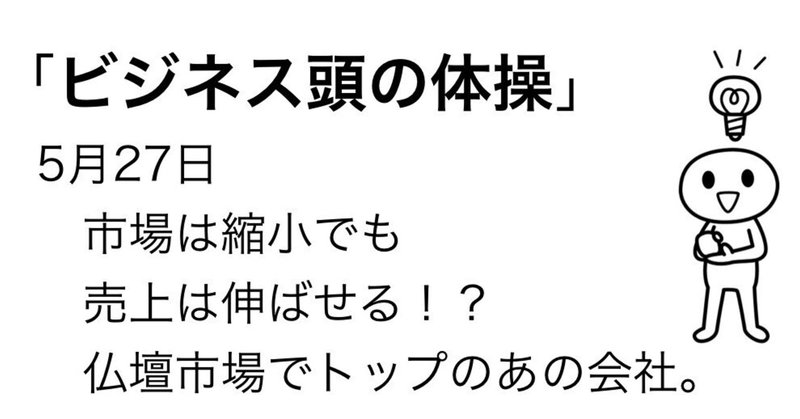
5月27日 市場は縮小でも売上は伸ばせる!?仏壇市場でトップのあの会社。
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→縮小する仏壇市場。どのような方向の事業モデル、マーケティングが考えられるだろうか?
東京都千代田区神田司町に事務局を置く全日本宗教用具協同組合(全宗協)が制定した「仏壇の日」(毎月27日)です。
西暦685年3月27日(旧暦)、天武天皇が「諸國(くにぐに)の家毎に佛舎(ほとけのみや)を作り、即ち佛像と経とを置きて礼拝供養せよ」との詔を出し立し、これ以来「仏壇」を拝むようになったとされるのに由来しています。
(5月27日の記念日は、海軍記念日とか日本海戦の日などでこちらで取り上げるのに適当なお題がなく、毎月27日の仏壇の日を取り上げることにしました)
仏壇。
昔は多くの家であったように思いますが、今はあんまり見かけないように思います。
東京商工リサーチの『全国「仏具店」の業績調査』によると、全国の仏具小売152社の最新期(2019年9月期~2020年8月期)の売上高合計は、515億6600万円(前期比4.4%減)と減少し、利益は前期の3億9100万円の黒字から、15億1100万円の赤字へ大幅に悪化しました。
原因としては、感染症拡大に伴う三密回避で法要や葬儀の縮小の影響が考えられますが、もともとマンション等の住宅事情、家族葬や小規模葬の広がりで厳しい状況のところに感染症が影響し、売上の急減に見舞われています。
全国の主な仏具小売152社のうち、赤字は47社(30.9%)と前期の27社(同17.7%)から1.7倍となっています。
仏具店は売上規模が1億円未満が102社(67.1%)、1〜5億円未満が36社(23.6%)と、5億円未満の零細、中小事業者が9割を占めます。
売上高10億円以上の大手7社の売上合計は360億円と全体の7割を占めています。
そのため、倒産や廃業、解散が多くなっています(下図)。

仏具に絞ったデータではありませんが、経済産業省によると、2002年の宗教用具の小売業者の事業所数は4,886箇所、売上高は2,705億円でしたが、2014年には事業所数が3004箇所、売上高1,639億円と、いずれも2002年から4割減となっています。

こうした厳しい環境の仏壇仏具業界ですが、最大手は「あの」株式会社はせがわです。2022年3月期の決算の概要は以下の通りで、売上高197.9億円、経常利益12.3億円となっています。

過去の決算資料を見ると、大体200億円前後の売上高で推移しており、直近5年間の売上高推移を見ても、コロナ禍の影響を脱した、という決算に見えます。

厳しい市場環境で、はせがわは店舗を商店街等の路面店からショッピングセンター内へと見直すこと、今の家に合うデザインの仏壇を投入すること、などの工夫を行なっています。
ちょっと興味深かったのですが、決算資料の中に以下のようなデータがありました。

この成約率、高い!と思ってしまいました。あんまり比較もしない、ということなんでしょうか…
縮小しているマーケットでも、ブランドを確立してしまえば、意外と競争はない、ということなのでしょうか?
一方で、単価が微減、というのは気になります。
このへん深掘りしてみたいですが、データなく…
最後に、はせがわではないのですが、デザイン性の高い、高価格帯(最高は500万円)の仏壇を投入しているメーカーを紹介した東洋経済の記事を紹介します。ご興味があればご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
仏壇。マーケット的には厳しい状況かもしれませんが、高級品シフトや店舗のロケーション変更など様々な工夫で生き残りを図っていることがわかりました。
一昨年7月から続けていますが、だいぶ溜まってきました。
以下のマガジンにまとめておりますのでよろしければ覗いてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
