
かがやけ、野のいのち 2 星寛治
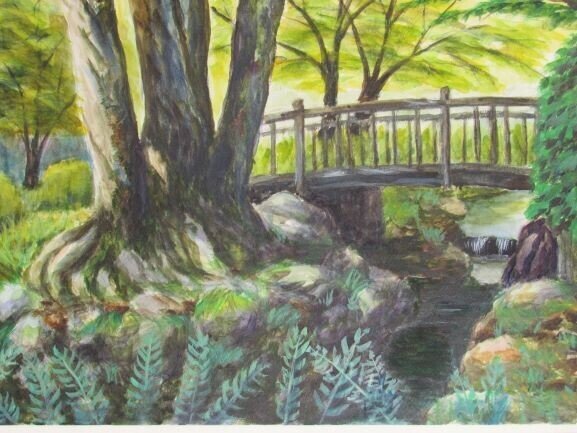
かがやけ、野のいのち 2 星寛治
序章 2
小さな町の大きな集い
一九八二年の晩秋のこと、外はみぞれを運んできそうな木枯らしがふきつけていた。ところが、わが高畠町の町営体育館のなかは、ものすごい熱気がうずまいていた。北は北海道から南は沖縄まで、列島の津々浦々から、第八回全国有機農業大会にかけつけた数百名の仲間たちの、白熱の討論がおこなわれていたからである。地元の人たちの参加をかぞえれば、二日間にわたって、延べ八〇〇名をこえる人びとが話し合いに加わった。
農業の集会といっても、参加者は農民ばかりではない。都市の消費者である主婦をはじめ、学者、大学生、教師、保母、医師、看護婦、栄養士など、じつに多彩な顔ぶれがあつまったのである。なかには子どもづれのお母さんも目だつ。
「なんかほかの大会とぜんぜんちがう雰囲気なのね。身なりも質素だし、バッグや足袋のはてまで手づくりのものが目だつのね。だけど、なごやかな中に、ピンと張りつめたものを感じたわ」
あとで、婦人会長さんがわたしに語ってくれた感想である。自前で旅費を負担し、はるばるこの地にあつまった人たちの目は、キラキラかがやいていた。
この会を主催したのは、日本有機農業研究会と高畠町有機農業研究会だけれど、これだけの大きな集まりを、四〇名たらずの地元の会員の力だけでやれるはずはない。町役場、教育委員会、農協、商工会などの全面的なバックアップがあって、はじめてできたのである。町長が歓迎のあいさつで述べたように、町をあげての受けざらづくりが必要であった。
かつて、有吉佐和子さんの『複合汚染』という記録小説が世に出てから、高畠の若者を中心とした動きが注目され、いつしか「有機農業のメッカ」とよばれたりした。
「とうとう憧れのたかはたにやってきた」
会場の内や外で、そういう若者やお母さんのことばを幾度も聞いた。わたしの胸はあつかった。
初日、天野慶之先生(東京水産大学学長)の記念講演のあと、わたしが「高畠町における有機農業運動十年の反省と課題」について報告をした。午後は各地の会員が、それぞれ困難をのりこえて、展望を見いだしつつある実践報告があいついだ。
夜の大交流パーティーは圧巻であった。ひろい体育館の床に、卓球台に白布をかぶせたテーブルが何十台もできあがり、そこに会員のおくさん方が心をこめてつくりあげた郷土料理が満載された。野菜、山菜、きのこ、果物など、いろどりゆたかな料理のまんなかには、放し飼いのニワトリの丸焼きなどもならんだ。そして、各テーブルには、紅葉の小枝がかざってあった。
農協組合長の音頭で、自然酒で乾杯が上げられると、あとはまったく自由でたのしい宴と化した。出店のサトイモの煮込みを、何ばいもおかわりする人たちの顔が、いかにもゆたかに見えた。
北から南まで、安全な本物の食べ物をつくり、あるいは熱心にそれを求めるなかまが、こんなにたくさんいる。その苦労話や手柄話に花がさく。みんな胸をひらいて語り合い、あたらしい友だちができた。
年齢や、職業や、立場をこえて、これほどうちとけ合い、理解しあえる関係もめずらしい。
「このおにぎりはおいしいね」
「うん、この青菜漬は味ちがうよ」
「ああ、丸かじりのリンゴの味は格別だわ」
食べることを通しての素朴な実感のなかには、立場のちがいなどありはしない。本音が通じる世界がそこにはあったのだ。
宴が果てて、人びとは宿にむかった。街のなかの数軒の旅館に、木枯らしのなかを十分以上もかけて歩きながら。ほおは熱くほてっていた。また、公民館や福祉センターの和室にざこねする青年にしても、深夜まで議論はつきなかった。
二日めは、役場や公民館の会議室などをすべて開放して、分科会がはじまった。稲作、野菜、果樹、畜産の生産技術のほかに、生産者と消費者の提携、教育と伝承など、それぞれの分野で熱っぽい討論がおこなわれていった。
もう冬を間近にひかえ、田や畑の作物をじっさいに見てもらえなかったのは残念だけれど、今年とれた生産物をもちより、手にとってたしかめてもらった。また、スライドの映像で、四季をとおした取りくみを見ていただいた。
日程の終わりには、それぞれ話し合われた内容の発表をうけて、全体会での論議がもりあがった。とりわけ、作り手と食べる側との結びつきの方法をめぐって、かなり激しいやりとりがあった。考え方や生き方のちがいがあらわれた場合、かんたんには妥協しない骨っぽさを、みんな持っていることを印象づけた。
最後に、日本の有機農業運動のリーダーである一楽照雄氏が、しめくくりのあいさつを、また地元の中川会長がお礼のあいさつをのべて、熱っぽいうずを巻き起こした大会は幕を閉じた。
わずか二日間の集会ではあったけれど、ここに結集されたエネルギーは大きかった。そして、二つの足跡をしっかり残してくれたように思う。一つは、食べ物の問題はひとり農家の問題にとどまらず、国民各層の身近なテーマになってきたことを示したこと。もう一つは、有機農業のめざす道が地域の人びとに理解され、かなり太い根っ子を張りつつあることを示したことであろう。

育てる農業にかける
むかしから農業はお天気まかせみたいなところがあった。稲にしても、ほかの作物にしても、風水害や干ばつなどに会わず、おだやかな天候の年は豊作だった。反対に、予期せぬ自然災害にみまわれれば、作物は大きな痛手を受け、農民のせっかくの苦労もむくわれないことが多い。だから人びとは、五穀豊穣を神に祈るときには、「かならずよい天候に恵まれますように」と願うのであった。
ところが、世の中が近代化されるにしたがい、農業にも科学的な方法がとり入れられるようになってきた。たとえば、生産に必要な農具、肥料、農薬などの資材が工業的につくられ、農家はそれを利用して、便利に、能率よく生産活動をおこなうことができる時代である。
とりわけ、ビニールなどが開発されると、これまで天候まかせであった苗育てや、野菜づくりや、果樹栽培などにおいて、トンネル、ハウスなどの施設化によって、自然の制約をすくなくする技術がひろがっていった。一九六〇年ごろから、そうした技術革新はめざましい勢いですすんだのである。そうして今日、機械や、化学肥料や、農薬や、除草剤などにたよらない農業は考えられないまでになった。
ところが、近代農法が定着した一九七〇年ごろから、様変わりをとげた農村のなかで、すこしずつおかしな徴候が見えだした。化学肥料や農薬をたくさんつかって、一時たいへんよく出来た作物が、いつのまにか病気にかかったり、連作障害といって、同じものを同じ畑で毎年つくりつづけると、作物の出来が極端にわるくなる、あるいは収穫前に落果するなど、あまりうまくいかなくなってきた。さらにあたらしい薬をつかっても、効果はうすいようである。また、冷害などに見舞われると、あまり抵抗力がなく、ガタッと減収することが多い。つまり、作物がひ弱な体質になってきたことに気づいたのである。
わたしたちは、頭をかかえてしまった。科学する農業という格好のよいことばに共鳴し、現実にあたらしい農法の成果に酔いしれているうちに、なにか足元の方からくずれていく不安を感じてきたのであった。
その原因はいったい何なのであろうか。なかまたちと真剣に考え合っていくうちに、
「結局、こりやあ、土がダメになってきたからではないかね。機械をつかうのに都合がわるいからといって、わらを焼いてしまい、化学肥料や農薬をまいて十分だと思ってきたけれど、十数年もたつうちに、土はガタガタにやせ衰えてきたのではないか」
遅ればせながら、ようやくそのことに気づいたのである。
「だとするなら、ぼくたちはもう一度、土の体力づくりに励まなければいけないね」
「草を刈り、わらを大事にして、よい堆肥をたくさんつくり、田畑に返すことが基本だね」
「もう、便利だからといって、危険な薬にたよるようなまねは止めようよ。それに、わたしたち自身の健康さえ、あぶなくなってきた」
「そうだね、環境をよごさないで、土の生命力を土台にして作物を育てる農法を研究しようではないか」
わかい農民たちは、そう考えた。それに、その以前から薬づけのようにしてつくられた作物は、見た目はきれいだけれど、栄養にとぼしかったり、残留毒性が食品公害をもたらすという不安もさけばれてもいた。そこで、百姓の基本に立ち帰ることをめざし、わたしたちは高畠町有機農業研究会を結成したのである。一九七三年九月、いまから十三年前の秋のことであった。
当時、わたしは三〇代の後半にさしかかっていた。新米百姓のころは、農業近代化のれい明期だったから、じっさいにはむかしからの伝統農法も体験してきた。しかし、有機農研に参加した農民は、ほとんど二〇代の若者たちで、近代化の落とし子みたいな人たちであった。農薬や除草剤をつかわない農法など、考えたこともなかった世代なのである。そんな若者たちが、堆肥だけで米つくりをやろう、といいだしたものだから、親たちも世間もおどろいた。口のわるい人からは、「頭のおかしい連中だ」と、わらわれもした。
生命の安全を旗印に船出した三八名の集団は、めざす筋道のただしさは確信していたが、じっさいに無農薬有機栽培とはどういう方法でやったらいいものか、皆目見当がつかなかった。村の古老に聞いたりしながら、とにかく堆肥だけで稲を育てることを申し合わせてスタートした。まったく手さぐりの出発だったわけである。
わたしの場合、まず自給用にと二〇アールの田を有機栽培に切り変えた。乳牛の堆肥二トンを入れただけで、あとはいっさいなにもほどこさずに踏みこんだ。家では、戦前、戦中、戦後を通して、一度も牛飼いをやめたことはないから、堆肥は休みなく田んぼにほどこしてきた。有機農業に切り換えるには、その堆肥の多めにほどこし、化学肥料や、田植えがすんだあと半月ぐらいたったときに、手押しの除草機で中耕除草する。そうすると、小さい雑草は泥をかぶって抑えられるわけである。
それから半月後、六月中下旬ごろに二回目の除草機押しをやる。このころになると、苗もかなり成長し、さかんに分けつ(株分かれ)をしてくるが、雑草のほうも勢いよく伸びてくる。特に野ビエなどは、除草剤をつかわないと、ワツとばかりに密生してくる。除草機を押すと、畦間(あざま)の草はうめこむことができるけれど、株間の草はそのまま残る。だから、七月初旬ごろからは、手取り除草をしなければいけない。四つんばいになって、来る日も来る日も草とのたたかいである。
まだ雑草の小さいうちはよいが、すこし手遅れになると、野ビエなどは強靭な根を張り、両手に渾身の力をこめないと抜けてこないようになる。そうなると、もう何倍も労力がかかってしまう。季節が梅雨明けにかかると、稲も成長するので、暑い草いきれのなかに頭をつっこんで、はいつくばる作業のつらさは、経験しないとわからない。その手取り除草は、一回だけでなく二回つづけてやった。見つけ残しや、後ではえた草がびっしり田面をおおい、稲があえぎそうだからである。さらに、穂が出てからヒエ抜きをする。ヒエの種子がみのってこぼれ落ちてしまうと、翌年からまたえらい目に会うことは目に見えている。だから、草取りだけで五回も手をかけるわけである。
病虫害の防除についても、一つやっかいなことが起きた。分けつ期に稲の茎葉を食いあらすドロオイムシが多発したからである。やっと勢いづいてきた稲田が、たちまち真っ白になってしまう。わたしはお年寄りに聞いて、座敷ほうきを持ち出し、葉にへばりついている虫を払い落とし、そのあと除草機で泥にうめる方法を試みた。田のそばの「ぶどうまつたけライン」という観光道路を走りぬけるドライバーが、わざわざ車を止めて、ニヤニヤしながらながめている。
「あのオッサン、ちっと頭おかしいんじゃないの」という表情である。わたしは麦わら帽子をさらにあみだにかぶり、それでもせっせと掃きつづけた。この仕事は、案外能率が上がるもので、十アール三十分ぐらいですますことができる。ふしぎなもので、こうして一回掃くだけで、ほとんどドロオイムシの被害はふせげて、稲はまた急速に緑をとりもどしたのである。
そんな苦労をつみかさねて育てた稲ではあったが、出穂前の姿はいまひとつ物足らない感じだった。背丈も低いし、茎数も少な目である。案の定、出た穂も短かめで、あまり多収はのぞめそうもないことがはっきりした。みのりは良かったものの、収穫してみると、いつも十俵(一俵は六十キログラム)前後とれる田んぼで六俵ぐらいしかとれなかった。はじめての挑戦とはいえ、四割の減収はこたえた。
「ああ、あんなに苦労してこれだけか」
わたしも、妻も正直がっかりした。しかし、
「化学肥料や農薬なしで、米つくりなどできっこないよ」
といわれてきた、現代の神話のようなものをくつがえし、
「こんなにべっこう色にかがやく、すばらしい米がとれたじゃないか」
そういう、ひそかな誇りと自信をいだくことができたことは、うれしかった。
なかまたちの多くも、三、四割の減収だった。人によっては半作ちかい例もあった。わたしたちは、その原因について考えあった。結局、地力、土の生命力で勝負しようとする農法で、切りかえた当初から安定した収量を期待するのはむりなのでは、という判断になった。すでに長いこと汚染された川畑は、本来の健康さをとりもどすために、何年かの月日が必要なのではなかろうか。それまで、わたしたちは、しんぼうづよく、土をゆたかにする努力をつづけるほかはないことを知った。
二年めも、だいたい同じようにして過ぎた。イモチ病や二化メイチュウの被害もすこしは出たが、ダメージを受けるほどにはひろがらなかった。稲の体そのものが、堅く、じょうぶにできてきた証拠だと思われた。
その秋、有吉佐和子さんが、「複合汚染」の取材に訪れ、四日間ほど滞在された。先生をかこむ懇談などを通して、この列島にひろがる汚染の深刻さにあらためて目をひらき、わたしたちの小さな運動の方向性に確信をもつことができた。しかし、二年めの成果も、不本意なものに終わった。日照りの影響を受けて、野菜などはみな、出来がわるかった。
三年め、東北地方を激甚な冷害がおそった。世にいう五一年(一九七六年)冷害である。山村では、真夏にうちわも扇風機もいらず、お盆にコタツを出すほどの冷たい夏であった。
「サムサノ夏ハオロオロアルキ」という宮沢賢治の詩の一節が、おそろしいほど現実みを帯びてせまってきた。いつもだと、七月末には早生稲がちらほら穂を出しはじめるのに、その年はお盆をすぎても出なかった。八月の二〇日すぎ、ようやく出穂がはじまり、穂ぞろいには八月末ごろまでかかった。山間の冷水がかかる田んぼでは、ついに穂を出さずじまいのところもあった。わたしの地域でも、冷害と病害がひろがり、白茶けた田んぼは見るも無惨であった。
そんなとき、ふしぎな現象が起こった。有機栽培の田んぼだけが、ポツリポツリと山吹色の穂波を見せはじめたのである。たった畦一本をはさんで、まさに対照的な光景があらわれたわけだから、道ゆく人はもちろん、わたしたち自身がおどろいた。ようやく三年めにして、汗と愛情をそそいで育てた稲は、空前の冷害にもめげず、その野生の生命力をうつくしいみのりに結晶させてくれた。わたしたちの胸は高鳴った。
じっさいに収穫してみると、わたしのところでも十俵をこえた。周辺が半作以下のときに、完全に平年作を確保したのである。平野部の会員では、十一俵半を記録した人もいた。その報告を聞いた有吉さんが、「手づくり稲作の凱歌」とたたえてくれた。稲をつくる、米をとる、という発想から、稲を育てる生き方に立ち帰ったわたしたちの筋道はけっして間違ってはいなかった。自然は、土は、稲を通して正直にこたえてくれたのである。

あったかい土
三年めの正直に感激したわたしたちだが、ふとまわりを見ると、三八名で発足した会員が一八名にまで減っていた。頭のなかで共鳴して、いきおいこんで駆け出してはみたものの、労すれど効なし、の現実に疑問を感じ、一人欠け、二人欠けして、いつしか半減していたのである。あるいは、家族の理解と協力を十分得られないことや、世間の有形無形の圧迫感に耐えきれず、やめていった人もあるだろう。つらいスランプの時代だったのである。
しかし、たとえ小面積でも実践にふみこんだ人は、失敗をくりかえしながらも土俵内にふみとどまった。環境と生育をよく観察し、失敗の原因は何かをつきとめようという姿勢をもちつづけた。そして翌年は、みずからあたらしい技術をあみ出し、より適切な手だてをとろうとした。わかい集団は、たえずしなやかなバネを備えていたのである。
「災害は忘れたころにやってくる」というが、北日本をおそう冷害禍は、一九七六年の記憶がまだ生なましいうちに、次つぎと立ちあらわれた。一九八〇年から八三年まで四年つづきの冷害がそれである。オホーツク海から南下した寒流が太平洋岸を洗い、偏東風(やませ)とよばれる冷たい風が夏じゅうふきつける。空はどんよりと曇り、時おりしぐれを運んでくる。うちつづく不作に、東北の農民の顏は暗く、空を見上げてため息をつくほかはなかった。
そんななかで、わたしたちの有機栽培の稲は健在であった。異常気象をはねかえし、四年問ともコンスタントに平年作を確保したのである。いったい、その秘密はなんであろうか。たしかに長いこと土づくりに精出してきた田んぼは、地力がついて、そこに育つ作物もたくましく健康になってきた。その姿は、見た目にもわかるほどである。つまり、病虫害だけでなく異常気像にもつよい稲が育ってきたわけである。
ただ、それだけでは感覚的な診断にすぎず、説得力が弱いと考えられる。そこで、温度計を田んぼの泥にさしこんで地温を計ってみた。七月中下旬のはだ寒い日に測定した結果、ふしぎなことに、十年も有機栽培をつづけてきた田んぼと、化学農法の田んぼでは、ほぼ三度の差があった。もちろん有機田のほうが高いのである。何か所かの調査は、おしなべて同じ傾向を示した。畦一本はさんで、その差はあまりにはっきりしていた。
「これだ。このあたたかい土が冷害をのりきった立て役者だ」
思わず、わたしたちはさけんだ。稲の一生のなかで、茎のなかに穂をはらんだ減数分裂期と、出穂後の開花授精の時期が、いちばんデリケートだ。その時期に、摂氏十七度以下の低温に会うと、生理障害をおこし、みのらない空っぽの穂が出やすい。そのとき、三度の地温の差は、限界温度を確保する決定的な意味をもった。
それにしても、この温い土はなぜ生まれたのであろうか。研究者によれば、ほんとうに肥えた土のひとにぎりには、数億から十億をこえる小動物、微生物、酵素、菌類などが生息し、生まれては死に、生きては死にして、一つの自然界を形成しているといわれている。その無数の目に見えない生命活動のエネルギーが、地温を三度も押し上げているのであった。それが、冷害をのりきって、べっこう色の米粒をもたらした科学的な根拠の一つである。つまり、生きている土の勝利なのであった。
その成果に自信を得たわたしたちは、毎年十アールずつ有機田にきりかえる目標をたてた。
「正しいとわかったことは、全部やらなけりゃダメじゃないか」
という批判もあった。ただ、農法を変えて土がゆたかになるまでには数年かかる。その間は、草とりに苦戦しなければならないし、収量も安定しない。最初から全面積を転換すると、農家経営はパニック状態になりがちである。牛の歩みといわれるかもしれないが、わたしたちはもともと農業というものは息の長い仕事だと考えて、とりくんできた。
ところで、十年たって後ろをふり返ってみたら、そこには幾筋かの小さな流れがあつまって、瀬音をたてる小川になっていた。わたしの家でも、すでに一ヘクタールちかくの田を有機栽培でやっている。会員の多くは、自分の能力いっぱいのところまで水準をたかめ、がんばるようになっていた。
経営の中身もまた変わってきた。稲作だけの専作経営(モノカルチャー)だった人も、ニワトリや牛を飼い、野菜や雑穀をつくり、多品目少量生産の形態にちかづいてきた。そうした生き方に共鳴する消費者と手を結んで、共につくりあげる運動をめざしてきた成果だ、といえるだろう。ひところ、発足当初の半分にまで減った会員が、実績があらわれるにつれてふえ、いまでは五〇名を越えるまでになった。
かなり年輩の農民の顔も見える。しかし、うれしいことには、二〇代、三〇代の若手が、また一挙にふえたことである。その多くは、農業をめぐる環境がますますきびしい中で、あえて専業農民として生きようという後継者たちである。と同時に、都市生活と定職をふりすてて、地域に土着した帰農青年たちの顔がめだつ。彼らは、物質文明のなかでの便利さや快適さが、かならずしも人間を幸せにしないことの矛盾に気づき、自然とともに生きる有機農業に活路を見いだした人びとである。その知的な顔が、大地のもつゆたかさときびしさにみがかれて、しだいにたくましく変わっていくことに気づくのである。

星寛治著「かがやけ、野のいのち」草の葉ライブラリー刊行
序章
幼かったころ
野球に熱中
苦悩の高校時代
新米百姓のころ
小さな町の大きな集い
育てる農業にかける
あったかい土
春
黒い土の香り
牛のお産
娘の受験
種まきのころ
バカ苗騒動
百姓志願の若者たち
リンゴの花満開
めんどりの体温がのこる卵
御領地の精神風土 たかはたの歴史①
夏
田の草取りの援農
共につくりあげる関係
東大で百姓大座談会
選挙カーと娘たち
こっちの水は甘いぞ
ばん回する稲
果物の宝庫
乾草のにおい
ブドウ産地の風景
魔法使いのような母
キャベツ畑の青ガエル
メキシコからの客
古代に思う
かてものの知恵 たかはたの歴史②
秋
山吹色のみのり
マツタケ狩り
稲刈りにきた医大生
リンゴの袋はがし
紅玉をつみとる
幻の農民一揆
落ち葉をひろう子どもたち
キビ餅、アワがゆ復活
つけ物の季節
鈴なりのふじリンゴ
凍みリンゴの話
義民高梨利右衛門の風景 たかはたの歴史③
冬
雪の中のくらし
雪の贈りもの
野の巨人逝く
充電したい時問
四国の子どもたちからの便り
満濃の子どもたちを訪ねる
作付け会議
消費地を訪ねる
進取と反骨と たかはたの歴史④
終章
農を継ぐ子どもたちに
四結会の村づくり
わが村はうつくしく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
