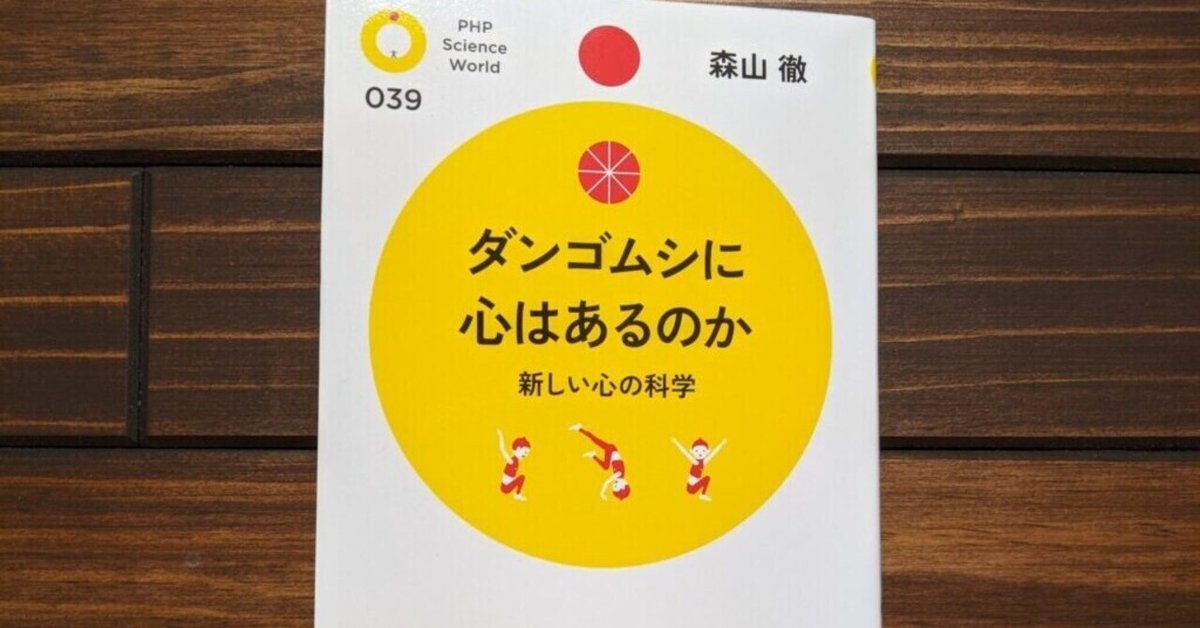
【読書メモ】ダンゴムシに心はあるのか(森山徹)【#19】
面白かったけど・・・
という感想です。
まず第1章で心を定義しています。
第2章で実験の説明があって、
第3章でその結果について
動物行動学的意味を説明しています。
最後に第4章でタコとかミナミコメツキガニの
実験や観察を紹介しています。
ここで第1章の心の定義について、
心の働きは「抑制するもの」としています。
行動の発現や感情の発露を抑制するものが
「心」の主な働きだとしています。
ここまではいいのですが、
この心という概念を、
石にも心がある、
ジュラルミンの板にも心がある
としています。
これは、論文では言っていないことなので、
おそらくこの本のために
サービス精神的に
書いているのだと思いますが、
この部分は
非常に良くないと思います。
石に心がある
と書いていることが悪いのではなく、
突然「疑似科学(ニセ科学)の論理」
に陥るところがよくないです。
第1章の最後を抜粋します
観察者によっては、心は石やジュラルミンの板にも備わっていて、見いだすことができるのです。ただし、観察対象の心を見いだすには、ある前提が必要です。観察者が、さまざまな状況に応じた観察対象の特定行動を見いだせるよう、対象ととことん付き合うということが、まず必要なのです。
科学であるなら「反証可能性」というのが必要です。
反証可能性というのは、
「提案されている命題や仮説が、実験や観察によって反証される可能性がある」
ことです。
ただし、科学でないことが
正しくないとは限りません。
科学でなくても
正しいことはたくさんあります。
宗教は科学ではありませんが、
信じている人にとっては正しいことです。
絵画や音楽の美しさは
見る人、聴く人によって
感じ方が異なるので
反証はできませんが、
どの人の感じ方も間違ってはいません。
アートだからです。
つまり、科学的であるということは、
同じ方法で行ったけど、
同じことが起きませんでした。
ということは、
これは認識できていない条件のような、
何か想定できていないものに
強く影響を受けている可能性がありますよね。
仮説が間違っているか、
別の追加すべき条件がある
ということが分かりますよね、
ということが出来るということです。
心の定義に戻ると、
ダンゴムシを使った実験は科学的で、
調査している条件設定も多彩で、
非常にレベルの高い研究だと思います。
著者が書いているように、
有名な査読ありの雑誌に論文が載った
というのも分かります。
しかし、第1章の心の定義のところだけ、
反証可能性がない理論に
すり変わっているんです。
石に心がない、
ジュラルミンの板に心がない
ということを反証しようとしても、
心が見いだせないのは、
とことん付き合っていないからだ!
という一言で終わってしまうのです。
なので、「新しい心の科学」という副題がついていますが、
ちょっと心に対する考察が
雑なように思いました。
抑制という意味では、
ダンゴムシにもタコにもミナミコメツキガニにも
心はあるのかもしれませんが、
なんとなく同意しかねる
という感想でした。
抑制は置いておいて、
一般的な話をすると、
猿には心はあるのでしょうか?
猫には心はあるのでしょうか?
ネズミは?
カラスは?
鶏は?
ヘビは?
カエルは?
メダカは?
カブトムシは?
ダンゴムシは?
哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫の
どの辺りまでが心があると考えられているんでしょうか?
ある程度のラインがあるのでしょうか?
そこが気になります。
おわり
頂いたサポートは、とてもモチベーションになっています。新しい記事を作る資料費として、感謝しながら有意義に使わせていただきます。 気功・太極拳を中心とした健康と、読んだ本について書いています。どちらも楽しんでいただけると嬉しいです。 サポートしてくれたあなたに幸せが訪れますように!
