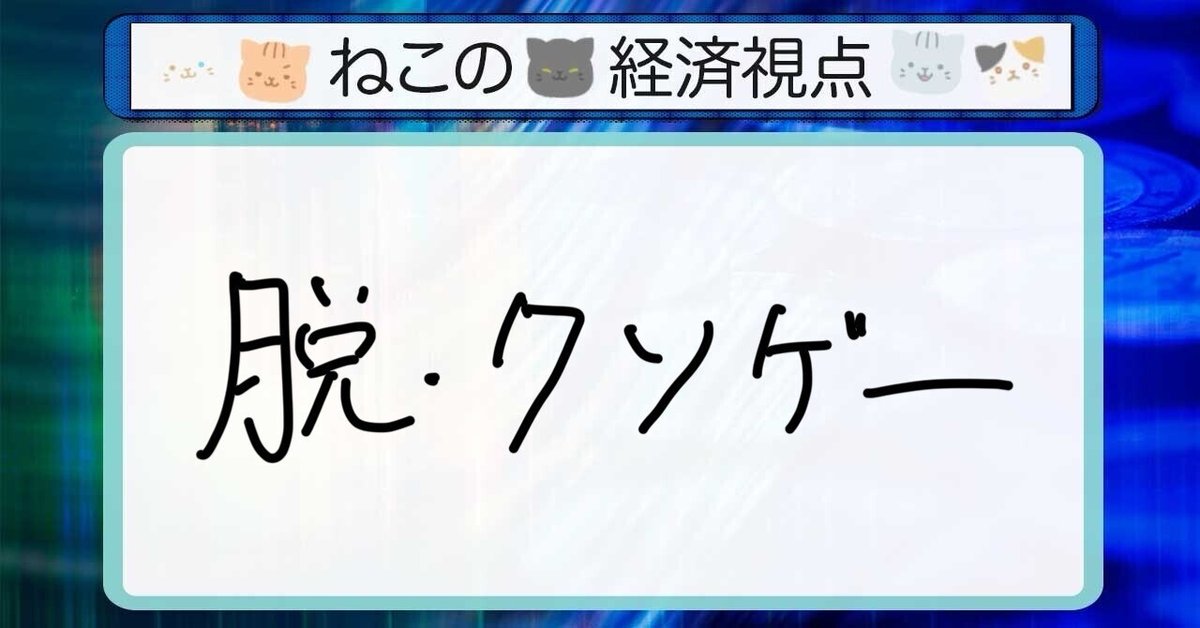
クソゲーから普通の世界へ

① 金利ある日常再び 家計に恩恵、メガ銀は普通預金で上げ
企業部門では企業の金利負担が増える一方で、産業界に新陳代謝をもたらす期待もある。日本総合研究所の試算では、もし借入金利が1%上昇すれば企業全体の経常利益は7.4%減少する。有利子負債の依存度が大きく収益力が弱い零細企業は21.1%減となる。
帝国データバンクの試算によると、稼ぎに比べ過大な負債を抱えている「ゾンビ企業」の割合は22年度時点で17%を占めており、推計で25万社にのぼる。19年度時点では15万社だったが、新型コロナウイルス禍で20年度以降に急増した。
金利のにゃい世界は言ってみればお金を借りたもん勝ちというか、資本コストを考えにゃくてよくて、制限のにゃい中でいろんなことができるという意味ではある種の「クソゲー」だったわけで😹 それができにくくにゃってくると、やはり規模が小さくて財務レバレッジを掛けまくってるようにゃところは投資先として除外してったほうがいいかにゃ?
とはいえ、低金利がゾンビ企業を生み出したという説は誇張されすぎてると言う人もいるにゃ⏬
② 日銀緩和「副作用より効果大きく」アダム・ポーゼン氏
「円安もデフレリスクを抑える要因になる。米経済は来年にかけて堅調な成長を続け、米連邦準備理事会(FRB)は今年の利下げを2回にとどめる可能性もある。(日米金利差が広がったままで)円安が続くと、日本にとってプラスとマイナスの両面があるが、差し引きではプラスの影響が大きい」
――終了したマイナス金利や長短金利操作(YCC)は政策効果が乏しく、副作用も大きかったという見方があります。
「(低金利ゆえに延命できる)ゾンビ企業を増やし、信用市場をゆがめたといった批判は誇張されている。日本経済がデフレ状態に近かったことを考慮すれば、(物価影響を除いた)実質金利を高くしないようにマイナス金利を導入し、デフレへの回帰を防いだことは適切だった。YCCは実質金利と信用・金融状況のバランスを取るうえで、より創造的で責任ある政策だったと評価している」
たぶん円安ににゃりすぎちゃってマイナス金利やらYCCやらが槍玉に上げられて、余計に悪者扱いされやすい土壌でゾンビ企業というワードがひとり歩きしてる感は確かに否めにゃいにゃ😾
けどそれより気にニャルのはFRBの利下げが2回になる可能性を指摘してること🙀 そうにゃれば150円どころじゃにゃくにゃってくるから、いやがおうにもインフレ圧力は収まらず、結果的に持続的な物価と賃金の上昇が続いていくことににゃって、まあ確かに差し引きで考えればプラスかにゃ? でもこれ以上の円安は怖いにゃ😱
③ 賃上げ企業に投資
コスト増を転嫁できる価格決定力を持ち、持続的な賃上げが可能な企業に投資を続けていく。人手不足で需要が旺盛なデジタルトランスフォーメーション(DX)や人材派遣関連、金利上昇の恩恵を受けやすい銀行株も注目している。
おおむね今回のマイナス金利解除を受けて特段投資戦略を変えたりはしにゃというプロの方々が多い印象。今後の投資先を見極めるポイントも、シンプルに価格決定力があって賃上げして人材を確保できるところが有望にゃのはこの先も揺るがにゃいにゃ😼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
