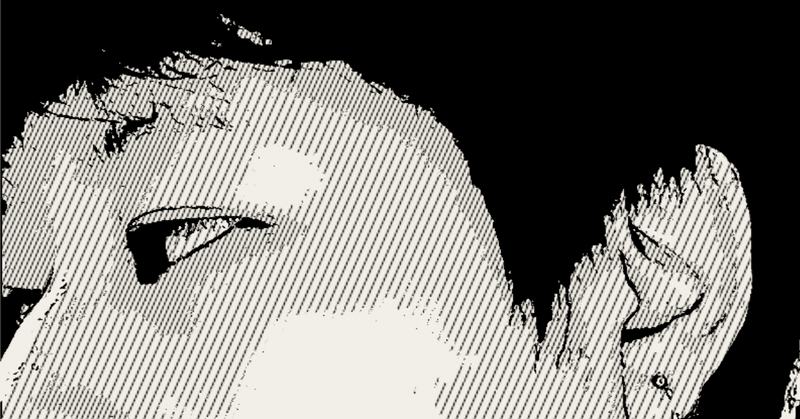
小説「アキラの呪い」(16)
前話はこちら。
アキラの呪い 15.16は連続更新。
間話2 「深夜:side晶」
深く静まり返った夜のことだった。
誰かがうめいていた。男の掠れた声が壁向こうから聞こえる。作業の手を止め、わたしは知らぬ間に歩の部屋の前へと立っていた。ドアノブを引くと、くぐもっていた声は鮮明になる。戸の隙間から闇が漏れ出て廊下を染めていた。その暗闇に惹かれたせいだろうか。部屋へと足を踏み入れ、気がつくとベッドを覗き込んでいた。弟が大きな体を窮屈そうに折り曲げ、蹲っている。彼を見下ろすのは久々で、見慣れない光景だった。その様はまるで獣の寝姿のようでもある。そして同じく獣のような唸りが喉から漏れて、部屋を這い回った。薄暗い室内でも、表情の険しさは明らかだった。深い皺が刻まれた眉間を触れるか触れないかのところで掠めてみる。そこだけ、別物のように盛り上がっていて、なんだか面白い。
何かから逃れようとするように、彼は一層激しく身を捩る。それと一緒にシーツが乱れ、幾重にも波を生んでいた。一体どんな夢を見ているのだろう。
そこでふっと正気に戻った。
なぜ、ここにいるのだろう。
やらなければならないことはまだまだ山のようにあるのに。その思いとは裏腹に足は貼りついたようにその場から動かなかった。
そんなに興味深いものだっただろうか?
何かを確認しなければならないと思った。ベッドの端に腰を下ろすと軋んだが、彼は起きる気配もない。振り向いてもう一度、まじまじと観察する。そういえば、この子の寝顔を見るのは本当に久しぶりだった。自然と手が伸び、触れたのは喉仏だった。私にはない、この盛り上がり。今は荒い息を吐きながら上下に揺れている。その動きを追うのにしばし夢中になってしまう。「ふふふっ」と、溢れた密やかな笑みが、唇を歪めた。指だけではない。彼の剥き出しの肌が寝苦しそうに身動きするたび、少しだけ私に触れた。するとその時、喉元が大きく動き喘ぐように吐き出した。
「ここのえさん…」
「ここのえ…」
自分の息が詰まるのを感じた。触れていた指先をそっと離す。目覚めてはいけない。無防備な姿をもう少し見ていたかった。九重とは私の古い苗字だった。夢には私がいるのだろうか。それとも母が?すると、思考を断ち切るような鋭い声が発される。
「違う!違う違う違う違う違う……!」
「あきら、アキラ、晶…ねえ、さ、ん」
久しぶりに名前を呼ばれて、自分の頬が強張るのがわかった。そう。昔は幼い声でアキラと呼んでいた。歩がそう呼ばなくなったのはいつの頃からだったか。残念ながら思い出せない。元々いろんな記憶が曖昧な方なのだ。それでも、もう呼ばれないのだと確信した時の喪失感だけは今でも覚えている。他のものが遠く失せていく中、ずっと消えなかった。焼け焦げた跡のようにずっと。目障りだった。消してしまいたかった。もう、呼ばれることはないだろうと思っていたのに。心の中ではそう呼んでいたのか。
「…歩」
「あんたはなぜ、呼ぶのをやめたの?」
「これを尋ねてみたかったの」
口に出して初めて、わたしは自分の欲求に気がついた。
「ねえ、なぜ?」
寝顔に問いかけても、応えなどあるはずもない。我ながら馬鹿馬鹿しいことをしてしまった。一連の行動を思い返して、呆れているとやがて彼の瞼がゆっくりと開き始めた。
わたしはそれを悟るや否や、足音を殺し、退出した。幸いにも弟が気がついた様子はなかった。ここで立ち去ってもよかったが、どうしても目覚めた歩を見てみたいという衝動に駆られた。それに、どんな夢を見ていたのかも尋ねてみたかった。私はどんな夢に登場していたのか、と。少し考えた末、やはり入ってみることにした。
ドアの前で姿勢を正すと、2度ノックした。短い声が応える。その声は悪夢故か疲れ切っている。彼はどんな顔でわたしを出迎えるだろうか。今はただ、それが楽しみだった。苦しんでいても悲しんでいてもいい。喜んでいても怒っていてもいい。彼の喜怒哀楽はわたしを楽しませる。それだけは、幼い頃から変わらないことだった。そしてこの悦びこそが、変わらず苦しみの源泉でもあるのだった。ドアが音もなく開く。隙間からは、あの子の潤んだ眼が見下ろしている。
***
間話2終わり。第四章へとつづく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
